第7節 グローバルマーケットの戦略的な開拓

人口減少や高齢化により農林水産物・食品の国内消費の減少が見込まれる中、農業・農村の持続性を確保し、農業の生産基盤を維持していくためには、我が国の農林水産物・食品の輸出拡大に向けた取組を強力に推進し、今後大きく拡大すると見込まれる世界の食市場を出荷先として取り込んでいくことが重要です。
本節では、政府一体となっての輸出環境の整備、輸出に向けた海外への商流構築、プロモーションの促進、食産業の海外展開の促進等について紹介します。
(1)農林水産物・食品の輸出促進に向けた環境の整備
(2兆円目標の達成に向け、輸出戦略を着実に推進)
人口減少に伴い国内市場が縮小する一方、海外市場が拡大する中で、国内の農業生産基盤を維持し、地方の「稼ぎ」の柱とするために、輸出の促進を図ることとしています。
令和5(2023)年12月には「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(以下「輸出戦略」という。)を改訂し、輸出先国・地域の多角化の推進、都道府県やJAグループと連携した地域ぐるみでの輸出産地の形成、輸出先国・地域における商流開拓や食品事業者の海外展開への支援を通じた戦略的サプライチェーンの構築、海外ライセンス指針も踏まえた知的財産の戦略的な保護・活用等を行うこととしています。
(生産者の所得向上にも寄与)
令和5(2023)年3月に公庫が実施した調査によると、輸出の収益性について、「国内向けより高い」と回答した農業者の割合は24.8%となっており、特に施設花きや施設野菜において高い水準となっています(図表1-7-1)。
国内の食市場の規模が縮小する中、今後大きく拡大することが見込まれる世界の食市場を出荷先として取り込み、国内の生産基盤を維持・拡大するためには、農林水産物・食品の輸出を拡大していくことが不可欠です。
農林水産物・食品の輸出を通じ、国内仕向けを上回る単価で販売することは、生産者の所得向上や海外需要拡大による国内価格の下支え等にもつながるものです。また、加工食品の中には、例えば日本酒のように国産原料を使用しているものがあります。このような国産原料の使用は、地域の生産者に安定的な販路を提供し、その所得の向上につながるものと考えられます。さらに、輸入原料を使用する場合でも、食品製造業が輸出により収益を上げることは、国産原料の買い手としての機能が地域で維持・強化されることにつながります。
(認定品目団体として新たに6団体を認定)
輸出戦略に基づき、農林水産省は、海外で評価される日本の強みを有し、輸出拡大の余地が大きく、関係者が一体となった輸出促進活動が効果的な29品目を輸出重点品目に選定し、ターゲット国・地域、輸出目標、手段を明確化しています。
また、輸出促進法(*1)に基づき、輸出重点品目ごとに、生産から販売に至る関係者が連携し、輸出の促進を図る法人を、法人からの申請により、国が「認定農林水産物・食品輸出促進団体」(以下「認定品目団体」という。)として認定しています。認定品目団体は、市場調査やジャパンブランドによる共同プロモーションといった個々の産地・事業者では取り組み難い非競争分野の輸出促進活動を行い、業界全体での輸出拡大に取り組んでいます。令和5(2023)年度は、新たに6団体(10品目)が認定され、合計15団体(27品目)となりました(図表1-7-2)。

*1 特集第3節を参照
(GFPの会員数は8,942に増加)
輸出産地・事業者の育成や支援を行うGFP(*1)(農林水産物・食品輸出プロジェクト)は、令和6(2024)年2月末時点で会員数が8,942となっていますが、輸出の熟度・規模が多様化しており、輸出事業者のレベルに応じたサポートを行う必要があるほか、新たに輸出に取り組む輸出スタートアップを増やしていく必要があります。このため、地方農政局等や都道府県段階で、現場に密着したサポート体制を強化することとしています。
また、公庫融資(農林水産物・食品輸出基盤強化資金(*2))や税制特例(輸出事業用資産の割増償却)の積極的な活用により、輸出に取り組む事業者を強力に後押しすることとしています。
さらに、輸出促進法に基づく輸出事業計画を策定した者に対し、輸出産地の形成に必要な施設整備等を重点的に支援するとともに、輸出産地・事業者をサポートするため、専門的な知見を持つ外部人材を「輸出産地サポーター」として地方農政局等に配置し、輸出事業計画の策定と実行を支援しています。
*1 Global Farmers/Fishermen/Foresters/Food Manufacturers Projectの略
*2 沖縄振興開発金融公庫でも貸付が行われている。
(旗艦的な輸出産地モデルを形成)

アスノツガル輸出促進協議会による
輸出産地の形成に向けた、りんごの栽培指導
資料:株式会社日本農業
農林水産物・食品の輸出の拡大に向けて、残留農薬や植物検疫といった規制の問題に対応することが求められるため、輸出先国・地域ごとや品目ごとに、産地が一体となって生産方式を転換していく必要があります。
また、青果物の輸出は、輸送中の品質保持が重要となることから、流通段階のみならず、産地における取組も重要となります。さらに、流通コストの削減のためには、安定的にコンテナを満載していくことも必要です。
農林水産省では、海外の規制や大ロット等のニーズに対応する輸出産地を形成するため、都道府県や農協が先導し都道府県版GFPを組織化するとともに、輸出支援プラットフォーム等との連携の下、輸出重点品目の生産を大ロット化し、流通コストの低減も図る旗艦的な輸出産地のモデル形成を推進しています。
令和5(2023)年度は、全国で12地区が採択されており、採択地区では、都道府県や農協、地域商社等の生産から流通・販売に至る関係者が一体となって輸出の推進体制の整備を図っています。
(輸入規制措置の撤廃・緩和が進展)
東京電力福島第一原子力発電所(とうきょうでんりょくふくしまだいいちげんしりょくはつでんしょ)の事故に伴い、55か国・地域において、日本産農林水産物・食品の輸入停止や放射性物質の検査証明書等の要求、検査の強化といった輸入規制措置が講じられていました。これらの国・地域に対し、政府一体となってあらゆる機会を捉えて規制の撤廃に向けた粘り強い働き掛けを行ってきた結果、令和5(2023)年度においては、輸入規制措置がEU等で撤廃され、規制を維持する国・地域は7にまで減少しました。
動植物検疫協議については、農林水産業・食品産業の持続的な発展に寄与する可能性が高い輸出先国・地域や品目から優先的に協議を進めています。令和5(2023)年度は、タイ及びニュージーランド向けのかんきつ類の輸出検疫条件が緩和されました。また、国内では各地で高病原性鳥インフルエンザや豚熱(ぶたねつ)が発生していますが、発生等がない地域から鶏卵・鶏肉や豚肉の輸出が継続できるよう、主な輸出先国・地域との間で協議を行っています。
このほか、輸出向けHACCP(*1)等対応の施設・機器整備や、地域の食品製造事業者等が連携した加工食品の輸出促進の取組等を支援しています。
*1 第1章第6節を参照
(2)主な輸出重点品目の取組状況
(コメ・コメ加工品の輸出額は前年に比べ増加)
商業用のコメの輸出額は、日本食レストランやおにぎり店等の需要開拓により、近年増加傾向にあります。令和5(2023)年は、前年に比べ27.5%増加し94億1千万円となりました(図表1-7-3)。また、パックご飯や米粉・米粉製品を含めた輸出額は、前年に比べ26.8%増加し104億9千万円となりました。
農林水産省では、輸出ターゲット国・地域として設定している香港、シンガポール、米国、中国、台湾を中心に、海外市場開拓や大ロットでの輸出用米の生産に取り組む産地の育成を進めていくこととしています。
(牛肉の輸出額は前年に比べ増加)
牛肉の輸出額は、我が国が誇る和牛の品質の高さが世界中で認められ、人気が高まっていることを背景として、近年増加傾向で推移しています。令和5(2023)年は、台湾や香港で外食需要が回復したこと等から、前年に比べ11.2%増加し578億円となりました(図表1-7-4)。
農林水産省では、畜産農家、食肉処理施設、輸出事業者等が連携して産地主導で取り組む新たな商流構築等を支援するとともに、輸出認定食肉処理施設の増加に向けた施設整備を支援しています。
(緑茶の輸出額は前年に比べ増加)
緑茶の輸出額は、海外の日本食ブームや健康志向の高まり等を背景として近年増加傾向で推移しています。令和5(2023)年は、前年に比べ33.3%増加し292億円となっており、平成25(2013)年と比べると約4.4倍に増加しています(図表1-7-5)。
また、有機栽培茶は海外でのニーズも高く、有機同等性(*1)の仕組みを利用した輸出量は増加傾向にあります。令和4(2022)年は前年に比べ2.3%増加し過去最高の1,342tとなりました。特にEUや米国が大きな割合を占めています。
*1 相手国・地域の有機認証を自国・地域の有機認証と同等のものとして取り扱うこと
(事例)海外に現地合弁企業を設立し、日本茶の販路開拓・拡大を推進(静岡県)


モロッコを拠点に
海外販売される日本茶
資料:Maruzen Tea Morocco
静岡県静岡市(しずおかし)の丸善製茶(まるぜんせいちゃ)株式会社では、茶の集積地であるモロッコでの加工・販売拠点の整備により、日本茶を世界に届ける取組を展開しています。
同社は、主に同県産原料茶の卸売のほか、緑茶等の茶製品の加工・製造を手掛けています。
平成30(2018)年には、海外販路の拡大に向け、茶の包装機械・資材を扱う日本企業と、加工を担うモロッコ企業と組み、現地に3社の合弁会社である「Maruzen Tea Morocco(マルゼンティーモロッコ)」を設立しました。令和元(2019)年には、茶の集積地であるモロッコでの営業許可を受け、日本産茶葉を現地工場で加工・包装し、本格的に輸出を開始しました。
海外輸出の茶を扱うためには、輸出先国・地域の残留農薬基準を満たす必要があり、基準を満たした茶葉を生産者から安定的に購入できるよう、GFPのサポートも活用しながら生産者への指導を実施しています。
同社では、有機JAS認証やエコサート(*)認証、ISO22000を取得し、安全・安心なお茶を海外に届ける体制を整えており、今後は、米国や中東地域での販路開拓・拡大を目指しています。
* エコサートは、フランスに本拠を置く有機農産物・加工食品等の国際認証機関。我が国においては、日本法人のエコサート・ジャパン株式会社が有機登録認証機関となっている。
(果実の輸出額は前年に比べ減少)
果実の輸出額は、我が国の高品質な果実が諸外国・地域で評価され、りんご、ぶどうを中心に近年増加傾向で推移しています。一方、令和5(2023)年は、夏季の高温の影響により収量が減少したこと等から、前年に比べ8.2%減少し290億円となりました(図表1-7-6)。
農林水産省では、りんご等の果樹について、既存園地の活用や水田への新植、省力樹形の導入等によって生産力を強化し、輸出拡大に対応できる生産量の確保を図っていくこととしています。
(事例)自社選果場を基盤とした共同出荷体制を構築し、輸出拡大を推進(山梨県)


シャインマスカットの栽培管理
資料:アグベル株式会社
山梨県山梨市(やまなしし)のアグベル株式会社では、自社選果場を活用した共同出荷体制を構築し、シャインマスカットの輸出拡大や人材育成に注力しています。
令和元(2019)年から香港等向けに輸出を開始した同社では、輸出ロットを確保するため、出荷組合を形成し、同県峡東(きょうとう)地域の農業者約80軒と連携して共同で出荷する体制を構築しています。輸出に当たっては、自社運営の選果場を活用し、選果や梱包(こんぽう)の手間等といった生産者の作業負担を軽減するとともに、残留農薬等の基準を満たす栽培を担保しています。また、市場を通さないことで中間コストを削減しつつ、最短のリードタイムで配送できる仕組みを構築しています。
また、現地ニーズへの細やかな対応のため、自社オリジナルのパッケージを制作し、見た目の上でも差別化するとともに、品質管理担当のスタッフを配置し、海外で好まれる品質の確保を追求しています。
さらに、同社では、業界の若返りを図るため、将来に向けて輸出産地の中核となる若手人材を育成しています。植付けから収入発生までのリードタイムが3~4年を要するぶどうの特性を加味し、独立までの収入の保証や、生産技術の伝授等の独立に向けた支援を実施しています。
同社では、長野県の農業者とも提携し、産地リレーによる持続的で安定した輸出体制を築いており、日本産シャインマスカットの普及に向けて一層の輸出拡大を図っていくこととしています。
(3)海外への商流構築、プロモーションの促進と食産業の海外展開の促進
(海外における日本食レストラン数が拡大)
令和5(2023)年の海外における日本食レストラン数(概数)は、令和3(2021)年の15万9千店から約2割増加し18万7千店となりました(図表1-7-7)。特にアジアでは、コロナ禍を経て、レストラン営業の再開や外出制限の解除、日本食人気の高まり、チェーン展開する食品企業の進出等により約2割の増加となっています。
また、日本産食材を積極的に使用する海外の飲食店や小売店を民間団体等が主体となって認定する「日本産食材サポーター店」は、令和6(2024)年3月末時点で約6千店が認定されています。日本食品海外(にほんしょくひんかいがい)プロモーションセンター(以下「JFOODO(ジェイフードー)」という。)では、世界各地の日本産食材サポーター店等と連携して、日本産食材等の魅力を訴求するプロモーションを実施しています。
(JETRO・JFOODOによる海外での販路開拓支援を実施)
JETRO(*1)では、輸出セミナーの開催、輸出関連制度やマーケット情報の提供、相談対応等の輸出事業者等へのサポートを行っています。また、海外見本市への出展支援、国内外での商談会の開催、サンプル展示ショールームの設置等によるビジネスマッチング支援等により、輸出に取り組む国内事業者への総合的な支援を実施しています。
また、JFOODOでは、「日本産が欲しい」という現地の需要を作り出すため、認定品目団体等と連携した取組を強化するとともに、品目横断的な取組にも着手し、新聞・雑誌や屋外、デジタルでの広告展開、PRイベントの開催といった現地での消費者向けプロモーションを戦略的に実施しています。

海外見本市での日本のブース
資料:独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)
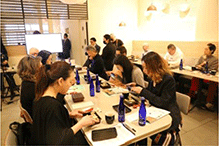
米国の高級和食店の関係者を
対象とした日本茶のセミナー
資料:日本食品海外プロモーションセンター(JFOODO)
*1 トピックス3を参照
(コラム)大規模展示・商談会を活用した農林水産物・食品輸出の取組が進展

国産酒類専用のパビリオン
資料:株式会社日本政策金融公庫

JETROによる食品輸出商談会
資料:独立行政法人日本貿易振興機構
(JETRO)
コロナ禍を経て、日本産農林水産物・食品への関心が高まる中、海外バイヤーにアピールする大規模展示・商談会が対面形式で開催され、積極的な商談等が行われています。
公庫では、魅力ある農林水産物づくりに取り組んでいる農林水産業者や、地元産品を活用したこだわりの食品を製造する食品企業を対象に、広域的な販路拡大の機会を提供する商談会「アグリフードEXPO」を開催しています。令和5(2023)年8月に東京都で開催された同商談会では、国内の農林水産業者や食品企業等465社が出展し、2日間で8,889人の来場者を集めました。展示会場では、輸出向けの特別フロアを設置し、出展者の輸出拡大につながる商談機会を提供したほか、地域性豊かで海外からの評価も高い国産酒類について、専用のパビリオンに集約し、一堂に集まるバイヤーに提案することで、国内外の販路拡大を支援しました。
また、JETROは、同会場内に日本産農林水産物・食品の取扱いを希望する世界18か国19人の海外バイヤーを招へいし、対面形式での食品輸出商談会の開催により、出展者等131社との間で206件の直接商談を実施しました。
海外市場での需要・商流づくりに当たっては、世界各国の優良バイヤーを招へいする国内での大規模展示・商談会や、海外現地での見本市等の場は、重要な商談機会となります。今後とも国内外の大規模展示・商談会等の活用を通じ、我が国農林水産物・食品の輸出拡大が一層進展することが期待されています。
(輸出の後押しとなる事業者の海外展開を支援)

主要な輸出先国・地域において、農林水産物・食品の輸出を行う事業者を包括的・専門的・継続的に支援するため、現地発の情報提供や新たな商流の開拓支援等を行う輸出支援プラットフォームを設置しています。
令和5(2023)年度は、新たに中国(北京、上海、広州、成都)、台湾(台北)、EU(ブリュッセル)、米国(ヒューストン)において輸出支援プラットフォームの拠点を設立し、合計で8か国・地域となっています(*1)(図表1-7-8)。
また、食産業事業者の海外展開を支援するため、海外現地において設備投資等を行う場合の案件形成への支援や資金供給の促進を行うとともに、投資円滑化法(*2)に基づき、輸出に取り組む事業者に投資する民間の投資主体への資金供給の促進に取り組むこととしています。
*1 ( )内は事務局設置都市
*2 正式名称は「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法」
(インバウンドの本格的な回復の動きを捉え、訪日外国人への日本食の理解・普及を推進)
日本政府観光局(にほんせいふかんこうきょく)(*1)(JNTO)の調査によると、個人旅行再開等の水際措置の緩和以降、インバウンドの回復が進む中、令和5(2023)年の訪日外客数は、前年から増加し2,506万6千人にまで回復しています(図表1-7-9)。
このような中、農林水産省を始めとする関係省庁は、海外の消費者に対して我が国の食品の調理方法、食べ方、食体験等を通じた地域の文化とのつながりの発信等を行うとともに、インバウンドの本格的な回復の動きを捉え、訪日外国人旅行者への日本食や食文化の理解・普及を図ることにより、我が国の農林水産物・食品の輸出市場とインバウンド消費を拡大する取組を支援しています。
これを受けて、JETRO・JFOODOとJNTOは、デジタルマーケティングや海外でのプロモーションイベント等で連携し、我が国の農林水産物・食品の輸出市場とインバウンド消費を相乗的に拡大することを目指しています。
*1 正式名称は「独立行政法人国際観光振興機構」
(「SAVOR JAPAN」認定地域に2地域を追加)
増大するインバウンドが、訪日外国人旅行者の更なる増加と農林水産物・食品の輸出増大につながるといった好循環を構築するためには、訪日外国人旅行者を日本食・食文化の「本場」である農山漁村に呼び込むことが重要です。このため、農林水産省は、食と食文化によりインバウンド誘致を図る農泊地域等を「農泊 食文化海外発信地域(SAVOR JAPAN(セイバージャパン))」に認定することで、ブランド化を推進する取組を行っています。インバウンドの本格的な回復に伴う訪日外国人旅行者の増加を見据え、令和5(2023)年度については新たに2地域(*1)を認定し、認定地域は令和5(2023)年10月時点で42地域となりました。

「SAVOR JAPAN(農泊 食文化海外発信地域)」について
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/savorjp/
*1 令和5(2023)年度に認定された地域は、静岡県富士山麓・伊豆半島地域(わさび)、福岡県八女市(八女茶)の2地域。( )内は、その地域の食
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883











