第6節 新たな価値の創出による需要の開拓

食品産業は、農業と消費者の間に位置し、食料の安定供給を担うとともに、国産農林水産物の主要な仕向先として、消費者ニーズを生産者に伝達する役割を担っています。また、多くの雇用・付加価値を生み出すとともに、環境負荷の低減等にも重要な役割を果たしています。
本節では、食品産業の動向やJAS(*1)を始めとした規格・認証の活用等について紹介します。
*1 Japanese Agricultural Standardsの略で、日本農林規格のこと
(1)食品産業の競争力の強化
(食品産業の国内生産額は96兆1千億円)
食品産業の国内生産額については、近年おおむね横ばい傾向で推移しており、令和4(2022)年は新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ外食支出が回復しつつあること等から、前年に比べ4.9%増加し96兆1千億円となりました(図表1-6-1)。このうち食品製造業では水産食料品や清涼飲料の生産額が増加したこと等から前年に比べ3.7%増加し38兆4千億円となり、関連流通業は前年に比べ2.6%増加し36兆4千億円となりました。
一方、全経済活動に占める食品産業の割合は前年に比べ0.2ポイント減少し8.6%となりました。このほか、食品産業の企業規模別の構成を見ると、大半が中小零細規模の企業となっています(図表1-6-2)。
(経営者の高齢化により事業継承の課題を抱える企業が多数存在)
中小企業が大半を占める食品産業では、経営者の高齢化により事業継承の課題を抱える企業が多くなっています(図表1-6-3)。
国内市場を対象としてきた食品事業者の中には、国内市場が縮小傾向にあること等を背景として、自身の世代での廃業を考え、将来に向けた生産拡大や設備の更新等の追加投資を控えるなど、撤退を視野に入れている事業者も見られています。
食料には食品製造業による加工を経て消費者に届くものが多いほか、地域の農林水産業と密接に関係し地域の食文化を反映する加工食品も多いことから、食品製造業を次世代につなげていくことが重要であり、食品製造業の事業継承の円滑化や食品産業の体質強化を図っていく必要があります。
(食品産業と農業の連携を推進)
食品産業を持続可能なものとするため、食品産業における国産原材料の利用促進や生産性の向上等を推進し、その体質強化・事業継続を図ることによって、消費者に食品や豊かな食文化を提供するとともに、原材料調達や製造工程等において持続性に配慮した食品産業への移行を一層推進していくことが重要となっています。
このため、農林水産省では、国産原材料への切替えによる新商品開発や産地との連携強化等を支援しています。
また、地域の食品産業を中心とした多様な関係者が参画するプラットフォームを形成し、地域の農林水産物を活用したビジネスを継続的に創出する仕組みである「地域食品産業連携プロジェクト」(LFP(*1))を推進しています。

地域食品産業連携プロジェクト(LFP)推進事業
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/seisaku/lfp-pj.html
*1 Local Food Projectの略
(事例)契約栽培を通じて原料の安定調達と産地との連携強化を推進(兵庫県)
兵庫県神戸市(こうべし)の食品事業者である株式会社マルヤナギ小倉屋(おぐらや)では、契約栽培を通じて原料の安定調達を図るとともに、産地との連携を強化する取組を推進しています。
同社は、豆、昆布、もち麦等の製造販売を行っており、独自の蒸し技術により開発した「蒸し大豆」は、大豆のおいしさと栄養価値を併せ持ち、食の洋風化にも対応する商品として市場規模が拡大しています。
一方で、蒸し大豆に適した品種である「北海道産トヨムスメ」は、農業者にとって作りにくく衰退品種となっていることから、トヨムスメの契約栽培を維持・拡大するために、栽培奨励金を支給するなどの施策を講じています。また、同社では、より安全で安心な商品を消費者に提供するため、環境に優しい農業を目指し、減農薬・減化学肥料による特別栽培大豆の契約栽培を奨励しています。さらに、我が国では栽培が難しい有機無農薬栽培大豆についても、技術力の高い農業者に依頼し、契約栽培による原料の確保に取り組んでいます。
このほか、同社では、食物繊維の摂取不足の解消に優れた「蒸しもち麦」を開発し、基幹工場が立地する同県加東市(かとうし)や地元の農協と連携し、地元産原料の確保に努めるとともに、もち麦の健康価値を伝える啓発活動に取り組み、地域農業の振興にも寄与しています。
同社では、「伝統食材のすばらしさを、次の世代へ」つなげていくことを目標としており、今後とも国内原料産地との連携を深化させていくこととしています。


生産者と連携した大豆作り
資料:株式会社マルヤナギ小倉屋

契約栽培を行っている大豆の圃場
資料:株式会社マルヤナギ小倉屋
(フードテック推進ビジョンに基づき、新市場創出のための環境整備を推進)
世界の食料需要の増大に対応した持続可能な食料供給のほか、個人の多様なニーズを満たす豊かで健康な食生活や食品産業の生産性の向上の実現が求められている中、フードテック(*1)を活用した新たなビジネスの創出への関心が世界的に高まっています。
そのような中、食品企業、ベンチャー企業、研究機関、関係省庁等に所属する者で構成される「フードテック官民協議会」では、令和5(2023)年2月に「フードテック推進ビジョン」を策定し、今後のフードテックの推進に当たり、目指す姿や必要な取組等を整理し、フードテックの6分野(*2)について、具体的な課題を工程表として整理しています。
農林水産省では、これらに沿って、オープンイノベーションとスタートアップの創業を促進するとともに、新たな市場を作り出すための環境整備を進め、フードテックの積極的な推進に取り組んでいくこととしています。
*1 生産から流通・加工、外食、消費等へとつながる食分野の新しい技術及びその技術を活用したビジネスモデルのこと
*2 6分野は、植物由来の代替たんぱく質源、昆虫食・昆虫飼料、スマート育種のうちゲノム編集、細胞性食品、食品産業の自動化・省力化、情報技術による人の健康実現
(コラム)2025年の大阪・関西万博に向けて、食の多様性に配慮した環境を整備
我が国では、令和7(2025)年に、大阪湾(おおさかわん)の人工島である夢洲(ゆめしま)を会場として、「2025年日本国際博覧会(にっぽんこくさいはくらんかい)」(以下「大阪(おおさか)・関西万博(かんさいばんぱく)」という。)を開催することとしており、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとし、ポストコロナの時代に求められる社会像を世界と共に提示していくこととしています。
公益社団法人関西経済連合会(かんさいけいざいれんごうかい)では、参画団体とともに、大阪・関西万博の開催を見据え、ムスリムやベジタリアン(菜食主義者)、ヴィーガン(完全菜食主義者)、食物アレルギーのある人等に配慮するといった食の多様性に対応でき、多様な信条や考えを持つ訪日外国人旅行者が安心して食事ができる環境を整える「食の多様性推進ラウンドテーブル(*)」を設立し、取組を推進しています。
今後は、食の多様性に対応した新たな名物料理の開発・販売や、ピクトグラム等を活用したメニュー表示の普及等を進めることにより、訪日外国人旅行者等が安心して食事を楽しめる環境の実現を後押しすることとしています。
なお、農林水産省では、大阪・関西万博に向けて、輸出拡大やインバウンド需要の拡大を図るため、和食や食文化、農泊体験といった我が国の農林水産・食品産業の有する魅力を世界に向けて発信するとともに、みどり戦略が目指す、環境と調和した持続可能な食料システムの姿を発信することとしています。
* 株式会社JTB及び株式会社YRK andが座長を務めている。

会場のイメージ
資料:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
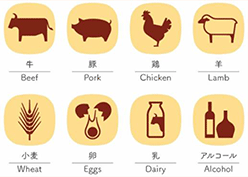
食材表示ツールのピクトグラム
資料:株式会社フードピクト
(2)食品流通の合理化
(農林水産物・食品分野で物流効率化に取り組む事業者数は増加傾向)
農林水産物・食品を消費者に届ける役割を担う食品流通業は、売上高に占める経費(販売費及び一般管理費)の割合が高く、営業利益率が低い状態にあります。また、食品流通はトラック輸送に大きく依存しており、「物流の2024年問題」による輸送費の上昇も懸念されています。このような中、食品流通業を持続的に発展させていくためには、技術の活用等を通じた流通の非効率性の解消が不可欠です。
このため、農林水産省では、パレットや段ボールサイズ等の物流標準化、ICTやロボット技術を活用した業務の省力化・自動化、コールドチェーンの整備による流通の高度化等の取組を支援しています。具体的には、青果物と花きの流通標準化ガイドラインの現場への普及、産地と卸売業者の間で出荷情報を共有するデータ連携システムの構築、流通合理化に対応した卸売市場や中継共同物流拠点の整備等を行っています。
また、「物流革新に向けた政策パッケージ(*1)」に基づき、自主行動計画の着実な実施のほか、一層の物流標準化や中継共同物流拠点の整備等を推進しています。
このような中、農林水産物・食品等の流通合理化に取り組む事業者数(*2)については、令和4(2022)年度は前年度に比べ42件増加し164件となりました(図表1-6-4)。
他方、農林水産物・食品の物流の現場での取組も進展しており、九州では、青果卸売業者が、九州各県の荷物を集約して大ロット輸送、モーダルシフトを行うための中継共同物流拠点を整備する取組を進めています。また、東北・北陸では、生産者団体が鉄道事業者と連携し、青森県から北陸を経由して大阪府へ米等を輸送する貨物列車の定期運行を開始しています。さらに、食品製造業者と生産者団体が、産地から加工工場に米を運ぶトラックを活用し、加工工場から産地に加工食品を運ぶことにより空車区間を解消する「ラウンド輸送」を開始するといった取組も見られています。
*1 トピックス2を参照
*2 「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」に基づく総合効率化計画又は「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に基づく食品等流通合理化計画の認定件数
(卸売市場の物流機能を強化)
卸売市場は、野菜、果物、魚、肉、花き等の日々の食卓に欠かすことのできない生鮮品等を、国民に円滑かつ安定的に供給するための基幹的なインフラであり、多種・大量の物品の効率的・継続的な集分荷、公正で透明性の高い価格形成等の重要な機能を担っています。
食料安全保障の強化が求められる中、持続的に生鮮食料品等の安定供給を確保していくため、単に老朽化に伴う施設の更新のみならず、物流施策全体の方向性と調和し、標準化・デジタル化に対応した卸売市場の物流機能を強化することが必要となっています。
農林水産省では、物流機能を強化するために、コールドチェーンの確保等に資する整備や中継共同物流拠点の施設整備を支援することとしています。
(3)規格・認証の活用
(JAS普及推進月間に新たな取組を展開)
近年、輸出の拡大や市場ニーズの多様化が進んでいることから、農林水産省では、JAS法(*1)に基づき、農林水産物・食品の品質だけでなく、事業者による農林物資の取扱方法、生産方法、試験方法等について認証する新たなJAS制度を推進しています。令和5(2023)年度は新たに木質ペレット燃料のJASを制定したほか、規格の更なる活用を視野に、既存のJASの見直しを行いました。さらに、令和5(2023)年11月のJAS普及推進月間に、新たな取組として、JASの認知を高め、活用を促進するためのポスターを作成し、周知活動を行いました。事業者や産地の創意工夫により生み出された多様な価値・特色が戦略的に活用され、我が国の食品・農林水産分野の競争力の強化につながることが期待されています。
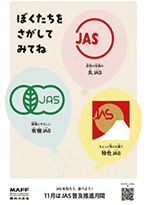
JAS普及推進月間を
呼び掛けるポスター
また、有機農産物加工食品について既に同等性を相互承認している米国やEU等と有機酒類の同等性交渉を進めています。令和5(2023)年8月にはカナダ、令和6(2024)年1月には台湾との間で、有機酒類の同等性が相互承認されました。今後、我が国の有機食品の輸出拡大につながることが期待されています。
このほか、農林水産省では、輸出促進に向け海外との取引を円滑に進めるための環境整備として、産官学の連携により、ISO(*2)規格等の国際規格の制定・活用を進めています。
*1 正式名称は「日本農林規格等に関する法律」
*2 International Organization for Standardizationの略で、国際標準化機構のこと
(JFS規格の取得件数は2,509件に増加)
食品の民間取引において、安全管理の適正化・標準化が求められるようになりつつあり、食品安全マネジメント規格への関心が高まっています。
日本発の食品安全マネジメントに関する認証規格である「JFS(*1)規格」の国内取得件数(JFS-A/B/C規格)は、運用開始以降、年々増加してきており、令和6(2024)年3月末時点で2,509件(*2)となりました(図表1-6-5)。
今後、JFS規格の更なる普及により、我が国の食品安全レベルの向上や食品の輸出力強化が期待されます。
農林水産省では、JFS規格の認証取得の前提となるHACCP(*3)に沿った衛生管理の円滑な実施を図るための研修や海外における認知度向上のための周知、取得ノウハウ等を情報発信して横展開する取組等を支援しています。
*1 Japan Food Safetyの略
*2 製造セクター以外の規格を含めた国内取得総件数は2,548件(令和6(2024)年3月末時点)
*3 Hazard Analysis and Critical Control Pointの略で、危害要因分析及び重要管理点のこと。我が国においては、令和3(2021)年6月から、原則全ての食品等事業者についてHACCPに沿った衛生管理が義務化されている。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883










