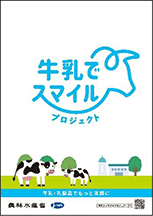第5節 食料消費の動向
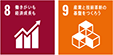
我が国においては、人口減少や高齢化により食市場が縮小することが見込まれるほか、社会構造やライフスタイルの変化に伴い、食の外部化や簡便化が進展することが見込まれています。また、足下では、食料品価格の上昇が見られるほか、食料品の価格高騰が食料消費に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。
本節では、食料消費や農産物・食品価格の動向、国産農林水産物の消費拡大の取組について紹介します。
(1)食料消費の動向
(食料の消費者物価指数は上昇傾向で推移)
消費者物価指数は上昇基調で推移しており、総合の消費者物価指数は令和5(2023)年10月に107.1となっています(図表1-5-1)。また、生鮮食品を除く食料の消費者物価指数は、同年11月に115.2となり、前年同月比で6.7%上昇しました。
(食料品の価格上昇に直面する消費者の購買行動に変化)
食料の消費者物価指数が上昇傾向で推移する中、食料品の価格上昇に直面する消費者の購買行動に変化が見られています。
内閣府が令和5(2023)年9~10月に実施した世論調査によると、食品価格値上げの許容度について、「1割高までであれば許容できる」と回答した人が37.5%で最も多くなりました(図表1-5-2)。また、値上げを許容できると考えている人は75.5%となっています。一方、直近2年の食品価格の高騰への対応として、「価格の安いものに切り替えた」が59.5%で最も多く、次いで「外食の機会を減らした」が42.2%となっています(図表1-5-3)。
食料品は、購入頻度の高い品目が多く、消費者が生活の中でその価格変化に直面しやすい商品であることから、食料品の価格高騰が食料消費に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。
(消費者世帯の食料消費支出は名目で増加、実質で減少)
消費者世帯(二人以上の世帯)における1人当たり1か月間の「食料」の支出額(以下「食料消費支出」という。)について、令和5(2023)年の平均値(*1)は、名目で約2万8千円となり、前年に比べ6.0%上昇しました。一方、物価変動の影響を除いた実質(*2)では約2万5千円となり、前年に比べ1.8%減少しました。
また、同年における食料消費支出を前年同月比で見ると、実質では前年を下回る状況が続いた一方、名目では前年を上回る状況が続きました(図表1-5-4)。食料価格の上昇により、食料消費支出が増加し、家計の負担感の増加につながっていることがうかがわれます。
1 各月ごとに算出した1人当たり1か月間の食料消費支出を基に、年間の平均値を算出したもの
2 令和5(2023)年各月の食料消費支出について、消費者物価指数(令和2(2020)年基準)を用いて物価の上昇・下落の影響を取り除いた上で、年間の平均値を算出したもの
(和牛肉の需要が減退し、和牛枝肉の卸売価格が下落)
物価高騰に伴う消費者の生活防衛意識の高まりにより、小売向けの引合いが弱まったこと等から、和牛肉の需要の減退が見られ、令和5(2023)年の和牛枝肉の卸売価格は、同年1月から11月まで前年同月の価格を下回って推移しました(図表1-5-5)。
農林水産省では、緊急的かつ強力に和牛肉の需要を喚起し、需給状況を改善させるため、令和5(2023)年度補正予算において、和牛肉の新規需要開拓、消費拡大・理解醸成やインバウンド需要の喚起を支援しています。
(令和5(2023)年の外食支出は、令和元(2019)年の約9割の水準で推移)
家計における食料支出の状況を見ると、外食への支出は、令和2(2020)年3月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により大きく減少しました。その後、コロナ禍から平時へと移行する中、令和5(2023)年の外食支出は、インバウンド需要が回復基調にある一方、物価上昇による消費者の生活防衛意識の高まり等の影響もあり、令和元(2019)年の約9割の水準で推移しています(図表1-5-6)。
(パブレストラン・居酒屋の売上高は、令和元(2019)年の約6~7割の水準で推移)
一般社団法人日本(にほん)フードサービス協会(きょうかい)の調査によると、令和5(2023)年1月以降の外食産業全体の売上高は、コロナ禍以前である令和元(2019)年同月を上回る100~120%の間で推移しました。
一方、一部の業態、特にパブレストラン・居酒屋の売上高については、令和元(2019)年同月比で見ると約6~7割の水準で推移しており、他の業態を大きく下回っています(図表1-5-7)。新型コロナウイルス感染症の影響下では接触機会や対面の機会が減少し、宴会の機会等も減少しましたが、コロナ禍から平時へと移行する中にあっても、夜間に酒類を提供する業態ではコロナ禍以前の宴会需要が十分には戻っておらず、消費者の価値観や生活様式が変化している様子がうかがわれます。
(食品類のEC市場は年々拡大)
経済産業省の調査によると、令和4(2022)年の「食品、飲料、酒類」(以下「食品類」という。)のEC(*1)市場規模(BtoC)は、前年に比べ9.2%増加し2兆7,505億円となりました。この結果、令和4(2022)年の食品類のEC化率は、前年と比べ0.4ポイント増加し4.2%となりました(図表1-5-8)。食品類のEC市場は年々拡大しており、スマートフォン等の身近なIT端末の普及や共働き世帯の増加といった社会構造の変化と共に、多くの人々にとって日常的な取引形態となっています。
また、近年、料理の調理手順等を動画で視聴できる、いわゆる「料理レシピ動画」を利用する消費者が増加しており、Webサイトやアプリで多様な料理レシピを配信するサービスも広がりを見せています。マルハニチロ株式会社が令和2(2020)年7月に実施した調査によると、使用している料理レシピは、「レシピサイト・レシピアプリ」が74.3%で最も多くなっています(図表1-5-9)。今後、このようなサービスの活用と合わせ、消費者が料理や食により一層関心を持ち、食の楽しさを実感する機会が増えることが期待されています。
1 Electronic Commerceの略で、電子商取引のこと
(食の外部化・簡便化が進展)
我が国においては、単身世帯の増加や女性の雇用者の増加等が見られ、社会情勢が変化する中、食に関して外部化・簡便化の進展が見られています。
一般社団法人日本惣菜協会(にほんそうざいきょうかい)の調査によると、中食(惣菜)市場の売上高については近年増加傾向で推移しており、令和4(2022)年は平成25(2013)年比で117.6%の10兆5千億円となっています(図表1-5-10)。
また、米の消費については、家庭でごはんを炊いて食べる家庭内消費の割合が減少し、中食や外食で食べる業務用消費の割合が拡大しています(図表1-5-11)。令和4(2022)年度の業務用向けの米の消費は全体の3割を超えており、今後も業務用需要のウェイトは拡大傾向で推移していくものと見込まれています。
農林水産省では、食の外部化・簡便化の進展に合わせ、中食・外食における国産農産物の需要拡大を図ることとしています。
(2)農産物・食品価格の動向
(牛肉・豚肉・鶏肉の小売価格はやや上昇、鶏卵の小売価格は下落基調に転換)
令和5(2023)年度における国産牛肉の小売価格は、流通コストの上昇等に伴い、やや上昇傾向で推移しました(図表1-5-12)。また、豚肉の小売価格は、輸入豚肉価格の高騰等により、やや上昇傾向で推移しました。さらに、鶏肉の小売価格は、輸入鶏肉の価格の高騰等により、やや上昇傾向で推移しました。
一方、鶏卵の小売価格は、高病原性鳥インフルエンザの影響による供給減等により上昇傾向で推移していましたが、夏季以降は需給が緩和し下落基調に転換しています。
(米の相対取引価格は前年産より上昇、野菜の小売価格は品目ごとの供給動向に応じ変動)
令和5(2023)年産米の令和6(2024)年2月までの相対取引価格は、民間在庫が減少したこと等から年産平均で玄米60kg当たり1万5,276円となり、前年産に比べ10.3%上昇しました(図表1-5-13)。
また、野菜は天候によって作柄が変動しやすく、短期的には価格が大幅に変動する傾向があります。令和5(2023)年においては、レタスは7~8月の好天の影響により出荷量が増加し、8月の小売価格は平年と比べて低下した一方、11~12月の干ばつ等の影響により出荷量が減少し、12月に大きく上昇しました(図表1-5-14)。トマトは夏の高温の影響による着果不良や生育前進によって出荷量が減少し、9~11月の小売価格は平年と比べて大きく上昇しました。たまねぎは北海道における8~9月の高温・干ばつの影響により出荷量が減少し、11月以降小売価格は平年と比べて大きく上昇しました。
(食パン・豆腐の小売価格は上昇傾向で推移)
穀物等の国際価格の上昇により、輸入原料を用いた加工食品の小売価格は上昇傾向で推移しています(図表1-5-15)。
食パンの小売価格は、原料小麦や包材、燃料等の価格上昇を受けて、令和5(2023)年12月には551円/kgとなり、前年同月比で5.8%上昇しました。また、豆腐の小売価格は、原料大豆や包材、燃料等の価格上昇を受け、一部の小売事業者において価格転嫁が進んだことから、令和5(2023)年6月には265円/kgとなり、前年同月比で11.8%上昇しました。このほか、食用油(サラダ油)の小売価格は、令和5(2023)年4月に506円/kgとなって以降、横ばい傾向で推移しています。
(3)国産農林水産物の消費拡大
(「米・米粉消費拡大推進プロジェクト」を開始)
米(*1)の1人当たりの年間消費量については、食生活の変化等により減少傾向で推移しており、令和4(2022)年度は前年度に比べ0.5kg減少し50.9kgとなりました(図表1-5-16)。
農林水産省では、米の消費を喚起する取組として「やっぱりごはんでしょ!」運動を展開しており、「BUZZ MAFF(ばずまふ)(*2)」での動画投稿やSNS・Webサイトでの情報発信等を実施しています。
また、令和5(2023)年8月から、国内で自給可能な食料である米や米粉の魅力を広め、消費拡大を図ることを目的として、「米・米粉消費拡大推進プロジェクト」を立ち上げました。令和5(2023)年度は、テレビCMの放映や特設サイト・SNSでの情報発信、米粉アンバサダーによる米粉料理の紹介等の取組を実施しました。
1 主食用米のほか、菓子用・米粉用の米を含む。
2 第1章第8節を参照
(「野菜を食べようプロジェクト」を展開)
野菜の1人当たりの年間消費量については、食生活の変化等により減少傾向で推移していますが、令和4(2022)年度は前年度と同じ88.1kgとなりました(図表1-5-17)。また、厚生労働省の調査によると、1人1日当たりの野菜摂取量は、年齢階層別で若い世代ほど少ない傾向が見られています。
農林水産省では、1人1日当たりの野菜摂取量を、目標値の350gに近づけることを目的として、「野菜を食べようプロジェクト」を実施しています。令和5(2023)年度は、同プロジェクトの一環として、漬物を通じた野菜の消費拡大を図るため、チラシによる情報発信、Webシンポジウム等の取組を実施しました。また、8月31日の「野菜の日」に合わせ、日頃の野菜摂取状況が把握できる測定機器を農林水産省内に設置し、職員や来庁者に対して日頃の食生活に適量の野菜を取り入れる習慣づくりを促す機会を設けました。
(茶の消費拡大に向け「出かけよう、味わおう!キャンペーン」を開始)
緑茶(*1)の1世帯当たりの年間消費量については近年減少傾向で推移しており、令和5(2023)年は前年に比べ25g減少し676gとなりました(図表1-5-18)。
農林水産省では、令和5(2023)年の新茶シーズンの本格化に併せて、観光需要が回復する機会を捉え、産地や事業者と連携して「出かけよう、味わおう!キャンペーン」を、同年4月から開始しました。
全国の茶産地での茶摘み体験や消費地も含めたお茶の淹(い)れ方体験、新茶の試飲会等の情報発信を行い、多くの消費者に日本茶の良さを体験してもらうなど、一層の消費拡大に取り組んでいます。
1 緑茶には、茶飲料を含まない。
(砂糖の需要拡大に向け「ありが糖運動」を展開)
砂糖の年間消費量については近年減少傾向で推移していますが、令和4(2022)砂糖年度は経済活動の回復等もあり前砂糖年度に比べ2千t増加し174万8千tとなりました(図表1-5-19)。
農林水産省では、砂糖の新規需要拡大のための商品開発等を支援しています。また、砂糖関連業界等による取組と連携しながら、砂糖の需要や消費の拡大を図る「ありが糖運動」を展開しており、WebサイトやSNSを活用しながら、情報発信を行っています。
(「花いっぱいプロジェクト」を展開)
切り花の1世帯当たりの年間購入額については近年減少傾向で推移していますが、令和5(2023)年は前年に比べ42円増加し8,034円となりました(図表1-5-20)。
農林水産省では、令和9(2027)年に神奈川県横浜市(よこはまし)で開催される2027年国際園芸博覧会を契機とした需要拡大を図るため、「花いっぱいプロジェクト」を展開しています。花きをより身近に感じてもらうため、花き業界と協力し、クリスマスやバレンタイン等のイベントに合わせた花贈りの提案や花きの暮らしへの取り入れ方等について、BUZZ MAFF等による広報活動を進めています。
(「牛乳でスマイルプロジェクト」を展開)
牛乳乳製品の1人当たりの年間消費量については、チーズや生クリームの消費量増加に伴い増加傾向にありましたが、令和4(2022)年度はヨーグルト等の原料となる脱脂粉乳の需要低迷等により前年度に比べ0.5kg減少し93.9kgとなりました(図表1-5-21)。
農林水産省では、酪農・乳業関係者のみならず、企業・団体や地方公共団体等の幅広い参加者と共に、共通ロゴマークにより一体感を持って、更なる牛乳乳製品の消費拡大に取り組むため、一般社団法人Jミルクと共に、「牛乳でスマイルプロジェクト」を展開しています。令和5(2023)年度においては、6月1日の「牛乳の日」、6月の「牛乳月間」に併せて、牛乳乳製品の消費拡大に向けた取組を実施しました。
(コラム)訪日外国人旅行者に国産牛乳乳製品の魅力を発信
酪農経営は飼料価格の高止まり等により生産コストが上昇し厳しい状況にある一方、生乳の需給は脱脂粉乳を中心に緩和傾向で推移しており、牛乳乳製品の需要拡大を図ることが不可欠となっています。
このような中、一般社団法人Jミルクでは、令和5(2023)年度において、今後増加が期待される訪日外国人旅行者に牛乳乳製品の魅力を発信し、国内外の需要を拡大する取組を実施しています。
同団体は、訪日外国人旅行者に我が国の牛乳乳製品のおいしさを知ってもらい、インバウンドの需要喚起を図るため、同年6月に、成田空港(なりたくうこう)で常温保存可能なロングライフ牛乳をウェルカムミルクとして配布しました。受け取った訪日外国人旅行者からは「とてもおいしい」、「どこで購入できるか教えてほしい」といった声が聞かれ、消費拡大に弾みがつくことが期待されています。
また、全国の主要国際空港でもウェルカムミルクの配布イベントを実施したほか、国内の観光地等で外国人旅行者に国産牛乳乳製品を用いた料理やデザート等の試食販売を実施しました。
同団体では、今後とも訪日外国人旅行者に国産牛乳乳製品の魅力を知ってもらい、帰国後も日本産の牛乳乳製品を購入してもらうことで、牛乳乳製品の輸出促進につなげることを目指しています。

ウェルカムミルクを受け取った訪日外国人旅行者
資料:一般社団法人Jミルク
(「#食べるぜニッポン」キャンペーンを展開)
令和5(2023)年8月に開始されたALPS処理水(*1)の海洋放出に伴い、中国等による全面的な輸入規制措置等が導入されたことにより、影響を受ける水産物の国内での消費拡大が重要となりました。このような状況の中、農林水産省では、水産物の国内消費を応援するため、同年9月からSNSを中心に「#食べるぜニッポン」キャンペーンを実施しています。「#食べるぜニッポン」という共通のハッシュタグやロゴ画像を用いて水産物の写真の投稿を呼び掛けるとともに、農林水産省Webサイトに専用ページを開設し、水産物消費に対する応援の輪の拡大に努めています。
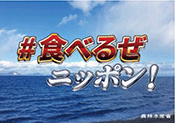
#食べるぜニッポン
1 トピックス3を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883