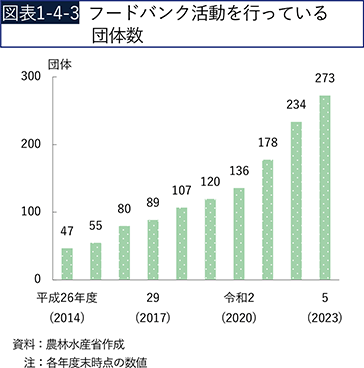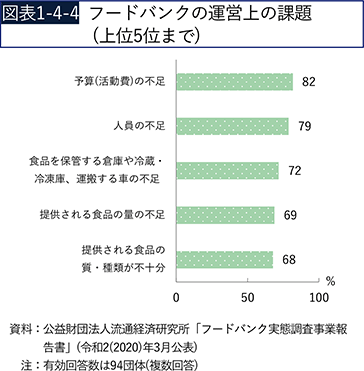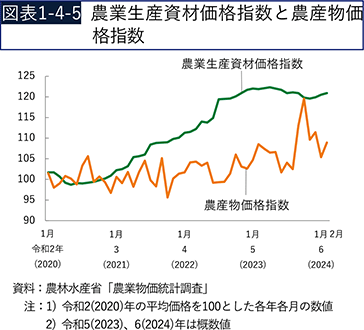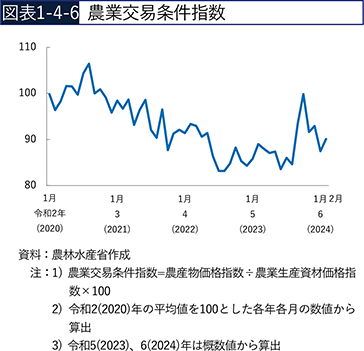第4節 円滑な食品アクセスの確保と合理的な価格の形成に向けた対応
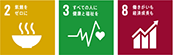
我が国においては、全ての国民が健康的な生活を送るために必要な食品を入手できない、いわゆる「食品アクセス」の問題への対応が重要な課題となっています。また、長期にわたるデフレ経済下で、農業・食品産業においては、生産コストが上昇しても、それを販売価格に反映することが難しい状況も見られています。
本節では、円滑な食品アクセスの確保に向けた対応や合理的な価格の形成のための取組等について紹介します。
(1)円滑な食品アクセスの確保に向けた対応
(食品へのアクセスが十分でない者が一定数存在)
公庫が令和6(2024)年1月に実施した調査によると、食料品店舗へのアクセスについて、「公共交通手段の利用又は徒歩により、15分以内で食料品店舗にアクセスすることができる」と回答した人は65.8%となっている一方、「15分以内ではできない」と回答した人は34.2%となっています(図表1-4-1)。
また、同調査によると、健康的な食事のための食料品の購入が手頃な価格でできているかどうかについて、「できている」と回答した人は59.9%となっている一方、「できていない」と回答した人は40.1%となっています(図表1-4-2)。我が国においては、平常時においても円滑な食品アクセスの確保に課題があることがうかがわれます。
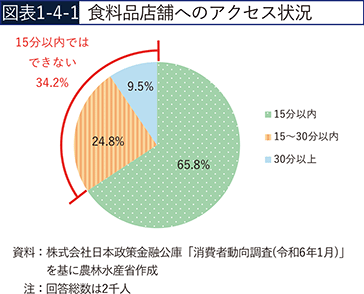
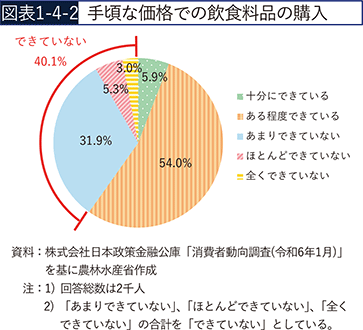
(地域の関係者が連携する体制づくりや買い物支援等の取組を促進)
人口減少・高齢化等により小売業や物流等の採算がとれない地域が発生し、このような地域を中心に、食品を簡単に購入できない、買い物困難者等が増加しています。このような問題に対処するため、地方公共団体や民間事業者では、地域の特色に応じてコミュニティバスや乗合タクシーの運行、移動販売車の運営、買い物代行サービスの提供等の取組を行っていますが、対応が追いつかない状況にあります。くわえて、「物流の2024年問題」により物を届けられない問題は一層深刻化することも考えられます。
また、非正規雇用の増加等により、低所得者層が増加しつつあり、生活困窮者等の経済的理由で十分かつ健康的な食事が取れていない者に対し、フードバンクやこども食堂等による無償又は安価で食品や食事を提供する取組が広がっています。一方、取り扱う食品には偏りがあり、フードチェーンがつながっていないなど、地域の関係者による各々の取組では不十分な状況も見られます。
このため、農林水産省では、産地から消費地までの幹線物流の効率化とともに、地域ごとに、食品アクセスに関する課題や実態を把握し、その課題解決に向けて、地方公共団体を中心に、生産者・食品事業者、農業協同組合(以下「農協」という。)、社会福祉協議会、特定非営利活動法人(以下「NPO(*1)法人」という。)等の地域の関係者が連携する体制づくりを図ることとしています。また、移動販売、無人型店舗、ドローン配送等の地域に応じたラストワンマイル物流の強化に向けた取組や買い物支援の取組、フードバンクやこども食堂等の取組を後押しすることとしています。
1 Non Profit Organizationの略で、非営利団体のこと
(事例)フードバンク協議会が中心となり県域単位で食料支援を展開(福岡県)


フードバンク団体
へのレタスの斡旋
資料:一般社団法人福岡県フードバンク
協議会
福岡県古賀市(こがし)に本拠を置く一般社団法人福岡県(ふくおかけん)フードバンク協議会(きょうぎかい)では、フードバンク活動に関わる関係者が一体となって、地域で生じた未利用食品を地域福祉に活用する取組を県内全域で展開しています。
同協議会は、未利用食品を必要とする人に無償で提供するフードバンク活動が県内で安定的に継続・発展していくことを目指し、福岡県の支援の下、生活協同組合(以下「生協」という。)や全国農業協同組合連合会福岡県(ふくおかけん)本部、NPO法人等を構成員として、平成31(2019)年4月に設立されました。
フードバンク活動においては、同協議会が関係者間の調整役となり、協力企業の新規開拓、寄贈食品の受付・管理や食品の分配、合意書の一括締結等を行い、活動の効率化・一元化を図ることで円滑な食品の受け渡しを実現しています。また、既存のフードバンク団体の活動範囲を拡大する支援や、新規フードバンク団体の立上げ支援等も実施しています。
このような取組の結果、フードバンク団体の近隣の事業所等が冷凍・冷蔵を含めた商品保管に協力する取組や、各フードバンク団体が協力企業店舗の店頭等で定期的にフードドライブを開催する取組等が行われています。食品の提供に関わる関係者の連携が促進されたことで、令和5(2023)年度の県内のフードバンクの食品取扱量は、同協議会設立の令和元(2019)年度時点と比較して約4倍に拡大し、より多くの人に食料を提供することができるようになりました。
同協議会では、今後とも県内で生じた未利用食品は県内の福祉に活用するという循環型社会の実現を目指し、フードバンク活動の普及・促進に一層尽力していくこととしています。
(フードバンク活動の支援を強化)
生産・流通・消費等の過程で発生する未利用食品を食品企業や農家等からの寄附を受けて、福祉施設や生活困窮者等に無償で提供する「フードバンク」と呼ばれる団体の役割が拡大しています。フードバンク活動は、未利用食品を必要とする者に届ける流通の一形態であり、食品ロスの削減に直結するほか、生活困窮者への支援等の観点からも意義のある取組であり、国民に対してフードバンク活動への理解を促進することが重要となっています。
フードバンク活動を行っている団体数(農林水産省Webサイトに掲載の希望があった団体に限る。)は、令和6(2024)年3月末時点で、全国で273団体となっています(図表1-4-3)。公益財団法人流通経済研究所(りゅうつうけいざいけんきゅうしょ)の調査によると、フードバンクの運営上の課題については、「予算(活動費)の不足」が82%で最も多く、次いで「人員の不足」、「食品を保管する倉庫や冷蔵・冷凍庫、運搬する車の不足」の順となっています(図表1-4-4)。
農林水産省では、未利用食品の提供等を通じた食品ロスの削減を推進するため、その受け皿となる大規模かつ先進的な取組を行うフードバンク等を支援しているほか、円滑な食品アクセスの確保の観点から、生活困窮者等への食料提供の充実を図るため、都道府県を通じてフードバンク等の新規立上げや取組拡大を支援することとしています。
(事例)「おもいやり食料」を提供するフードバンク活動を展開(愛媛県)


「おもいやり食料」の提供
資料:特定非営利活動法人eワーク愛媛

フードドライブへの食品の持込み
資料:特定非営利活動法人eワーク愛媛
愛媛県新居浜市(にいはまし)の特定非営利活動法人eワーク愛媛(えひめ)では、未利用食品を「おもいやり食料」として活用するフードバンク活動を展開しています。
同法人では、平成24(2012)年からフードバンク事業を展開しており、安全性や品質に問題がなく、まだ食べられるにもかかわらず、パッケージの印刷ミスや缶のへこみ、規格外品であるといった様々な理由で廃棄されている「もったいない食料」を橋渡しして、食料を必要としている個人や団体に活用してもらう活動を推進しています。
令和4(2022)年度においては、食品の寄贈元は86団体まで増加しており、提供先は87団体に拡大しています。また、同年度の食料取扱量は61tとなっており、食材購入費換算では約3,673万円に相当しています。
生活困窮者への直接提供では、スタッフが対面で対応し、食品の提供時に困り事の相談に応じるなど、単なる食品提供で終わらない支援活動を行っています。
同法人では、フードバンクの役割を食品ロス削減と生活困窮者支援のみにとどまらないものと位置付け、「もったいない食料」を大切にして「ありがとう」につなげる「おもいやり食料」として活用することを重視しています。
今後は、家庭からの食品の寄贈先として位置付けている「フードドライブ」の設置箇所の拡充を含め、より良い食文化への転換や、住みやすく活気ある地域の創出を図ることを目指し、フードバンク活動を展開していくこととしています。
(こども食堂等による食料提供の取組を推進)
こども食堂は、子供たちを中心に無料又は安価で栄養のある食事や温かな団らん、共食の場を提供する、地域住民等による自主的な取組です。特定非営利活動法人全国(ぜんこく)こども食堂支援(しょくどうしえん)センター・むすびえが令和5(2023)年9~11月に実施した調査によると、こども食堂の箇所数は全国で9,132か所となっています。
こども食堂は、共食の場の提供のほか、子供の居場所づくりや生活困窮者等への食品アクセスの確保の観点からも重要な取組です。
農林水産省では、食育を推進する観点から、こども食堂等地域での様々な共食の場を提供する取組を支援してきており、令和2(2020)年度からは政府備蓄米の無償交付を行っています。令和5(2023)年度の交付数量は、学校等給食向けが約10t、こども食堂向けが約13t、こども宅食向けが約127t、合計で約150tとなっています。
また、生活困窮者等への食料提供の充実を図るため、都道府県を通じてこども食堂等の新規立上げや取組拡大を支援することとしています。
(事例)子育て世帯を対象として「こども食堂」の取組を推進(東京都)


こども食堂を運営するスタッフ
資料:動坂ごはん
東京都文京区(ぶんきょうく)の「動坂(どうざか)ごはん」では、子育て世帯を対象として、こども食堂の取組を推進しています。
同団体は、地域の催し等で食事の手伝いを行う中で、支援できることがないかとの思いから、令和元(2019)年6月にこども食堂を開設し、弁当を配付する取組を開始しました。
同団体によるこども食堂は、同区内の子育て世帯を対象として、毎月1回開催しており、弁当配付を中心とした運営を行っています。食品の調達については、社会福祉協議会からの支援や大人の参加者から徴収した参加費を基に、スーパーマーケットから購入しているほか、農業者や企業から食材提供を受けています。
また、こども食堂での居場所づくり等の取組を通して、母子家庭の情報を社会福祉協議会と共有することで、困っている家庭の橋渡し役としての活動も展開しています。
このような取組を行う中で、母子家庭で食事を作る時間が取れない家庭からは、喜びや感謝の声が寄せられています。また、訪れたついでに気軽に悩み事等を相談できるほか、地域での交流の機会を提供する場所としても役立てられています。
同団体では、対面形式での開催への変更や、食材の調達先の確保等に課題を有していますが、今後とも、地域で連携しながら、子供の食育や見守り支援等を含め、こども食堂の取組を推進していくこととしています。
(2)合理的な価格の形成に向けた対応
(農業生産資材価格の上昇と比べて農産物価格の上昇は緩やか)
農業経営体が購入する農業生産資材価格に関する指数である農業生産資材価格指数については、令和3(2021)年以降、飼料や肥料等の価格高騰により上昇し、令和5(2023)年4月に122.3となりました。その後は横ばい傾向で推移しており、令和6(2024)年2月時点で120.9となっています(図表1-4-5)。
一方、農業経営体が販売する農産物の生産者価格に関する指数である農産物価格指数については、令和4(2022)年以降、野菜や花き等の価格が上昇したことを受け、おおむね上昇基調で推移し、令和6(2024)年2月時点では108.9となっています。
両者の推移を比較すると、農産物価格指数の上昇率は、令和5(2023)年10月に野菜等の価格高騰により119.6となる一時的な上昇はあったものの、農業生産資材価格指数の上昇率と比べて緩やかな動きとなっています。飼料や肥料原料の高騰等により農業生産資材価格が高い水準で推移する一方、農産物価格への転嫁は円滑に進んでいないことがうかがわれます。
(農業交易条件指数は令和2(2020)年を下回る水準で推移)
農産物価格と農業生産資材価格の相対的な関係の変化を示す農業交易条件指数については、令和5(2023)年は88.9となりました。引き続き、令和2(2020)年を下回る水準で推移しており、生産者の収益環境が厳しい状況下に置かれていることがうかがわれます(図表1-4-6)。
農業経営の安定化を図り、農産物が将来にわたって安定的に供給されるようにするためには、生産コストの上昇等が、食料システム全体で考慮されることが重要となっています。
(コスト高騰に伴う農産物・食品への価格転嫁が課題)
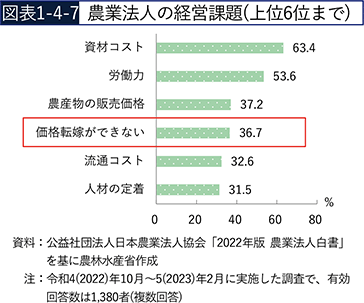
農産物の価格については、品目ごとにそれぞれの需給事情や品質評価に応じて形成されることが基本となっていますが、流通段階での価格競争の厳しさといった様々な要因で、農業生産資材等のコスト上昇分を適切に取引価格に転嫁することが難しい状況にあります。
公益社団法人日本農業法人協会(にほんのうぎょうほうじんきょうかい)が令和4(2022)年10月~5(2023)年2月に実施した調査によると、調査時点で抱えている経営課題について、「価格転嫁ができない」と回答した農業者の割合は36.7%で4番目に多い結果となりました(図表1-4-7)。
また、中小企業庁が令和5(2023)年10~12月に実施した調査(*1)によると、食品製造業(中小企業)におけるコスト増に対する価格転嫁の割合は53.1%となっています。
飼料、肥料、燃油等の農業生産資材や原材料の価格高騰は、生産者や食品企業の経営コストの増加に直結し、最終商品の販売価格まで適切に転嫁できなければ、食料安定供給の基盤自体を弱体化させかねません。
このため、農業生産資材や原材料価格の高騰等による農産物・食品の生産コストの上昇等について、消費者の理解を得つつ、食料システム全体で、合理的な費用を考慮した価格形成の仕組みづくりに向けて環境整備を進めていくことが必要です。
1 中小企業庁「価格交渉促進月間(2023年9月)フォローアップ調査」(令和6(2024)年1月公表)
(農業者自らがコスト構造を把握・説明できることが重要)
合理的な価格の形成の取組に向けては、生産コストの実態を消費者まで伝達することが必要です。生産・加工・流通・小売等の各事業者を通じて、消費者までコスト構造を伝達するためには、フードバリューチェーンの起点である農業者自らがコスト構造を把握し、説明できるようにする必要があります。そのためにも、農業者による経営管理能力の向上が必要となっています。
(事例)生産コストを「見える化」し、取引先との交渉に活用(茨城県)

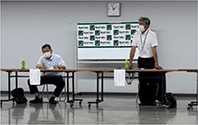
取引先向けの説明会
資料:全国農業協同組合連合会茨城県本部
茨城県茨城町(いばらきまち)に本拠を置く全国農業協同組合連合会茨城県(いばらきけん)本部(以下「JA全農いばらき」という。)では、価格転嫁の理解促進に向けて、主要品目・作型別に生産費の上昇額の試算表を作成し、生産コスト上昇の「見える化」を推進しています。
農業生産資材の高騰の影響を受ける中、取引先に対して産地側のコストの状況が伝わりにくいことが課題となっています。このため、JA全農いばらきでは、生産費が考慮された価格形成の実現に向け、農業生産資材の価格高騰の影響を数値で示すため、野菜や果樹、花き等の36品目について、県の統計を基に、6項目(肥料、農薬、光熱動力、出荷資材、労働賃金、運賃)に関し、平成30(2018)年度と令和4(2022)年度の生産費を比較し、その上昇額を算出した試算表を、県内JAの理解を得て完成させました。
JA全農いばらきでは、大手卸売会社向けに説明会を開催し、当該試算表をバイヤー等との価格交渉の場で活用することを要請したほか、県内の各市場や、直接取引している食品企業等にも説明を行いました。
これらの取組により、取引価格の値上げに応じる取引先も見られており、価格交渉の場で生産費の上昇を客観的に示すことの重要性が再認識されています。
JA全農いばらきでは、管内の農協が地域の生産状況に応じて独自の試算表を作成するなど、生産コスト上昇の「見える化」の取組が更に拡大することを期待しています。
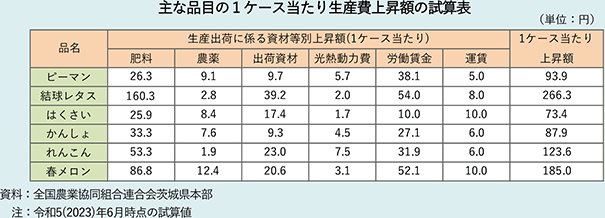
(円滑な価格転嫁や取引の適正化に係る取組を推進)
政府は、令和3(2021)年に決定した「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を価格に適切に転嫁できる環境整備に取り組んでいます。具体的には、公正取引委員会において、独占禁止法(*1)の「優越的地位の濫用」に関して、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分の価格転嫁が適切に行われているか等を把握するための更なる調査を実施するなど、コスト上昇分を適正に転嫁できる環境の整備を進めています。
農林水産省では、令和3(2021)年12月に食品製造業者と小売業者との取引関係において、問題となり得る事例等を示した「食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン」を策定するとともに、令和6(2024)年3月には、卸売市場の仲卸業者等と小売業者との取引関係において、問題となり得る事例等を示した「卸売市場の仲卸業者等と小売業者との間における生鮮食料品等の取引の適正化に関するガイドライン」を策定しました。これらを普及させることで、取引上の法令違反の未然防止、食品製造業者、卸売市場の仲卸業者等や小売業者の経営努力が報われる適正な取引の推進を図っています。
1 正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」
(フェアプライスプロジェクトを開始)
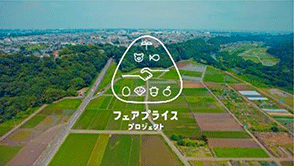
適正な価格形成の理解・共感を
深めるための広報動画
国際情勢の影響により、食品の原材料や農業生産資材、エネルギー価格の高騰に加え、円安の進行で、様々な食品の生産・流通コストが上昇し、農林水産業・食品産業は深刻な影響を受けています。
このため、農林水産省では令和5(2023)年7月に「フェアプライスプロジェクト」を立ち上げ、農林水産業の現状や今後の我が国の食の未来について考え、合理的な価格の形成による持続可能な食料供給の実現に向けた理解と共感を深めることを狙いとした広報活動を行っています。
(合理的な価格の形成のための取組を推進)
持続可能な食料供給を実現するためには、生産だけでなく、流通、加工、小売等のフードチェーンの各段階の持続性が確保される必要があり、また、これらが実現することは消費者の利益にもかなうものです。
このような持続可能な食料供給の実現に向けて、農林水産省では令和5(2023)年8月に「適正な価格形成に関する協議会」を設立しました。同協議会では、適正取引を推進するための仕組みについて、統計調査の結果等を活用し、食料システムの関係者の合意の下でコスト指標を作成し、これをベースに各段階で価格に転嫁されるようにするなど、取引の実態・課題等を踏まえて構築することとしています。
令和5(2023)年度においては、まずは「飲用牛乳」と「豆腐・納豆」を対象として、実務に精通した取引担当者等によるワーキンググループで検討を進めるとともに、その他の品目についても、コストデータの把握・収集、価格交渉や契約においてどのような課題があるか等について協議会で検討を進めています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883