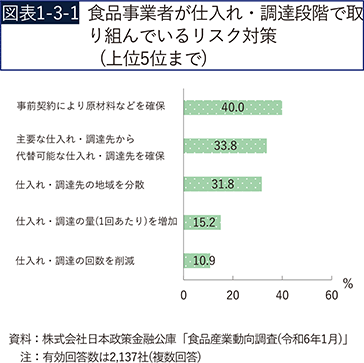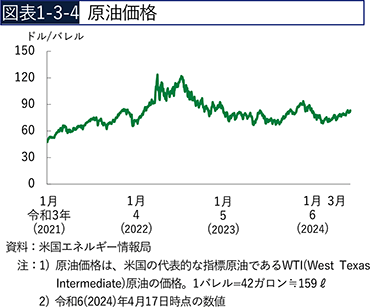第3節 食料供給のリスクを見据えた総合的な食料安全保障の確立
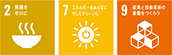
食料は人間の生活に不可欠であり、食料安全保障は、国民一人一人に関わる国全体の問題です。しかしながら、世界的な人口増加等に伴う食料需要の増大を始め、気候変動や異常気象の頻発化に伴う食料生産の不安定化、ロシアによるウクライナ侵略等による食料品・農業生産資材の価格高騰等により我が国の食料をめぐる情勢は大きく変化しており、サプライチェーン(*1)の混乱等の様々な要因により大幅な食料供給不足が発生するリスクが増大しています。
本節では、サプライチェーンの状況や食料安全保障の強化を図る取組等について紹介します。
1 農林水産物を生産し、食品加工、流通、販売により消費者に食品が届き、最終的に廃棄されるまでの一連の流れを指す。
(1)サプライチェーンの状況
(サプライチェーンの強靱化に向けた取組が一層重要)
食をめぐる情勢が大きく変化する中、サプライチェーンの持続性を高め、その強靱性(きょうじんせい)を確保することが重要な課題となっています。
食料安全保障の観点で見ると、サプライチェーンの混乱は食料供給に与える影響が大きいことから、その強靱化に向けた取組が一層重要になっています。
令和6(2024)年1月に公庫が実施した調査によると、食品事業者が仕入れ・調達段階で取り組んでいるリスク対策については、「事前契約により原材料などを確保」を挙げた企業が40.0%で最も多く、次いで「主要な仕入れ・調達先から代替可能な仕入れ・調達先を確保」、「仕入れ・調達先の地域を分散」の順となっています(図表1-3-1)。食品事業者がサプライチェーンの強靱化に向けて、原材料の安定調達等に必要な措置を講じる動きが見られています。
また、農林水産省では、令和4(2022)年6月に公表した「食料の安定供給に関するリスク検証(2022)」において、食料安全保障上のリスクの一つとして「サプライチェーンの混乱」を取り上げ、国内物流の混乱、保管施設、加工処理施設等の稼働に支障が生じるなど、国内のサプライチェーンに影響が生じた場合に、国内の農林水産業や食品産業に与えるリスクについて、分析・評価を実施しました。
国内生産の側面では、季節や品目により主産地が変化し、生鮮品で穀物等と比較して日持ちしない野菜や果実、生乳、水産物に加え、食肉処理施設や小売店における食肉カット技術者の人材不足等が懸念される国産の牛肉、豚肉、鶏肉は、サプライチェーンに影響が及ぶことが懸念されています。
輸入の側面では、小麦や大豆、なたね、砂糖類、飼料穀物については、製粉・油脂製造・精製糖・飼料工場が太平洋(たいへいよう)側に偏在しており、南海(なんかい)トラフ地震等の大地震が発生した場合、代替地での製造が難しいことから、サプライチェーンに大きな影響が及ぶことが懸念されています。
(農林水産業分野では、エネルギー利用の約9割以上を化石燃料に依存)
経済産業省の調査によると、令和3(2021)年度における農林水産業のエネルギー消費量は、前年度並みの23万8千TJ(テラジュール)(*1)となっています(図表1-3-2)。
農林水産業分野では、エネルギー利用の約9割以上を化石燃料に依存しており、電力の利用は全体の5.4%となっています(図表1-3-3)。化石燃料の中では、A重油の消費が最も多く、次いで軽油、ガソリン、灯油の順となっています。特にA重油は、農業分野では施設園芸の暖房に用いられる燃焼式加温機で多く消費されています。軽油やガソリンは農業機械、灯油は穀物を乾燥させる乾燥機で利用されることが多くなっています。
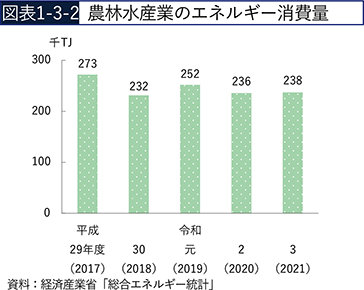
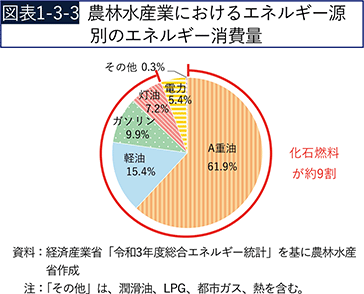
また、原油価格は、ロシアによるウクライナ侵略直後に大きく上昇し、令和4(2022)年度以降はおおむね下落基調にあるものの、高い水準で不安定に推移しています(図表1-3-4)。
化石燃料については、その価格は地政学上のリスクや国際的な市場の影響等の他律的な要因に左右されやすいことから、農業経営に係る価格の見通しを立てることが難しい農業生産資材と言えます。農林水産分野の持続的な発展に向けては、地域の再生可能エネルギー資源の一層の活用といった化石燃料に依存しない持続可能なエネルギー調達も重要となっています。
1 テラ・ジュールの略。テラは10の12乗のこと。ジュールは熱量単位
(2)食料安全保障の確保を図るための体制
(輸入の安定的確保と不測の事態に的確に対処するための対応を推進)
農林水産省では、輸入食料の安定的確保に向け、国際協調を通じた輸出規制措置の透明性向上と規律の明確化を推進するとともに、諸外国・地域等との情報交換や国際機関との協力を通じた国際的な食料需給状況の分析の強化を推進しています。
また、不測の要因により食料の供給に影響が及ぶおそれのある事態に的確に対処するため、政府として講ずべき対策の基本的な内容、実施手順等を示した「緊急事態食料安全保障指針」に基づき、不測時のレベルに応じて必要な措置を講ずることとしています。

食料安全保障について
URL:https://www.maff.go.jp/j/
zyukyu/anpo/index.html
一方、同指針は法令に基づくものではなく、政府の意思決定や指揮命令についての法令上の根拠となるものではないこと等の課題が存在することから、我が国の食料安全保障上のリスクが高まる中、不測時の対応根拠となる法制度を検討することとし、令和5(2023)年8月に「不測時における食料安全保障に関する検討会」を立ち上げ、その基本的な考え方を取りまとめた上で、「食料供給困難事態対策法案(*1)」を第213回通常国会に提出したところです。
1 特集第3節を参照
(不測時に備えた穀物の備蓄を実施)
政府は国内の米の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、米を100万t程度(*1)備蓄しています。あわせて、海外における不測の事態の発生による供給途絶等に備えるため、食糧用小麦については国全体として外国産食糧用小麦の需要量の2.3か月分を、飼料穀物についてはとうもろこし等100万t程度をそれぞれ民間で備蓄しています。
食料の備蓄強化に向けては、国内外の食料安全保障の状況を適切に把握・分析の上、これらを踏まえて、備蓄の基本的な方針を明確にしていくことを検討することとしています。
1 10年に1度の不作や、通常程度の不作が2年連続した事態にも国産米をもって対処し得る水準
(平時からの取組が不測時の取組にも有効)
農業者の減少や高齢化が急速に進み、農業の生産基盤の脆弱化(ぜいじゃくか)や地域コミュニティの衰退等の国内農業をめぐる厳しい情勢がある中で、不測時に備えて平時から食料の安定供給に向けた取組を進め、過度な輸入依存度を低減していくとともに、国内外の食料需給を平時から把握しておくことは、不測の事態の未然防止や不測の事態における対応力の強化にも有効です。このため、国内の生産基盤やサプライチェーンの維持・強化に向けた各種施策とともに、(1)適切かつ効率的な備蓄の運用、(2)主要な輸入相手国の生産や輸出能力の把握、(3)国内外の食料需給に関する情報の収集といった取組を平時から推進することが重要となっています。
(食料・農業生産資材等の安定的な輸入の確保を推進)
国内生産で国内需要を満たすことができない一部の食料・農業生産資材については、国内の需要を満たすために一定の輸入が不可欠である中、気候変動によるリスクや地政学的リスクの高まり等も踏まえ、平時から安定的な輸入を確保するための環境整備が重要となっています。このため、輸入相手国における穀物等の集出荷・港湾施設等への投資案件の形成を支援するとともに、輸入先国の多角化に向けて、輸入相手国との政府間対話の活用、官民による情報共有等を推進することとしています。
(食料の安定的な輸入に向け、港湾機能を強化)
我が国では、食料や農業生産資材の多くを海外に依存しており、その多くが海運を通じて輸入されています。輸入された物資は、例えば飼料用とうもろこしについては、港湾付近に立地するサイロに一時保管された後、飼料工場で加工され、最終需要者である畜産農家で利用されています。輸入穀物の多くは、バルク船と呼ばれる貨物船で輸送されていますが、世界で利用されるバルク船は、輸送効率化のために大型化される傾向にあります。一方、我が国の港湾では、岸壁の水深が10~14mであることが多く、大型バルク船が接岸できる水深14m以上の港湾は限られていることから、食料の安定供給のためにも、大型船に対応できる港湾整備等が重要となっています。
国土交通省では、ばら積み貨物の安価で安定的な輸入を実現するため、大型船に対応した港湾機能の拠点的確保や企業間連携の促進等による効率的な海上輸送網の形成に向けた取組を推進しています。また、国際海上コンテナターミナルや国際物流ターミナルの整備といった港湾機能の強化を推進しています。
(事例)港湾整備により飼料穀物の大量一括輸送を実現(北海道)


釧路港の国際物流ターミナル
資料:釧路西港開発埠頭株式会社
北海道釧路市(くしろし)では、穀物を運搬する船舶が入港する釧路港(くしろこう)において、大型船に対応した国際物流ターミナルを整備することにより、飼料原料となる穀物の大量一括輸送体制を構築しています。
同港は、全国の約5割の乳牛を飼養する生乳・乳製品の一大産地である北海道東部地域を背後圏とし、乳牛等の飼料となるとうもろこし等の飼料原料を、令和4(2022)年度には年間166万t取り扱っています。また、埠頭(ふとう)周辺には、穀物用サイロ、飼料工場等が集積しており、飼料供給拠点として重要な役割を担っています。
一方、釧路港を始め、我が国の港湾は水深不足のため、パナマックス船等の大型船が満載で入港できる港湾は少なく、積載量を減らし、大型船は他港で貨物を卸してから入港するなど、非効率な輸送を余儀なくされています。このような非効率な輸送を解消するため、釧路港においては大型船の接岸が可能となる水深14mの岸壁を擁する国際物流ターミナルを平成30(2018)年11月に整備しました。
同施設の整備により、穀物の主要生産地域である北米に最も近い釧路港に大型船が最初に寄港し、同港で多くの穀物を降ろすことで、船が軽くなり船底が上がるため、その後、他港へ穀物を運ぶことが可能となり、大量一括輸送による安定的かつ効率的な海上輸送網の形成を実現しています。
同港の周辺では、飼料原料保管用サイロを始めとした受入設備の整備も進められています。同市では、今後とも、食料の安定供給の確保に不可欠な拠点施設として、港湾の管理・運営を行なっていくこととしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883