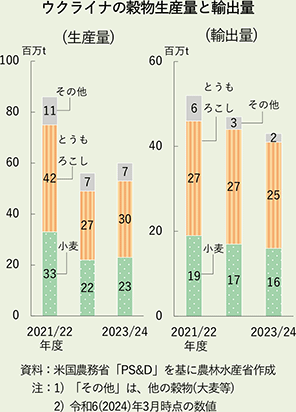第2節 国際的な食料需給と我が国における食料供給の状況

世界の食料需給は、途上国を中心とした世界人口の急増による食料需要の増加、気候変動による異常気象の頻発化、地政学リスクの高まり等により不安定化しています。また、食料の国際価格は、新興国の需要やエネルギー向け需要の増大、地球規模の気候変動の影響等により上昇傾向で推移しています。一方、我が国においては食料の6割以上を輸入に依存しており、増大する輸入リスクに対応し、将来にわたって食料の安定的な供給を図ることが重要となっています。
本節では、国際的な食料需給や食料価格の動向、我が国における食料供給の状況、食料の輸入状況等について紹介します。
(1)国際的な食料需給の動向
(2023/24年度における穀物の生産量、消費量は前年度に比べて増加)
令和6(2024)年3月に米国農務省が発表した資料によると、2023/24年度における世界の穀物消費量は、途上国の人口増加、所得水準の向上等に伴い、前年度に比べて5千万t(1.8%)増加し28億1千万tとなる見込みです(図表1-2-1)。
また、生産量は、主に単収の伸びにより消費量の増加に対応しており、2023/24年度は前年度に比べて6千万t(2.2%)増加し28億1千万tとなる見込みです。
2023/24年度の期末在庫率は、前年度に比べて0.7ポイント低下し27.5%となる見込みです。FAO(*1)が安全在庫水準としている17~18%を上回っていますが、中国を除いた場合の期末在庫率は12.3%にとどまっており、世界的な不作が発生した場合には、食料不足や価格高騰が起こりやすい状況にあります。
2023/24年度における世界の穀物等の生産量を品目別に見ると、小麦はインド、米国等で増加するものの、豪州、カザフスタン等で減少することから、前年度に比べて0.3%減少し7億9千万tとなる見込みです(図表1-2-2)。
とうもろこしは、ブラジル、メキシコ等で減少するものの、米国、アルゼンチン等で増加することから、前年度に比べて6.3%増加し12億3千万tとなる見込みです。
米は、インド等で減少するものの、米国等で増加することから、前年度に比べて0.2%増加し5億2千万tとなる見込みです。
大豆は、ブラジル、米国等で減少するものの、アルゼンチン等で増加することから、前年度に比べて5.0%増加し4億tとなる見込みです。
期末在庫率については、小麦、米は前年度に比べて低下する一方、とうもろこし、大豆は前年度に比べて上昇する見込みです。
*1 特集第2節を参照
(世界の経済成長の鈍化等により、中期的には穀物等の需要の伸びは鈍化の見込み)
世界経済は、中期的には、中国の成長の鈍化や人口減少が見込まれる一方、インド等の新興国・途上国において相対的に高い経済成長率が維持されると見られています。将来的に先進国だけでなく途上国の多くの国で、経済成長はコロナ禍以前より鈍化すると見られ、世界経済はこれまでより緩やかな成長となる見込みです。
このような中、令和14(2032)年における世界の穀物等の需給について、需要面においては、途上国の総人口の増加、新興国・途上国を中心とした相対的に高い所得水準の向上等に伴って食用・飼料用需要の増加が中期的に続くものの、先進国だけでなく新興国・途上国においても今後の経済成長の弱含みを反映して、穀物等の需要の伸びは鈍化してコロナ禍以前より緩やかとなる見通しとなっています。供給面では、今後、全ての穀物の収穫面積が僅かに減少する一方、穀物等の生産量は、主に生産性の上昇によって増加する見通し(*1)となっています。
世界の食料需給は、農業生産が地域や年ごとに異なる自然条件の影響を強く受け、生産量が変動しやすいこと、世界全体の生産量に比べて貿易量が少なく輸出国の動向に影響を受けやすいこと等から、不安定な要素を有しています。
また、気候変動や大規模自然災害、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病、新型コロナウイルス感染症等の流行、ロシアによるウクライナ侵略といった多様化するリスクを踏まえると、食料の安定供給の確保に万全を期す必要があります。
*1 農林水産政策研究所「2032年における世界の食料需給見通し」(令和5(2023)年3月公表)
(フォーカス)ウクライナの穀物輸出量は前年度に比べ減少する見通し
令和6(2024)年3月に米国農務省が公表した資料によると、ウクライナの2023/24年度における小麦生産量は、史上最高の単収となる見通しを受け、前年度比8.8%増加の2,340万tの見通しとなっていますが、輸出量は、前年度比6.5%減少の1,600万tの見通しとなっています。また、2023/24年度におけるとうもろこし生産量は、天候に恵まれたことにより前年度比9.3%増加の2,950万tの見通しとなっている一方、輸出量は前年度比9.7%減少の2,450万tの見通しとなっています。
また、ウクライナ農業政策・食料省による令和5(2023)年8月時点の予測によると、2023/24年度の穀物・油糧種子の作付面積は、前年度比6%減少の1,949万haの見通しとなっています。
さらに、同省の令和5(2023)年12月時点の予測によると、2023/24年度の穀物・油糧種子の生産量は、天候に恵まれたことから、前年度比7%増加の8,130万tの見通しとなっています。一方で、ロシアによるウクライナ侵略以前において過去最高を記録した、2021/22年度の1億600万tと比較すると、23%減少しています。
一方、令和4(2022)年7月の国際連合(以下「国連」という。)、ウクライナ、ロシア、トルコの4者によるウクライナ産穀物の黒海(こっかい)経由での輸出再開に関する合意により、穀物等3,283万tが輸出されていましたが、令和5(2023)年7月にロシアの離脱で停止し、その後、再開については決定されていません。
代替輸出ルートとして、臨時回廊からの輸出や、ドナウ川(がわ)沿いの運河等を利用しルーマニアのコンスタンツァ港(こう)等を経由した輸出が行われています。代替輸出ルートのうち、陸路の輸送は減少傾向にある一方、臨時回廊からの輸出量は同年10月以降増加しています。
我が国ではウクライナから穀物をほとんど輸入していませんが、今後ともウクライナ情勢が国際穀物貿易や価格に与える影響等について注視していく必要があります。
(世界のバイオ燃料用農産物の需要は増加の見通し)
近年、米国、EU等の国・地域において、化石燃料への依存の改善や温室効果ガス排出量の削減、農業・農村開発等の目的から、バイオ燃料の導入・普及が進展しており、とうもろこしやさとうきび、なたね等のバイオ燃料用に供される農産物の需要が増大しています。
令和5(2023)年6月にOECD(*1)(経済協力開発機構)及びFAOが公表した予測によると、令和4(2022)年から令和14(2032)年までに、バイオエタノールの消費量は1億2,917万kLから1億5,098万kLへ、バイオディーゼルの消費量は5,718万kLから6,694万kLへとそれぞれ増加する見通しとなっています(図表1-2-3)。
*1 Organisation for Economic Co-operation and Developmentの略
(2)国際的な食料価格の動向
(小麦・とうもろこし・大豆の国際価格は、おおむねウクライナ侵略前の水準まで低下)
穀物等の国際価格は、新興国の畜産物消費の増加等を背景とした需要やバイオ燃料等のエネルギー向け需要の増大、地球規模の気候変動の影響等のほか、令和4(2022)年のロシアによるウクライナ侵略が重なったこともあり、近年上昇傾向で推移しています。
小麦の国際価格は、主要輸出国である南米や北米での高温乾燥等の天候不良が続いたことに加え、ロシアによるウクライナ侵略等により、令和4(2022)年3月に過去最高値を更新し、523.7ドル/tとなりました。令和6(2024)年3月時点では、令和2(2020)年以前と比較して高い水準にあるものの、おおむねウクライナ侵略前の水準まで低下しています(図表1-2-4)。
また、とうもろこし、大豆の国際価格については、南米での乾燥等もあり、令和6(2024)年3月時点では、令和2(2020)年以前と比較して高い水準にあるものの、おおむねウクライナ侵略前の水準まで低下しています。

(食料価格指数は世界的に緩やかに下落)
FAOが公表している食料価格指数(*1)については、令和4(2022)年3月に食料品全体で160.3に達して以降緩やかに下落しており、令和6(2024)年3月は118.3となりました(図表1-2-5)。
品目別では、穀物、植物油の価格指数は低下傾向にあります。砂糖は、足下の需給逼迫(ひっぱく)の懸念や原油価格の上昇を受け、令和5(2023)年9月に162.7と前年同月比で48.4%上昇しました。
*1 国際市場における五つの主要食料(穀物、肉類、乳製品、植物油及び砂糖)の国際価格から計算される世界の食料価格の指標
(小麦に続き、とうもろこし・大豆も売越しに転換)
有利な投資先を求める投機資金は、令和2(2020)年後半以降、需給が引き締まり価格上昇が見込まれた穀物市場に流入し、投機筋の買越枚数については、とうもろこしでは令和3(2021)年1月に53万5千枚となり、小麦や大豆でも高水準となりました。その後、小麦は令和4(2022)年8月以降、とうもろこしは令和5(2023)年8月以降、大豆は令和6(2024)年1月以降、いずれも売越しの状況となっています(図表1-2-6)。

穀物や原油等の商品市場の規模は、株式市場や債券市場と比較して極めて小さく、まとまった金額の買いによって相場が上がりやすいという特徴を有しています。巨額の運用資金を有するヘッジファンド等からの投機資金の穀物市場への流入については、引き続き注視していく必要があります。
(令和5(2023)年4月期の輸入小麦の価格を抑制)
輸入小麦の政府売渡価格は、国際相場の変動の影響を緩和するため、4月期と10月期の年2回、価格改定を行っていますが、ロシアによるウクライナ侵略等を受け、令和4(2022)年10月期と令和5(2023)年4月期に価格高騰対策を実施しました。
令和4(2022)年10月期には、通常6か月間の算定期間を1年間に延長してその影響を平準化し、同年10月期の政府売渡価格は同年4月期の価格を適用し、実質的に据え置く緊急措置を実施しました(図表1-2-7)。
また、令和5(2023)年4月期には、物価上昇全体に占める食料品価格上昇の影響の高まりを受け、価格の予見可能性、小麦の国産化の方針、消費者の負担等を総合的に判断した結果、ウクライナ侵略直後の急騰による影響を受けた期間を除く直近6か月間の買付価格を反映した水準まで上昇幅を抑制し、令和4(2022)年10月期と比べて5.8%上昇となる7万6,750円/tとする激変緩和措置を実施しました。
一方、令和5(2023)年10月期からは、買付価格がウクライナ情勢前の水準に落ち着きつつあることを踏まえ、直近6か月間の買付価格をベースに算定しています。
(3)我が国における食料供給の状況
(国産と輸入先上位4か国による食料供給の割合は約8割)
我が国の食料供給は、国産と輸入先上位4か国(米国、豪州、カナダ、ブラジル)で、供給熱量の約8割を占めています(図表1-2-8)。今後の食料供給の安定性を維持していくためには、これらの輸入品目の国産への置換えを着実に進めるとともに、主要輸入先国との安定的な関係を維持していくことも必要となっています。
(生産努力目標の達成に向け、国内農業の生産基盤を強化)
食料・農業・農村基本計画においては、官民総力を挙げて取り組んだ結果、農業生産に関する課題が解決された場合に実現可能な国内の農業生産の水準として、令和12(2030)年度における生産努力目標を主要品目ごとに示しています。
令和4(2022)年度における生産努力目標の達成状況を見ると、大麦・はだか麦が101%、米が100%、鶏肉が99%、豚肉が98%となっている一方、大豆は71%、かんしょは83%、さとうきびは83%となっています(図表1-2-9)。
農林水産省では、生産努力目標の達成に向け、担い手の育成・確保や農地の集積・集約化、農地の大区画化、水田の畑地化・汎用化、スマート農業技術の導入、国産飼料の生産・利用拡大等により国内農業の生産基盤強化を図るとともに、今後も拡大が見込まれる加工・業務用需要や海外需要に対応した生産を進めています。
(4)我が国における食料輸入の状況
(農産物の輸入額は前年に比べ2.0%減少)
令和5(2023)年の農産物輸入額は、前年に比べ2.0%減少し9兆536億円となりました(図表1-2-10)。このうち農産品は1.9%減少し6兆6,340億円、畜産品は2.4%減少し2兆4,174億円となりました。
(我が国の主要農産物の輸入構造は少数の特定国に依存)
令和5(2023)年の農産物輸入額を国・地域別に見ると、米国が1兆8,154億円で最も高く、次いで中国、豪州、ブラジル、タイ、カナダの順で続いており、上位6か国が占める輸入割合は約6割程度になっています(図表1-2-11)。
品目別に見ると、とうもろこし、大豆、小麦の輸入は、特定国への依存傾向が顕著となっており、上位2か国で8~9割を占めています。小麦については、米国、カナダ、豪州の上位3か国に99.8%を依存している状況です。
豚肉や果実類といった一部の品目では輸入先の多角化が進みつつあるものの、我が国の農産物の輸入構造は、依然として米国を始めとした少数の特定国への依存度が高いという特徴があります。
海外からの輸入に依存している主要農産物の安定供給を確保するためには、輸入相手国との良好な関係の維持・強化や関連情報の収集等を通じて、輸入の安定化や多角化を図ることが重要です。一方、食料・農業生産資材の価格高騰の影響やウクライナ情勢等を踏まえると、国内の農業生産の増大に向けた取組がますます重要となっています。
(コラム)国内の食料消費全ての生産に必要な農地面積は、国内農地面積の約3.1倍
小麦や、油脂類・飼料の原料となる大豆、なたね、とうもろこし等については、我が国の限られた農地では大量に生産することが難しく、生産に適した気候で広大な農地を有する米国や豪州、カナダ等で大規模に生産されたものが輸入されています。我が国における品目別自給率は、令和4(2022)年度においては、それぞれ小麦が15%、大豆が6%、油脂類が14%と低い状況となっています。
このように今日の豊かな食生活は、国内で生産された食料だけでなく、輸入された食料や飼料に多くを支えられています。国内で消費される食料全てを生産するために必要な農地面積は、国内の農地面積の約3.1倍に相当する1,355万haとなっており、現状においては、全てを国産で賄うことは不可能な状況にあります。
このため、食料の安定的な供給については、国内の農業生産の増大と併せて安定的な輸入と備蓄の確保を図ることにより、国内農業が様々な課題を抱えている中で、その力が衰退することなく将来にわたって発揮され、また、その力が増進していくように効率的に取り組んでいく必要があります。
一方、主食用米については、食の多様化や簡便化、少子高齢化、人口減少等により、需要量は減少しており、作付面積も減少しています。食料安全保障の観点からは、農地の有効利用が不可欠であり、水田を畑地等に転換し、麦や大豆等の需要のある作物を生産していくことが重要となっています。
我が国においては、農産物の過度な輸入依存からの脱却を図るため、小麦、大豆等の本作化、米粉の利用拡大、食品原材料の国産切替えといった食料安全保障の強化に向けた構造転換を進め、早期に食料安全保障の強化を実現していく必要があります。
(将来の食料輸入に不安を持つ消費者の割合は約8割)
将来の食料輸入に対する消費者の意識について、公庫が令和6(2024)年1月に実施した調査によると、77.8%の人が日本の将来の食料輸入に「不安がある」と回答しました(図表1-2-12)。また、日本の将来の食料輸入について「不安がある」と回答した人にその理由を聞いたところ、「国際情勢の変化により、食料や生産資材の輸入が大きく減ったり、止まったりする可能性があるため」と回答した人が58.4%と最も高くなりました(図表1-2-13)。世界的な食料需要の増加や国際情勢の不安定化等に伴う食料安全保障上のリスクが高まる中、将来にわたって食料を安定的に確保していくことが求められています。
農林水産省では、農産物や農業生産資材等の安定輸入のための海外の情報収集、事業者と政府の間での情報共有を図るとともに、海外生産・物流といった我が国への輸入に係る事業への投資拡大を推進することとしています。また、輸入先との間で、政府間・民間事業者間で安定的な輸入に係る枠組み作り等を進めることとしています。

安定的な輸入の確保
URL:https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/yunyu.html
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883