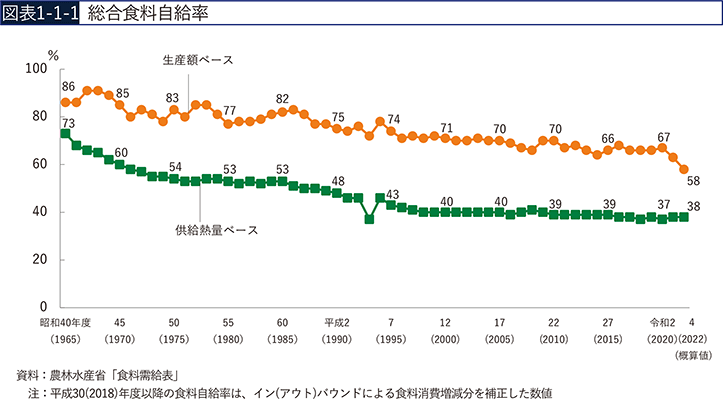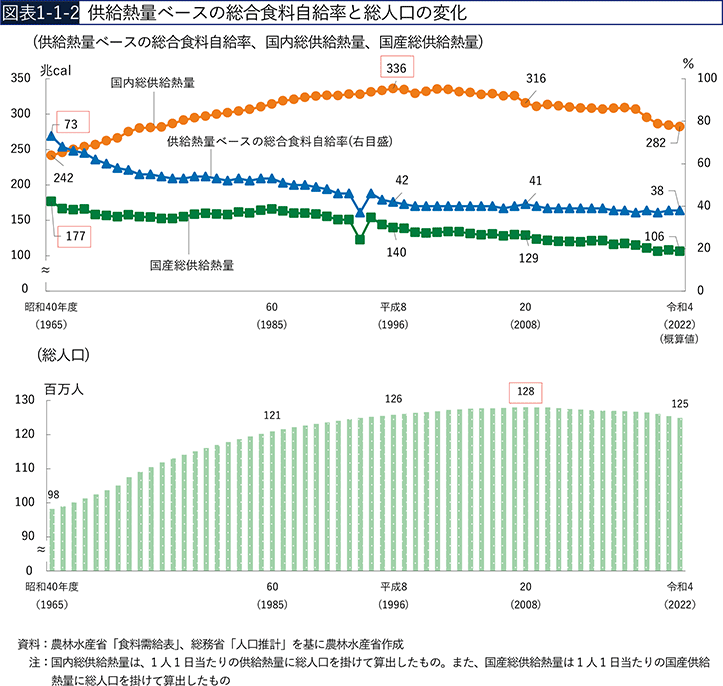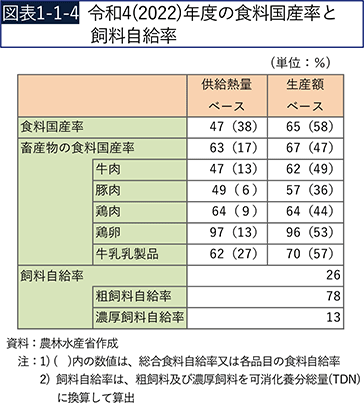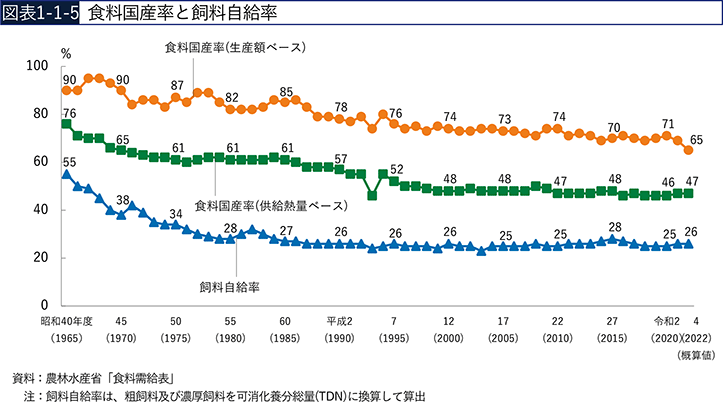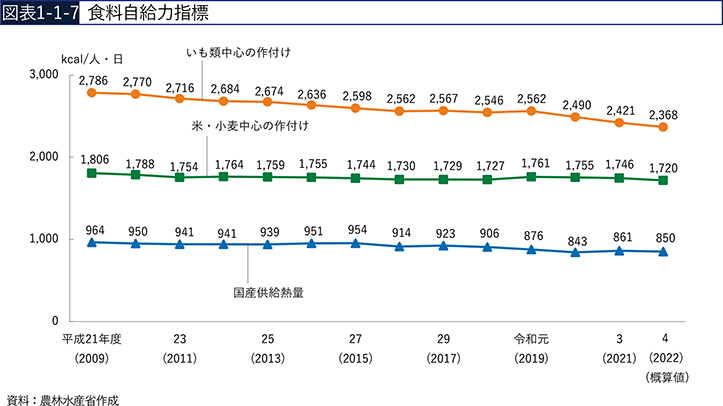第1節 食料自給率と食料自給力指標
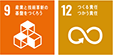
令和2(2020)年3月に閣議決定した「食料・農業・農村基本計画」において、令和12(2030)年度を目標年度とする総合食料自給率の目標を設定するとともに、国内生産の状況を評価する食料国産率の目標を設定しました。また、食料の潜在生産能力を評価する食料自給力指標についても同年度の見通しを示しています。
本節では、食料自給率・食料国産率、食料自給力指標等の動向等について紹介します。
(1)食料自給率・食料国産率の動向
(供給熱量ベースの食料自給率は38%、生産額ベースの食料自給率は58%)
食料自給率は、国内の食料消費が国内生産によってどれくらい賄えているかを示す指標です。供給熱量ベースの総合食料自給率は、生命と健康の維持に不可欠な基礎的栄養価であるエネルギー(カロリー)に着目したものであり、消費者が自らの食料消費に当てはめてイメージを持つことができるなどの特徴があります。
令和4(2022)年度の供給熱量ベースの総合食料自給率は、前年産において豊作だった小麦が平年並みの単収へ減少(作付面積は増加)し、魚介類の生産量が減少した一方、原料の多くを輸入に頼る油脂類の消費減少等により、前年度と同じ38%となりました(図表1-1-1)。
一方、生産額ベースの総合食料自給率は、食料の経済的価値に着目したものであり、畜産物、野菜、果実等のエネルギーが比較的少ないものの高い付加価値を有する品目の生産活動をより適切に反映させることができます。令和4(2022)年度の生産額ベースの総合食料自給率は、輸入された食料の量は前年度と同程度でしたが、国際的な穀物価格や飼料・肥料・燃油等の農業生産資材の価格上昇、物流費の高騰、円安等を背景として、総じて輸入価格が上昇し、輸入額が増加したことにより、前年度に比べ5ポイント低下し58%となりました。
食料・農業・農村基本計画においては、総合食料自給率について、令和12(2030)年度を目標年度として、供給熱量ベースで45%、生産額ベースで75%に向上させる目標を定めています。
(食生活の変化等に伴い、過去60年間で食料自給率は大きく変動)
供給熱量ベースの総合食料自給率は、分母である国内総供給熱量(国内消費)と、分子である国産総供給熱量(国内供給)から算出されますが、過去60年間を振り返ると、総人口の変動や食生活の変化等の影響を受け、大きな変動が見られています(図表1-1-2)。
我が国の食料自給率は、長期的には低下傾向にあり、供給熱量ベースの総合食料自給率は平成10(1998)年度に40%まで低下し、以降はおおむね40%程度で推移しています。長期的に食料自給率が低下してきた主な要因としては、食生活の多様化が進み、国内で自給可能な米の消費が減少したこと、輸入依存度の高い飼料を多く使用する畜産物の消費が増加したこと等が考えられます(図表1-1-3)。
平成20(2008)年以降は、総人口が減少基調に転換する中、国内消費は減少傾向で推移している一方、米の消費減少等を背景として国内供給も減少傾向で推移しており、食料自給率は横ばい傾向で推移しています。
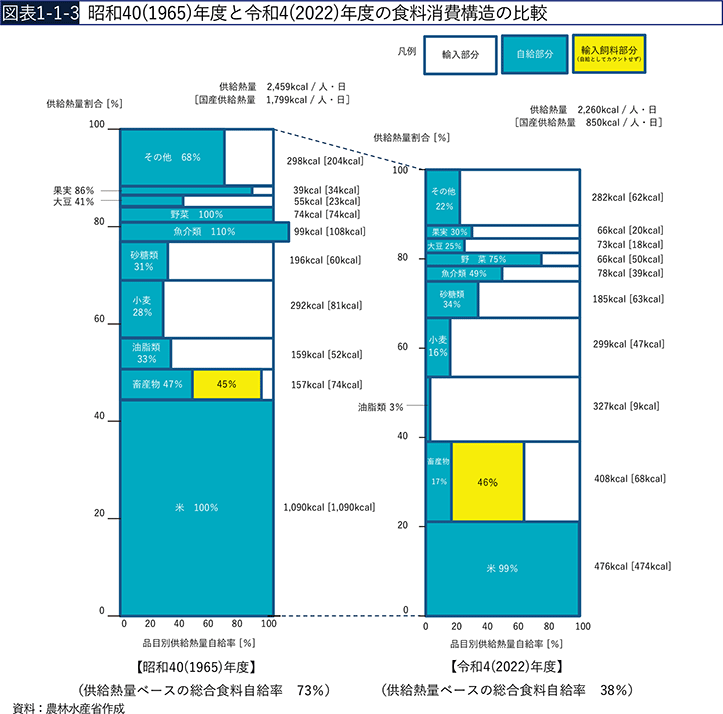

食料自給率・食料自給力について
URL:https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011_2.html
(供給熱量ベースの食料国産率は47%、飼料自給率は26%)
食料国産率は、飼料が国産か輸入かにかかわらず、畜産業の活動を反映し、国内生産の状況を評価するものです。需要に応じて増頭・増産を図る畜産農家の努力が反映され、また、国産畜産物を購入する消費者の実感に合うという特徴があります。
令和4(2022)年度の供給熱量ベースの食料国産率は、前年度と同じ47%となりました。また、飼料自給率は、前年度と同じ26%となりました。その内訳を見ると、粗飼料自給率は前年度に比べ2ポイント上昇し78%となった一方、濃厚飼料自給率は前年度と同じ13%となりました(図表1-1-4、図表1-1-5)。
食料自給率は輸入飼料による畜産物の生産分を除いているため、畜産業の生産基盤強化による食料国産率の向上と、国産飼料の生産・利用拡大による飼料自給率の向上を共に図っていくことで、食料自給率の向上が図られます。
(事例)飼料自給率の向上に向け、とうもろこしの二期作を大規模展開(熊本県)


飼料用とうもろこしの収穫
資料:菊池地域農業協同組合
熊本県菊池市(きくちし)の菊池(きくち)地域農業協同組合(以下「JA菊池」という。)では、畜産経営の自給飼料の確保に向け、コントラクター利用組合を中核とした、飼料用とうもろこしの二期作を大規模に展開しています。
JA菊池の管内は、九州地方でも有数の畜産地帯ですが、地域の担い手が減少する中、自給飼料の確保や労働負担の軽減が課題となっています。このため、JA菊池では、三つのコントラクター利用組合を組織し、管内3地区で、プランタや自走式ハーベスタ等の大型機械の共同利用による自給飼料生産の拡大・効率化の取組を進めています。
このうち平成12(2000)年に設立された七城(しちじょう)コントラクター利用組合(りようくみあい)では、飼料用とうもろこしの二期作を行っており、春播(はるま)きとうもろこしを4月に播種(はしゅ)し7月に収穫した後、夏播(なつま)きとうもろこしを8月に播種し11月に収穫しています。飼料用とうもろこしの収穫面積は増加傾向で推移しており、令和5(2023)年は260haとなっています。
同組合では、飼料用とうもろこしの播種・収穫に関する作業を受託し、同組合で雇用した人材が作業を請け負うことで、畜産農家の作業負担を軽減しています。生産された飼料用とうもろこしは、全て管内の畜産農家が利用しており、飼料価格高騰対策として生産コストの低減につながっているほか、循環型農業の推進にも寄与しています。
このほか、JA菊池では、飼料自給率の向上や飼料輸送に係るCO2削減等を図るため、飼料用米を配合飼料に20%程度混ぜて給餌した乳用種去勢牛を、「えこめ牛(ぎゅう)」として販売する取組を推進しており、あっさりとした食味で食べやすい牛肉として注目を集めています。
JA菊池では、今後とも、とうもろこしを始めとした飼料作物の生産を推進することで、飼料自給率の向上を図り、飼料生産基盤に立脚した力強い畜産経営を確立することを目指しています。
(2)食料自給力指標の動向
(いも類中心の作付けでは推定エネルギー必要量を上回る)
食料自給力指標は、食料の潜在生産能力を評価する指標であり、栄養バランスを一定程度考慮した上で、農地等を最大限活用し、熱量効率が最大化された場合の1人1日当たりの供給可能熱量を試算したものです。
令和4(2022)年度の食料自給力指標は、今日の食生活に比較的近い「米・小麦中心の作付け」で試算した場合、農地面積の減少、魚介類の生産量減少、小麦の単収減少等により、前年度を26kcal/人・日下回る1,720kcal/人・日となり、日本人の平均的な推定エネルギー必要量2,168kcal/人・日を下回っています(図表1-1-6)。
一方、供給熱量を重視した「いも類中心の作付け」で試算した場合は、労働力(延べ労働時間)の減少、農地面積の減少、魚介類の生産量減少等により、前年度を53kcal/人・日下回る2,368kcal/人・日となりましたが、日本人の平均的な推定エネルギー必要量を上回っています。
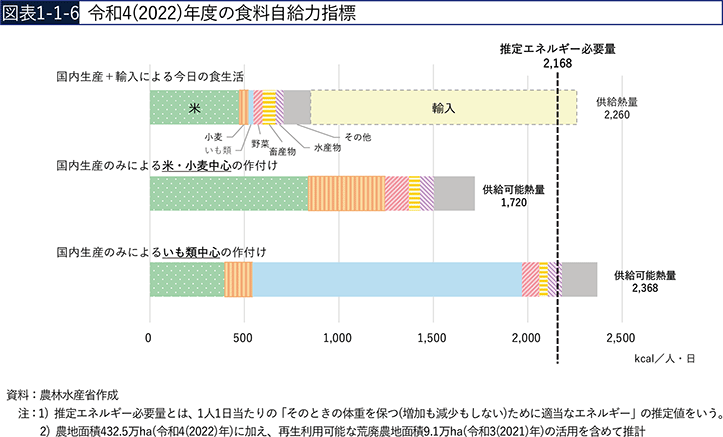
食料自給力指標は、近年、農地面積が減少する中で、米・小麦中心の作付けでは小麦等の単収向上により横ばい傾向となっている一方、より労働力を要するいも類中心の作付けでは、労働力(延べ労働時間)の減少により減少傾向となっています(図表1-1-7)。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883