第1節 農村人口の動向と地方への移住の促進

我が国の農村では、人口減少と高齢化が並行して進行しており、特に農業集落は小規模化が進行するなど、その影響が強く表れています。このような中で、地方の活性化を図っていくためには、地方への移住・定住を促進し、都会から地方への人の流れを生み出すことが重要となっています。
本節では、農村人口の動向や地方移住の促進に向けた取組等について紹介します。
(1)農村人口の動向
(農村における人口減少と高齢化が進行)
農村において人口減少と高齢化が並行して進行しています。総務省の国勢調査によると、令和2(2020)年の人口は、平成27(2015)年と比べ都市で1.6%増加したのに対し、農村では5.9%減少しています(図表4-1-1)。農村では生産年齢人口(15~64歳)、年少人口(14歳以下)が大きく減少しているほか、総人口に占める老年人口(65歳以上)の割合は、都市の25%に対し、農村では35%となっており、農村において高齢化が進んでいることがうかがわれます。
また、国立社会保障(こくりつしゃかいほしょう)・人口問題研究所(じんこうもんだいけんきゅうじょ)が令和3(2021)年6月に実施した調査によると、令和3(2021)年の平均出生子ども数は、農村が1.97人となり、都市の1.74人を上回る状況にある一方、農村・都市ともに、平均出生子ども数は減少傾向で推移しています(図表4-1-2)。
(特に中山間地域での人口減少と高齢化が顕著)
農業地域類型別の人口構成の変化を見ると、中山間地域での人口減少と高齢化が顕著になっています。平成12(2000)年と令和2(2020)年を比較すると、山間農業地域で30%減少したほか、中間農業地域で18%減少、平地農業地域で10%減少しており、中山間地域の人口減少率が高くなっています(図表4-1-3)。
また、令和2(2020)年の老年人口の割合は、山間農業地域で42%、中間農業地域で37%、平地農業地域で33%となっており、中山間地域で高齢化が進んでいます。
(農村では製造業や医療・福祉等の多様な産業が展開)
総務省の国勢調査によると、令和2(2020)年の農村の産業別就業者数は、「製造業」が348万人で最も多く、次いで「医療、福祉」となっています(図表4-1-4)。一方、「農業、林業」は156万人で全体の8.6%となっており、農村では第一次産業に限らず多様な産業が展開しています。農村人口の減少・高齢化が進む中、人口減少を緩和し、農村での就業機会を確保するためには、農村における産業の振興や農村での起業を進めることが重要です。
(2)農業集落の動向
(農業集落の小規模化や混住化が進行)
我が国の「地域の基礎的な社会集団」である農業集落は、地域に密着した水路・農道・ため池等の農業生産基盤や収穫期の共同作業・共同出荷といった農業生産面のほか、集落の寄り合い(*1)等の協働の取組や伝統・文化の継承といった生活面にまで密接に結び付いた地域コミュニティとして機能しています。
しかしながら、農業集落は小規模化が進行するなど、人口減少と高齢化の影響が強く表れており、総戸数が9戸以下の小規模な農業集落の割合については、令和2(2020)年は平成22(2010)年の6.6%と比べて1.2ポイント増加し7.8%となりました。また、農業集落に占める農家の割合を見ると、令和2(2020)年は5.8%にまで低下しており、混住化が大きく進展している様子がうかがわれます(図表4-1-5)。
小規模な集落では、農地の保全等を含む集落活動の停滞のほか、買い物がしづらくなるといった生活環境の悪化により、単独で農業生産や生活支援に係る集落機能を維持することが困難になるとともに、集落機能の低下が更なる集落の人口減少につながり、集落の存続が困難になることが懸念されています。このため、広域的な範囲で支え合う組織づくりを進めるとともに、農業生産の継続と併せて生活環境の改善を図ることが重要です。集落機能の維持はその地域の農地の保全や農業生産活動の継続にも影響することから、農村における労働人口の確保やコミュニティ機能の維持は重要な課題となっています。
1 地域の諸課題への対応を随時検討する集会、会合等のこと
(高齢化が進む農業集落では生活の利便性が低い傾向)
高齢化率別の農業集落の生活環境を見ると、老年人口の割合が高い農業集落では、生活の利便性が低い傾向にあります(図表4-1-6)。生活の利便性が低いと、更なる人口減少・高齢化につながり、集落存続の危機が深まります。このサイクルを断ち切るため、買い物や医療、教育等へのアクセスのほか、高齢者の見守り等の福祉サービスといった日々の生活に必要な生活環境の改善が重要になっています。
(農村人口の減少により営農継続が困難となるリスクが拡大)
農村のコミュニティ機能の低下に伴い、これらの集落に存在する農地での営農の継続が懸念されています。
令和32(2050)年の農地面積は、コミュニティとしての機能が失われる9人以下の小規模集落では31万ha、コミュニティ機能の維持が困難になる可能性の高い高齢化進行集落では67万ha、両方の条件を満たす存続危惧集落では26万9千haとなることが予測されています(図表4-1-7)。農村人口の減少により営農継続が困難となるリスクは拡大しており、食料安全保障の観点からも農村人口の維持・増加が課題となっています。
(農業集落の自立的な発展を目指す取組が各地で展開)
農業の停滞や過疎化・高齢化等により農村地域の活力の低下が見られる一方、地域住民が主体となって農業集落の自立的な発展を目指す取組も各地で進められています。
地域住民が地方公共団体や事業者、各種団体と協力・役割分担をしながら、行政施設や学校、郵便局等の分散する生活支援機能を集約・確保し、周辺集落との間をネットワークで結ぶ「小さな拠点」では、地域の祭りや公的施設の運営等の様々な活動に取り組んでいます。
総務省では、過疎地域を始めとした条件不利地域において、「集落ネットワーク圏」(小さな拠点)の形成に向けて、住民の暮らしを支える生活支援や、生業(なりわい)の創出を支援するとともに、優良事例を周知することとしています。

「小さな拠点」を整備し、多世代の交流を促進
資料:滋賀県甲賀市
農林水産省では、地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上や雇用の増大に結び付ける取組に対し、取組の発展段階に応じて総合的に支援し、農林水産業に関わる地域コミュニティの維持と農山漁村の活性化や自立化を後押ししています。
(3)移住の促進
(農村への関心の高まりを背景として、地方移住の相談件数は増加傾向)
内閣府が令和5(2023)年9~10月に実施した世論調査によると、5年前と比較して、農村地域への関心が高まったと回答した人は32.7%となっています(図表4-1-8)。
また、地方暮らしやUIJターンを希望する人のための移住相談を行っている認定NPO法人ふるさと回帰支援(かいきしえん)センター(*1)への相談件数については、近年増加傾向で推移しており、令和5(2023)年は前年に比べ13%増加し、過去最高の5万9,276件となりました(図表4-1-9)。

地方への移住・交流の促進に向けて、内閣官房は、デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)により、東京圏外へ移住して起業・就業する者に対する地方公共団体の取組を支援しています。また、総務省は、就労・就農支援等の情報を提供する「移住・交流情報ガーデン」の利用を促進しています。
農林水産省は、農村関係人口の創出・拡大等に向け、(1)農繁期の手伝い等農山漁村での様々な活動に、都市部等からの多様な人材が関わる機会を創出する仕組みの構築、(2)多世代・多属性の人々が交流・参加する場である「ユニバーサル農園」の導入等を推進し、農業への関心層の獲得により、将来的な農村の活動を支える主体となり得る人材の確保を図っています。
1 正式名称は「特定非営利活動法人100万人のふるさと回帰・循環運動推進・支援センター」
(事例)島の日常の魅力を発信し、地域活性化や移住促進の取組を展開(鹿児島県)

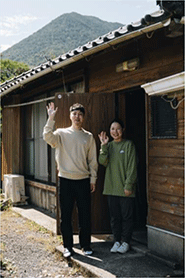
甑島への移住者
資料:東シナ海の小さな島ブランド
株式会社
鹿児島県薩摩川内市(さつませんだいし)の「東(ひがし)シナ海(かい)の小(ちい)さな島(しま)ブランド株式会社」は、東シナ海に位置する離島の甑島(こしきしま)において、島の日常の魅力を発信し、地域ブランドの確立を図るとともに、地域の活性化や移住の促進を図る取組を展開しています。
同島では、人口減少や高齢化が進む中、集落コミュニティの維持・存続に困難を来し、集落の空き家問題も深刻化しています。このような課題の解決に向け、同社では、地域に根差した生活文化や環境を活かした事業を展開し、地域活性化や移住の促進に取り組んでいます。
同社は、豆腐の製造・販売からスタートし、その後、キビナゴや柑橘(かんきつ)等の地場産品を利用した商品開発、古民家を改装したベーカリー、港の旧待合所を再開発したカフェレストランの運営等の多様な事業を展開しています。舟宿を改装した古民家ホステルでは、朝ごはんに地場産の豆腐や干物を提供するなど、宿泊客に島の日常の魅力を伝えています。
また、観光まちづくり組織として、玉石垣の再生活動に取り組みながら島内に豊富にある自然の魅力を伝える観光ガイドの取組や体験コンテンツ等を駆使した地域活性化にも取り組んでいます。
このような取組の結果、島の魅力に触れ、移住を希望する人が増加傾向にある一方、島で暮らしたいけれど誰を頼ったらいいのか分からないという移住希望者も見られています。同社では、移住者のスタッフも多数雇用していることから、実体験に基づいて相談に乗ることや、多様な事業活動の中で働く場を提供することにより、移住の促進に寄与しています。また、集落内の空き家を借り上げ、整備を行った上で移住者に貸し出すなど、空き家を壊すのではなく活かす方向で集落の活性化に取り組んでいます。
同社では、今後ともUIターン等の移住・定住や交流人口の拡大に向けた取組を推進するとともに、人材育成のための研修や街づくり関連のワークショップの開催といった地域づくり人材の育成を進め、同島の活性化に尽力していくこととしています。
(サテライトオフィスの開設数は拡大傾向で推移)
都市部の企業等が地方に、遠隔勤務のためのオフィスである「サテライトオフィス」を開設し、本社機能の一部移転や二地域居住のワークスタイルを実践するケースが増えてきています。また、地方においても雇用機会の創出や移住・定住の促進、新しい産業の創出に向けて、サテライトオフィスの誘致に取り組む地方公共団体が増えています。
令和4(2022)年10月に総務省が公表した調査によると、全国の地方公共団体が関わったサテライトオフィスの開設数については、近年増加傾向で推移しており、令和3(2021)年度は505か所開設され、累計では1,348か所となっています。
また、新たな企業が進出してきたことによる波及効果については、「移住者や二地域居住者の増加」、「地元人の雇用機会の創出」、「交流人口・関係人口の拡大」、「空き家・空き店舗の活用」、「地元企業との連携による新たなビジネスの創出」といった回答が挙げられています。
(事例)「にぎやかな過疎の町」の実現に向け、サテライトオフィスを誘致(徳島県)

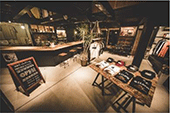
クリエイティブ複合施設
「at Teramae」
資料:株式会社あわえ

進出企業の協力による
小学生の就労体験
資料:株式会社あわえ
徳島県美波町(みなみちょう)では、「にぎやかな過疎の町」の実現に向け、地域課題を地域の資源と捉え、技術と起業のマインドを持った若者を誘致する「サテライトオフィス・プロジェクト」を推進しています。
同町では人口が6千人を切り、高齢化率は49%、空き家率は19%となるなど、地域課題が山積しています。このため、防災や空き家問題、地方創生等の地域課題についても資源として捉え、課題解決に関心を持つ企業の誘致につなげています。
役場内にはサテライトオフィスの誘致に取り組む担当者を置き、地域活性化支援事業を手掛ける「株式会社あわえ」とも連携しながら、サテライトオフィスの誘致と誘致後のサポートに積極的に取り組んでいます。
地域課題の解決に共に取り組むパートナーであるサテライトオフィス開設企業の取組は、認定こども園の高台移転、子供の安否確認、藻場の回復等多岐に渡っており、それぞれの企業が持つアイデアやノウハウを活かしながら、地域に貢献する動きが見られています。また、企業関係者による町内の祭りへの参加や、サテライトオフィスでの地元の子供たちの就労体験の実施等により、地域住民との関わりも広がっています。
サテライトオフィスへの関心が高まる中、同町では県内で最多となるサテライトオフィス企業の進出・集積や、若者移住者の増加といった地域活性化につながる変化が見られ、新たな「にぎわい」が生まれつつあります。
同町では、にぎやかな過疎の町を実現するため、「にぎやかそ」のキャッチフレーズの下に、関係者が一丸となって取組を進めており、今後とも、人口減少局面が続く厳しい現実にもしっかりと向き合いながら、サテライトオフィスの誘致や進出企業との連携により、にぎやかな町づくりを推進していくこととしています。
(農泊に取り組む地域におけるワーケーション需要への対応を推進)
リモートワークが普及する中、時間や場所にとらわれない働き方として「ワーケーション(*1)」が注目されています。
近年、企業がワーケーションの滞在先として地方の農山漁村を選ぶケースが増えており、各地方公共団体でも農山漁村をワーケーションの受入地域として積極的に誘致することで地域の活性化を図るケースも増えています。
国土交通省の調査によると、従業員100人以上の企業におけるワーケーション制度の導入率については、令和5(2023)年は前年に比べ増加し17.0%となっています(図表4-1-10)。また、ワーケーションの導入推進や利用促進のために、受入地域や施設に対して希望する環境やサービスとして、「セキュリティやスピード面が確保されたWi-Fi等の通信環境」が36.9%で最も多く、次いで「執務に必要な個室などのプライベートな空間」となっています。
農林水産省では、農泊に取り組む地域におけるワーケーション需要に対応するため、施設の改修、無線LAN環境の整備、オフィス環境の整備、企業等への情報発信等を支援しています。
1 「ワーク(仕事)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせたもので、観光地やリゾート地や帰省先等でパソコン等を使って仕事をすること
(デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づき人の流れを創出)

デジタル田園都市国家構想
URL:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/index.html(外部リンク)
「デジタル田園都市国家構想」は、デジタル技術の活用によって、地域の個性を活かしながら、地方の社会課題の解決や魅力の向上を図り、地方活性化を加速させるものであり、高齢化や過疎化に直面する農山漁村こそ、地域資源を活用した様々な取組においてデジタル技術を活用し、地域活性化を図ることが期待されています。
政府は、農村における人口減少を補うために、積極的に都市から農村への移住を進めることとしており、DX(*1)を進めるための情報基盤の整備、デジタル技術を活用したサテライトオフィス等の整備を行い、地方公共団体間の連携を促進しつつ、移住を促進するための農村における環境整備を進めることとしています。
また、農林水産省では、魅力ある豊かな「デジタル田園」の創出に向けて、関係府省と連携し、中山間地域等におけるデジタル技術の導入・定着を推進する取組を支援するとともに、デジタル技術の活用に係る専門人材の派遣や起業家等とのマッチング、スマート農業やインフラ管理等に必要な情報通信環境の整備等を支援することとしています。
1 第3章第8節を参照
(新たな「国土形成計画(全国計画)」を策定)
国土交通省は、令和5(2023)年7月に、新たな「国土形成計画(全国計画)」を策定・公表しました。同計画では、未曽有の人口減少、少子高齢化の加速化といった時代の重大な岐路に立つ中、「新時代に地域力をつなぐ国土」の形成を目指し、国土の刷新に向けて、「デジタルとリアルが融合した地域生活圏の形成」、「持続可能な産業への構造転換」等の四つの重点テーマを掲げ、更にこれらを効果的に実行するため、「国土基盤の高質化」と「地域を支える人材の確保・育成」を分野横断的なテーマとして掲げています。
農林水産分野においては、地域生活圏の形成に資する取組として、地域資源とデジタル技術を活用した中山間地域の活性化を推進するとともに、持続可能な産業への構造転換に向けて、食料安全保障の強化を目指した農林水産業の活性化等を推進することとしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883













