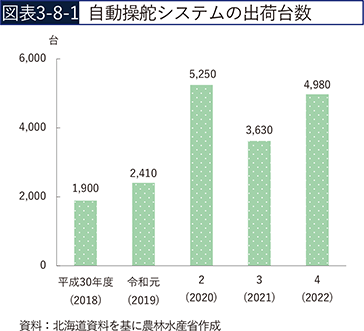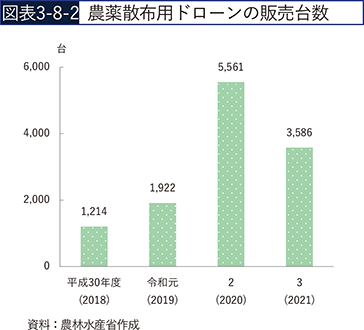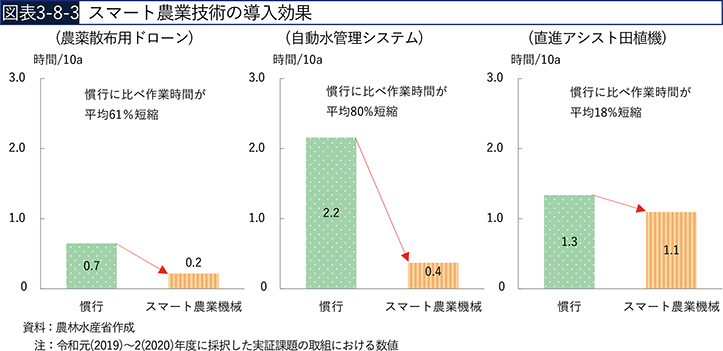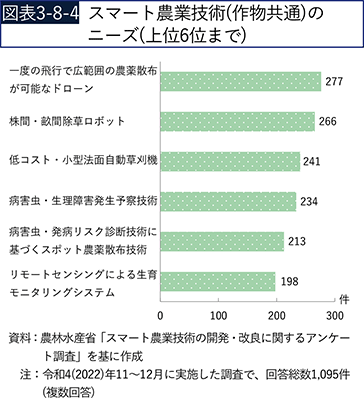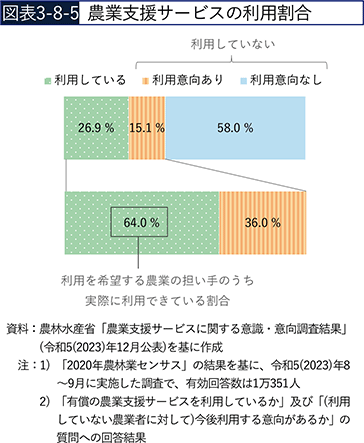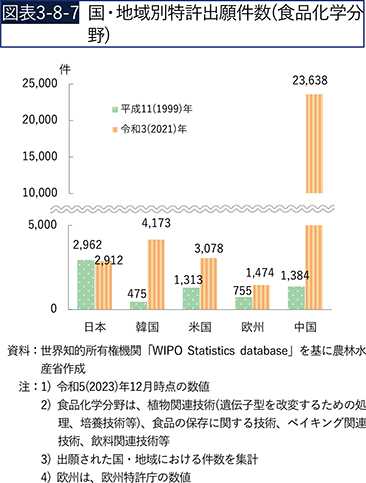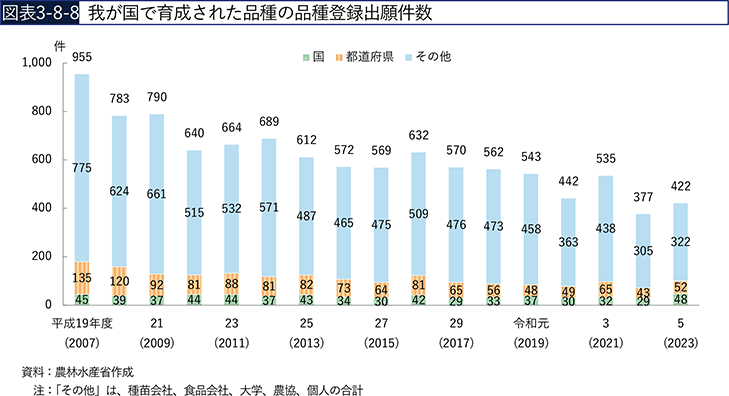第8節 スマート農業技術等の活用による生産・流通現場のイノベーションの促進
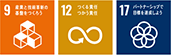
農業分野における生産・流通現場でのイノベーションの進展や、農業施策に関する各種手続や情報入手の利便性の向上は、高齢化や労働力不足等に直面している我が国の農業において、経営の最適化や効率化に向けた新たな動きとして期待されています。
本節では、スマート農業技術の導入状況や産学官連携による研究開発の動向、農業・食関連産業におけるデジタル変革に向けた取組等について紹介します。
(1)スマート農業技術の活用の推進
(農作業の自動化等を推進)
ロボット・AI・IoT等の先端技術やデータを活用し、農業の生産性向上等を図る取組が各地で広がりを見せています。
生産現場においては、ロボットトラクター、スマートフォンで操作する水田の水管理システム等の活用により、農作業を自動化・省力化する取組が進められているほか、位置情報と連動した営農管理システムの活用により、作業の記録をデジタル化・自動化し、熟練者でなくても生産活動の主体になることも容易となっています。また、ドローン等を活用したセンシングデータや気象データのAI解析により、農作物の生育や病虫害を予測し、高度な農業経営を行う取組等も展開されています。
農業分野におけるスマート農業技術の導入に関して、例えばGPS等の位置情報とハンドルの自動制御により、高精度な作業や軽労化に資する自動操舵(そうだ)システムの出荷台数については、令和4(2022)年度は前年度に比べ1,350台増加し4,980台となっています(図表3-8-1)。一方、農薬散布用ドローンの販売台数については、令和3(2021)年度は前年度に比べ1,975台減少し3,586台となっています(図表3-8-2)。
(スマート農業実証プロジェクトにおいて、作業の省力化や負担軽減の効果を確認)
農林水産省は、スマート農業技術を、実際の生産現場に導入して効果を明らかにするため、令和元(2019)年度以降、全国217地区で生産性や経営改善に関する実証を行う「スマート農業実証プロジェクト」(以下「実証プロジェクト」という。)を展開しています。水田作、畑作、露地野菜、施設園芸、花き、果樹、茶、畜産等の様々な品目で実証を行うとともに、スマート農業の普及状況や政策課題に合わせて実証プロジェクトのテーマを設定してきました。
その結果、農業機械の自動運転や遠隔操作による労働時間の削減、環境・生産データを活用した栽培管理による収量・品質の向上や化学農薬・化学肥料の削減、スマート農業機械のシェアリングや農業支援サービス事業体の活用による導入コストの低減等の効果が様々な品目で確認されました。また、農作業経験がない女性や新規就農者であっても、熟練農業者並みの速度・精度で作業が可能となるなどの成果も得られました。
スマート農業技術の導入効果を品目別に見ると、水田作では各農場の平均で、総労働時間が平均9%削減、単収が9%増加しています。また、技術別に見ると、農薬散布用ドローンで平均61%、自動水管理システムで平均80%、直進アシスト田植機で平均18%の作業時間の短縮を図れること等が明らかになっています(図表3-8-3)。

スマート農業実証プロジェクト
URL:https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/smart_agri_pro.htm(外部リンク)
(スマート農業の実装に当たって導入コスト等の課題も判明)
実証プロジェクト等を通じて、労働時間の削減や収量増大の効果等を確認できた一方、様々な課題も明らかになっています。
例えば果樹や野菜の収穫等といった人手に頼っている作物でスマート農業技術の開発が不十分な領域があり、開発の促進を図る必要があります。また、スマート農業機械等の導入コストが高いこと、それらを扱える人材が不足していること、従来の栽培方式にスマート農業技術をそのまま導入してもその効果が十分に発揮されないこと等の課題も判明しました。
農林水産省では、技術開発が不十分な領域が多数あることが明らかになったことを踏まえ、生産現場で必要とされているスマート農業技術の把握を行っています。令和4(2022)年11~12月に実施した調査によると、「一度の飛行で広範囲の農薬散布が可能なドローン」が277件で最も多く、次いで「株間・畝間除草ロボット」、「低コスト・小型法面(のりめん)自動草刈機」の順となっており、農業生産の省力化に直結する機械の開発・改良のニーズが高くなっています(図表3-8-4)。また、品目別では、露地野菜、施設園芸、果樹・茶の分野でいずれも「自動収穫ロボット」のニーズが高くなっています。
農林水産省では、これらの結果を踏まえ、スマート農業技術・機器の開発が必ずしも十分でない品目や分野を対象に、生産現場で求められるスマート農業技術の開発・改良を推進しています。
(農業支援サービス事業体の育成を推進)
スマート農業機械の導入コストが高いことや、扱える人材が不足していること等の課題に対しては、農業支援サービス事業体の活用が有効です。近年、ドローンやIoT等の最新技術を活用して農薬散布作業を代行するサービスやデータを駆使したコンサルティングといったスマート農業を支える農業支援サービスの取組が人手不足に悩む生産現場で広がっています。
令和5(2023)年度に実施した調査によると、農業支援サービスの利用を希望する農業の担い手のうち実際に利用できている割合は64.0%となっています(図表3-8-5)。
より多くの農業者が農業支援サービスを利用できる環境を作るためには、事業参入者の更なる拡大が重要であることから、通年で農業機械を稼働するためのニーズの確保、作業に必要な農業機械の導入や専門的な人材の育成、機械化が進展していない労働集約型作物に対するサービスの提供拡大等への対応も進めていく必要があります。
このため、農林水産省では、農業支援サービス事業体の新規参入、既存事業者による新たなサービス事業の育成・普及を進めることとしており、新規事業の立上げ当初のビジネス確立のための取組や他産地への横展開、サービスの提供に必要なスマート農業機械等の導入を支援しています。
また、農業支援サービス事業体に対する農業者の認知度の向上、農業支援サービス提供事業者と農業者のマッチング機会の創出を図るため、「農業支援サービス提供事業者が提供する情報の表示の共通化に関するガイドライン」に沿って情報表示を行う事業者のサービス内容等を農林水産省のWebサイト上で公開しているほか、マッチングサイトの構築を支援しています。
(事例)多様な農業支援サービスを展開し、中山間地の農業生産を後押し(広島県)


中山間地の樹園地で
作業するリモコン草刈機
資料:大信産業株式会社
広島県尾道市(おのみちし)の大信産業(たいしんさんぎょう)株式会社は、中山間地域等の農業生産の維持・発展を図るため、多様な農業支援サービスを展開しています。
同社は、肥料・農薬等の農業生産資材の卸販売やハウス・かん水設備の設計施工等を幅広く行っている一方、近年は農業用ドローンの普及のため、技術講習会を企画するなど、スマート農業の推進に注力しています。
スマート農業を活用した農業支援サービスとしては、農業用ドローンを活用した防除・施肥を始め、リモコン草刈機による樹園地の草刈り、リモートセンシングによる生育診断等の受託作業を実施しています。特に農業用ドローンは、急傾斜地の樹園地等では、自動航行による薬剤散布を行うことで、大幅な省力化を実現でき、高齢化が進む中山間地域での農業生産の維持に大きく貢献することが期待されています。
同社では、水稲やかんきつを対象にドローンによる防除を行っており、かんきつについては3Dカメラ付きドローンで撮影した映像を基に飛行ルートを作成し自動で防除作業を行っています。ドローンによる防除実績(延べ面積)は拡大傾向で推移しており、令和4(2022)年度は445haとなっています。防除作業は基本的に農協を経由して受注しており、防除作業料(農薬費を含む。)は水稲で4千円/10a程度、かんきつで8千円/10a程度(*)に設定されています。
ドローンの利用については、個人での購入はハードルが高い側面もあることから、同社では農業支援サービスの一層の活用・普及に向けて、効率的な自動飛行ルートの設定技術の向上とともに、農協等のオペレーターの育成・技能向上等を図っていくこととしています。今後とも進歩する農業技術に対応し、より高品質で安全な農産物の生産をサポートしていくこととしています。
農協によって受託料金が異なる場合がある。
(2)イノベーションの創出・技術開発の推進
(農林水産・食品分野においてもスタートアップの取組が拡大)
我が国における経済成長の実現のためには、新しい技術やアイデアを生み出し、成長の牽引(けんいん)役となるスタートアップの活躍が不可欠です。農林水産業や食品産業の現場においては、バリューチェーンの川上から川下まで様々な課題を抱えており、これらの課題解決に向けて、独自の技術シーズを新規事業につなげ、イノベーションを創出するスタートアップの研究開発力に大きな期待が寄せられています。
一方、農林水産・食品分野では、IT系や製薬・創薬等の分野に比べて、研究開発後、サービスを展開し、利益を回収するまでに相対的に長い期間を要するケースが多いといった特性が見られ、成長資金の流入が少ない状況にあります。
このため、農林水産省では、スマート農業技術にも対応した品種開発の加速化、農林漁業者等のニーズを踏まえ、現場では解決が困難な技術問題に対応する研究開発等を国主導で推進しています。
さらに、日本版SBIR(*1)制度を活用し、農林水産・食品分野において新たな技術・サービスの事業化を目指すスタートアップ・中小企業が行う研究開発等を発想段階から実用化段階まで切れ目なく支援することとしています。また、スタートアップ等が有する先端技術の社会実装を促進するため、新たに中小企業イノベーション創出推進事業を実施し、大規模な技術実証を支援しています。
このほか、投資円滑化法(*2)に基づき、スマート農業技術やフードテックのスタートアップ等に投資する民間の投資主体への資金供給を促進することとしています。

スタートアップによるピーマン自動収穫ロボットの開発
資料:AGRIST株式会社
1 Small Business Innovation Researchの略で、中小企業者による研究技術開発と、その成果の事業化を一貫して支援する制度のこと
2 第1章第7節を参照
(ムーンショット型研究開発を推進)
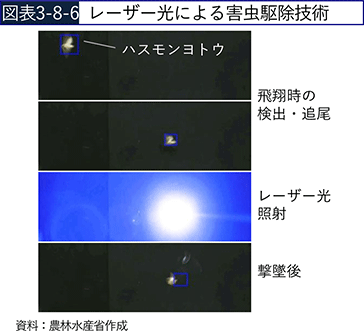
内閣府の総合科学技術・イノベーション会議(CSTI(システィ)(*1))では、困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題等を対象とした目標を設定し、その実現に向けた挑戦的な研究開発(ムーンショット型研究開発)を関係府省と連携して実施しています。このうち農林水産・食品分野においては、「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」することを目標として掲げ、食料の生産と消費の両面から八つの研究開発プロジェクトに取り組んでいます。これまでに、AIが害虫の不規則な動きを検知し、レーザー光照射で撃ち落とす技術の開発、牛の胃からメタンガス抑制機能を持つ細菌を分離・特定するなどの研究成果が生まれており、引き続き目標の実現に向けて研究開発を進めていくこととしています(図表3-8-6)。
1 Council for Science, Technology and Innovationの略
(「知」の集積と活用の場によるイノベーションを創出)
食品化学分野の特許出願件数については、欧米や中国等が中長期的に増加しているのに対し、我が国の特許出願件数はおおむね横ばい傾向で推移しています(図表3-8-7)。我が国における農林水産・食品分野の研究開発力を強化するためには、多様な分野を含めた産学官連携の量的・質的な深化を図っていく必要があります。
このため、農林水産省では、農林水産・食品分野におけるオープンイノベーションの促進を目的とした「「知」の集積と活用の場」を設け、イノベーションの創出に向けて、基礎から実用化段階までの研究開発やその成果の社会実装・事業化等を推進しています。令和6(2024)年3月時点で、多様な分野の業種から4,800以上の企業・大学等が参画し、海外各地域の嗜好性(しこうせい)分析に基づく輸出向けの日本酒、カニ殻由来のキチンナノファイバーを利用した化粧品といった新たな技術・商品の開発等が進められています。さらに、このような優れた研究成果の速やかな社会実装や事業化を推進するため、アグリビジネス創出フェア等を通じて幅広く情報発信を行っています。
(品種登録の出願件数は減少傾向で推移)
我が国における品種登録の出願件数については近年減少傾向で推移していますが、令和5(2023)年度は前年度に比べ45件増加し422件となっています(図表3-8-8)。
優良な新品種は農業の強みの源泉であり、その開発力の低下は我が国の農業競争力にも影響が及ぶことが懸念されています。食料の安定供給を確保するためには、生産性向上を始めとした課題に対応した画期的な品種を開発していくことが必須であり、そのためには品種開発力の充実・強化が必要です。
(スマート育種基盤やゲノム編集技術の活用等を推進)
農林水産省では、みどり戦略の実現に向け、スマート農業技術にも対応した品種開発の加速化や、生産現場の技術問題の解決を図る研究開発等を国主導で推進しています。これらの品種育成の迅速化を図るため、最適な交配組合せを予測するツールといった新品種開発を効率化する「スマート育種基盤」の構築を推進し、国の研究機関、都道府県の試験場、大学、民間企業等による品種開発力の充実・強化に取り組むこととしています。さらに、内閣府の研究開発プログラム「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP(*1))」では、令和5(2023)年度から、植物性たんぱく質の供給源として重要な役割を担っている食用大豆について、高収量・高品質な大豆品種開発のための育種プラットフォームの構築等を進めています。
また、近年では天然毒素を低減したジャガイモを始め、ゲノム編集(*2)技術を活用した様々な研究が進んでいます。一方で、ゲノム編集技術は新しい技術であるため、理解の促進が必要です。農林水産省は、ゲノム編集技術を活用した現場を体験できるオープンラボ交流会を実施したほか、大学や高校に専門家を派遣して出前講座等を行うなど、消費者に研究内容を分かりやすい言葉で伝えるアウトリーチ活動を実施しています。
このほか、令和5(2023)年5月に、花粉症に関する関係閣僚会議で決定された「花粉症対策の全体像」に基づき、花粉症の症状緩和を目指し、農研機構で開発されたスギ花粉米について、実用化に向けた更なる臨床研究等を実施することとしています。
1 Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Programの略
2 酵素等を用い、ある生物がもともと持っている遺伝子を効率的に変化させる技術
(3)農業施策の展開におけるデジタル化の推進
(令和6(2024)年2月に「農業DX構想2.0」を取りまとめ)
農業者の高齢化や労働力不足が進む中、社会の変化に的確に対応しつつ、生産性を向上させ、農業を持続的に成長できる産業としていくためには、発展著しいデジタル技術を積極的に活用して、経営の高度化や生産から流通・加工、販売等の変革を進め、生産性の向上を図ることが不可欠です。
農林水産省では、農業・食関連産業のデジタル変革(DX(*1))推進の羅針盤・見取り図として、令和3(2021)年3月に「農業DX構想」を策定し、その後、同構想の実現に向けたプロジェクトとして、食料・農業・農村の各分野の現場や行政実務等に係る様々なプロジェクトに取り組んできました。
他方、農業DX構想の策定以降も、生成AIやWeb3といったデジタル技術の目覚ましい発展が見られること、国内外の情勢が著しく変化していることを踏まえ、令和5(2023)年6月には「農業DX構想の改訂に向けた有識者検討会」が設置され、今後の農業・食関連産業のデジタル化の方向性や進め方等に関する議論が行われました。その結果、令和6(2024)年2月に農業・食関連産業のDXの実現に向けた、農業・食関連産業やテック企業等の関係者に対する「マイルストーンを示すナビゲーター」として「農業DX構想2.0」が取りまとめられました。農業DX構想2.0では、行政のみならず、農業・食関連産業関係者が取り組むべきDXへの道筋、テック企業を含む関係者が留意すべき事項が示されたほか、デジタル技術の導入後の活用方法に習熟するまでの支援策として、他の農業者等の導入事例の紹介、デジタル技術の導入に成功した後のイメージの提示、取組が目指す未来予想図のイメージ等が盛り込まれました。
1 Digital Transformationの略で、データやデジタル技術を駆使して、顧客や社会のニーズを基に、経営や事業・業務、政策の在り方、生活や働き方、さらには、組織風土や発想の仕方を変革すること。DXのXは、Transformation(変革)のTrans(X)に当たり、「超えて」等を意味する。
(eMAFF及びeMAFF地図の活用を推進)
「農林水産省共通申請サービス(eMAFF(イーマフ))」は、農林水産省が所管する行政手続をオンライン化し、利用者の利便性を向上させるものです(図表3-8-9)。
eMAFFは令和4(2022)年度末までに、農林水産省が所管する3,300を超える行政手続のオンライン化を実現しています。農林漁業者等を始め、地方公共団体等への普及活動を進めつつ、市町村等における審査体制の確立、オンライン利用の推進活動等の取組を令和6(2024)年度から本格化することとしており、利用者の声を聞きながら、利便性の向上や操作性の改善にも取り組むこととしています。
また、「農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF(イーマフ)地図(ちず))」は、農業に必要不可欠な農地に関する様々な制度のデータをデジタル地図の技術を活用して統合し、農地関係業務を抜本的に効率化するものです。
令和4(2022)年度からeMAFF農地ナビや現地確認アプリの運用を開始しており、令和5(2023)年度においては、制度ごと、関係機関ごとに個別に管理されている農地情報を一元的に管理し、農地関連行政手続のオンライン化、現地確認の効率化を図るため、地方公共団体等のほとんどで農地情報の紐付(ひもづ)けを実施したところであり、農業現場等においてeMAFF地図等の活用がより一層促進されることが期待されています。
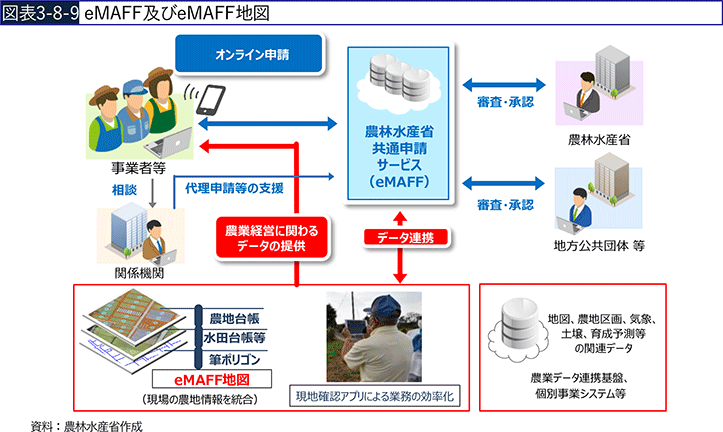
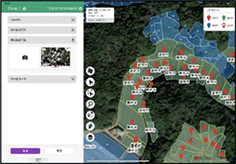
現地確認アプリの活用例
資料:農林水産省作成
(農林水産行政が保有するデータ活用に向けた環境整備等を推進)
農林水産業の生産・経営やそれらを取り巻く社会情勢の変化・多様化が加速する中、行政においてもデータを活用してその変化を的確に捉え、政策運営に活かしていくことの重要性が高まっています。農林水産省では、保有するデータをより使いやすく整備・蓄積するとともに、その組織的活用や人材育成を進めることによりデータ駆動型の行政を推進するため、「農林水産省データマネジメント・データ活用基本方針書」を令和5(2023)年10月に策定しました。
また、整備・蓄積されるデータの公開(オープンデータ化)を推進し、農林水産省が提供するオープンデータの充実や利便性向上を図ることとしています。
このほか、政府において、関係省庁における生成AIの業務利用に関し、令和5(2023)年5月に「ChatGPT(チャットジーピーティー)等の生成AIの業務利用に関する申合せ」が行われ、農林水産省では、これに留意しつつ、業務の効率化等の観点から生成AIを利用しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883