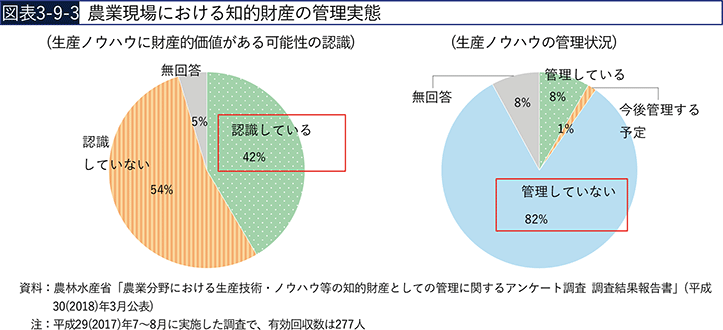第9節 知的財産の保護・活用の推進
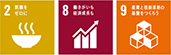
我が国では、農業分野における知的財産としての価値に対する認識や保護・活用に関する知識が十分ではなく、得られるべき利益を逸している事例が確認されています。また、今後、海外市場も視野に入れた農業への転換を目指していく中で、我が国における農業の強みの源泉となっている知的財産を適切に保護・活用することが重要となっています。
本節では、知的財産の保護・活用の取組について紹介します。
(知的財産の保護・活用に関して十分に浸透していない状況)
我が国の農林水産物・食品は、農林水産事業者や食品等事業者、地方公共団体・試験研究機関の関係者等の高品質・高付加価値なものを作る技術やノウハウ、我が国の食文化や伝統文化等の「知的財産」によって、諸外国に類を見ない特質・強さを有しています(図表3-9-1)。
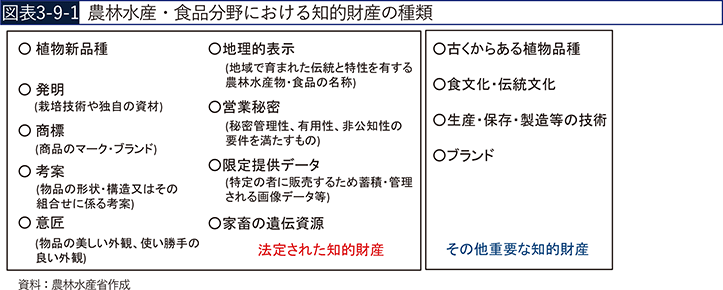
一方、知的財産の保護・活用については、生産技術や品種を無償で共有する慣習や、国・都道府県の品種開発が公的資金により行われていることから、開発費用が価格に上乗せされていないなどの背景があり、十分に浸透していない状況です。
このため、我が国の農林水産・食品産業分野の知的財産を戦略的に創出・保護・活用することにより、我が国の農林水産業・食品産業の国際競争力の強化を図ることが重要となっています。
(海外への無断流出の事例が複数確認)
我が国では農業の競争力強化のために、輸入品との差別化に向けた高品質化・ブランド化を重視し、これまで優れた品種や技術の開発・普及を推進してきた結果、世界的に高く評価されるジャパンブランドが確立されるに至っています。
しかしながら、これまで我が国の農業界では、農業分野における知的財産としての価値に対する認識や、保護・活用に関する知識が十分ではなく、このことが海外や国内他産地への無断流出につながっており、得られるべき利益を逸している事例も複数確認されています。

中国において「香印翡翠」の名称での
販売が確認されているシャインマスカット
今後、海外市場も視野に入れた農業への転換を目指していく中で、我が国における農業の強みの源泉となっている知的財産を適切に保護・活用していくことは極めて重要な課題です。そのため、知的財産に関する法令に基づく審査・実行体制の充実を始めとして、その実効性を高める取組を進め、我が国の農業競争力の維持・強化だけでなく、適切な対価を得ることを通じて継続的な研究開発を行っていくことが求められています。
(品種管理体制の強化に向けた育成者権管理機関の取組を推進)
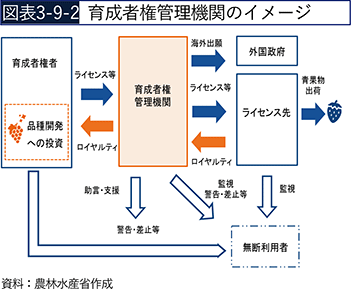
海外への品種の流出は、品種登録出願中や普及段階において生じている可能性がある一方、育成者権者である公的機関や個人育種家等では、登録品種の適切な管理や侵害対策の徹底が難しい現状にあります。
このため、植物新品種の育成者権者に代わって海外での登録出願、ライセンスを行うとともに、警告・差止等の侵害対応やこれらの助言・支援を行う育成者権管理機関の取組を、農研機構、JA全農、一般社団法人日本種苗協会(にほんしゅびょうきょうかい)、公益社団法人農林水産(のうりんすいさん)・食品産業技術振興協会(しょくひんさんぎょうぎじゅつしんこうきょうかい)(JATAFF)等が連携して、令和5(2023)年度から開始しました(図表3-9-2)。今後、同機関の取組を通じ、海外現地のライセンス先が実効的な監視を行うことで、現地制度に基づく差止等の法的措置も講じやすくなります。
(植物品種の審査のため、米国との間で協力覚書に署名)
我が国の植物品種の諸外国・地域における侵害に対処するためには、当該国・地域において品種登録が行われることが不可欠です。このため、我が国は、「植物の新品種の保護に関する国際条約」(UPOV(ユポフ)(*1)条約)の枠組みの下、加盟国・地域が、相手国・地域からの出願品種の審査に当たり、その相手国・地域における審査結果を活用する審査協力を進め、円滑な審査や迅速な登録を推進しています。
令和5(2023)年10月には、農林水産省と米国農務省との間で、「日米審査協力覚書」について署名を行いました。これにより、我が国から米国への出願品種の審査に当たり、米国は我が国の品種登録審査結果を用いることが可能となりました。我が国からの輸出拡大に向け、米国での審査期間の短縮による我が国における優良品種の保護の迅速化が期待されています。
1 International Union for the Protection of New Varieties of Plantsの略で、植物新品種保護国際同盟のこと
(農林水産物・食品の海外での模倣品疑義情報相談窓口を設置)
我が国の農林水産物・食品は、海外で高く評価されている一方、海外で模倣品(偽物)の流通が多数発見されています。
このため、農林水産省では、我が国の農林水産物・食品の海外での模倣品がジャパンブランドの毀損や輸出促進の阻害要因となることから、特許庁、外務省、JETROの関係省庁等と連携して、模倣品疑義情報を受け付ける窓口を設置しました。令和5(2023)年11月にタイ(バンコク)、同年12月に中国(北京、上海、広州、成都)、香港(香港)、令和6(2024)年3月に台湾(台北)の輸出支援プラットフォーム内に相談窓口を設置し、既に海外展開している又は海外展開を検討中の事業者・団体から広く情報提供や相談を受け付けています。これらの情報を基に、現地での商標取得等の権利化を促進するとともに、産地偽装等が疑われる事案については現地当局に情報提供の上、適切な取締りを依頼することとしています。
(和牛遺伝資源の管理・保護を推進)
和牛は関係者が長い年月をかけて改良してきた我が国固有の貴重な財産であり、和牛の改良を継続的・効果的に促進し、国内の生産振興や和牛肉の輸出拡大を図るためには、精液等の遺伝資源の適正な流通管理を行い、知的財産としての価値を保護することが重要です。
農林水産省では、和牛遺伝資源の生産事業者と、その譲渡先との間で、使用者の範囲等について制限を付す契約を普及させることにより、知的財産としての保護を図り、和牛遺伝資源の管理・保護を推進しています。
また、令和4(2022)年度には、家畜改良増殖法に基づき、全国の家畜人工授精所1,175か所への立入検査を実施し、法令遵守の徹底を図りました。
(知的財産の戦略的な活用を推進)
農業現場には、熟練農業者の優れた技術・ノウハウや栽培データ等の重要な知的財産が多数存在していますが、農業現場ではこれらは保護すべき知的財産であるとの意識が希薄な状況にあります。
農業者を対象に実施した調査によると、農業者の約4割はノウハウに財産的価値がある可能性を認識しつつも、8割以上はノウハウを管理していないとの結果が見られています(図表3-9-3)。一方、知的財産の戦略的な活用により、知的財産の創出や保護に係るコストを回収し、ライセンス収入を得られる知的財産ビジネスが可能になります。
農林水産省では、育成者権者が、我が国の品種の無断栽培を実効的に抑止しつつ、国内農業の振興や輸出促進に寄与する戦略的な海外ライセンスを行うための指針となるものとして、令和5(2023)年12月に「海外ライセンス指針」を策定しました。
また、我が国の優れた品種や技術等の知的財産を侵害や流出から守り、収入に変えていくため、農業・食品分野における関係者の知的財産教育を充実させるとともに、知的財産を戦略的に活用できる専門人材の育成・確保に取り組んでいます。また、学生向け教材として作成したテキストの活用や学生向け講座の拡大を図りながら、農業分野の知的財産に明るい次世代人材の育成を図っています。
(事例)知的財産権を活用して特産品のブランド価値を向上(長野県)
長野県飯田市(いいだし)に本所を置く「みなみ信州(しんしゅう)農業協同組合」(以下「JAみなみ信州」という。)では、地域特産物である「市田柿(いちだかき)」の知的財産権の使用や権利の行使を始め、国内外にわたる戦略を構築し、知的財産の活用による輸出促進や地域への貢献等広範囲にわたる活動を展開しています。
市田柿は、同県飯田市、下伊那郡(しもいなぐん)の各町村及び飯島町(いいじままち)、中川村(なかがわむら)に古くから伝わる伝統加工品の干し柿であり、JAみなみ信州の柿部会では、令和5(2023)年12月時点で1,836人の生産者がおり、令和4(2022)年度の販売額は26億4千万円となっています。
JAみなみ信州では、海外産の模倣品の流通等を契機に、産地全体での品質向上やブランドの維持・向上を図るため、平成18(2006)年に地域団体商標を取得したほか、平成19(2007)年に市田柿(いちだかき)ブランド推進協議会(すいしんきょうぎかい)を設立し、平成28(2016)年には地理的表示(GI(*))として登録されました。また、海外で模倣品が出回る中、平成21(2009)年に香港、平成22(2010)年に台湾で商標登録を行いました。さらに、GI取得は国・地域単位で必要となるため、これまでにタイ、ベトナム、マレーシア、シンガポールで登録を行っています。
また、JAみなみ信州では、知的財産を多様な側面から複合的に保護する「知財ミックス」によるブランド力の強化を図ってきており、地域特産品の名称や農業技術の保護、農家所得の向上に向け、知的財産の一層の活用を推進していくこととしています。今後は、市田柿の甘く、もっちりとした品質を維持するため、温暖化等に耐え得る技術改良や機械化に取り組むほか、消費者のニーズに合わせた商品等の開発、海外へのスペシャルティフードとしての輸出も視野に入れた取組を展開していくこととしています。
Geographical Indicationの略

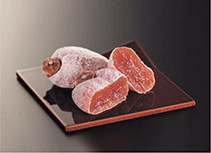
GI登録されている「市田柿」
資料:みなみ信州農業協同組合

台湾でのプロモーション活動
資料:みなみ信州農業協同組合
(新たに19産品がGI登録)
地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。同制度は、国による登録によりそのGI産品の名称使用の独占が可能となり、模倣品が排除されるほか、産品の持つ品質、製法、評判、ものがたり等の潜在的な魅力や強みを「見える化」し、GIマークと相まって、効果的・効率的なアピール、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツールとして機能するものです。
国内のGI登録産品については、令和5(2023)年度は新たに19産品が登録され、これまでに登録された国内産品は、同年度末時点で43都道府県の計145産品となりました(図表3-9-4)。
また、日EU・EPAにより、日本側GI108産品、EU側GI121産品が相互に保護され、日英EPAにより、日本側GI77産品、英国側GI30産品が相互に保護されています。このほか、二国間の協力枠組みに基づき、タイとの間で日本側GI6産品、タイ側GI2産品、ベトナムとの間で日本側GI3産品、ベトナム側GI2産品が登録されています。
農林水産省では、令和4(2022)年11月にGI保護制度の運用を見直し、農林水産物・食品の輸出拡大、所得や地域の活力向上に資するようGI保護制度の活用を推進しています。令和5(2023)年度にはこのような運用見直しの効果もあり、GI申請数の拡大が見られています。また、GIマークの活用とともに、GI産品と他業種とのコラボレーションを通じて、市場においてGIやGIマークを露出する機会を増やし、実需者の認知・価値を向上させていくこととしています。
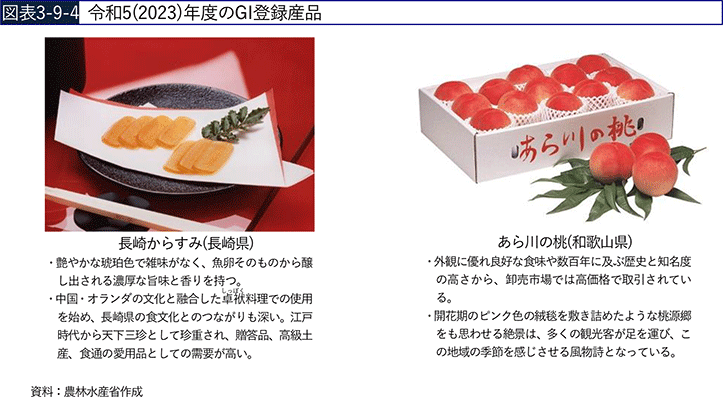
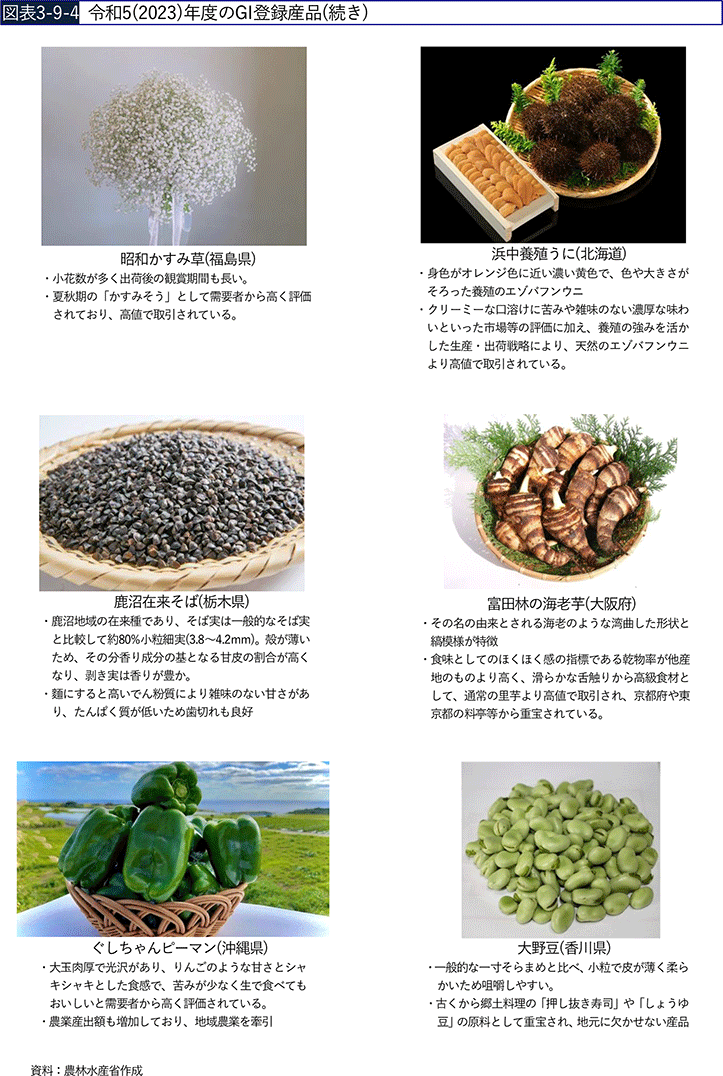

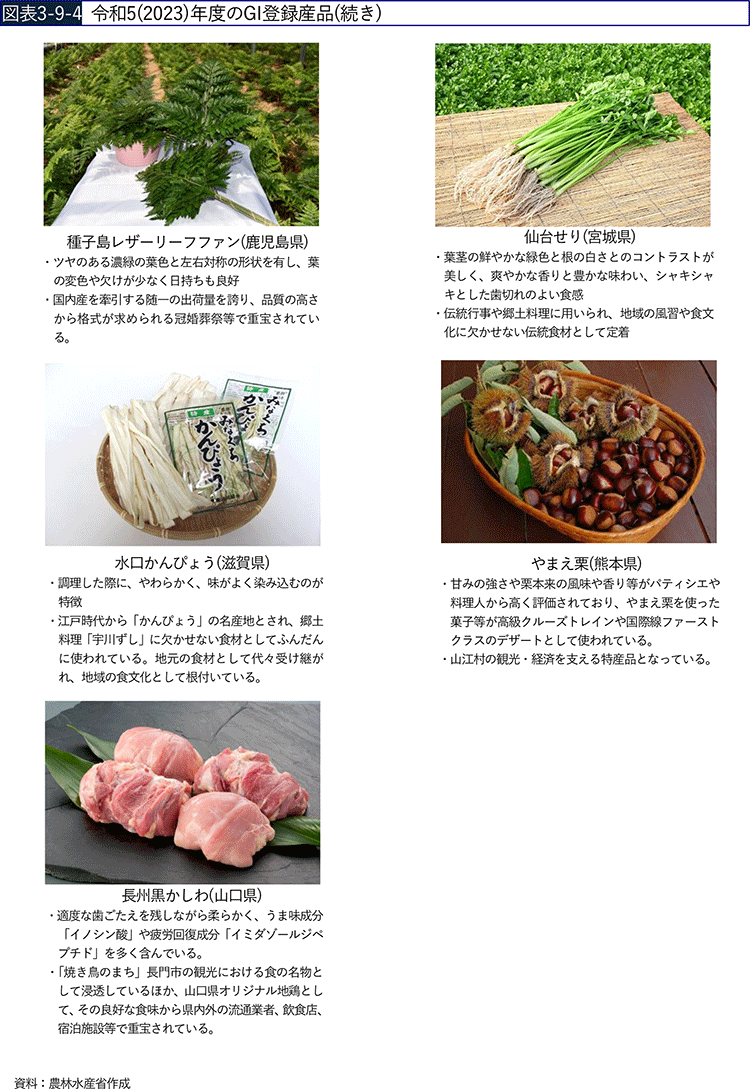

知的財産・地域ブランド情報
URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883