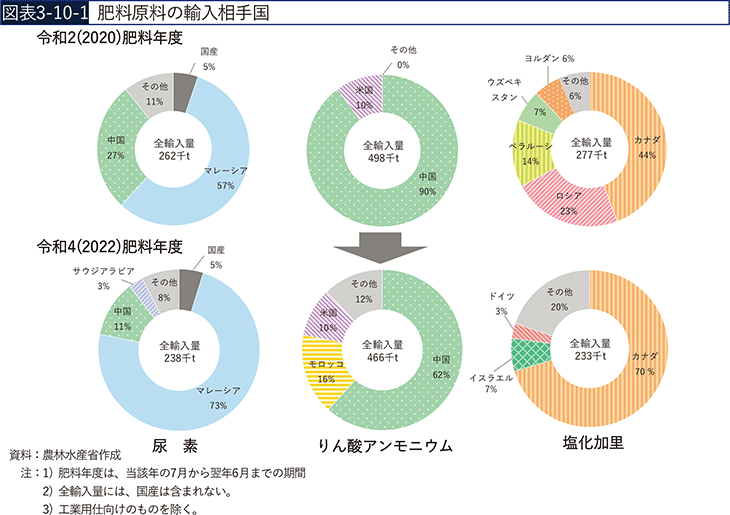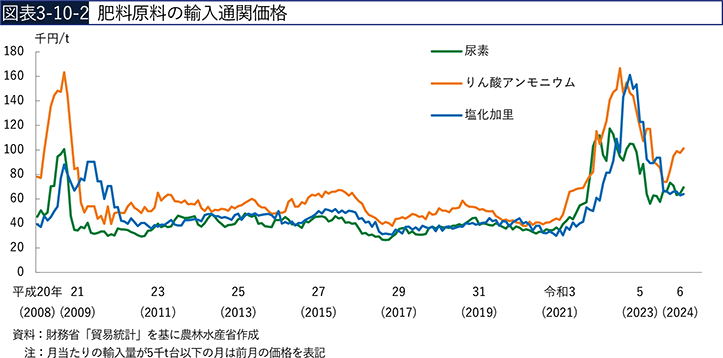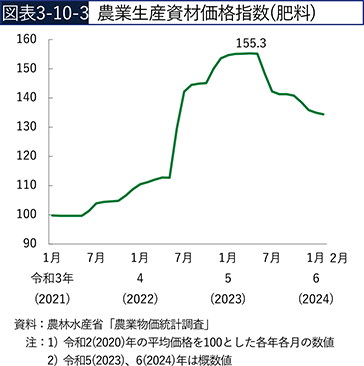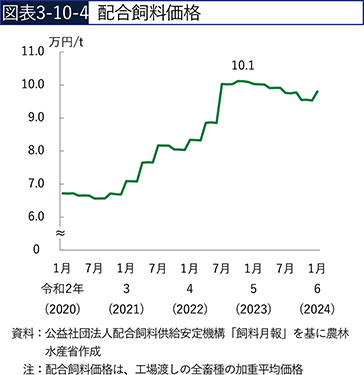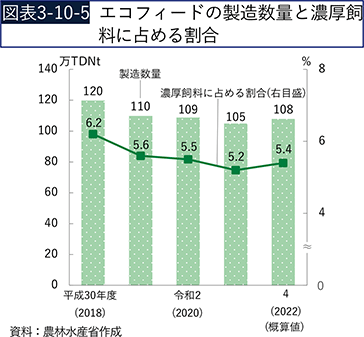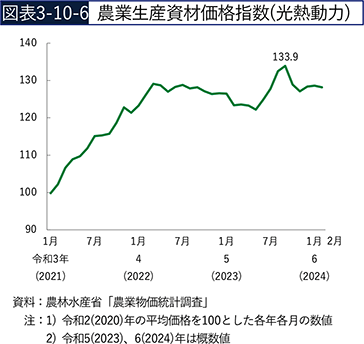第10節 農業生産資材の安定確保と国産化の推進
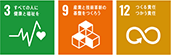
農業生産に必要な肥料や飼料等の農業生産資材については、価格高騰や原料供給国からの輸出の停滞等の安定供給を脅かす事態が生じるなど、食料安全保障上のリスクが増大しています。このため、輸入依存度の高い農業生産資材について、未利用資源の活用を始め、国内で生産できる代替物へ転換していくことが重要となっています。
本節では、農業生産資材の安定確保に向けた取組や価格高騰への対応について紹介します。
(1)肥料原料の安定確保と肥料価格高騰への対応
(化学肥料原料は特定国からの輸入に大きく依存)
主要な肥料原料の資源は、世界的に偏在しています。りん鉱石は、中国、モロッコ、エジプトの3か国で世界の経済埋蔵量の約8割を占めています。また、加里鉱石は、カナダ、ベラルーシの2か国で約7割を占めています。
このような中、我が国では、りん酸アンモニウムや塩化加里のほぼ全量を、尿素は95%を海外産出国から輸入しています(図表3-10-1)。化学肥料原料の大部分を特定国からの輸入に依存している状況の下では、輸出国側の輸出制限や国際価格の影響を受けやすいことから、輸入の安定化や多角化、輸入原料から国内資源への代替を進めていく必要があります。
令和3(2021)年秋以降、中国による肥料原料の輸出検査の厳格化やロシアによるウクライナ侵略の影響により、我が国の肥料原料の輸入が停滞したことを受け、りん酸アンモニウムのモロッコからの輸入割合の上昇を始めとして、調達国を多角化する動きも見られています。
(肥料原料の輸入通関価格は令和5(2023)年1月以降、下落基調に転換)
肥料原料の輸入通関価格は、令和3(2021)年以降、上昇傾向にある中で、ロシアによるウクライナ侵略や為替相場の影響等の要因も重なり、尿素は令和4(2022)年4月に過去最高値となる11万7千円/t、りん酸アンモニウムは令和4(2022)年7月に過去最高値となる16万7千円/t、塩化加里は令和4(2022)年10月に過去最高値となる16万1千円/tとなるなどの価格上昇が見られました(図表3-10-2)。その後、国際的な需要の落ち着き等を背景として、令和5(2023)年1月以降は下落基調に転じています。
また、我が国の農業生産資材価格指数(肥料)は、令和3(2021)年以降、上昇傾向で推移していましたが、令和5(2023)年4月に155.3に達して以降は低下しています(図表3-10-3)。
肥料価格の高騰は、農業経営にも影響を及ぼすことから、国際情勢等も踏まえ、今後も価格動向を注視していく必要があります。
(肥料原料の過度な輸入依存からの脱却に向け、肥料の国産化を推進)
国際情勢に左右されにくい安定的な肥料の供給と持続可能な農業生産を実現することが求められている中、肥料原料の過度な輸入依存からの脱却に向け、国内資源を活用した肥料への転換を進めています。
このため、農林水産省では、肥料の国産化を図るため、畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源等の国内資源の肥料利用を推進することとしています。
具体的には、肥料の原料供給事業者、肥料製造事業者、肥料利用者の連携による堆肥等の高品質化・ペレット化等に必要な施設整備、国内肥料資源の利用拡大に必要な圃場(ほじょう)での効果実証や機械導入等を支援するとともに、地域によって偏在する家畜排せつ物を原料とした堆肥を有効活用するため、ペレット化し広域流通させる取組の実証を支援しています。
さらに、肥料価格の高騰が農業経営に及ぼす影響の緩和を図るため、令和4(2022)年度の予備費を活用し、令和4(2022)年6月~5(2023)年5月に販売された肥料を対象に、予算額788億円の規模で、化学肥料の使用量の低減に向けた取組を行う農業者に対し、前年度からの肥料コスト上昇分の7割を支援しました。
また、肥料価格高騰対策と併せて、化学肥料の使用量低減に取り組む地域活動を支援する追加対策を実施し、土壌診断に基づく適正施肥や堆肥等の国内資源の利用等の取組を支援しました。
くわえて、堆肥等の有機物は土壌の性質によって効果が異なり、供給コストも要することから、国内資源由来肥料についての効率的・効果的な利用と流通を推進するため、全国の農地土壌で地力調査を実施して、土壌の性質に応じた利用ポテンシャルを明らかにすることとしています。
(国内資源の肥料利用の拡大を推進)
農林水産省は、国内資源の肥料利用の拡大に向け、原料供給から肥料製造、肥料利用に至るまで連携した取組を各地で創出していくことを目的として、令和5(2023)年2月に「国内肥料資源の利用拡大に向けた全国推進協議会」を設置しました。
同協議会では、同年6月に、「国内肥料資源の利用拡大プロジェクト」を立ち上げ、(1)生産現場等における栽培実証データ等の知見の集約、(2)国内資源由来肥料に関する取組内容等の発信、(3)国内肥料資源推進ロゴマークの活用促進を図ることとしており、各地で国内資源由来肥料の利用拡大に取り組む「ヒト」や「情報」のネットワーク化を進め、各地域における取組をより一層後押しすることとしています。

国内肥料資源推進ロゴマーク
(下水汚泥資源の利用を促進)
輸入依存度の高い肥料原料の価格が高騰する中で、持続可能な食料システムの構築に向け、下水汚泥資源の活用に対する関心が高まっています。
国土交通省が実施した調査によると、令和4(2022)年時点で我が国の全汚泥発生量に占める肥料利用の割合は約1割となっています。下水汚泥資源中には肥料成分である窒素やりん等が含まれますが、これまでその多くが主に焼却灰として埋立てや建設資材等に活用されていることから、今後は肥料としての利用を更に拡大していくことが必要です。
令和5(2023)年度においては、農林水産省と国土交通省が連携し、下水汚泥資源の肥料利用の促進に向けた技術実証や大規模案件の形成支援、シンポジウムによる情報発信等に取り組みました。
このほか、農林水産省では、肥料成分を保証できる新たな公定規格である「菌体りん酸肥料」を創設し、令和5(2023)年10月に施行しました。肥料成分が保証可能となることで農業者にとって使いやすい肥料となるほか、他の肥料の原料としても利用可能になることから、汚泥資源を使用した新たな肥料の開発が進むことが期待されます。
(事例)未利用資源を活用した肥料の開発・販売を推進(福岡県)


回収された再生りん
資料:福岡市和白水処理センター
福岡県福岡市(ふくおかし)に所在する全国農業協同組合連合会福岡県(ふくおかけん)本部(以下「JA全農ふくれん」という。)は、同市と連携し、未利用の下水汚泥資源を活用した肥料の開発・販売を推進しています。
博多湾(はかたわん)の環境保全を目的として、下水の高度処理を行っている同市の和白水処理(わじろみずしょり)センターでは、下水を浄化する過程でりんを回収し、「再生りん」として肥料原料に活用しています。令和4(2022)年度のりん回収量は、設備の更新により前年度の約10倍となる99tに増加しました。
JA全農ふくれんでは、再生りんを肥料原料として活用し、県内JAグループの堆肥を使った有機質配合肥料を同年9月から製造・販売しており、令和5(2023)年度の販売量は1,320tとなっています。従来使用していた化学肥料と比べて収量・品質は同等であり、価格は約20~30%安いことから、肥料価格高騰の影響を受ける農業者の経営安定に寄与しています。
一方で、肥料の需要は、施肥の時期に高まるため、オフシーズンは在庫の問題が生じるほか、水処理施設での一時保管場所の確保等の課題を解決する必要があります。
下水から回収する再生りんは、安定的な供給が可能な都市資源であり、再生りんの有効活用は脱輸入依存や環境負荷の低減につながるため、JA全農ふくれんでは、今後とも同市と連携しながら、再生りんの有効活用の促進に取り組むこととしています。
(肥料原料の備蓄の取組を支援)
肥料は、我が国の食料安定供給に極めて重要な役割を果たしていますが、主要な化学肥料の原料となる資源は特定の地域に偏在しており、そのほとんどの供給を輸入に依存しています。また、世界的な穀物需要の増加や紛争の発生等の国際情勢の変化により、原料の供給途絶リスクが顕在化しています。
このため、令和4(2022)年5月に成立した経済安全保障推進法(*1)に基づく特定重要物資として肥料を指定し、その安定供給に取り組む肥料原料の輸入事業者・肥料製造事業者による肥料の供給確保計画の認定を行い、肥料原料の備蓄の取組を支援することとしています。具体的には、令和9(2027)年度までにりん酸アンモニウム及び塩化加里について、それぞれの年間需要量の3か月分に相当する数量を備蓄する体制の構築に向けて、事業者の参画を進めており、令和6(2024)年3月末時点で、7事業者の供給確保計画を認定し、りん酸アンモニウムでは1.9か月分、塩化加里では2.8か月分の備蓄体制を構築しています。
1 正式名称は「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」
(2)国産飼料の生産・利用の拡大と飼料価格高騰への対応
(配合飼料価格は引き続き高い水準で推移)
家畜の餌となる配合飼料は、その原料使用量のうち約5割がとうもろこし、約1割が大豆油かすとなっています。我が国は原料の大部分を輸入に依存していることから、穀物等の国際相場の変動に価格が左右されます。とうもろこしの国際相場は、バイオエタノール向け需要の拡大や主産国における生産動向、ロシアによるウクライナ侵略等を背景に、高い水準で推移しています。配合飼料の工場渡価格は、令和4(2022)年10月に過去最高となる10万1千円/tとなって以降、とうもろこしの国際価格が下落したこと等を受け、やや低下傾向で推移していますが、依然として高水準にあることから、今後も価格動向を注視していく必要があります(図表3-10-4)。
(飼料の過度な輸入依存からの脱却に向け、国産飼料の生産・利用拡大を促進)
我が国の畜産経営において、令和4(2022)年の経営費に占める飼料費の割合を畜種別に見ると、約4~7割となっています。
農林水産省では、飼料価格高騰による畜産経営への影響を緩和するため、令和4(2022)年度において、国費総額で約1,900億円の予算を措置し、配合飼料価格安定制度等により生産者に補塡金を交付しました。また、令和5(2023)年度においては、配合飼料価格の高止まりが継続し、配合飼料価格安定制度の仕組み上、補塡が急減することによる、飼料コストの急増が懸念されたことから、一定期間にわたり連続で補塡が続いた後の配合飼料価格の高止まり等の場合に、飼料コストの急増を段階的に抑制する「緊急補塡」を制度内に設けて、必要な財源を措置しました。緊急補塡は、令和5(2023)年度第1四半期から第3四半期まで発動しています。
さらに、国産飼料の生産・利用拡大のため、耕畜連携、飼料生産組織の規模拡大、中山間地における地域ぐるみの取組、独立行政法人家畜改良(かちくかいりょう)センターにおける国内育成品種の供給能力強化、広域流通体制の構築、飼料の増産に必要な施設整備等を支援しています。
(事例)地域内耕畜連携による自給飼料の生産拡大と広域流通を推進(高知県)


稲WCS収穫作業
資料:南国市耕畜連携協議会
高知県南国市(なんこくし)の南国市耕畜(なんこくしこうちく)連携協議会(れんけいきょうぎかい)では、地域内の耕畜連携による自給飼料生産の拡大と広域流通を推進しています。
同市は、同県内における稲作の主要な生産地であり、輸入飼料価格の高騰を機に、耕種農家が飼料用稲を栽培・収穫・調製するとともに、酪農家が運搬・保管・給餌する取組を開始しました。
同協議会は、平成27(2015)年度に同市内の耕種農家及び畜産農家により設立され、令和5(2023)年11月末時点で、耕種農家9戸及び畜産農家3戸が構成員として活動しています。
同協議会では、平成27(2015)年に県の補助事業を活用して稲WCS(*)専用収穫機等を導入し、利用・供給体制の確立を進めてきました。また、構成員である畜産農家へ稲WCSを供給し、堆肥を耕種農家の圃場へ還元する体制の確立を進めてきました。
これにより、水田で生産した稲WCSを牛に給餌し、牛ふん由来の堆肥を活用して稲WCSを生産する「耕畜連携」を通じた資源循環型農業の取組が拡大しています。稲WCSの作付・収穫面積については、令和5(2023)年は64.4haとなっており、平成28(2016)年と比べて2倍以上に拡大しています。稲WCSの生産拡大とともに、その供給先も周辺地域に拡大しており、国産飼料の広域流通に寄与しています。
同協議会では、今後とも耕畜連携による地域資源の有効活用を推進しながら、土づくりや肥料コストの削減、環境負荷の低減等を図っていくこととしています。
第3章第1節を参照
(耕畜連携への支援を強化)
生産現場においては、耕種農家の生産した国産飼料を畜産農家が利用する取組が増加しているほか、水田では、水稲の収穫に伴い、稲わらやもみ殻といった利用価値の高い副産物が産出され、家畜の飼料や敷料等の有用な資源として活用されています。また、家畜の飼養に伴い排出される家畜排せつ物は堆肥にすることにより、肥料や土壌改良資材等の有用な資源として活用されています。
農業生産資材価格が高騰し、耕種農家・畜産農家双方の経営に影響が見られる中、耕種農家と畜産農家が連携し、飼料作物と堆肥を循環させる「耕畜連携」の取組について、その重要性が一層高まっています。
農林水産省では、飼料作物を生産する耕種農家への飼料給与情報や飼料分析結果の提供のほか、耕畜連携協議会が行う畜産農家と耕種農家のマッチング活動といった国産飼料の生産・利用拡大のための取組を支援しています。
(エコフィードの製造数量は前年度に比べ増加)
食品製造副産物等を利用して製造された飼料である「エコフィード(*1)」の利用は、食品リサイクルによる資源の有効活用や国産飼料の生産・利用拡大等を図る上で重要な取組です。
令和4(2022)年度のエコフィードの製造数量は、前年度に比べ2.5%増加し108万TDN(*2)tとなり、濃厚飼料全体の5.4%に相当する水準となっています(図表3-10-5)。
農林水産省では、地域の未利用資源を新たに飼料として活用するため、エコフィードの生産・利用を推進しています。
1 食品製造副産物等を有効活用した飼料のこと。「環境にやさしい(ecological)」や「節約する(economical)」等を意味する「エコ(eco)」と飼料を意味する「フィード(feed)」を併せた造語
2 第3章第1節を参照
(3)燃料価格高騰への対応
(燃料価格の高騰に対し、施設園芸農家等に向けた支援策を実施)
我が国の施設園芸経営において、令和4(2022)年の経営費に占める燃料費の割合は約2~4割となっています。
農業生産資材価格指数(光熱動力)は、令和3(2021)年以降、上昇傾向で推移し、令和5(2023)年9月には過去10年間で最高となる133.9となりました(図表3-10-6)。
令和5(2023)年度においては計画的に省エネルギー化等に取り組む産地を対象に、施設園芸及び茶の農業者と国で基金を設け、燃油・ガスの価格が一定の基準を超えた場合に補塡金を交付しました。また、施設園芸農家向けのヒートポンプ等の導入を支援しました。
(電気料金の高騰に対し、農業水利施設への支援を実施)
食料の安定供給に不可欠な公共・公益性の高い農業水利施設は、維持管理費に占める電気料金の割合が大きく、エネルギー価格高騰による影響を受けやすくなっています。このため、農林水産省では、農業水利施設の省エネルギー化を進めるとともに、エネルギー価格高騰の影響を緩和するため、令和4(2022)年度から、農業水利施設の省エネルギー化に取り組む土地改良区等に対し、電気料金高騰分の一部を支援しています。なお、本支援は、エネルギー価格が低下してきたこと等を踏まえ、令和6(2024)年度をもって終了しますが、営農に配慮し、電力消費のピークを過ぎる同年9月まで実施することとしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883