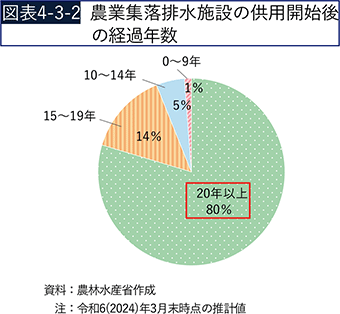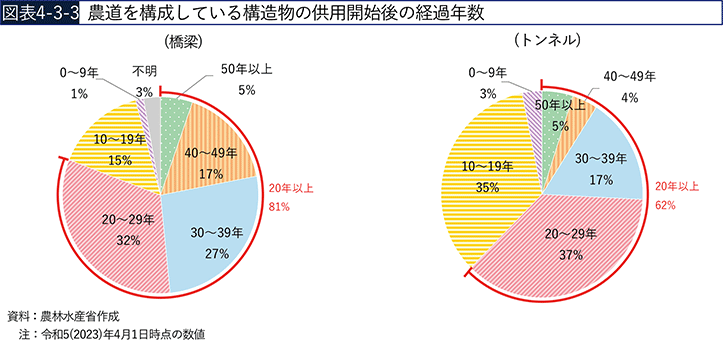第3節 農村に人が住み続けるための条件整備
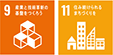
地域住民の生活や就業の場である農村地域においては、人口減少や高齢化により集落機能が低下し、農地・農業用水路等の保全や買い物・子育て等の集落の維持に不可欠な機能が弱体化する地域が増加していくことが懸念されています。
本節では、農村に人が住み続けるための条件整備として、地域コミュニティ機能の維持・強化や生活インフラの確保に関する取組について紹介します。
(1)地域コミュニティ機能の維持・強化
(集落機能を補完する農村RMOの形成が重要)
中山間地域を始めとした農村地域では、商店やガソリンスタンドの撤退等による生活サービスの低下や集落の小規模化により、農業生産活動のみならず、農地・農業用水路等の保全や買い物・子育て等の生活支援等の取組を行うコミュニティ機能の弱体化が懸念されています。
このため、複数の集落の機能を補完して、農用地の保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等の地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織である「農村型地域運営組織」(以下「農村RMO(*1)」という。)を形成していくことが重要となっています(図表4-3-1)。
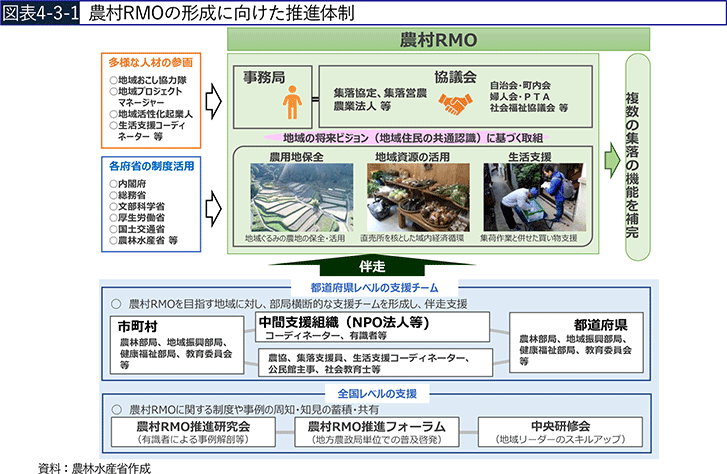
農林水産省では、令和8(2026)年度までに農村RMOを100地区で形成する目標に向けて、農村RMOを目指す団体等が行う農用地の保全、地域資源の活用、生活支援に係る将来ビジョンの策定、これらに基づく調査、計画作成、実証事業等の取組に対して支援を行うこととしています。また、地方公共団体や農協、NPO法人等から構成される都道府県単位の支援チームや全国プラットフォームの構築を支援し、農村RMOの形成を後押ししています。
1 特集第3節を参照
(事例)農村RMOを主体として地域の活性化に向けた活動を展開(岡山県)


住民によるワークショップ
資料:吉縁起村協議会

無人店舗「スマート・縁起村」
資料:吉縁起村協議会
岡山県真庭市(まにわし)の吉(よし)地区では、「吉縁起村協議会(よしえんぎむらきょうぎかい)」を主体として、特産品の開発・販売や無人店舗の設置といった地域の活性化に向けた活動を展開しています。
中山間地に位置し過疎・高齢化の進む同地区では、小学校やバス路線の廃止を契機に、住民主体で自治会の枠を超えた話合いを開始し、平成30(2018)年12月に地域おこしグループである「吉縁起村」を設立しました。
同グループでは、「相愛(そうあい)」、「寿老(すろう)」といった縁起の良い地名等を活用することで地区の知名度を高めることを目標に、令和元(2019)年度から、県道沿いに設置したテントで農産物等の販売を開始しました。令和3(2021)年度には、県の支援を受けて、観光案内所や特産品製造・販売所の機能を併せ持つ、地域の拠点施設「吉縁起村(よしえんぎむら) 立寄処(たちよりどころ)」の整備を行いました。また、活動資金を確保し自立運営が可能な取組とするために、特産品の開発・販売を行うとともに、集落協定の広域化を契機として中山間地域等直接支払制度に関する事務を担っています。
令和4(2022)年12月には、農村RMOとして「吉縁起村協議会」を設立し、耕作放棄地の再生や拠点施設での小中学生向け学習指導、コンビニエンスストアを求める住民の声を受けたキャッシュレス型無人店舗の設置といった地域を活性化させる活動を展開しています。
同地区では、今後とも地域が一体となり、拠点施設を交流やつながりの場として維持・発展させながら、住民の生きがいと幸福感の創造に向けた取組を推進していくこととしています。

農村型地域運営組織(農村RMO)の推進
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/nrmo/
(農村地域における交通・教育・医療・福祉等の充実を推進)
地方では、地域経済の活性化や東京圏への過度の一極集中の是正、人口減少・少子高齢化への対応、教育の質の維持・向上、適切な医療水準の確保といった解決すべき社会課題はより複合的なものとなっています。
このため、多岐にわたる地方の社会課題の解決に向け、デジタルの力等を活用した、地方の自主的・主体的な取組の支援のほか、人口減少が進む農村においては、担い手の育成や農地の集積・集約化等の農業政策に加え、交通・教育・医療・福祉といった地域に定住するための条件を維持・確保する取組を促進することが重要となっています。
このような中、国や地方公共団体等においては、生活の利便性向上や地域交流に必要な道路等の整備を推進するとともに、活力ある学校づくりに向けたきめ細やかな取組を推進しています。また、へき地における医療の確保を図るとともに、住まい・医療・介護・予防・生活支援が包括的に確保される体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。

地方公共団体が運営委託する
予約型乗合タクシー
資料:北海道更別村

JAグループによる高齢者福祉活動
資料:愛知県厚生農業協同組合連合会
(2)生活インフラ等の確保
(農業・農村における情報通信環境の整備を推進)
農業水利施設等の管理の省力化・高度化やスマート農業の実装、地域の活性化を図るため、ICT等の活用に向けた情報通信環境を整備することが重要な課題となっています。
農林水産省では、総務省と連携しつつ、農業・農村における情報通信環境の整備に取り組んでおり、行政、土地改良区、農協、民間企業等による官民連携の取組を通じて、普及・啓発や不足する知見・人材のサポート等を行っています。また、令和5(2023)年度は、全国21地区において、光ファイバ、無線基地局等の情報通信環境整備に係る調査、計画策定、施設整備を実施しました。
(標準耐用年数を超過した農業集落排水施設は全体の約8割)
農業集落排水施設は、農業用水の水質保全等を図るため、農業集落におけるし尿、生活雑排水の汚水等を処理するものであり、農村の重要な生活インフラとして稼働しています。
一方、供用開始後20年(機械類の標準耐用年数)を経過する農業集落排水施設の割合が令和6(2024)年3月末時点で80%となるなど、老朽化の進行や災害への脆弱性(ぜいじゃくせい)が顕在化するとともに、施設管理者である市町村の維持管理に係る負担が増加しています(図表4-3-2)。
このような状況を踏まえ、農林水産省では、農業集落排水施設が未整備の地域に関しては引き続き整備を進めるとともに、既存施設に関しては、広域化・共同化による維持管理の効率化、長寿命化・老朽化対策を進めるため、地方公共団体による機能診断等の取組や更新整備等を支援しています。
また、国内資源である農業集落排水汚泥のうち、肥料等として再生利用されているものは、令和5(2023)年3月末時点で約7割となっています。みどり戦略の推進に向け、農業集落排水汚泥資源の再生利用を更に推進することとしています。
(農道の適切な保全対策を推進)
農道は、圃場(ほじょう)への通作や営農資機材の搬入、産地から市場までの農産物の輸送等に利用され、農業の生産性向上等に資するほか、地域住民の日常的な移動に利用されるなど、農村の生活環境の改善を図る重要なインフラです。令和5(2023)年8月時点で、農道の総延長距離は17万793kmとなっています。一方、農道を構成している構造物については、同年4月時点で供用開始後20年を経過するものの割合が、橋梁(きょうりょう)で81%、トンネルで62%となっています(図表4-3-3)。経年的な劣化の進行も見られる中、構造物の保全対策を計画的・効率的に実施し、その機能を適切に維持していくためには、日常管理や定期点検、効率的な保全対策に取り組むことが重要です。
このため、農林水産省では、市町村や土地改良区等を対象に、非技術系の職員であっても容易に理解でき、直接点検等の実施にも役立つ手引案を作成し、保全対策の推進に取り組むとともに、農道の再編・強靱(きょうじん)化や拡幅による高度化といった農業の生産性向上や農村生活を支えるインフラを確保するための取組を支援しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883