第4節 農村を支える新たな動きや活力の創出
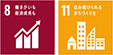
持続可能な農村を形成していくためには、地域づくりを担う人材の養成等が重要となっています。また、都市住民も含め、農村地域の支えとなる人材の裾野を拡大し、活力の創出を図っていくためには、農村関係人口の創出・拡大や関係の深化を図っていくことが必要となっています。
本節では、地域の支えとなる人材の裾野を拡大する取組や農村の魅力を発信する取組について紹介します。
(1)都市と農山漁村の交流の推進
(農村地域との関わりを持っている人は約6割)
内閣府が令和5(2023)年9~10月に実施した世論調査によると、今日の農村地域との関わりについて、「農村地域との関わりを持っていない」と回答した人は約4割となっており、約6割が何らかの関わりを持っていることがうかがわれます(図表4-4-1)。また、今後の農村地域との関わりの持ち方として、「農村地域の特産品の購入をしたい」と回答した人が約5割となっています。
都市住民等が農業・農村に関わることで、農村のファンとも言うべき「農村関心層」を創出し、農村地域の関係人口である「農村関係人口」の創出・拡大や関係の深化を図っていくことが求められています。
(事例)オーナー制度を活用し、農村景観の保全や都市と農村の交流を推進(奈良県)


棚田オーナー制度の稲作体験
資料:一般財団法人明日香村地域振興公社

いもほりオーナー制度の
さつまいも収穫体験
資料:一般財団法人明日香村地域振興公社
奈良県明日香村(あすかむら)では、村内の農業振興のため、オーナー制度を活用し、農村景観の保全や都市と農村の交流を図る取組を展開しています。
豊かな自然と歴史遺産が調和する地域として知られる同村では、歴史的景観を支え続ける「農」を守り続けていくためには、農業者だけに任せるのではなく、その負担を「農」を通じて都市と分かち合うことが必要であるとの考えから、平成8(1996)年度から「あすかオーナー制度」に取り組んでいます。
同制度は、事務局を務める一般財団法人明日香村(あすかむら)地域振興公社(ちいきしんこうこうしゃ)が、実施主体となるNPO法人等と連携しながら、各地区で「棚田オーナー」や「いもほりオーナー」等のプログラムを実施しています。オーナーは会費を支払うことで、田植や稲刈り、収穫といった農作業等を体験できるほか、地元農業者の栽培指導を受けることもできます。
同制度により、農山村の魅力を多くの人々に知ってもらうことができるほか、耕作放棄地や遊休農地の増加を防ぐことができ、地域の活性化にも役立っています。また、農作業等を通じて都市住民が継続的に同村と関わりを持てるようになっています。令和4(2022)年度においては、総計で約620口のオーナーが地域の垣根を越えて参加し、同制度を通じて同村の農業や自然を体感しつつ、地域と共同で村内の景観保全に取り組みました。
同村では、都市住民との交流機会の拡大を更に図っていくため、プログラム拡充の検討やSNSによる情報発信等によりオーナー制度の充実・強化を図り、地域農業の継続的な発展を図っていくこととしています。
(農村関係人口の裾野拡大に向けては複線型アプローチが必要)
農村関係人口については、「農山漁村への関心」や「農山漁村への関与」の強弱に応じて多様な形があると考えられ、段階を追って徐々に農山漁村への関わりを深めていくことで、農山漁村の新たな担い手へとスムーズに発展していくことが期待されます。しかしながら、同時に、このような農山漁村への関わり方やその深め方は、人によって多様であることから、その裾野の拡大に向けては複線型のアプローチが重要となっています(図表4-4-2)。
例えば農泊や農業体験により農山漁村に触れた都市住民が、援農ボランティアとして農山漁村での仕事に関わるようになり、二地域居住を経て、最終的には就農するために農山漁村に生活の拠点を移すといったケースも想定されます。
また、都市農村交流を更に発展させ、都市に居住しながらも特定の農村に継続的に訪問することや、ボランティアに参加すること等により特定の農村と継続的に関わる者の増加を図り、当該地域における農産物・食品等の消費拡大や共同活動への参加を通じた集落機能の補完等を進めることも重要です。
農林水産省では、農村関係人口を増加させるため、従来の都市と農村の交流に加え、食を始めとする農業や農村が有する様々な資源を活用して、二地域居住や農泊等を推進することとしています。
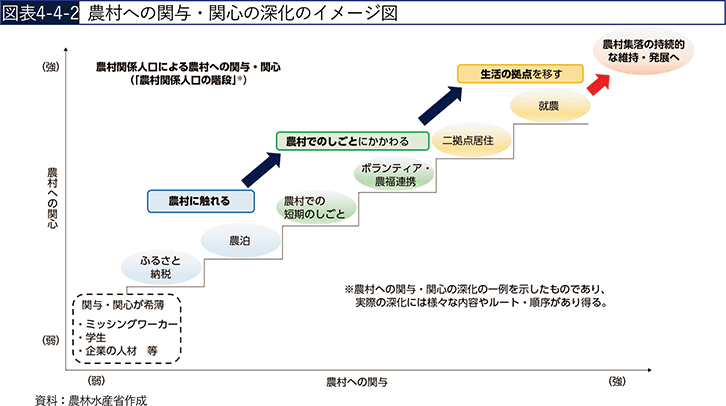
(コラム)NFTを活用し、「デジタル村民」として地域との交流を深める取組が始動

NFT購入者が参加する
地域イベント
資料:鳥取県智頭町

地域資源NFTとして
発行されたデジタルアート
資料:静岡県松崎町
近年、「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」(以下「NFT」という。)等のWeb3に関連した技術や仕組みを駆使して社会課題を解決しようとする動きが活発化しています。
鳥取県智頭町(ちづちょう)と静岡県松崎町(まつざきちょう)では、人口減少下の社会における新たな価値創造として、コミュニティへの貢献をNFTの発行により還元し、いわゆる「デジタル村民」として継続的に地域への関わりを深める人材を増やす取組を推進しています。
両町では、広域的に連携し、内閣府の広域連携SDGsモデル事業として採択された「日本で最も美しい村デジタル村民の夜明け事業」を活用し、美しい村デジタル村民権が付与された「地域資源NFT」を販売する取組等を実施しています。
地域資源NFTは、ブロックチェーンに記録される代替不可能なデジタルデータであるNFTに基づき発行されます。購入者には、宿泊割引や棚田デジタルオーナー会員券等のインセンティブのほか、地域の課題解決プロジェクト等に参画できる権利等が付与されています。
令和5(2023)年度においては、NFT収入による事業の自走化に向けて、地域の祭りでイベント専用NFTを発行したほか、地域特産の栄久(えいきゅう)ぽんかんをNFTの仕組みを活用して販売するなど、共創型地方創生プラットフォームである「美しい村DAO(*)」を活用して、デジタル村民と地域住民が一体となって、未来の地域づくりを進める取組が始動しています。
デジタル村民という新たな関係人口の創出・拡大により、経済・社会・環境の相乗効果が発揮されるとともに、過疎地における新しい社会システムのモデルとなることが期待されています。
Decentralized Autonomous Organizationの略で、分散型自律組織のこと
(子どもの農山漁村交流プロジェクトを推進)
内閣官房、総務省、文部科学省、農林水産省、環境省は、子供の農山漁村での宿泊による農林漁業体験や自然体験活動等を行う「子ども農山漁村交流プロジェクト」を通じ、都市農村交流を推進しています。同プロジェクトは、子供たちの学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識等を育み、力強い成長を支える教育活動として、農山漁村での長期宿泊体験活動を推進するものです。
農林水産省では、農泊地域等の受入側(農山漁村)に対して、都市と農山漁村の交流を促進するための取組への支援や、交流促進施設等の整備への支援を行っています。
(事例)農業体験を中心とした子供農村交流体験活動を推進(滋賀県)
滋賀県日野町(ひのちょう)の一般社団法人近江日野交流(おうみひのこうりゅう)ネットワークでは、農業体験を中心とした子供農村交流体験活動を推進しています。
同法人は、町、観光協会、商工会、観光施設、受入家庭等でネットワークを構成し、体験型教育旅行やインバウンド、企業研修の受入れの中心的役割を担っています。
体験型教育旅行では、子供たちが体験を通して交流を深め、人としての成長を促すことが最も大切であるとの考えの下、教室の中だけでは学ぶことが難しい「ひとりひとりが考え、行動する力」を養うことができる場を提供しています。
参加する子供たちは、受入家庭ごとに4人程度のグループに分けられ、最大2泊3日の日程で農業体験を中心とした交流活動に臨みます。プログラムには、野菜の種まきや草取り、収穫作業のほか、稲刈りや竹林の整備、伝統料理の調理等があり、子供たちは、農村のありのままの暮らしを体験し、受入家庭との交流を深めていきます。
参加者からは「都会では経験できない貴重な体験ができた」、「初対面の人と話すことに自信を持てるようになった」、「受入家庭との絆が生まれた」といった声が聞かれています。
同法人では、近江商人(おうみしょうにん)の「三方よし」の考えにならい、「訪れる人々に心からの感動を、迎えるものに自信と誇りの回復を、地域に活力を」を合言葉に取組を進めており、今後とも、教育効果の高い受入活動が展開できるよう、地域一体となって取り組んでいくこととしています。


中学生による田植体験
資料:一般社団法人近江日野交流ネットワーク

伝統料理の調理体験
資料:一般社団法人近江日野交流ネットワーク
(2)多様な人材の活躍による地域課題の解決
(「半農半X」の取組が広がり)
農業・農村への関わり方が多様化する中、都市から農村への移住に当たって、生活に必要な所得を確保する手段として、農業と別の仕事を組み合わせた「半農半X」の取組が広がりを見せています。
半農半Xの一方は農業で、もう一方の「X」に当たる部分は会社員や農泊運営、レストラン経営等多種多様です。Uターンのような形で、本人又は配偶者の実家等で農地やノウハウを継承して半農に取り組む事例、食品加工業、観光業等の様々な仕事を組み合わせて通年勤務するような事例も見られています。
農林水産省では、新規就農の促進等のほか、関係府省等と連携し、半農半Xを実践する者等の増加に向けた方策として、「人口急減地域特定地域づくり推進法(*1)」の仕組みの活用を推進しています。
1 正式名称は「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」
(特定地域づくり事業協同組合の認定数は着実に増加)
特定地域づくり事業協同組合制度は、人口急減地域特定地域づくり推進法に基づき、地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うものであり、令和6(2024)年3月末時点の特定地域づくり事業協同組合数は、前年同月末時点と比べ23件増加し95組合(*1)となっています。本制度の活用により、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を図ることが期待されています。
1 人口急減地域特定地域づくり推進法に基づく認定を受け、特定地域づくり事業推進交付金の交付が決定されている組合の数値
(地域おこし協力隊の隊員数は前年度に比べ増加)
令和5(2023)年度の「地域おこし協力隊」の隊員数は前年度に比べ753人増加し7,200人となっています(図表4-4-3)。都市地域から過疎地域等に生活の拠点を移した隊員は、全国の様々な場所で地場産品の開発、販売、PR等の地域おこしの支援、農林水産業への従事、住民の生活支援等の地域協力活動を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組を行っています。
総務省は、地域おこし協力隊の推進に取り組む地方公共団体に対して、必要な財政上の措置を行うほか、都市住民の受入れの先進事例等の調査等を行っています。
(3)地域を支える体制・人材づくり
(地方公共団体における農林水産部門の職員数は減少傾向で推移)
近年、地方公共団体の職員、特に農林水産部門の職員が減少しています。同部門の職員数については、令和5(2023)年は7万8,678人となっており、平成17(2005)年の10万2,887人と比較して2割以上減少しました(*1)(図表4-4-4)。
また、地方公共団体は、農林水産業の振興等を図るため、生産基盤の整備や農林水産業に係る技術の開発・普及、農村の活性化等の施策を行っており、これらの諸施策に要する経費である農林水産業費の純計決算額は、令和4(2022)年度においては3兆3,624億円と、平成17(2005)年度の約8割の水準となっています(図表4-4-5)。
農村地域においては、各般の地域振興施策を活用し、新しい動きを生み出すことができる地域とそうでない地域との差が広がり、いわゆる「むら・むら格差」の課題も顕在化しています。
このような中、地方における農政の現場では、地域農業の持続的な発展に向け、地方公共団体等の職員がデジタル技術を活用して現地確認事務の効率化を図る取組、農業経営の改善をサポートする取組等が見られており、地域における農政課題の解決を図る動きが進展しています。
農業現場の多様なニーズに対応することが困難となってきている中、地方公共団体においては、今後とも限られた行政資源を有効に活用しながら、それぞれの地域の特性に即した施策を講じていくことが重要となっています。
農林水産省では、現場と農政を結ぶため、全国の地域拠点に地方参事官室を配置し、地方公共団体と連携しつつ、農政の情報を伝えるとともに、現場の声をくみ上げ、地域と共に課題を解決することにより、農業者等の取組を後押ししています。
1 総務省「地方公共団体定員管理調査結果」によると、令和5(2023)年の地方公共団体の職員数(280万1,596人)は、平成17(2005)年の職員数(304万2,122人)と比較して、約1割減少している。
(「農村プロデューサー」の養成が本格化)
地域への愛着と共感を持ち、地域住民の思いをくみ取りながら、地域の将来像やそこで暮らす人々の希望の実現に向けてサポートする人材を育成するため、農林水産省は、「農村プロデューサー」養成講座を開催しています。オンラインの入門コース、オンラインと対面講義を併用した実践コースから成る同講座は、開講から3年目となる令和6(2024)年3月末時点で、地方公共団体の職員や地域おこし協力隊の隊員等267人が実践コースを受講しました。
また、農林水産省は、農山漁村の現場で地域づくりに取り組む団体や市町村等を対象に相談を受け付け、取組を後押しするための窓口である「農山漁村地域づくりホットライン」を、本省を始め、全国の地方農政局等や地域拠点に開設しています。
(4)農村の魅力の発信
(棚田地域振興法に基づく指定棚田地域は727に拡大)
我が国においては、棚田を保全し、棚田地域の有する多面的機能の維持増進を図ることを目的とした棚田地域振興法に基づき、市町村や都道府県、農業者、地域住民等の多様な主体が参画する指定棚田地域振興協議会による棚田を核とした地域振興の取組を、関係府省横断で総合的に支援する枠組みを構築しています。農林水産大臣等の主務大臣は、令和5(2023)年度までに、同法に基づき累計で727地域を指定棚田地域に指定したほか、指定棚田地域において同協議会が策定した認定棚田地域振興活動計画は累計で194計画となっています。
また、棚田の保全と地域振興を図る観点から、令和3(2021)年度には、「つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~」として、優良な棚田271か所を農林水産大臣が認定しました。

つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanadasen.html
(世界農業遺産に新たに2地域が認定)
世界農業遺産は、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業システムをFAO(*1)が認定する制度であり、令和5(2023)年7月に、新たに兵庫県兵庫美方(ひょうごみかた)地域と埼玉県武蔵野(むさしの)地域の2地域が認定され、国内の世界農業遺産認定地域は15地域となりました。
また、日本農業遺産は、我が国において重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域を農林水産大臣が認定する制度であり、認定地域は24地域となっています。
令和5(2023)年度においては、農業遺産地域の魅力を広く発信し、地域活性化を図る取組の一環として、農業遺産地域の高校生による、複数の農業遺産地域の産品を使った食品のアイデアを競う「高校生とつながる!つなげる!ジーニアス農業遺産ふーどコンテスト」を開催しました。
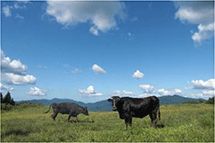
兵庫県兵庫美方地域

埼玉県武蔵野地域
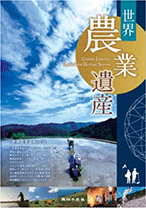
世界農業遺産のポスター
1 特集第2節を参照
(世界かんがい施設遺産に新たに4施設が登録)
世界かんがい施設遺産は、歴史的・社会的・技術的価値を有し、かんがい農業の画期的な発展や食料増産に貢献してきたかんがい施設をICID(*1)(国際かんがい排水委員会)が認定・登録する制度であり、令和5(2023)年11月に、我が国で新たに山形五堰(やまがたごせき)(山形県山形市(やまがたし))、本宿用水(ほんじゅくようすい)(静岡県長泉町(ながいずみちょう))、北山用水(きたやまようすい)(静岡県富士宮市(ふじのみやし))及び建部井堰(たけべいせき)(岡山県岡山市(おかやまし))の4施設が登録され、国内登録施設数は51施設となりました。

山形五堰(山形県山形市)
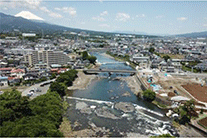
本宿用水(静岡県長泉町)
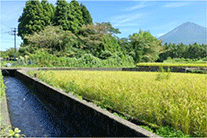
北山用水(静岡県富士宮市)
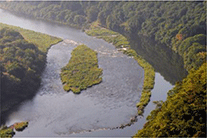
建部井堰(岡山県岡山市)
1 International Commission on Irrigation and Drainageの略
(熊本県山都町の通潤橋が農業施設として初めて国宝に指定)
令和5(2023)年9月に、熊本県山都町(やまとちょう)の通潤橋(つうじゅんきょう)が、農業施設としては初めて国宝に指定されました。同施設は、農業用水として使用されている石橋で、新田開発史上で傑出した存在として評価されました。通潤橋は、我が国最大級の石造りアーチ水路橋で、橋の上部にサイホンを用いた3本の石の通水管が敷設され、今日でも地域の棚田を潤しています。

通潤橋
資料:熊本県山都町
(「ディスカバー農山漁村の宝」に27団体と2人を選定)
農林水産省と内閣官房は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に向け、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことによる地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例を「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」として選定し、全国に発信することにより、農山漁村地域の活性化等に対する国民の理解の促進、優良事例の他地域への横展開を図るとともに、地域リーダーのネットワークの強化を推進しています。
第10回の選定となる令和5(2023)年度は全国から27団体と2人を選定し、選定数は累計で315件となりました。また、第10回記念賞として、過去に選定された取組を対象に、選定後に著しい発展性がみられ、全国の模範となる事例として1団体を決定しました。

「大あなご」の地産地消を図る催し
(「ディスカバー農山漁村の宝」(第10回選定)のグランプリ受賞)
資料:大田商工会議所

ディスカバー農山漁村の宝
URL:https://www.discovermuranotakara.com(外部リンク)
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883








