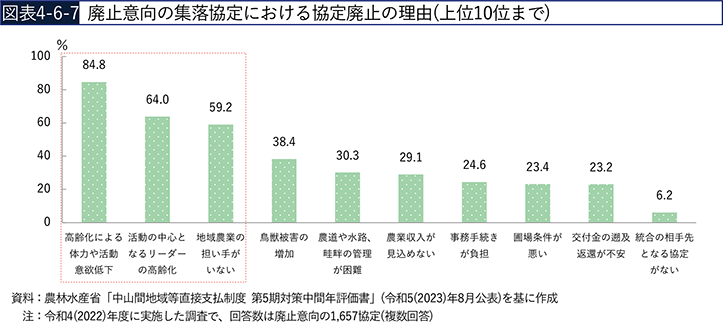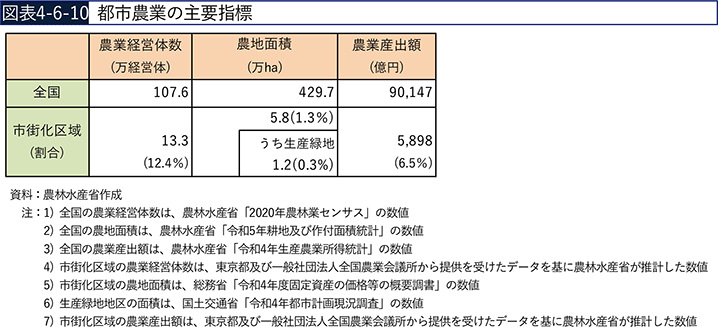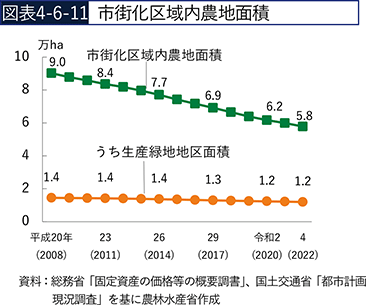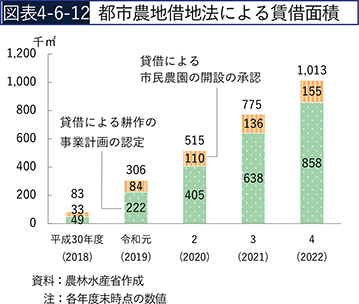第6節 中山間地域の農業の振興と都市農業の推進

中山間地域(*1)は、食料生産の場として重要な役割を担う一方、傾斜地等の条件不利性とともに、人口減少や高齢化、担い手不足、荒廃農地(*2)の発生、鳥獣被害の発生といった厳しい状況に置かれており、将来に向けて農業生産活動を維持するための活動を推進していく必要があります。
一方、都市農業は、新鮮な農産物の供給のみならず、都市住民の良好な生活環境の保全にも寄与しており、その推進を図ることが必要です。
本節では、中山間地域の農業や都市農業の振興を図る取組、荒廃農地の発生防止・解消に向けた対応について紹介します。
1 農業地域類型区分の中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域のこと
2 第3章第5節を参照
(1)中山間地域農業の振興
(中山間地域の農業産出額は全国の約4割)

中山間地域での
飼料用とうもろこしの生産
資料:農事組合法人ひまわり農場
我が国の人口の約1割、総土地面積の約6割を占める中山間地域は、農業経営体数、農地面積、農業産出額ではいずれも約4割を占めており、我が国の食料生産を担うとともに、国土の保全、水源の涵養(かんよう)、豊かな自然環境の保全や良好な景観の形成といった多面的機能の発揮においても重要な役割を担っています(図表4-6-1)。
一方、中山間地域には傾斜地が多く存在し、圃場(ほじょう)の大区画化や大型農業機械の導入、農地の集積・集約化等が容易ではないため、規模拡大等による生産性の向上が平地に比べ難しく、営農条件面で不利な状況にあります。
経営耕地面積規模別の農業経営体数の割合を見ると、1.0ha未満については、平地農業地域で約4割であるのに対し、中間農業地域、山間農業地域では共に約6割となっています(図表4-6-2)。
また、中山間地域では、このような営農条件の不利性に加え、人口減少・高齢化に伴う担い手の不足や鳥獣被害の発生といった厳しい条件に置かれており、農業生産活動を維持するために総合的な施策を講じる必要があります。
(中山間地域等の特性を活かした複合経営等を推進)
中山間地域を振興していくためには、地形的制約等がある一方、清らかな水、冷涼な気候等を活かした農作物の生産が可能である点を活かし、需要に応じた市場性のある作物や現場ニーズに対応した技術の導入を進めるとともに、耕種農業のみならず畜産、林業を含めた多様な複合経営を推進することで、新たな人材を確保しつつ、小規模農家を始めとした多様な経営体がそれぞれにふさわしい農業経営を実現する必要があります(図表4-6-3)。
このため、農林水産省では、中山間地域等直接支払制度により生産条件の不利を補正しつつ、中山間地農業ルネッサンス事業等により、多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現や、地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承に向けた取組を総合的に支援しています。また、米、野菜、果樹等の作物の栽培や畜産、林業も含めた多様な経営の組合せにより所得を確保する複合経営を推進するため、農山漁村振興交付金等により地域の取組を支援しています。

(中山間地域等直接支払制度の協定数は前年度に比べ増加)
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方公共団体による支援を行う制度として平成12(2000)年度から実施してきており、平成27(2015)年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた措置として実施しています。
令和2(2020)年度から始まった第5期対策では、人口減少や高齢化による担い手不足、集落機能の弱体化等に対応するため、制度の見直しを行い、新たな人材の確保や集落機能の強化、集落協定の広域化、棚田地域の振興を図る取組等に対して加算措置を設けています。
令和4(2022)年度の同制度の協定数は前年度と比べ141協定増加し2万4千協定となり、協定面積は前年度と比べ4千ha増加し65万6千haとなりました(図表4-6-4)。
(中山間地域等直接支払制度の実施により営農を下支え)
令和5(2023)年8月に公表した「中山間地域等直接支払制度 第5期対策中間年評価書」によると、集落協定が実施している主な共同活動としては、「鳥獣害対策」を行う集落協定が60.2%で最も多く、次いで「協定農用地以外の農用地の保全活動」が51.9%となっています(図表4-6-5)。
また、集落協定が同制度に取り組んだ効果としては、「水路・農道等の維持、環境の保全」、「荒廃農地の発生防止」と回答した集落協定がそれぞれ8割以上となっています(図表4-6-6)。
一方、令和元(2019)年度で活動を廃止した集落協定の多くが小規模の協定であり、高齢化や担い手不足を理由に廃止しています。
さらに、令和6(2024)年度末に活動を廃止する意向を持っている協定における廃止意向の理由については、「高齢化による体力や活動意欲低下」が84.8%で最も多く、次いで「活動の中心となるリーダーの高齢化」が64.0%、「地域農業の担い手がいない」が59.2%となっています(図表4-6-7)。廃止意向がある協定についても、その半数以上が小規模の協定となっています。
人口減少・高齢化の進行により、集落による共同活動の継続が困難になることが予想される中、周辺の協定や多様な組織、非農業者等の参画を促進し、共同活動が継続できる体制づくりを進めることが必要となっています。
(山村への移住・定住を定め、自立的発展を促す取組を推進)
振興山村(*1)は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全や良好な景観の形成、文化の伝承等に重要な役割を担っているものの、人口減少や高齢化等が他の地域より進んでいることから、国民が将来にわたってそれらの恵沢を享受することができるよう、地域の特性を活かした産業の育成による就業機会の創出、所得の向上を図ることが重要となっています。
農林水産省は、地域の活性化・自立的発展を促し、山村への移住・定住を進めるため、地域資源を活かした商品の開発等に取り組む地区を支援しています。
1 山村振興法に基づき指定された区域。令和6(2024)年4月時点で、全市町村数の約4割に当たる734市町村において指定
(コラム)FAOやEUでは山地ラベル認証制度を展開
山地で暮らす人々が、生態系や天然資源を保全しつつ生計を営み続けられるように、農林漁業の持続可能性を高めることが、国際社会の課題となっています。この課題に応えるために注目されているのが、「山地ラベル認証制度」です。
同制度は、山地で生産された農産物・食品に山地ラベルと呼ばれる認証ラベルを付して、消費者が識別できるようにする支援制度です。どの商品が山地で生産された産品なのかを消費者が見分けられるようにすることで、消費者が購買行動を通じて山地に住む人たちの生計や暮らしを応援することが可能となります。
FAO*に設置されている組織「山地パートナーシップ」では、平成28(2016)年からイタリアのスローフード協会(きょうかい)と共同で、ボリビアやインド等の山地の生産者が生産した産品を「山地パートナーシップ産品」として認証しています。FAOのWebサイトによると、令和6(2024)年3月時点で8か国35生産団体、生産者数約1万8千人が生産する45産品が登録されています。
また、EUでは、山地で生産された農産物等に対して加盟各国が定める山地ラベルを付すことで、消費者が積極的に選んで購入することを後押ししています。
山地で生産された農産物・食品を市場で差別化し、付加価値を高めることで、山地で暮らす人々の所得の向上や農林漁業の維持・発展につながることが期待されています。
特集第2節を参照
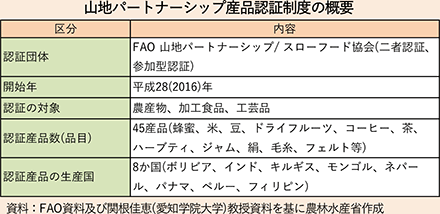
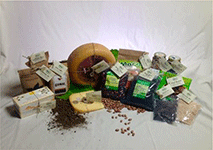
山地パートナーシップ産品の例
資料:©FAO/Mountain Partnership
(33道府県の55地域を「デジ活」中山間地域に登録)
人口減少・高齢化が進行し条件不利な中山間地域等は、一方で豊かな自然や魅力ある多彩な地域資源・文化等を有し、次の時代につなぐ価値ある拠点としての可能性を秘めています。「デジ活」中山間地域は、基幹産業である農林水産業の「仕事づくり」を軸として、地域資源やデジタル技術を活用し、多様な内外の人材を巻き込みながら、社会課題解決に向けて取組を積み重ねることで活性化を図る地域であり、令和4(2022)年12月に閣議決定された「デジタル田園都市国家構想総合戦略」(令和5(2023)年12月改訂)におけるモデル地域ビジョンの一つとして位置付けられています。

「デジ活」中山間地域について
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/
digikatsu/index.html
「デジ活」中山間地域として登録された地域においては、農林水産業に関する取組を中心に、高齢者の見守り、買い物支援、地域交通等の様々な分野の取組が計画されています。令和5(2023)年度には、33道府県の55地域を「デジ活」中山間地域に登録し、農林水産省を始めとした関係府省が連携して、職員による現地訪問、施策紹介、申請相談、関連施策による優遇措置等により、その取組を支援しています。
(事例)「デジ活」中山間地域として、農用地の適切な保全等を推進(三重県)

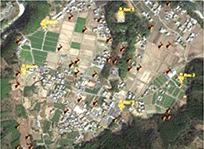
マイクロフォンによる
シカの発生地点推定
資料:京都先端科学大学
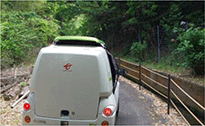
超小型モビリティの活用
による見回りパトロール
資料:勢和農村RMO協議会
三重県多気町(たきちょう)では、「デジ活」中山間地域として、農用地保全や資源の活用、子育て世代や高齢者サポートの充実等の活動を展開しています。
同町の勢和(せいわ)地区では、人口減少やコロナ禍に伴う地域内のつながりの減少、離農、荒廃農地の増加等の課題に対応するため、令和4(2022)年に勢和農村(せいわのうそん)RMO協議会を設立するとともに、同協議会を主体として獣害対策やスマート農業、生活支援サービス等の地域課題の解決や将来像の実現に向けた活動を展開しています。
このうち獣害対策については、マイクロフォンを活用しシカの動きを分析するとともに、罠に掛かるとカメラで撮影し、スマートフォンにアラートを届ける仕組みを構築しています。今後は、実証活動の対象範囲を拡充しながら、実装につなげることとしています。
また、スマート農業については、情報ネットワーク環境の構築、遠隔監視カメラや遠隔自動水門の活用により、水田の水位管理、洪水緩和等や作業時間の大幅な削減を図り、安全・安心な管理を実現しています。今後は、ランニングコストの問題を解消して実装につなげるとともに、効率的な維持管理や農用地の適切な保全等を図ることを目指しています。
さらに、生活支援サービスについては、超小型モビリティの活用による見守りパトロールやデマンドタクシーの運営を行っています。
このような取組を踏まえ、同町は、令和5(2023)年6月に「デジ活」中山間地域に登録されたところであり、今後とも地域住民が協力し、地域資源やデジタル技術を活用しながら、自立型社会の実現に向けた取組を推進していくこととしています。
(2)荒廃農地の発生防止・解消に向けた対応
(圃場が未整備の農地や土地条件が悪い農地を中心に、荒廃農地が発生)
荒廃農地の面積については、近年おおむね横ばい傾向で推移しており、令和4(2022)年は前年に比べ6千ha減少し25万3千haとなっています(図表4-6-8)。このうち再生利用が可能な農地は9万ha、再生が困難と見込まれる農地は16万3千haとなっています。
令和3(2021)年1月に実施した調査によると、荒廃農地の発生原因について、土地の条件に着目した要因としては、「山あいや谷地田(やちだ)など、自然条件が悪い」の割合が25%で最も高く、次いで「基盤整備がされていない」、「区画が不整形」、「接道がない、道幅が狭い」がそれぞれ16%となっています(図表4-6-9)。また、所有者に着目した要因としては、「高齢化、病気」の割合が30%で最も高く、次いで「労働力不足」が19%、「地域内に居住していない」が17%となっています。土地・所有者以外に着目した要因としては、「農業機械の更新ができない」が29%で最も多くなっています。
このように、傾斜地や未整備地等の生産条件の不利な地域において、農業者の高齢化や労働力不足等を背景に、農業機械の更新等を契機として、離農を選択している状況がうかがわれます。さらに、離農後の農地についても、条件が悪いこと等を理由に引受け手が見つからず、荒廃農地の発生につながっているケースが多いことがうかがわれます。
(荒廃農地の発生防止と解消に向けた取組を推進)
荒廃農地は周辺農地に悪影響を及ぼし、その解消には多額の費用を要することから、まずはその発生を防止することが重要です。このため、農林水産省では、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域での協議により目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」の策定を推進し、農地の適切な利用の確保を図っていくこととしています。あわせて、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理機構を活用した農地の集積・集約化により、農地の効率的・総合的な利用を図ることとしています。また、荒廃のおそれのある農地は、区画が不整形、狭小、排水不良等のため、農地の条件が悪く、借り手が見つからない場合が多いことから、基盤整備により生産性向上を図るほか、水田の畑地化・汎用化による高収益作物の導入等により、適地適作を進めていくことも有効です。さらに、日本型直接支払制度による営農の下支え、スマート農業技術の活用、鳥獣被害対策の推進に加え、あらゆる政策努力を払ってもなお従来の農業生産活動が困難な場合にあっては、粗放的な利用による農地の維持・保全等に総合的に取り組むこととしています。
(事例)移住者等を巻き込み荒廃農地の粗放的利用を展開(富山県)


地域ぐるみの話合い
資料:富山県立山町

作付けされたカモミール
資料:富山県立山町
富山県立山町(たてやままち)の釜ヶ渕(かまがふち)地区は、整備済の優良農地を集積するとともに、新規就農者の受入れや支援体制等を構築し、管理負担の大きい荒廃農地を粗放的に利用することにより、地域の活性化を図っています。
同地区では、住宅が集まる中心部に未整備の農地が残っており、作付効率が悪いことから草刈り等の保全管理のみが行われている農地も多く、近年では農地所有者の高齢化に伴う荒廃化が懸念されています。また、山際の農地では、イノシシやサル等による獣害の対策に苦慮していました。
このため、同町では、地域ぐるみの話合いにより、農地を「生産性向上エリア」と「粗放的管理エリア」に区分けした地域の将来像を作成しました。
生産性向上エリアでは、条件の良い農地を新規就農者や担い手に集積するため、同町の仲介や地元農業者同士の協力による利用調整、農地の集約化が進められました。また、粗放的管理エリアでは、牧場やゲストハウスの経営を行う農業者や地域おこし協力隊等の移住者により、馬等の放牧や養蜂の利用、カモミール等の省力作物の作付けといった粗放的利用のための取組が進められました。
このような取組の結果、荒廃農地の発生が防止されたほか、地域の活性化に向けた機運が高まり、農泊の実証や各種交流イベントの実施等の取組にもつながっています。
同地区では、これらの取組が今後とも一体的に推進されるよう、令和5(2023)年度から地域計画の策定を進めているところであり、引き続き地域ぐるみの話合いを進め、荒廃農地の発生防止・有効活用、低コスト管理に取り組むこととしています。
一方、耕作放棄された荒廃農地については、できる限り早期に解消することが重要であることから、農業委員会による所有者への利用の働き掛けにより荒廃農地の解消に取り組むとともに、これらの取組による荒廃農地の解消事例を広く周知しています。これらの結果、令和4(2022)年度に再生利用された荒廃農地面積は1万1千haとなりました。
(3)多様な機能を有する都市農業の推進
(市街化区域の農業産出額は全国の約1割)
都市農業は、都市という消費地に近接する特徴から、新鮮な農産物の供給に加えて、農業体験・学習の場や災害時の避難場所の提供、都市住民の生活への安らぎの提供等の多様な機能を有しています。

都市住民でにぎわう農業体験農園(東京都)
資料:特定非営利活動法人全国農業体験農園協会
都市農業が主に行われている市街化区域内の農地の面積は、我が国の農地面積全体の1%である一方、農業経営体数と農業産出額ではそれぞれ全体の12%と7%を占めており、消費地に近いという条件を活かした、野菜を中心とした農業が展開されています(図表4-6-10)。
農林水産省では、都市住民と共生する農業経営の実現のため、農業体験や農地の周辺環境対策、防災機能の強化等の取組を支援することにより、多様な機能を有する都市農業の振興に向けた取組を推進しています。
(都市農地貸借法に基づき賃貸された農地面積は拡大傾向)
生産緑地制度(*1)は、良好な都市環境の形成を図るため、市街化区域内の農地の計画的な保全を図るものです。市街化区域内の農地面積が一貫して減少する中、生産緑地地区(*2)の面積はほぼ横ばいで推移しており、令和4(2022)年の同面積は前年並みの1万2千haとなっています(図表4-6-11)。
また、都市農業の振興を図るため、意欲ある農業者による耕作や市民農園の開設等による都市農地の有効活用を促進しています。農地所有者が、意欲ある農業者等に安心して農地を貸付けすることができるよう、都市農地貸借法(*3)に基づき貸借が認定・承認された農地面積については、令和4(2022)年度は前年度に比べ23万8千m2増加し101万3千m2となりました(図表4-6-12)。
農林水産省では、都市農地貸借法の仕組みの現場での円滑かつ適切な活用を通じ、貸借による都市農地の有効活用を図ることとしています。
1 三大都市圏特定市における市街化区域農地は宅地並に課税されるのに対し、生産緑地に指定された農地は軽減措置が講じられる。
2 市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500m2以上の農地
3 正式名称は「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883