第5節 担い手への農地集積・集約化と農地の確保

農業者の減少・高齢化等の課題に直面している我が国の農業においては、荒廃農地(*1)の拡大が更に加速し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。このような中、食料安全保障の強化や農業の成長産業化を進めていくためには、生産基盤である農地が持続性をもって最大限利用されるよう取組を進めていく必要があります。
本節では、農地面積の動向や担い手への農地の集積・集約化の取組、地域計画(*2)の策定に向けた取組等について紹介します。
1 現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地
2 トピックス1を参照
(1)農地の動向
(農地面積は減少傾向で推移)
令和5(2023)年の農地面積(*1)は、荒廃農地からの再生等による増加があったものの、耕地の荒廃や転用等による減少を受け、前年に比べ2万8千ha減少し430万haとなりました(図表3-5-1)。作付(栽培)延べ面積も減少傾向が続いている中、令和4(2022)年の耕地利用率は前年に比べ0.1ポイント低下し91.3%となっています。
1 農林水産省「耕地及び作付面積統計」における耕地面積の数値
(所有者不明農地への対応を推進)
相続未登記農地の面積は、令和4(2022)年3月末時点で52.0万ha、このうち遊休農地(*1)は2万9千haとなっています。また、相続未登記のおそれのある農地の面積は50万9千ha、このうち遊休農地は2万9千haとなっています。
通常、所有者不明農地であっても、農業委員会が行う探索・公示の手続により農地中間管理機構(以下「農地バンク」という。)経由で担い手へ貸付けできる仕組みを措置し、担い手への農地の集積・集約化を進めています。農地バンクに貸付けを行った所有者不明農地の面積は、令和5(2023)年3月末時点で168haとなっています。
また、所有者不明土地の解消に向けて、令和3(2021)年に民法等が改正され、令和6(2024)年4月から相続登記の申請が義務化されることとなっています。
1 以下の(1)、(2)のいずれかに該当する農地をいう。
(1) 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
(2) その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地((1)に掲げる農地を除く。)
(企業の農業参入は一貫して増加傾向)
農地を借りて農業経営を行うリース法人数は、平成21(2009)年の農地法改正によりリース方式による参入を全面解禁して以降、一貫して増加傾向で推移しており、令和4(2022)年1月時点では前年に比べ335法人増加し4,202法人となりました(図表3-5-2)。また、リース法人の借入面積の合計は1万4,224ha、1法人当たりの平均面積は3.4haとなっています。
農林水産省では、農地バンクを中心としてリース方式による企業の参入を促進することとしています。
(一般法人の農地所有の特例について、構造改革特区に移行)
我が国においては、農地法上、基本的に、農地を所有できる法人は農地所有適格法人に限られており、その他の一般法人は貸借による農地の権利取得が認められています。
他方、国家戦略特区においては、一定の要件の下、農地所有適格法人以外の法人の農地の所有(法人農地取得事業)を認める農地法の特例が設けられ、その期限である令和5(2023)年8月末まで兵庫県養父市(やぶし)において本特例を活用した農地の権利取得が行われました。
一般法人の農地所有の特例については、令和5(2023)年9月に改正構造改革特別区域法(*1)が施行され、対象となる法人や地域に係る要件、区域計画の認定に係る関係行政機関の長による同意の仕組みを維持した上で、地方公共団体の発意による構造改革特別区域法に基づく事業に移行することとなりました。
本事業は、(1)市町村が農業者から農地を購入した上で法人に売り渡す、(2)法人が農地を不適正利用した場合には、市町村が買い戻すこと等により、農地の適正利用を担保することとしています。
1 正式名称は「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」
(外国法人が議決権を有する日本法人等による農地取得は0.1ha)
令和4(2022)年に外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者による農地取得はありませんでした(*1)。また、外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者について、これらが議決権を有する日本法人又は役員となっている日本法人による農地取得は1社、0.1haとなっています(*2)。
我が国において農地を取得する際には、農地法において、取得する農地の全てを効率的に利用して耕作を行うこと、役員の過半数が農業に常時従事する構成員であること等の要件を満たす必要があります。このため、地域とのつながりを持って農業を継続的に営めない者は農地を取得することはできず、外国人や外国法人が農地を取得することは基本的に困難であると考えられます。
このほか、令和5(2023)年9月から、改正構造改革特別区域法に基づく農業委員会への報告事項等に法人の役員の国籍等を追加するとともに、これに合わせ、農地法においても農地所有者の国籍等を申請書の記載事項等に追加することとしました。
1 居住地が海外にある外国人と思われる者について、平成29(2017)年から令和4(2022)年までの累計は1者、0.1ha
2 平成29(2017)年から令和4(2022)年までの累計は6社、67.6ha(売渡面積5.3haを除く。)
(2)農地の集積・集約化の推進
(農地の総権利移動の面積は近年横ばい傾向で推移)
農地の総権利移動の面積については、近年横ばい傾向で推移しており、令和3(2021)年は前年に比べ6.7%減少し29万9千haとなりました(図表3-5-3)。また、令和3(2021)年の農地の権利移動の件数は、前年に比べ2万2千件減少し53万9千件となりました。
(担い手への農地集積率は前年度に比べ0.6ポイント上昇)
農地中間管理事業を創設した平成26(2014)年4月以降、担い手への農地集積率については増加傾向にあり、令和4(2022)年度は前年度に比べ0.6ポイント上昇し59.5%となりました(図表3-5-4)。
農業者の減少が進行する中、農業の生産基盤を維持する観点から、農地の引受け手となる農業経営体の役割が一層重要となっており、農地バンクの活用や基盤整備の推進により、担い手や目標地図に位置付けられた受け手への農地の集積・集約化を進めていく必要があります。
(事例)担い手への農地集積率が高い地区において目標地図を先行的に作成(福井県)
福井県若狭町(わかさちょう)では、地域計画の策定に向け、担い手への農地集積率が高い地区において、目標地図を先行的に作成しています。
同町では、農業者の高齢化や担い手不足のため、不耕作地が増えることが懸念されており、農地の集積・集約化を早急に進めていくことが必要となっています。また、特産のうめの生産者が減少しており、新たな担い手の育成も急務となっています。
このため、同町では分散錯圃(ぶんさんさくほ)を解消し、担い手への農地の集約を図るため、離農する農地所有者等については、原則として農地バンクに貸し付け、人・農地プランに基づき、担い手に農地を集積・集約化することとしています。
令和4(2022)年3月には、担い手への農地集積率が高い瓜生(うりゅう)地区において、目標地図の素案を先行的に作成しました。同地区での目標地図の作成に当たっては、作成の過程で農地の受け手となる担い手の意識が高まり、担い手同士の連携が高まるなどの変化が見られており、令和3(2021)年には80%台だった担い手への農地集積率が、令和5(2023)年には90%台になりました。
今後は、令和6(2024)年度までに町内7地区で地域計画を策定することとしており、10年後の目標地図の姿に向けて、数年ごとに現況地図を確認しながら、農地の集積・集約化等の取組を進めていくこととしています。

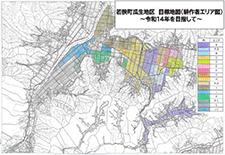
瓜生地区の目標地図の素案
資料:福井県若狭町

農業委員と認定農業者との
意見交換会
資料:福井県若狭町
(農地バンクの活用が進展)
農業現場においては、農地が分散している状況を改善し、農地を引き受けやすくしていくことが重要となっており、農地バンクにおいては、地域内に分散・錯綜(さくそう)する農地を借り受け、まとまった形で担い手へ再配分し、農地の集積・集約化を実現する農地中間管理事業を行っています。令和4(2022)年度の農地バンクの借入面積は4万5千haとなったほか、転貸面積は5万3千ha、そのうち新規集積面積は1万7千haとなっています。
農地の集積・集約化を進めることによって、(1)作業がしやすくなり、生産コストや手間を減らすことができる、(2)スマート農業等にも取り組みやすくなる、(3)遊休農地の発生防止を図れるなどの効果が期待できます。
農地バンクは、地域計画の中で、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した目標地図に位置付けられた受け手に対して、農地の集積・集約化を進めていくこととしています。
農林水産省では、農地バンクが分散した農地をまとめて借り受けた場合には、農業者の費用負担がない基盤整備、農地の集約化等に取り組む地域等への機構集積協力金の交付、出し手に対する固定資産税の軽減等の支援措置を講じています。
(3)地域計画の策定の推進
(地域計画の策定に必要な取組を支援)
地域計画は、令和5(2023)年4月に施行された改正農業経営基盤強化促進法(*1)や基本要綱に基づき、これまでの人・農地プランを基礎として、市町村が農業者等との協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や、農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地を表示した地図等を明確化し、公表するものです。
農林水産省では、地域での話合いをコーディネートする専門家の活用を始め、市町村による地域計画の策定に必要な取組や農業委員会の活動経費を支援しています。また、地域計画の策定の参考となる地域計画策定マニュアルや飼料も含めた地域計画策定のポイントの作成、地域計画の策定に向けて参考となる事例の紹介、先進的な地域とのWeb意見交換会を実施しています。

地域計画の策定に向けた先進的な地域とのWEB意見交換会
URL:https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku_ikenkoukankai.html
1 トピックス1を参照
(令和6(2024)年度までに地域計画の策定を行う予定がある市町村は1,636)
令和6(2024)年2月に集計した全国の市町村の取組状況によると、令和5(2023)年11月時点で、令和5(2023)年度に協議の場を設置する予定がある地区は18,798(1,493市町村)、目標地図の素案を作成する予定がある地区は3,896(492市町村)、地域計画の策定・公告を行う予定がある地区は1,488(239市町村)となっています(図表3-5-5)。また、令和6(2024)年度までに地域計画の策定を行う予定がある地区は23,326(1,636市町村)となっています。
地域によって取組状況に濃淡が見られているところ、農林水産省では、令和7(2025)年3月までに各市町村で地域計画の策定が着実に進められるよう、市町村や都道府県、農業委員会、農地バンク、農協、土地改良区等の関係機関・団体と連携しながら、現場の取組を親身になって後押ししていくこととしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883









