第4節 農業経営の安定化に向けた取組の推進
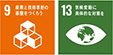
農業の現場では、原油価格・物価高騰等の影響も見られる中、自然災害等の様々なリスクに対応し、農業経営の安定化を図るためには、収入の減少を補償する収入保険や金融面での支援等が重要となっています。
本節では、農業経営の動向、農業経営の安定化に向けた取組について紹介します。
(1)農業経営の動向
(主業経営体1経営体当たりの農業所得は363万円)
令和4(2022)年における主業経営体1経営体当たりの農業粗収益は、畜産収入が減少したこと等から、前年に比べ36万4千円減少し2,035万9千円となっています(図表3-4-1)。
また、農業経営費は、肥料費、飼料費、動力光熱費等が増加したことから、前年に比べ34万2千円増加し1,673万円となりました。この結果、農業粗収益から農業経営費を除いた農業所得は、前年に比べ70万6千円減少し362万9千円となっています。
さらに、収益性を測る指標である売上高経常利益率を見ると、主業経営体1経営体当たりの売上高経常利益率については、近年原油価格や農業生産資材価格が高騰する中、令和元(2019)年以降、低下傾向で推移しており、令和4(2022)年は前年に比べ2.8ポイント低下し20.3%となっています。
なお、産業別の売上高営業利益率を見ると、その水準等は産業ごとに異なっており、一部の産業では、農業と同様に低下傾向で推移しているものも見られています(図表3-4-2)。
(法人経営体1経営体当たりの農業所得は76万円の赤字)
令和4(2022)年における法人経営体1経営体当たりの農業粗収益は、作物収入が増加したこと等から、前年に比べ491万7千円増加し1億2,679万円となっています(図表3-4-3)。
また、農業経営費は、飼料費、動力光熱費が増加したこと等から、前年に比べ992万6千円増加し1億2,755万4千円となりました。この結果、農業所得は前年に比べ500万9千円減少し76万4千円の赤字となっています。
さらに、法人経営体1経営体当たりの売上高経常利益率については、令和4(2022)年は前年に比べ3.4ポイント低下し1.5%となっています。
(フォーカス)おおむね横ばい傾向にある農業生産性の一層の向上が重要
生産性とは、生産を行うための労働や資本等に対して得られる産出物の割合を意味しています。生産性を測る指標としては、労働生産性や土地生産性等があります。
このうち労働生産性は、投入した労働量からどれくらいの価値が生み出されたかを表す指標です。農業従事者1人当たりの労働生産性については、令和4(2022)年は前年に比べ6万4千円減少し58万3千円となっています(図表1)。
一方、土地生産性は、単位面積当たりでどれくらいの価値が生み出されたかを表す指標です。経営耕地面積10a当たりの土地生産性については、令和4(2022)年は前年に比べ7千円減少し6万9千円となっています(図表2)。
今後10~20年先を見ると、基幹的農業従事者の減少が避けられない状況の中で、農業生産を維持・拡大していくためには、おおむね横ばい傾向にある農業生産性の一層の向上を図ることが重要となります。そのためには、担い手への農地の集積・集約化を進めるとともに、スマート農業を始めとした農業生産性改善のための設備投資や、国内外の新規需要の開拓等を更に推進していくことが重要となっています。
(2)経営所得安定対策の着実な実施
(経営所得安定対策の加入申請件数は、前年度に比べ減少)
経営所得安定対策は、農業経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正するための畑作物の直接支払交付金(以下「ゲタ対策」という。)や農業収入の減少が経営に及ぼす影響を緩和するための米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(以下「ナラシ対策」という。)を交付するものです。
令和5(2023)年度におけるゲタ対策については、加入申請件数は前年度に比べ631件減少し4万521件となった一方、作付計画面積は前年度に比べ3千ha増加し52万9千haとなりました(図表3-4-4)。
また、ナラシ対策については、収入保険への移行のほか、継続加入者についても作付転換や高齢化に伴う規模縮小等により、加入申請件数は前年度に比べ5,654件減少し5万4,161件、申請面積は前年度に比べ3万9千ha減少し59万6千haとなっています。
(3)収入保険の普及促進・利用拡大
(収入保険の加入者は着実に拡大)
収入保険は、農業者の自由な経営判断に基づき収益性の高い作物の導入や新たな販路の開拓にチャレンジする取組等に対する総合的なセーフティネットであり、品目の枠にとらわれず、自然災害だけでなく価格低下等の様々なリスクによる収入の減少を補償しています。
令和5(2023)年の加入経営体数は、農業者の関心が高まったこと等を背景に、前年に比べ1万1,776経営体増加し9万644経営体となりました(図表3-4-5)。これは青色申告を行っている農業経営体数(35万3千経営体)の25.7%に当たります。さらに、令和6(2024)年の加入実績は、同年1月末時点で9万3,286経営体となっています。
品目別に見ると、同年1月末時点の加入経営体数は、米が5万7,460経営体で最も多く、次いで野菜、果樹の順となっています(図表3-4-6)。
自然災害による損害を補償する農業共済と合わせた農業保険全体で見た場合、令和4(2022)年産における水稲の作付面積の81%、麦の作付面積の96%、大豆の作付面積の85%が加入していることになります。
また、令和4(2022)年12月に、農業保険法の施行後4年を迎えた収入保険の今後の取組方針を決定したことを踏まえ、令和5(2023)年度において、(1)甚大な気象災害による影響を緩和する特例、(2)青色申告1年分のみでの加入、(3)保険方式のみで9割まで補償する新たな補償タイプの創設について、令和6(2024)年に保険期間が始まる収入保険の加入者から実施できるよう措置したところです。
(高温等の影響による一等米比率の減少に対し、高温耐性品種の転換等を推進)
令和5(2023)年産米の農産物検査における水稲うるち玄米の一等米比率は、北陸や東北の日本海(にほんかい)側において白未熟粒(しろみじゅくりゅう)が発生したこと等により、令和5(2023)年12月末時点で61.3%と、例年に比べ低い水準となりました(図表3-4-7)。
高温等の影響による農産物の収量や収入の減少に対しては、農業共済や収入保険によって対応しています。また、水稲共済においては、高温障害の影響が広範に見られる場合に、その影響を加味した損害評価を行う特例があり、令和5(2023)年産について新潟県(にいがたけん)農業共済組合に適用しました。
一方、農業保険に未加入の農業者も見られることから、農業保険への加入促進に加え、高温環境に適応した栽培体系への転換に向けて、地域の実情や品目に応じた高温耐性品種や栽培技術の導入等の実証や機械導入を支援しています。
(4)農業金融・税制
(農業向けの新規貸付額は、農協系統金融機関や公庫では増加傾向)
農業向けの融資においては、農協系統金融機関(信用事業を行う農協及び信用農業協同組合連合会並びに農林中央金庫)、地方銀行等の一般金融機関が短期の運転資金や中期の設備資金を中心に、公庫がこれらを補完する形で長期・大型の設備資金を中心に、農業者への資金供給の役割を担っています。農業向けの新規貸付額については、平成29(2017)年度と令和4(2022)年度を比較すると、農協系統金融機関や公庫では増加しています(図表3-4-8)。
農林水産省では、物価高騰等の影響を受けた農業者等が円滑な資金の融通を受けられるよう、金融支援対策を講じています。
(ESGに配慮した農林水産業・食品産業向けの投融資を推進)
持続可能な経済社会づくりに向けた動きが急速に拡大する中、長期的な視点を持ちESG(*1)の非財務的要素にも配慮することで社会課題の解決と成長の同期を目指す金融の在り方が注目されています。また、地域金融の領域では、地域の基幹産業である農林水産業・食品産業を対象とした取組の更なる進展が期待されています。
農林水産省では、令和6(2024)年3月に、地域金融機関によるESGの要素を考慮した事業性評価に基づく投融資・本業支援を推進するため、「農林水産業・食品産業に関するESG地域金融モデル事例集」、「農林水産業・食品産業に関するESG地域金融実践ガイダンス(第3版)」を公表しました。
1 特集第2節を参照
(事例)高校等に研究費用を助成し、アグリビジネスの活性化をサポート(岐阜県)
岐阜県大垣市(おおがきし)に本店を置く地方銀行である株式会社大垣共立銀行(おおがききょうりつぎんこう)は、アグリビジネスを支援する専用窓口を設置し、農業者への融資に加え、補助金等に関する情報提供、ビジネスマッチング等の支援を行っています。また、アグリビジネスファンドによる出資支援や独自ブランドによる農産品の販売支援等を通じ、同行グループ全体で農業分野に注力し、事業者に寄り添った支援を行っています。
このような中、OKBの愛称で知られる同行では、平成26(2014)年3月に「OKBアグリビジネス助成金」制度を創設し、岐阜県、愛知県、三重県及び滋賀県の4県を対象として、アグリビジネスの成長・発展を継続的に支援してきました。同制度の下で、将来のアグリビジネスの担い手による特徴的なアイデアが幾つも具体化しており、地域農業の活性化を支える一つの契機となっています。
第10回目となる令和5(2023)年度は、同年8月に、SDGs推進等の観点から、9件(高校部門で8件、大学部門で1件)の受賞が決定し、地球に優しい鶏卵開発への挑戦等の研究課題が採択されました。
同行では、今後とも、同制度の活用・普及等を通じてアグリビジネスの活性化をサポートするとともに、地域と一体となってSDGs達成に向けた取組を強化していくこととしています。


アグリビジネス助成金の贈呈式
資料:株式会社大垣共立銀行

研究課題に挑戦する高校生
資料:株式会社大垣共立銀行
(農業者等向けにインボイス制度への相談対応を実施)
令和5(2023)年10月から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始され、事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、仕入先からインボイス(適格請求書)の交付を受け、保存しておくことが必要となりました。
一方で、農業者等が、卸売市場や協同組合等に一定の委託をして小売業者等に販売する場合には、当該小売業者等は、卸売市場や協同組合等が発行する書類に基づいて仕入税額控除の適用を受けることができるなどの特例が設けられています。
卸売市場や協同組合等以外に出荷している農業者等においては、取引先からインボイスを求められる場合もあるため、取引形態に応じた適切な対応の考え方が分かる資料を作成して公表するなどの対応を行ってきたところです。
農林水産省では、インボイス制度の円滑な定着に向け、引き続き農業者等を対象とする説明会や専用ダイヤルによる相談対応、広報資料の作成・公表等を行い、制度の周知等に努めるとともに、関係省庁とも連携して農業者等に寄り添ったきめ細やかな対応を行っていくこととしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883















