第10節 国際交渉への対応と国際協力の推進
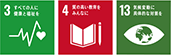
国際交渉においては、我が国の農林水産業が「国の基(もとい)」として発展し、将来にわたってその重要な役割を果たしていけるよう交渉を行うとともに、我が国の農林水産物・食品の輸出拡大につながる交渉結果の獲得を目指しています。また、途上国の自立的な経済発展を支援するため、様々な形態による農林水産分野の協力を行っています。
本節では、経済連携交渉等の国際交渉への対応状況や国際協力の推進等について紹介します。
(1)国際交渉への対応
(複数の国・地域とのEPA/FTAの交渉を実施)
特定の国・地域で貿易ルールを取り決めるEPA(*1)/FTA(*2)等の締結が世界的に進み、令和6(2024)年1月時点では399件に達しています。
我が国においても、令和6(2024)年3月時点で、21のEPA/FTA等が発効済・署名済です(図表1-10-1)。これらの協定により、我が国は世界経済の約8割を占める巨大な市場を構築することになります。輸出先国・地域の関税撤廃等の成果を最大限活用し、我が国の強みを活かした品目の輸出を拡大していくため、我が国の農林水産業の生産基盤を強化していくとともに、新市場開拓の推進等の取組を進めることとしています。
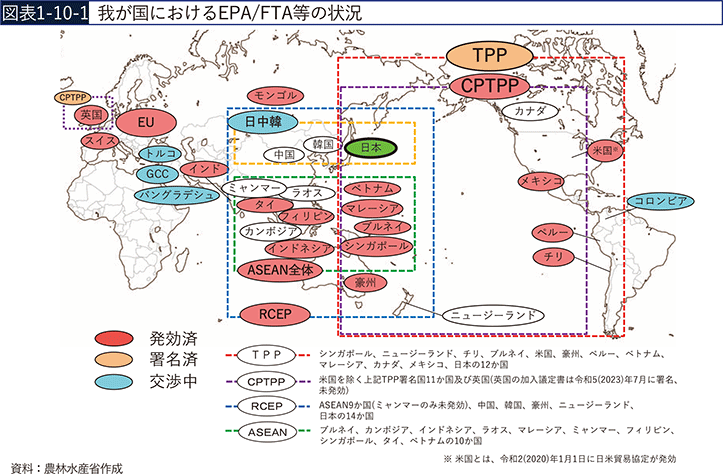
令和5(2023)年度においては、GCC(*3)(湾岸協力理事会)との間でFTA交渉を令和6(2024)年中に再開することを発表したほか、イスラエル、バングラデシュ、それぞれとの間で共同研究を実施しました。さらに、令和6(2024)年3月に日・バングラデシュEPA交渉を開始することを決定しました。

EPA/FTA等に関する情報
URL:https://www.maff.go.jp/j/
kokusai/renkei/fta_kanren/
また、世界共通の貿易ルールづくり等が行われるWTO(*4)(世界貿易機関)においても、これまで数次にわたる貿易自由化交渉が行われてきました。平成13(2001)年に開始されたドーハ・ラウンド交渉においては、依然として途上国と先進国の溝が埋まっていないこと等により、農業分野等の交渉に関する今後の見通しは不透明ですが、我が国としては、世界有数の食料輸入国としての立場から公平な貿易ルールの確立を目指し交渉に臨んでおり、我が国の主張が最大限反映されるよう取り組んでいます。
1 Economic Partnership Agreementの略で、経済連携協定のこと
2 Free Trade Agreementの略で、自由貿易協定のこと
3 Gulf Cooperation Councilの略
4 World Trade Organizationの略
(IPEFの三つの分野で交渉が進展)
米国、日本、豪州等14か国が参加するインド太平洋経済枠組み(IPEF(アイペフ)(*1))については、令和5(2023)年11月の閣僚級会合においてIPEFサプライチェーン協定に署名するとともに、クリーン経済及び公正な経済の分野で実質妥結しました。一方、貿易の分野については引き続き協議が行われることとなりました。
1 Indo-Pacific Economic Frameworkの略
(令和5(2023)年7月にCPTPP締約国及び英国が英国加入議定書に署名)
「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(CPTPP(*1))への英国の加入手続について、CPTPP締約国及び英国の間での協議が進められ、令和5(2023)年7月にCPTPPへの英国加入議定書の署名が行われました。
日本側の関税に関する措置については、現行のCPTPPの範囲内で合意しました。また、英国側の関税については、短・中粒種の精米等の関税撤廃を獲得しました。
我が国においては、同年12月に同議定書の効力発生のための国内手続が完了しました。
1 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnershipの略
(インドでG20農業大臣会合が開催)
令和5(2023)年6月に、インドでG20農業大臣会合が開催されました。同会合において我が国は、ロシアによるウクライナ侵略は明白な国際法違反であるとともに、世界の食料安全保障に大きな悪影響を及ぼすものであるとして、ロシアを最も強い言葉で非難しました。また、G7宮崎農業大臣会合で得た成果を踏まえ、(1)農業の持続可能性の向上は生産性を高める方法で行われるべきであること、(2)既存の国内農業資源を最大限活用すること、(3)あらゆる形のイノベーションが活用されるべきであることを主張しました。なお、会合での議論の内容を踏まえ、議長国インドから「成果文書及び議長総括」が発出されました。
(WTO農業交渉で、我が国は農産物の輸出規制に係る提案を実施)
令和5(2023)年10月にスイスで行われたWTO農業交渉会合では、我が国は農産物の輸出規制に係る提案を行いました。その内容は、農産物の輸出規制措置の導入に当たっての条件を明確化することや各加盟国が実施する輸出規制措置の情報共有を進めるものです。農林水産省では、輸出規制の透明性を高める議論をWTOの場で行うことにより、世界的に関心の高まる食料安全保障の確保に向けて、我が国の貢献を各国にアピールしていくこととしています。
一方、令和6(2024)年2~3月にアラブ首長国連邦で開催された第13回WTO閣僚会議では、農業分野の今後の作業計画等について議論されましたが、合意には至らず、議論が継続されることになりました。
(2)G7宮崎農業大臣会合の開催
(G7宮崎農業大臣会合を開催)
令和5(2023)年4月22~23日にかけて、宮崎県宮崎市(みやざきし)で国内の農業生産を担当する大臣が集まるG7宮崎農業大臣会合を開催しました。会合では、我が国が議長を務め、強靱(きょうじん)で持続可能な農業・食料システムの構築に向けて各国間で議論を行いました。特に農業の持続可能性を向上させるための各国の取組について相互に紹介した上で、G7として世界のために何ができるか、これから注力すべき分野は何かについて議論しました。我が国からは、みどり戦略を紹介し、生産性向上と持続可能性の両立の必要性を強調しながら、イノベーション技術の開発・普及の重要性を主張しました。

G7宮崎農業大臣会合で議論する農林水産大臣

マンゴー農園を視察する各国農業大臣
(「G7農業大臣声明」及び「宮崎アクション」を採択)
G7宮崎農業大臣会合では、食料安全保障をテーマに、特に強靱で持続可能な農業・食料システムの構築について議論し、今後の農業・食料政策の方向性として、(1)自国の生産資源を持続可能な形で活用すること、(2)農業の生産性向上と持続可能性を両立させること、(3)あらゆる形のイノベーションにより、農業の持続可能性を向上させることについて共通認識を得ました。
また、会合での議論を取りまとめた「G7農業大臣声明」や、より生産性が高く強靱で持続可能な農業・食料システムを構築するために、G7各国が取り組むべき行動を要約した「宮崎アクション」を採択しました。
具体的には、(1)既存の国内農業資源を持続的に活用し、貿易を円滑化しつつ、地元・地域・世界の食料システムを強化する途を追求し、サプライチェーンを多様化すること、(2)増え続ける世界人口を養いつつ、ネットゼロを達成するために温室効果ガス排出を削減し、生物多様性の損失を食い止め反転させるなどの長期的な課題に注力すること、(3)あらゆる形のイノベーションの実施や持続可能な農業慣行の促進により、農業・食料システムの持続可能性を向上させること等が盛り込まれました。
(コラム)G7宮崎農業大臣会合において高校生が提言を発表

高校生の提言
資料:G7宮崎農業大臣会合協力推進協議会
令和5(2023)年4月に開催されたG7宮崎農業大臣会合を機に、宮崎県内の高校生20人が、食や農業についての体験や議論を通して提言をまとめ、各国の農業大臣の前で英語での発表等を行いました。
提言の発表を行った「高校生の提言」プロジェクトチームは、14の県立高校の生徒で構成されており、メンバーが相互に協力して、各国代表への提言を準備しました。G7宮崎農業大臣会合では、若者らしいアイデアや情熱を盛り込んだプレゼンテーションビデオが紹介され、提言が発表されました。
具体的には、(1)自然環境への負荷、廃棄物、格差をゼロにすることを目指した、「国と国、人と人が共に」実施する共同研究、(2)「生産者と消費者が共に」農業の魅力をもっと知るため、若者に人気のある媒体や機会を利用して農業の魅力発信を行う「クールアグリキャンペーン」の実施、(3)「食と文化が共に」つながり続け、「食」に感謝することが当たり前な社会になるよう、子供たちに本物の農業を体験させる教育活動という三つの内容を提言しました。
「共に」をキーワードとした提言は、各国の大臣や関係者から高い評価を受けるとともに、G7宮崎農業大臣会合の成功に大きく貢献するものとなりました。
(日・IFAD共同声明に署名し、ELPSイニシアティブを立上げ)
G7宮崎農業大臣会合の機会に先立ち、令和5(2023)年4月に、農林水産大臣は、国際農業開発基金(こくさいのうぎょうかいはつききん)(IFAD(イファッド)(*1))総裁と会談し、日・IFAD共同声明の署名・発出を行うとともに、先進国等の民間企業による途上国の小規模農業者等への支援を促進するための「民間セクター・小規模生産者連携強化(ELPS(エルプス)(*2))」イニシアティブを立ち上げました。日本政府からの任意拠出金を用いてIFADが実施するもので、我が国のリーダーシップによる新たな国際協力の取組として、G7農業大臣声明に明記され、G7各国から歓迎されました。
1 International Fund for Agricultural Developmentの略
2 Enhanced Linkages between Private sector and Small-scale producersの略
(第5回G7 CVOフォーラムを開催)
G7宮崎農業大臣会合では、鳥インフルエンザ等の越境性動物疾病や薬剤耐性(AMR(*1))等の世界的な課題について、G7各国の獣医当局が協力し、情報交換するためG7 CVO(*2)(首席獣医官)フォーラムの開催が合意されました。これを受けて、令和5(2023)年9月に東京都で第5回G7 CVOフォーラムが開催されました。
G7各国の首席獣医官や獣医当局の専門家のほか、FAOやWOAH(*3)(国際獣疫事務局)の代表者等が出席し、アフリカ豚熱(ぶたねつ)等の越境性動物疾病対策、AMR対策、鳥インフルエンザ対策の三つの世界共通の課題について議論等を行いました。
1 第1章第9節を参照
2 Chief Veterinary Officersの略
3 World Organisation for Animal Healthの略
(3)国際協力の推進
(ウクライナへ農業分野での支援・協力に向けた取組を開始)
農林水産省とウクライナ農業政策・食料省は、令和5(2023)年10月に「日ウクライナ農業復興戦略合同タスクフォース」の設置に合意し、同年11月には、第1回タスクフォースを開催しました。我が国からは農林水産省のほか、ウクライナの農業復興に取り組む関係機関、農業機械メーカー等の民間企業から約100人が参加し、両国の関係省庁・関係企業の初会合を行いました。また、同年12月には、ウクライナ農業政策・食料省の幹部等を我が国に招へいしました。
令和6(2024)年2月に東京都で開催された「日・ウクライナ経済復興推進会議」では、両国首脳立会の下、農業機械メーカー等日本企業6社とウクライナ農業政策・食料省等との間で計8本の覚書を締結しました。また、日本企業のウクライナ農業復興への参画を促し、農業生産力の回復を通じたウクライナ復興支援に貢献するため、農業生産力の回復に向けた全体設計に必要な調査や日本企業による実現可能性調査の実施支援を進めています。
(アフリカへの農業協力を推進)

イネの有望系統の開発支援
資料:アフリカ稲センター
アフリカ各国が食料安全保障を強化し、経済発展を達成するためには、各国の農業生産の増加や所得の向上が不可欠です。我が国は、アフリカに対して農業の生産性向上や持続可能な食料システム構築等に向けた様々な支援を通じ、アフリカ農業の発展に貢献しています。
令和5(2023)年度は、アフリカにおける市場ニーズに適合したイネの開発や栽培方法の確立を支援したほか、我が国企業が有する先端技術や農業生産資材等を導入し、農業生産性の向上やフードバリューチェーンの強化に貢献しました。
今後ともアフリカ各国や関連する国際機関等との連携を図りつつ、農業分野の課題解決を図ることとしています。また、各国の投資環境や消費者ニーズを捉え、我が国の食産業の海外展開や農林水産物・食品の輸出に取り組む企業を支援していくこととしています。
(「ASEAN+3緊急米備蓄」を推進)

フィリピンでの
支援米の放出式典
我が国は東アジア地域(ASEAN(*1)10か国、日本、中国及び韓国)における食料安全保障の強化と貧困の撲滅を目的とした米の備蓄制度である「ASEAN+3緊急米備蓄」(APTERR(アプター)(*2))について、平成24(2012)年の協定発効以来、現物備蓄事業への拠出や事務局への日本人専門家の派遣等を通じ、積極的に支援しています。令和5(2023)年度には、我が国からラオスとフィリピンにコメの支援を行ったほか、我が国が提案した「持ち帰り支援」の最初の事例として、フィリピンの小学校の児童に対しコメを提供しました。また、APTERRについては、ASEAN+3首脳会議において、食料安全保障の確保に向けた効果的な実施や協力の強化が求められており、我が国は活動の更なる発展に貢献していくこととしています。
1 Association of South-East Asian Nationsの略で、東南アジア諸国連合のこと
2 ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserveの略
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




