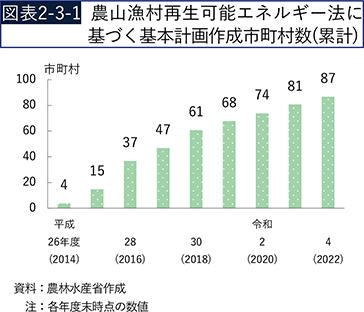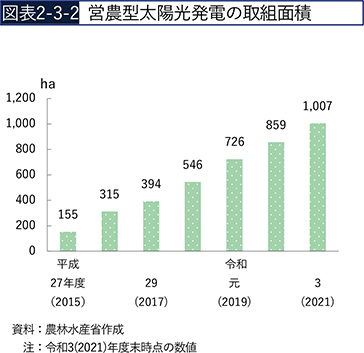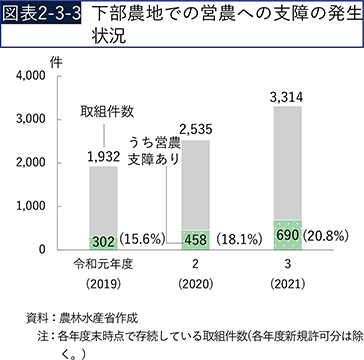第3節 バイオマスや再生可能エネルギーの利活用の推進
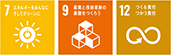
バイオマスの活用は、農山漁村の活性化や地球温暖化の防止、循環型社会の形成といった我が国が抱える課題の解決に寄与するものであり、その推進が求められています。また、エネルギーの安定供給等の観点から、国産の再生可能エネルギーを導入することが重要であるほか、農山漁村における再生可能エネルギーの導入に当たっては、地域に豊富に存在するバイオマス、水、太陽光等の資源を有効活用し、地域の所得向上等につなげることも重要です。
本節では、バイオマスや再生可能エネルギーの利活用推進の取組について紹介します。
(1)バイオマスの利活用の推進
(農山漁村や都市部におけるバイオマスの総合的な利用を推進)
持続的に発展する経済社会の実現や循環型社会の形成には、みどり戦略に示された生産力の向上と持続性の両立を推進し、バイオマスを製品やエネルギーとして活用するなど、地域資源の最大限の活用を図ることが重要です。
我が国には、温暖・多雨な気候条件により、バイオマスが豊富に存在していますが、「広く薄く」存在しているため、その活用に当たっては経済性の向上が課題であり、バイオマスを効果的に活用する取組を総合的に実施することが重要です。令和4(2022)年9月に閣議決定した「バイオマス活用推進基本計画」では、農山漁村だけでなく都市部も含め、新たな需要に対応した総合的なバイオマスの利用を推進することとしています。このため、農山漁村や都市部に存在するバイオマスについて、種類ごとの利用率の目標を設定し、堆肥や飼料等の既存の利用に支障のないよう配慮しつつ、バイオガス等の高度エネルギー利用を始め、より経済的な価値を生み出す高度利用を推進しています。

家畜排せつ物や食品廃棄物等を原料とするバイオガス発電施設
資料:株式会社ビオクラシックス半田

バイオマスの活用の推進
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/
(バイオマスを活用した技術開発が進展)
製品やエネルギーの各分野において、バイオマスを活用した技術開発が進められており、バイオマス活用推進基本計画では、これらの社会実装を見込むイノベーションを通じて、製品やエネルギーの産業化が進展することを前提とし、製品・エネルギー市場のうち、国産バイオマス関連産業の市場シェアを令和元(2019)年の約1%から令和12(2030)年の約2%に拡大することを目指すこととしています。
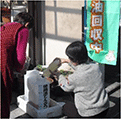
市民による
廃食用油の回収
資料:京都府京都市

バイオディーゼルを
使用したごみ収集車
例えば植物由来の食用油については、家庭で使用後の廃食用油を回収し、これを原料としてバイオディーゼル燃料を製造し、公共交通機関等の燃料として利用している事例、高純度バイオディーゼル燃料を製造・利用している事例も見られています。また、航空分野の脱炭素化に向け導入促進が求められているSAF(*1)については、令和12(2030)年までに本邦エアラインの燃料使用量の10%を置き換えるという目標に向けて、廃食用油等を原料としたSAFの製造が始まっています。一方で、原料調達が課題の一つとなっており、多様な原料の収集・確保に向け、関係省庁の連携を図ることとしています。廃食用油は配合飼料等の原料として再利用されているほか、近年輸出も増加していることから、配合飼料原料等としての需要に配慮しつつ、国内で資源循環を円滑に行っていく必要があります。
1 Sustainable Aviation Fuelの略であり、持続可能な航空燃料のこと
(バイオマスの活用による農山漁村の活性化や所得向上に向けた取組を推進)
バイオマスを製品やエネルギーとして持続的に活用していくことは、2050年カーボンニュートラルの実現に資するとともに、農山漁村の活性化や地球温暖化の防止、持続可能な循環型社会の形成といった我が国の抱える課題の解決に寄与するものであり、その推進が強く求められています。
意欲ある農林漁業者を始め、地域の多様な事業者が、農山漁村に由来する資源と産業を結び付け、地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を促す農山漁村の6次産業化は、我が国の農山漁村を再生させるための重要な取組です。
農林水産省では、みどり戦略に基づき、バイオマスの持続的な活用に向け、その供給基盤である食料・農林水産業の生産力向上と持続性を確保するとともに、重要な地域資源である農地において、荒廃農地の発生防止の観点から資源作物の栽培の可能性についても検討を進めることとしています。
また、下水汚泥の肥料利用の拡大やSAFの導入促進といったバイオマスの活用に向けた新たな取組を関係府省等と連携し推進することにより、地域の活性化や所得向上を推進することとしています。
(バイオマス産業都市を新たに2町選定)
地域のバイオマスを活用したグリーン産業の創出と地域循環型エネルギーシステムの構築を図ることを目的として、経済性が確保された一貫システムを構築し、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした環境に優しく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域を、関係府省が共同で「バイオマス産業都市」として選定しています。令和5(2023)年度においては新たに2町を選定し、バイオマス産業都市に選定した地域は、累計で103市町村となりました。バイオマス産業都市に選定された地域に対して、地域構想の実現に向けた各種施策の活用、制度・規制面での相談・助言等を含めた支援のほか、バイオマスの活用を促進する情報発信、技術開発・普及、人材の育成・確保等を行っています。
(2)再生可能エネルギーの利活用の推進
(農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画を作成した市町村数は87に増加)
みどり戦略においては、温室効果ガス削減のため、令和32(2050)年までに目指す姿として、我が国の再生可能エネルギーの導入拡大に歩調を合わせた、農山漁村における再生可能エネルギーの導入に取り組むこととしています。
カーボンニュートラルの実現に向けて、農山漁村再生可能エネルギー法(*1)の下、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー発電を促進することとしています。
農林水産省では、農山漁村再生可能エネルギー法に基づき、市町村、発電事業者、農業者等の地域の関係者から成る協議会を設立し、地域主導で農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー発電を行う取組を促進しています。
農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画を作成し、再生可能エネルギーの導入に取り組む市町村数については、令和4(2022)年度は前年度に比べ6市町村増加し87市町村となりました(図表2-3-1)。また、農山漁村再生可能エネルギー法を活用した再生可能エネルギー発電施設の設置数も年々増加しており、設備整備者が作成する設備整備計画の認定数は、令和4(2022)年度末時点で107となりました。
1 正式名称は「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」
(営農型太陽光発電の取組面積が拡大)
農地に支柱を立て、上部空間に太陽光発電設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う営農型太陽光発電は、農業生産と再生可能エネルギーの導入を両立し、適切に取り組めば、作物の販売収入に加え、発電電力の自家利用等による農業経営の更なる改善が期待できる有用な取組です。その取組面積については年々増加しており、令和3(2021)年度は前年度に比べ149ha増加し1,007haとなりました(図表2-3-2)。
一方、太陽光パネル下部の農地において作物の生産がほとんど行われないなど、農地の管理が適切に行われず営農に支障が生じている事例も増えており、その件数は令和3(2021)年度末時点で存続している取組のうち約2割となっています(図表2-3-3)。
事業者に起因して支障が生じている取組に対しては、農業委員会又は農地転用許可権者により、事業者に対する営農状況の改善に向けた指導が行われていますが、指導に従わなかった結果、事業の継続に必要な農地転用の再許可が認められないようなケースも発生しています。
このため、太陽光パネルの下部の農地における営農が適切に行われるよう、農地法や再エネ特措法(*1)等の関係法令に違反する事例に対して、厳格に対処するなどの対応が必要であり、令和6(2024)年3月に一時転用の許可基準等の法令への位置付けのほか、ガイドラインの作成を行いました。
1 正式名称は「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」
(事例)営農型太陽光発電を活用し、地域農業の活性化を推進(千葉県)


営農型太陽光発電の発電設備
資料:市民エネルギーちば株式会社

下部農地での大豆の有機栽培
資料:市民エネルギーちば株式会社
千葉県匝瑳市(そうさし)の市民(しみん)エネルギーちば株式会社では、営農型太陽光発電を活用し、地域主導で環境に配慮した市民発電所づくりを展開するとともに、地域農業の活性化を推進しています。
同社は、県内の環境や自然エネルギーに高い関心を持つ有志により設立された発電事業者であり、平成26(2014)年9月に、我が国初の市民出資型営農型太陽光発電として運転を開始して以降、営農型太陽光発電と市民発電所の設置・運営に特化した活動を展開しています。
令和5(2023)年4月には、同社が中心となって「匝瑳(そうさ)おひさま発電所(はつでんしょ)」を開設し、国内最大規模となる地域共生型営農型太陽光発電の事業に取り組んでいます。同市内の約6.5haの耕作放棄地を利用し、発電出力1,920kW、パネル出力2,703kWの発電を行うとともに、下部農地では麦類や大豆の有機栽培を行うことで、脱炭素化や環境保全のほか、雇用の創出、地域農業の活性化を目指すこととしています。
また、同社の子会社として設立された農地所有適格法人では、営農型太陽光発電事業の営農部門として農業経営に取り組むことで、太陽光発電による売電収入が得られるため、一般的には再生産可能な収益の確保が難しい品目でも経営が可能となり、持続可能な農業を確立しつつあります。
同社では、営農型太陽光発電を中心とした自然エネルギーと有機農業の融合による地域再生を目指しており、今後とも耕作放棄地を再生し、地域課題を解決する取組を市内全域で進めるとともに、営農型太陽光発電を学習する拠点となるアカデミーでの研修等を通じて、営農型太陽光発電を総合的に実践できる人材の育成に注力していくこととしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883