第2節 気候変動への対応等の環境政策の推進

我が国では、気候変動対策において、令和32(2050)年までにカーボンニュートラルの実現を目指しており、あらゆる分野ででき得る限りの取組を進めることとしています。また、みどり戦略や令和4(2022)年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP(*1)15)で採択された「昆明(こんめい)・モントリオール生物多様性枠組」等を踏まえ、生物多様性の保全等の環境政策も推進しています。
本節では、農林水産分野における温室効果ガス排出削減の取組や生物多様性の保全に向けた取組等について紹介します。
1 第2章第1節を参照
(1)地球温暖化対策の推進
(農林水産分野における温室効果ガスの排出量は4,790万t-CO2)
令和4(2022)年度における我が国の農林水産分野の温室効果ガス排出量は4,790万t-CO2となりました(図表2-2-1)。農林水産分野が占める温室効果ガス排出量の割合は全体の約4%であるものの、メタンの排出量は約8割、一酸化二窒素は約5割を占めています。
農林水産省では、「農林水産省地球温暖化対策計画」及び「農林水産省気候変動適応計画」に基づき、農林水産分野での気候変動に対する緩和・適応策を推進しています。今後、これらの計画やみどり戦略等に沿って、更なる温室効果ガスの排出削減や地球温暖化への適応に資する新技術の開発・普及を推進していくこととしています。
(食料・農業分野の持続可能な発展と気候変動対応の強化に向けたエミレーツ宣言が公表)
令和5(2023)年11~12月にアラブ首長国連邦のドバイで国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)が開催され、農業分野では、持続可能な農業及び強靱(きょうじん)な食料システム等の実現、メタンを含む非CO2ガスについて令和12(2030)年までの大幅な削減の加速等の内容を含む決定文書が採択されました。
また、同会議の首脳級セッションとして令和5(2023)年12月に開催された世界気候行動サミットでは、「持続可能な農業、強靭な食料システム及び気候行動に関するエミレーツ宣言」が公表され、食料・農業分野の持続可能な発展と気候変動対応の強化を目指し、持続可能な生産性の向上に向けたイノベーションの推進、あらゆる形態の資源動員の拡大等が提唱されました。同宣言はG7宮崎農業大臣会合の閣僚宣言で盛り込まれた内容を後押しするものとなっています。
このほか、COP28の食料・農業・水デー(12月10日)には、農業分野におけるJCM(*1)プロジェクトの形成も見据え、「アジアモンスーン地域における農業分野の温室効果ガスの削減とイノベーション」をテーマとしたセミナーを実施し、みどり戦略や日ASEANみどり協力プランについて発信しました。また、JIRCASにおいてはアジアモンスーン地域への農業技術の実装促進の取組紹介を行いました。
1 Joint Crediting Mechanismの略で、二国間クレジット制度のこと
(気候変動の緩和策として農業由来の温室効果ガス排出削減に向けた取組を推進)
農林水産省では、農業由来の温室効果ガス排出削減のため、施設園芸や農業機械の省エネルギー化等を進めています。また、農地土壌から排出されるメタン等の温室効果ガスを削減するため、水稲栽培における中干し期間の延長や秋耕(しゅうこう)といったメタンの発生抑制に資する栽培技術について、その有効性を周知するとともに、これらの技術を取り入れたグリーンな栽培体系への転換を支援しています。
畜産分野では、家畜排せつ物の管理や家畜の消化管内発酵に由来するメタン等が排出されることから、排出削減技術の開発・普及を進めることとしています。さらに、家畜排せつ物管理方法の変更について、地域の実情を踏まえながら普及を進めるとともに、アミノ酸バランス改善飼料の給餌については、家畜排せつ物に由来する温室効果ガスの発生抑制だけでなく、飼料費削減の効果も期待できることを周知しつつ普及を進めていくこととしています。
(気候変動の影響に適応するための品種・技術の開発・普及を推進)
農業生産は気候変動の影響を受けやすく、各品目で気候変動によると考えられる生育障害や品質低下等の影響が見られています。
農林水産省は、地球温暖化の影響と考えられる農業現場における高温障害等の影響やその適応策等について、報告のあった内容を取りまとめ、「地球温暖化影響調査レポート」として公表しています。
令和5(2023)年10月に公表した調査によると、水稲では、高温耐性品種の作付割合が年々増加しており、令和4(2022)年産は12.8%となっています(図表2-2-2)。また、水稲の適応策については、白未熟粒(しろみじゅくりゅう)や胴割粒(どうわれりゅう)の抑制対策として、「水管理の徹底」が最も多く行われています。
我が国においては、高温等の影響を回避・軽減する適応技術や高温耐性品種の導入、適応策の農業現場への普及指導等の取組が行われています。
また、気温の上昇に適応するため、より温暖な気候を好む作物への転換等の事例も見られています。
さらに、農研機構では、高温等の影響を考慮した農産物の収量や品質、栽培適地等の予測モデルを構築する取組を進めています。
農林水産省では、今後とも、農林水産省気候変動適応計画に基づき、気候変動に適応する生産安定技術・品種の開発・普及等を推進する取組を進めていくこととしています。

高温によるりんごの着色不良
資料:農研機構

高温による白未熟粒(左)と正常粒(右)の断面
資料:農研機構
(2)生物多様性の保全と利用の推進
(農林水産業は生物多様性に立脚)
亜熱帯から亜寒帯までの広い気候帯に属する我が国では、それぞれの地域で、それぞれの気候風土に適応した多様な農林水産業が発展し、地域ごとに独自の豊かな生物多様性が育まれてきました。
農林水産業は、気候の安定、水の浄化、受粉、病害虫の天敵、土壌形成、光合成や栄養循環等の生物多様性から得られる様々な「生態系サービス(*1)」に支えられており、様々な作物は、生物の遺伝的な多様性を利用し改良を重ねて得られたものです。農林水産業は、食料や生活資材等を供給する必要不可欠な活動として、地域経済の発展のみならず、地域の文化や景観を支えると同時に、人間と自然の共存を実現し、多様な生物種の生息・生育に重要な役割を果たしています。
1 人々が生態系から得られる便益のこと
(農業が有する環境・持続可能性への負の影響への関心が高まり)
農林水産業は、生物多様性に立脚すると同時に、農林水産業によって維持される生物多様性も多く存在し、農山漁村において様々な動植物が生息・生育するための基盤を提供する役割を持っています。一方、経済性や効率性を優先した農地・水路の整備、農薬・肥料の過剰使用等により、生物多様性に負の影響をもたらす側面もあります。
このため、将来にわたって持続可能な農林水産業を実現し、豊かな生態系サービスを享受していくためには、農林水産業が生態系に与える正の影響を伸ばしていくとともに負の影響を低減し、環境と経済の好循環を生み出していく視点が重要となっています。
我が国においては、食料供給を生態系サービスの一つと位置付けるという国際的な議論を踏まえ、農業が農地に限らず河川や海洋まで含めて環境に負の影響を与え、持続可能性を損なう側面もあるという前提に立ち、農業による温室効果ガスの排出削減、生物多様性の損失の防止といった環境への負荷を低減するための取組についても基本的施策に位置付け、環境に配慮した持続可能な農業を主流化する必要があります。
(コラム)「ネイチャーポジティブ(自然再興)」の考え方が広く浸透
令和4(2022)年12月に、生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。同枠組には「2030年ミッション」として「ネイチャーポジティブ(自然再興)」の考え方が取り入れられました。
ネイチャーポジティブは、生物多様性の損失を止めることから一歩前進させ、損失を止めるだけではなく回復に転じさせるという強い決意を込めた考え方です。
自然の回復力を超えた資本の利用によって、社会は物質的には豊かになった一方で、生態系サービスは過去50年間で劣化傾向にあることが指摘されています。私たちが持続的に生態系サービスを得ていくためには、地球規模で生じている生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せるネイチャーポジティブに向けた行動が急務となっています。
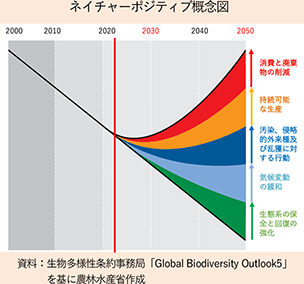
また、ネイチャーポジティブはいわゆる自然保護だけを行うものではなく、社会・経済全体を生物多様性の保全に貢献するよう変革させていく考え方であり、経済界からも注目を浴びています。投資家の企業に対する気候変動対応への要請が先行している中、更に「ネイチャーポジティブ」を目指しているかどうかも重要な評価指標となってきています。
農林水産業の観点からは、生産から消費に至る各段階において生物多様性への負の影響を軽減し正の貢献を増大させるための支援を講じ、我が国における持続可能な農林水産業の拡大を図ることが求められています。
我が国においては、令和5(2023)年3月に閣議決定した「生物多様性国家戦略2023-2030」に基づき、「2030年ネイチャーポジティブ(自然再興)」の実現に向けた取組を推進することとしています。
(農林水産省生物多様性戦略を改定)
令和4(2022)年12月に採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」では、農林水産関連について、持続的な農林水産業を通じた食料安全保障への貢献、陸と海のそれぞれ30%以上の保護・保全(30by30目標)、環境中に流出する過剰な栄養素や化学物質等(農薬を含む。)による汚染リスク削減等の令和12(2030)年目標が盛り込まれました。
農林水産省では、みどり戦略や昆明・モントリオール生物多様性枠組等を踏まえ、令和5(2023)年3月に、生物多様性保全を重視した農林水産業を強力に推進するため、「農林水産省生物多様性戦略」を改定しました。
同戦略では、環境と経済がともに循環・向上する社会を目指しており、農山漁村における生物多様性と生態系サービスの保全、農林水産業による地球環境への影響低減による保全への貢献、生物多様性への理解と行動変容の促進等に加え、サプライチェーン全体での取組を通じた生物多様性の主流化を図ることとしています。
(農村の水辺環境における生態系ネットワークの保全を推進)
農村の水辺環境においては、多様な生物がその生活史を全うできるよう、河川、水田、水路、ため池等を途切れなく結ぶ生態系ネットワークを保全する必要があります。また、農村の水辺環境を形成する水田や水路等の整備・更新の際には、生物多様性保全に配慮することが重要です。
農林水産省では、農業農村整備事業の実施に際しては、生態系ネットワーク保全等に配慮した調査計画、設計、施工、維持管理のための留意事項をまとめた資料等を作成するとともに、生態系に配慮した施設の整備を地域住民の理解や参画を得ながら計画的に推進しています。

魚類の移動障害を解消する水路魚道

多様な水深を確保する多自然型護岸
(生物多様性保全に配慮した農業を推進)
田園地域や里地里山は、人の適切な維持管理により成り立つ多様な環境がネットワークを形成し、持続的な農林業の営みを通じて、多様な野生生物が生息・生育する生物多様性の豊かな空間となっています。
このため、田園地域等において生物多様性が保全され、国民に安定的に食料を供給し、豊かな自然環境を提供できるよう、農林水産業のグリーン化等を通じて、環境負荷の低減や生物多様性保全をより重視した農業生産、田園地域等の整備・保全を推進することが求められています。
農林水産省では、土壌の性質を改善し、化学肥料・化学農薬の使用量低減に効果の高い技術を用いた持続性の高い農業生産方式の導入の促進を図るとともに、有機農業や冬期湛水(たんすい)管理といった生物多様性保全に効果の高い営農活動への取組等を支援しています。
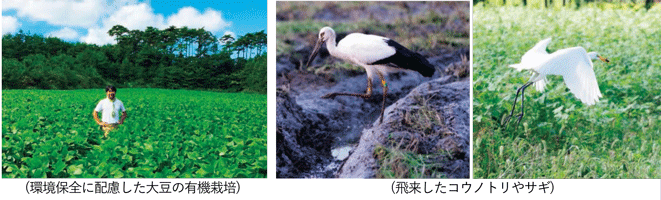
生物多様性を重視した大規模有機栽培
資料:株式会社金沢大地
(事例)地域一体となって生物多様性の保全に配慮した農業を推進(佐賀県)


冬水たんぼに飛来した野鳥
資料:佐賀県佐賀市
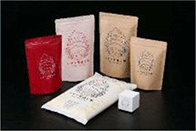
ブランド化した特別栽培米
資料:佐賀県佐賀市
佐賀県佐賀市(さがし)の「シギの恩返(おんがえ)し米推進協議会(まいすいしんきょうぎかい)」では、化学肥料・化学農薬の使用量低減や冬期湛水の実施といった生物多様性の保全に効果の高い営農活動を実施しています。
同市の東(ひがし)よか干潟付近の農地では、長年、多くの農家が農薬や化学肥料を減らす米づくりを行っており、地域に広がるクリーク(*1)網等は絶滅危惧種を含む多様な生物の生息地となっています。
平成27(2015)年5月に、東よか干潟がラムサール条約湿地(*2)として登録されたことを契機として、平成29(2017)年7月に、県、市、農協、大学、民間企業等を構成員として同協議会が設立され、東与賀(ひがしよか)地区の減農薬・減化学肥料米や特別栽培米をブランド化し付加価値を高める「シギの恩返し米プロジェクト」を開始しました。
同協議会では、「生き物を育む環境づくり」、「安全安心で持続可能な米づくり」等をテーマに、野鳥の餌場・休憩場を生み出すために水張りをする「冬水(ふゆみず)たんぼ」や下水道由来肥料の活用等の実証試験に取り組みました。また、化学肥料を使用せず、農薬の使用回数を削減し生産された米は、地域の環境保全に貢献するほか、食味にも優れ、販売量は年々拡大しています。
令和4(2022)年度からは生産・販売の取組については農業者主体の「シギの恩返し米生産部会」に引き継がれ、令和5(2023)年度は約4.8haの農地で取組が進められています。同協議会では、今後とも人や生き物と自然環境の永続的な共存を目指し、普及啓発等の取組を進めていくこととしています。
1 用水源、用水路、排水路、貯水池、調整池等の機能を持つ河川下流部の低平な水田地帯に掘られた人工水路のこと
2 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」に定められた国際的な基準に従って、締約国が指定した自国の湿地。条約事務局が管理する「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に掲載
(TNFD枠組みの最終版が公開)
昆明・モントリオール生物多様性枠組における「2030年ネイチャーポジティブ」の実現に向けて、企業に自社の事業活動が環境に及ぼす影響や依存度に関して情報開示を求める動きが加速しています。
自然に関する企業のリスク管理と開示の枠組みを構築するために設立された国際組織であるTNFD(*1)(自然関連財務情報開示タスクフォース)では、令和5(2023)年9月に、情報開示の枠組(フレームワーク)の最終版(Ver1.0)を公開しました。
農林水産省では、食料・農林水産業に関わる企業が環境負荷の低減を促進するとともに、自然資本関連の情報開示義務等に関する国際動向について必要な情報を入手し、スムーズな移行を進められるよう、関係省庁と連携して後押ししています。
1 Taskforce on Nature-related Financial Disclosuresの略で、民間企業や金融機関が、自然資本及び生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開示するための枠組みを構築する国際的な組織のこと
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883







