第1節 みどりの食料システム戦略の推進
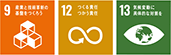
我が国の食料・農林水産業は、大規模自然災害の増加、地球温暖化、生産基盤の脆弱(ぜいじゃく)化、地域コミュニティの衰退、生産・消費の変化といった持続可能性に関する様々な政策課題に直面しています。また、SDGs(*1)や環境を重視する動きが加速し、あらゆる産業に浸透しつつあり、我が国の食料・農林水産業においても的確に対応していく必要があります。これらを踏まえ、農林水産省は令和3(2021)年5月に「みどり戦略(*2)」を策定し、さらに、令和4(2022)年7月には「みどりの食料システム法(*3)」が施行されました。
本節では、みどり戦略の意義のほか、調達、生産、加工・流通、消費の各段階での取組の推進状況を紹介します。
1 特集第1節を参照
2、3 特集第2節を参照
(1)みどり戦略の実現に向けた施策の展開
(食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現)
みどり戦略は、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるため、中長期的な観点から戦略的に取り組む政策方針です。
みどり戦略では、令和32(2050)年までに目指す姿として、農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現、化学農薬使用量(リスク換算)の50%低減、鉱物資源や化石燃料を原料とした化学肥料使用量の30%低減、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%に拡大といった14の数値目標(KPI(*1))を掲げています。また、その実現のために、調達から生産、加工・流通、消費までの各段階での課題の解決に向けた行動変容、既存技術の普及、革新的な技術・生産体系の開発と社会実装を、時間軸をもって進めていくこととしています。
1 Key Performance Indicatorの略で、重要業績評価指標のこと
(みどりの食料システム法に基づき環境負荷低減に向けた取組を推進)
みどりの食料システム法においては、環境負荷低減に取り組む生産者の事業活動(環境負荷低減事業活動)や、環境負荷の低減に役立つ機械や資材の生産・販売、研究開発、環境負荷低減の取組を通じて生産された農林水産物の流通の合理化等により環境負荷低減事業活動を支える事業者の取組(基盤確立事業)を、それぞれ都道府県、国が認定し、認定を受けた生産者や事業者に対し、税制特例や融資制度等の支援措置を講ずることとしています。
令和5(2023)年3月末までに全ての都道府県においてみどりの食料システム法に基づく基本計画が作成され、生産者の計画認定については、令和6(2024)年3月末時点で4千人以上が認定されています。また、事業者の計画認定については、同年3月末時点で64の事業計画が認定されています(図表2-1-1)。
さらに、みどりの食料システム法では、地域ぐるみの取組の創出を図るため、市町村等の発意で特定区域(モデル地区)を設定し、有機農業を促進するための栽培管理協定の締結等が可能となっています。令和6(2024)年3月末時点で、全国16道県29区域で特定区域が設定されており、このうち2県3区域で地域ぐるみの取組を行う生産者の計画認定、1区域で同協定の締結が行われ、具体的な取組が開始されています。
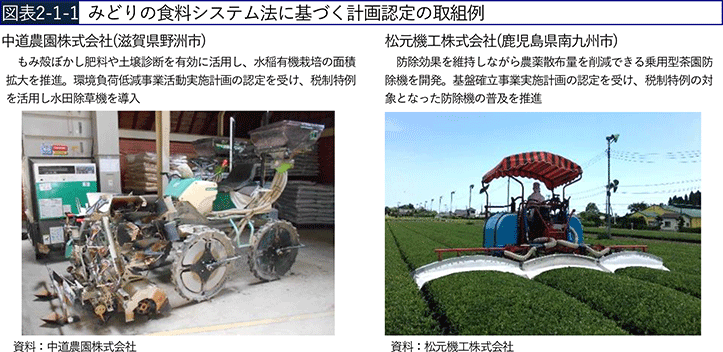
(地球温暖化防止のために環境に配慮した生産手法を推進すべきと考える人が約6割)
内閣府が令和5(2023)年9~10月に実施した世論調査によると、温室効果ガスの排出量の削減や化学農薬・化学肥料の使用量削減等の環境に配慮した生産手法を推進することについて、「地球温暖化を防止するために推進すべき」を挙げた人が57.8%で最も多く、次いで「持続可能な未来のための目標であるSDGsの流れを踏まえると推進すべき」が43.0%となっています(図表2-1-2)。
(みどり戦略に対する国民の認知・理解が一層進むよう取組を強化)
みどりの食料システム法では、国が講ずべき施策として、関係者が環境と調和のとれた食料システムに対する理解と関心を深めるよう、環境負荷の低減に関する広報活動の充実等を図ることとしています。
農林水産省は、みどり戦略に係る意見交換を実施するとともに、令和6(2024)年1月から、将来を担う若い世代の環境に配慮した取組を促すため、「みどり戦略学生チャレンジ(全国版)」を開催し、大学生や高校生等の個人・グループによる、みどり戦略に基づいた活動の実践と、その内容を発信する取組を募集しています。
(2)みどり戦略に基づく取組の状況
(農林水産業のゼロエミッション化に向けた取組を推進)
政府が掲げる2050年カーボンニュートラルの実現に向け、みどり戦略においては、令和32(2050)年までに農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現を目指すこととしています。
その実現に向けて、農林水産業の燃料燃焼によるCO2排出量の削減、燃料使用量削減に資する農業機械の担い手への普及、省エネルギーなハイブリッド型園芸施設等への転換、農山漁村における再生可能エネルギー導入を推進することとしています。
特に施設園芸に関しては、加温設備を備えた温室の大部分が化石燃料に依存している状況にあり、令和3(2021)年の加温面積に占めるハイブリッド型園芸施設等の割合は10.6%となっています(図表2-1-3)。
農林水産省では、環境負荷低減の技術を活用した持続可能な園芸施設への転換を促進するため、SDGsに対応し、環境負荷低減と収益性向上を両立したモデル産地を育成する取組を支援しています。
(化学肥料の使用量の更なる低減に向けた取組を推進)
りんや窒素は、作物の生育に不可欠な栄養素であり、化学肥料にも含まれる一方、不適切な使用が行われた場合には、水圏の富栄養化等の原因となることから、その資源を適切に利用しつつ、収支バランスを健全に保つことが重要です。
令和3(2021)年の化学肥料使用量は、85万t(NPK総量(*1)・生産数量ベース)で、基準年である平成28(2016)年比で約6%の低減となっています。
肥料の施用については、土壌や作物によって異なるため、単純に比較することはできませんが、我が国における窒素収支とりん収支は諸外国と比べ比較的高い水準となっています(図表2-1-4)。我が国は、りんや窒素等の成分を含有する、主要な化学肥料原料の大部分を海外に依存しており、食料安全保障の観点からも化学肥料使用量の更なる低減を図ることが必要となっています。
農林水産省では、みどりの食料システム法に基づき化学肥料の使用低減等に係る計画の認定を受けた生産者やその活動を支える事業者に対し、税制特例や融資制度等の支援措置を講じているほか、土壌診断による適正な肥料の施用や堆肥等の活用を促進しています。
1 肥料の三大成分である窒素(N)、りん酸(P)、加里(K)の全体での出荷量のこと
(化学農薬の使用による環境負荷の低減に向けた取組を推進)
みどり戦略においては、環境負荷低減のため、化学農薬を使用しない有機農業の拡大、化学農薬のみに依存しない病害虫の発生予防に重点を置いた「総合防除」等を推進しています。
コロナ禍に伴う国際的な農薬原料の物流停滞の影響により、農薬の製造・出荷が減少したこと等の特殊事情があった令和3(2021)農薬年度(*1)の化学農薬使用量(リスク換算)は、令和元(2019)農薬年度比で約9%低減となっていたところ、令和4(2022)農薬年度は、リスクの低い農薬への切替えといった取組の効果が現れたことにより、約4.7%の低減となりました。
農林水産省では、みどりの食料システム法に基づき、化学農薬の使用低減等の環境負荷低減に係る計画の認定を受けた生産者やその活動を支える事業者に対し、税制特例や融資制度等の支援措置を講じているほか、化学農薬のみに依存せず、病害虫の予防・予察に重点を置いた総合防除を推進するため、産地に適した技術の検証、栽培マニュアルの策定等の取組を支援しています。
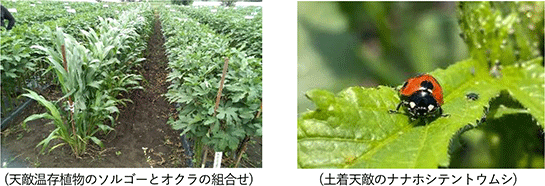
総合防除の導入による化学農薬の使用量低減
資料:いぶすき農業協同組合(左)、鹿児島県指宿市(右)
1 農薬年度は、前年10月から当年9月までの期間
(グリーンな栽培体系への転換に向けた取組を推進)
化学肥料・化学農薬の使用量低減、有機農業面積の拡大、農業における温室効果ガスの排出量削減を推進するため、堆肥、緑肥等の活用、自動抑草ロボットによる雑草防除、水稲栽培における中干し期間の延長等の産地に適した環境に優しい栽培技術と省力化に資する技術を取り入れたグリーンな栽培体系への転換を図ることが求められています。

乗用型除草機による雑草防除
資料:秋田県にかほ市
このため、農林水産省では、みどりの食料システム戦略推進交付金等により、スマート農業技術の活用、化学肥料・化学農薬の使用量低減、有機農業の推進、温室効果ガスの排出量削減等の環境負荷低減に取り組む水稲や野菜等の産地を創出することとしています。
令和5(2023)年度においては、産地に新たに取り入れる技術の検証、グリーンな栽培体系の実践に向けた栽培マニュアルの作成等を支援しました。
(みどり戦略の実現に向けた技術の開発・普及を推進)
農林水産省では、みどり戦略の実現に向け、スマート農業技術にも対応した品種開発の加速化、農林漁業者等のニーズを踏まえた現場では解決が困難な技術問題に対応する研究開発等を国主導で推進しています。例えば少ない施肥でも生育可能なトマト等の果菜類の開発、省農薬で機械化に適するりんごの開発等を進めています(図表2-1-5)。
また、令和3(2021)年度に、みどり戦略で掲げた各目標の達成に貢献し、現場への普及が期待される技術について、「「みどりの食料システム戦略」技術カタログ」として取りまとめており、令和5(2023)年5月には、「現在普及可能な技術」を作目別に追加収録したVer.3.0を公開しました。
この中では、技術の概要、技術導入の効果、みどり戦略における貢献分野(温室効果ガス削減等)、導入の留意点、価格帯、研究開発・改良、普及の状況、技術の問合せ先等を記載しています。
さらに、同カタログに掲載された技術をテーマとして、農業者・関係者が持つ技術情報を交流・議論・発展させる「みどり技術ネットワーク会議」を全国9か所で開催したほか、全国各地での議論内容を踏まえて、令和6(2024)年3月に「第1回みどり技術ネットワーク全国会議」を開催しました。
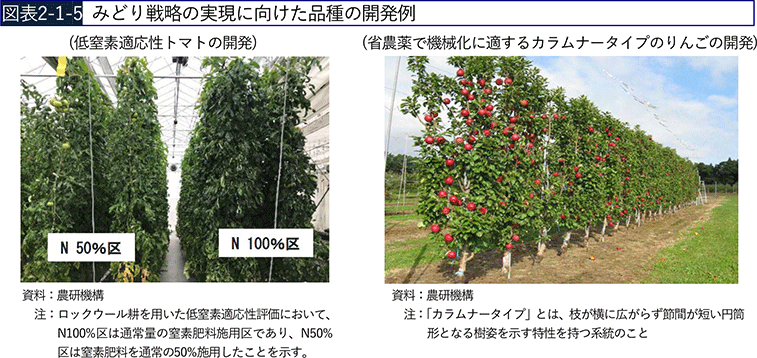
(3)有機農業の拡大に向けた施策の展開
(世界の有機農業の取組面積は拡大傾向で推移)
世界の有機農業の取組面積については、令和4(2022)年は9,637万haとなっており、過去15年間で約3倍に拡大しています(図表2-1-6)。また、国別の1人当たり年間有機食品消費額は、スイスを始め、欧州諸国で高い傾向にあります(図表2-1-7)。一方、我が国は欧米諸国と比較して低位な水準にあり、生産・消費両面での取組が必要となっています。
(我が国の有機農業の取組面積は拡大傾向で推移)
我が国では、有機農業の推進に関する法律において、「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業と定義されています。
我が国の有機農業の取組面積については、令和3(2021)年度は前年度に比べ5.6%増加し2万6,600haとなっており、その耕地面積に占める割合は0.6%となっています(図表2-1-8)。
農林水産省では、有機農業の拡大に向けた現場の取組を推進するため、広域的に有機農業の栽培技術を提供する民間団体の指導活動、農業者の技術習得支援等による人材育成、有機農業者グループ等による有機農産物の安定供給体制の構築、事業者と連携して行う需要喚起等の取組を支援することとしています。
また、市町村が主体となり、生産から消費まで一貫した取組により有機農業拡大に取り組むモデル産地である「オーガニックビレッジ」については、令和6(2024)年1月末時点で93市町村において取組が開始されています。
さらに、令和5(2023)年12月に、茨城県常陸(ひたち)大宮市(おおみやし)において、全国で初めて有機農業を促進するための栽培管理協定が締結され、地域ぐるみで有機農業の団地化の促進を図る取組が開始されています。
このほか、有機農業を生かして地域振興につなげている又はこれから取り組みたいと考える市町村、都道府県、民間企業・民間団体の情報交換等の場を設けるための「有機農業と地域振興を考える自治体ネットワーク」を設置し、地方公共団体間での有機農業の取組推進に関する情報共有等を促進しています。
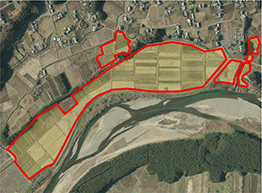
有機農業の栽培管理協定区域
資料:茨城県常陸大宮市
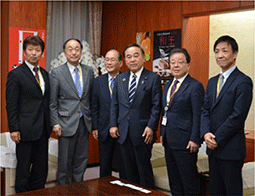
オーガニックビレッジに取り組む
市町村長と農林水産大臣
(フォーカス)市町村別の有機農業の取組面積割合は高知県馬路村が首位
農林水産省は、令和5(2023)年8月に、「有機農業の取組面積が耕地面積に占める割合が高い市町村」及び「有機農業の取組面積が大きい市町村」を公表しました。
令和3(2021)年度に有機農業の取組面積が耕地面積に占める割合が最も高い市町村は、高知県馬路村(うまじむら)で81%となっており、次いで山形県西川町(にしかわまち)が15%、宮城県柴田町(しばたまち)が13%、秋田県小坂町(こさかまち)が11%、島根県江津市(ごうつし)が10%となっています(図表1)。
高知県馬路村では、農薬を使用せず、発酵鶏ふんや落ち葉を活用したユズの有機栽培を村全体で推進していることが、取組割合の高さにつながっています。
一方、令和3(2021)年度に有機農業の取組面積が最も大きい市町村は、北海道標茶町(しべちゃちょう)で418haとなっており、次いで福井県大野市(おおのし)が367ha、北海道興部町(おこっぺちょう)が314ha、北海道浜中町(はまなかちょう)が294ha、北海道釧路市(くしろし)が223haとなっています(図表2)。
北海道標茶町では、町域で発生・排出が行われるバイオマス資源をメタン発酵消化液に転換し、有機肥料として可能な限り循環活用する取組の推進等により、有機農業の拡大につなげています。
各市町村において有機農業の取組面積を拡大していくためには、地域ぐるみで有機農業を推進していくことが重要であり、農林水産省では、地域の農業者や農業者団体、加工・流通事業者、地域の住民といった多様な関係者が参画の下、販路を確保しながら、人材の育成や生産性の向上等を着実に進めることで、将来にわたって持続的な産地を創出していくこととしています。
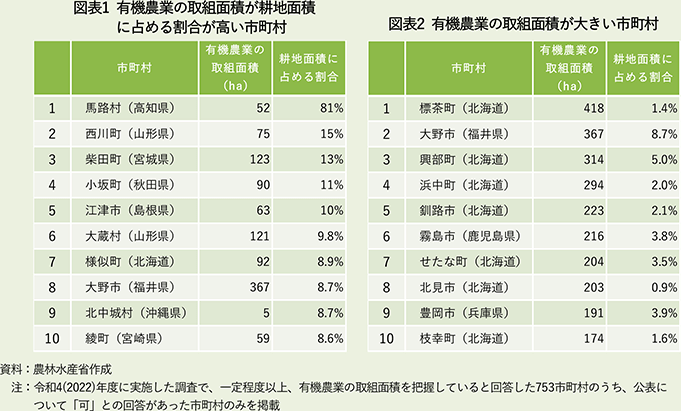
(我が国の有機農業の有機食品市場は拡大傾向で推移)
我が国の有機食品の市場規模は拡大傾向で推移しており、令和4(2022)年11月に実施した調査によると、令和4(2022)年の市場規模は2,240億円と推計されており、平成29(2017)年の1,850億円と比べ約2割増加しています。また、「週に1回以上有機食品を利用」している消費者の割合は、平成29(2017)年と比べ15.1ポイント増加し32.6%となっており、有機食品を利用する消費者の裾野も拡大しています(図表2-1-9)。
農林水産省では、有機農産物の販路拡大と新規需要開拓を促進するため、有機農産物の新規取扱いや生産者と事業者とのマッチングの取組を支援しています。
また、国産の有機食品の需要喚起に向け、事業者と連携して取り組むためのプラットフォームである「国産有機(こくさんゆうき)サポーターズ」を立ち上げており、令和6(2024)年3月末時点で111社が参画しています。
このほか、令和5(2023)年4月に、生産・加工・流通等の事業者で構成される一般社団法人日本有機加工食品(にほんゆうきかこうしょくひん)コンソーシアムが設立され、有機加工食品(パン等)の更なる生産拡大に取り組むとともに、産地・実需間の需給調整の仕組みや国産有機原料の活用を発信する取組を試行的に導入するなど、国産有機農産物等に関わる新たな市場の創出に向けた取組も広がりを見せています。
(4)環境保全型農業の推進
(環境保全型農業直接支払制度の実施面積は前年度に比べ増加)
化学肥料・化学農薬の使用を原則5割以上低減する取組と併せて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に対しては、環境保全型農業直接支払制度による支援を行っています。
令和4(2022)年度の実施面積は、前年度に比べ1千ha増加し8万3千haとなりました(図表2-1-10)。また、支援対象取組別に見ると、全国共通の取組では、「堆肥の施用」が25.6%で最も多く、次いで「カバークロップ(*1)」、「有機農業」の順となっています(図表2-1-11)。
1 土壌侵食の防止や有機物の供給等を目的として、主作物の休閑期や栽培時の畦間、休耕地、畦畔等に栽培される作物
(事例)環境に配慮して生産した農産物を直接供給する取組を推進(長崎県)


直売所での農産物販売
資料:農事組合法人ながさき南部生産組合

全筆圃場検査
資料:農事組合法人ながさき南部生産組合
長崎県南島原市(みなみしまばらし)の農事組合法人ながさき南部生産組合(なんぶせいさんくみあい)では、安全・安心な農産物の生産等の環境と調和した持続的な農業生産を推進し、消費者の信頼確保に努めるとともに、地元のみならず全国で多様な販路の確保に取り組んでいます。
同組合は、令和5(2023)年11月時点で142人の生産者で構成されており、約200haの農地で、たまねぎやトマト、ばれいしょ等を生産しています。
同組合では、島原半島(しまばらはんとう)内の畜産農家から調達した堆肥や有機質肥料を土壌診断結果に基づいて使用し、有機物資源の地域内循環を推進するとともに、有機農業や化学農薬の使用量を低減する取組を実施しています。また、圃場(ほじょう)ごとに栽培記録を作成し、内部監査委員による全筆(ぜんぴつ)圃場検査を行っているほか、残留農薬検査結果の公表、バイヤーや消費者を対象とした「公開監査」を全国に先駆けて導入するなど、品質管理を強化し、食の安全の確保に努めています。
販売面では、全国の消費者グループや大手生協との取引が約7割を占めていますが、取引品目・価格等を事前に決め、契約栽培を行うことで、安定的な収益を確保しています。また、同県諫早市(いさはやし)に直売所を設けているほか、九州を始め、全国の生協等の店舗にインショップを常設し、組合員の収入確保を図っています。
同組合では、食と農を通じて地域の自立と自然との共生を目指しており、今後とも、環境保全型農業を積極的に推進しながら、島原半島の中山間地で新しい農業のビジネスモデルを構築していくこととしています。
(堆肥等の活用による土づくりを推進)
農地土壌は農業生産の基盤であり、農業生産の持続的な維持向上に向けて、土壌の物理性や化学性、生物性を有機物等の施用や緑肥作物の導入等により改善し、生産力を高める「土づくり」に取り組むことが必要です。
土づくりにおいて重要な資材である堆肥の施用量は、農業者の高齢化の進展や省力化の流れの中で長期的に減少を続け、近年は横ばい傾向で推移しています。
農林水産省では、農業現場での土づくりを推進するため、土壌診断とその結果を踏まえた堆肥等の実証的な活用を支援しています。また、土壌診断における簡便な処方箋サービスの創出を目指し、AIを活用した土壌診断技術の開発を推進しています。さらに、土づくりに有効な堆肥の施用を推進するとともに、好気性強制発酵(*1)による堆肥の高品質化やペレット化による広域流通等の取組を推進しています。
1 攪拌装置等を用いて強制的に酸素を供給し、堆肥を発酵させる方法
(農業由来の廃プラスチックの適正処理対策を推進)
農業及び畜産業の生産現場では、農業用ハウスやマルチ等のプラスチック資材が使用されていることから、その排出による環境への負荷を低減するため、使用量の削減や、使用後に適切に回収し、リサイクル等の適正処理を進めることが重要です。
生分解性マルチは、作物収穫後に土壌中にすき込むことで、土壌中の微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解されるため、使用後の廃プラスチック処理が不要となり、プラスチックの排出抑制に貢献する資材です。また、作物収穫後の撤去・回収作業が不要になるといったメリットもあり、生分解性マルチの利用量(樹脂の出荷量)は、過去15年間で約3倍に増加しています。
農林水産省では、生分解性マルチへの転換に向けた取組のほか、農業用ハウスの被覆資材やマルチといった農業由来の廃プラスチックの適正処理対策を推進することとしています。
(5)みどり戦略に基づく取組の世界への発信
(国際会議において、みどり戦略に基づく我が国の取組を紹介)
みどり戦略の実現に向けた我が国の取組事例について、広く世界に共有する取組を進めています。
令和5(2023)年度においては、我が国を訪問した各国要人との面談の場、国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP(*1)28)、G20といった国際会議等のあらゆる機会を捉え、みどり戦略に基づく我が国の取組を紹介しました。
1 Conference of the Partiesの略
(農業技術のアジアモンスーン地域での実装を促進)
気候変動の緩和や持続的農業の実現に資する技術のアジアモンスーン地域での実装を促進するため、国立研究開発法人国際農林水産業研究(こくさいのうりんすいさんぎょうけんきゅう)センター(以下「JIRCAS」という。)において、みどりの食料(しょくりょう)システム国際情報(こくさいじょうほう)センターを設置し、技術情報の収集・分析・発信やアジアモンスーン地域での共同研究等の取組を進めています。
JIRCASでは、国内での研究や国際共同研究で得た成果から、アジアモンスーン地域での活用が期待され、持続可能な食料システムの構築に貢献し得る技術を「技術カタログ(*1)」として取りまとめ、令和5(2023)年度においては、G7宮崎農業大臣会合を始めとした様々な国際会議の場において、我が国の農業技術や共同研究の状況を発信しました。
1 正式名称は「アジアモンスーン地域の生産力向上と持続性の両立に資する技術カタログ」
(日ASEANみどり協力プランを採択)
令和5(2023)年10月にマレーシアで開催された日ASEAN農林大臣会合において、みどり戦略に基づくイノベーションを通して得られた我が国の技術を、ASEAN(*1)地域における強靱(きょうじん)で持続可能な農業・食料システムの構築に活用することを目的として我が国が提案した「日ASEANみどり協力プラン」が、全会一致で採択されました。同年12月に東京都で開催された日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議においても、内閣総理大臣が同プランに基づく協力を強化していく旨を表明しました。
今後、同プランに基づき、関係省庁や関係機関、民間企業等と連携して、各国と更なる協力プロジェクトの形成を進めていくこととしています。
1 第1章第10節を参照
(コラム)日ASEANみどり協力プランに基づくプロジェクトを展開
温室効果ガスの排出等に伴う気候変動の影響により食料安全保障上のリスクが高まる中、生産性を高めつつ持続的な農業・食料システムを構築することが、各国の課題となっています。そのための世界共通の技術や手法があるわけではなく、それぞれの地域や国の環境や農業条件に適した措置を採ることが効果的です。
我が国におけるみどり戦略に基づく取組は、高温多湿で、水田中心の農業が営まれ、中小規模農家の割合が高いといった特徴を共有するASEAN各国の持続的な食料システムの取組モデルとなり得るものです。一方、ASEANにおいても、令和4(2022)年10月に「ASEANにおける持続可能な農業のためのASEAN地域ガイドライン」を策定し、生産性が高く、経済的に実行可能で、環境的に健全な農業への移行を目指しています。
このような考えから、「日ASEANみどり協力プラン」は、我が国において得られた新技術やイノベーションを活かした協力プロジェクトを盛り込んでいます。具体的には、トラクターや田植機等の自動操舵(そうだ)技術による生産性向上と労働時間の削減、衛星データを活用した農地自動区画化・土壌診断技術による肥料の削減、二国間クレジット制度(JCM(*))を活用した農業分野での気候変動の緩和促進、ICTを活用した水田の水管理の高度化による気候変動影響緩和等が挙げられます。
既に各国において優先的に取り組むプロジェクトの協議・実証が進んでおり、今後はその推進を図っていくこととしています。
第2章第2節を参照
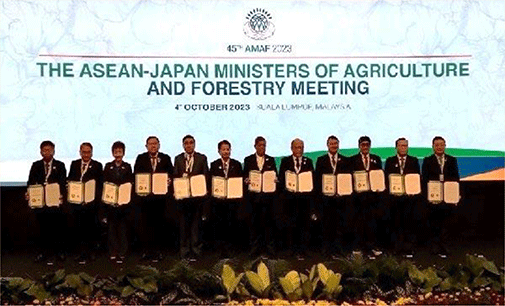
日ASEAN農林大臣会合
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883














