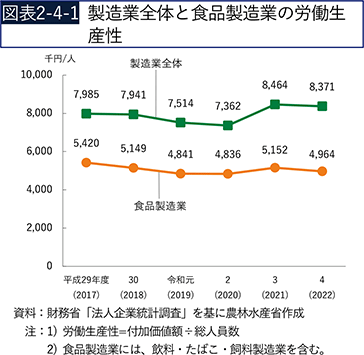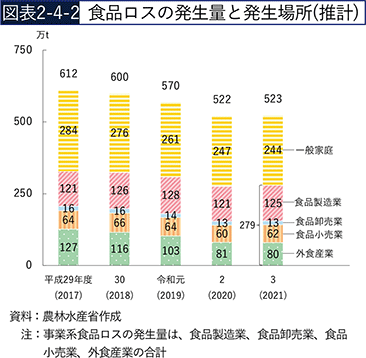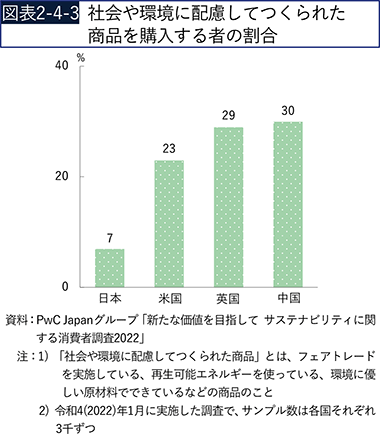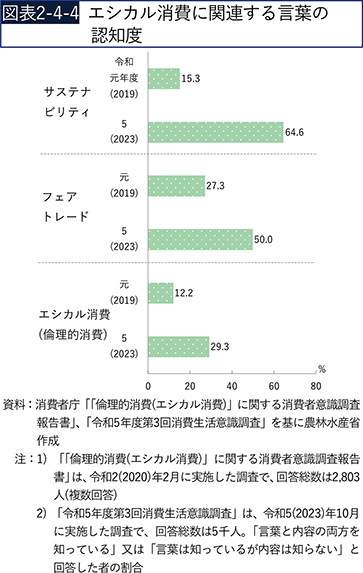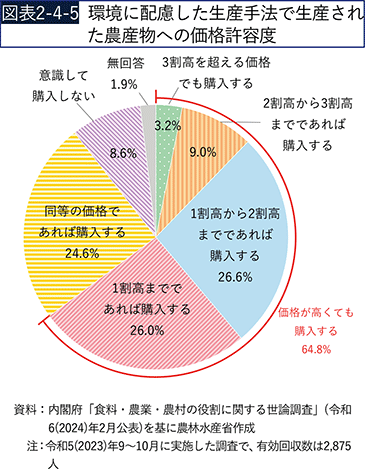第4節 持続可能な食品産業への転換と消費者の理解醸成の促進
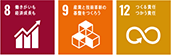
持続可能な食料システムの構築のため、フードチェーンをつなぐ食品産業においても、持続可能な方法で生産された原材料を使用し、食品ロスを削減するなど、環境や人権に配慮した持続可能な産業に移行することが求められています。また、このような取組の重要性について消費者の理解を深め、環境や持続可能性に配慮した消費行動への変化を促していくことも重要です。
本節では、持続可能な食品産業の推進に向けた取組や消費者への理解醸成を図る取組について紹介します。
(1)持続可能な食品産業への転換
(食品産業による持続可能性に配慮した取組を促進)
農業・食品産業については、温室効果ガスの排出削減や水質汚濁防止等を通じ、一層環境と調和のとれたものに転換していく方向が国際的にも主流化しています。また、一部のプランテーションにおける強制労働や児童労働といった環境に限らず労働者の人権への配慮等を求める声も高まりつつあります。

未活用のブロッコリーの茎を
チップスにした製品
資料:オイシックス・ラ・大地株式会社
このような中、持続可能な食料システムの構築のため、フードチェーンをつなぐ食品産業においても、持続可能な方法で生産された原材料を使用し、食品ロスを削減する取組を始めとして、環境や人権に配慮した持続可能な食品産業に転換することが求められています。
農林水産省では、食品産業の持続可能性の向上に向けて、国産原材料の利用促進、環境や人権に配慮した原材料調達等を支援することとしています。また、農林水産物を活用する新たなビジネス創出の仕組みの構築等により、地域の食品産業の関係者が連携して行う取組を支援することとしています。
(「食品産業の持続的な発展に向けた検討会」を開催)
農林水産省では、令和5(2023)年8月から、食料システムを構成する関係者が参加して議論し、将来にわたって持続可能な食料システムの実現に向けた具体的な食料施策を整理することを目的として、「食品産業の持続的な発展に向けた検討会」を開催しています。
同検討会では、食品産業の持続的な発展を図るため、環境や人権への配慮を始め、国際的なマーケットに向けた取組や世界の食市場の確保、新たな需要の開拓、原材料の安定調達、食品産業の生産性向上、食品産業の事業継続・労働力確保、食品分野の物流効率化等について検討することとしています。
(食品リサイクル法に基づく基本方針を改定)
農林水産省では環境省とともに、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、CO2排出量削減の観点から、「エネルギー利用の推進」や「焼却・埋立の削減」、「社員食堂等からの食品廃棄物削減」の重要性を明らかにするため、令和6(2024)年2月に食品リサイクル法(*1)に基づく基本方針の改定を行いました。
1 正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」
(農業・食品産業分野におけるプラスチックごみ問題への対応を推進)

プラスチック包材から紙包材に
パッケージを切り替えた製品
資料:味の素株式会社
近年、国内外でプラスチックの持続的な利用が課題となっている中、農業・食品産業分野においても、多くのプラスチック製品を活用していることから、積極的に対応していく必要があります。
農林水産省では、令和4(2022)年4月に施行されたプラスチック資源循環促進法(*1)等に基づき、農業・食品産業分野における各企業・団体の自主的な取組を促進するとともに、それらの取組の発信を通じて国民一人一人の意識を高めていくこととしています。
1 正式名称は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
(2)ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立
(食品製造業の労働生産性は前年度に比べ低下)
令和4(2022)年度における食品製造業の労働生産性は、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した人員が回復傾向にあることに加え、国際情勢の不安定化に伴う原材料費高騰等の影響を受けて付加価値額が同程度であったことから、前年度に比べ18万8千円/人低下し496万4千円/人となっています(図表2-4-1)。食品製造業の人手不足・人材不足が引き続き課題となる中、生産性の向上が急務となっています。
このため、農林水産省では経済産業省等と連携し、労働生産性の向上に資するAI、ロボット、IoT等の先端技術の研究開発、実証・改良から普及までを体系的に支援することとしています。
(持続可能性に配慮した輸入原材料調達を促進)
世界的なSDGsの取組が加速し、輸入原材料に係る持続可能な国際認証等が欧米の食品企業を中心に拡大する中で、食品企業が原材料を調達する際には、生産現場の環境・人権に配慮することが世界的に必要とされています。
国内においては、上場食品企業のうち「持続可能性に配慮した輸入原材料調達」に関する取組を実施している企業の割合は、令和4(2022)年は38.6%となっています。
食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料の調達については、売上の向上につながりにくく、コスト増加等の企業負担が増えるなどの課題が見られることから、農林水産省では、食品企業による人権尊重の取組を支援するための手引き作成のほか、セミナーの実施や優良事例の横展開の促進等による業界支援、消費者理解の促進を図っています。
(事例)パームやカカオ等の主原料のサステナブル調達を推進(大阪府)


パーム農園管理のための研修
資料:不二製油グループ本社株式会社

持続可能性に配慮した商品
資料:不二製油株式会社
大阪府大阪市(おおさかし)の不二製油(ふじせいゆ)グループ本社(ほんしゃ)株式会社は、重要課題の一つとして「サステナブル調達」を掲げ、「サプライヤー行動規範」の下、パームやカカオ等の主原料の生産地における環境負荷の低減と人権課題の解決に取り組んでいます。
同社では「責任あるパーム油調達方針」に基づき、購入・使用するパーム油の生産地域や調達ルートを特定するため、トレーサビリティの向上に取り組んでいます。令和元(2019)年度に、搾油工場までのトレーサビリティ100%を達成し、令和4(2022)年度には、農園までのトレーサビリティを93%まで確保しています。
また、マレーシアのグループ会社においては、専門家やNPO法人等と協働しながら、サプライチェーンの改善活動に取り組んでいます。平成29(2017)年には、サプライヤーである搾油工場や農園で働く200人以上の移民労働者にパスポートが返却され、300人の移民労働者が自らの理解できる言語で雇用契約書を締結するなどの成果が得られています。
さらに、平成30(2018)年には、サプライチェーン上の環境・人権問題を受け付け、改善するための仕組みとして「グリーバンス(苦情処理)メカニズム」の運用を開始しました。受け付けた苦情については、手順書に基づき対応し、直接サプライヤーに対するエンゲージメント(積極的働き掛け)を行うなど、問題の改善に取り組んでいます。
同社では、これらの取組のほか、インドネシアやマレーシアにおいて、ステークホルダーと協働して地域全体の持続可能性を改善していく活動への参画や、マレーシア・サバ州で、小規模農家の「RSPO(*)(持続可能なパーム油のための円卓会議)認証」の取得や環境再生型農業の導入を支援しています。今後とも持続可能性に配慮した製品の生産・開発に取り組むとともに、サプライチェーン上での環境・人権等の社会課題の解決を図るため、サプライヤーと相互に信頼を醸成しながら、環境保全、人権尊重、公正な事業慣行、リスクマネジメント等に取り組んでいくこととしています。
Roundtable on Sustainable Palm Oilの略
(3)食品ロスの削減の推進
(令和3(2021)年度の食品ロスの発生量は523万t)
我が国の食品ロスの発生量については、令和3(2021)年度は前年度に比べ1万t増加したものの、コロナ禍以前の令和元(2019)年度と比べると47万t減少し523万tと推計されています(図表2-4-2)。食品ロスの発生量を場所別に見ると、一般家庭における発生(家庭系食品ロス)は前年度に比べ3万t減少し244万tとなっています。一方、食品産業における発生(事業系食品ロス)は前年度に比べ4万t増加し279万tとなっています。その要因としては、コロナ禍における度重なる行動制限に伴う需要予測の精度の不足のほか、外食市場を中心に市場の縮小が続いていることが考えられます。
(事業系食品ロスの削減に向け、納品期限緩和等の商慣習の見直しを推進)
農林水産省では、コロナ禍から平時に移行する中、食品ロス量も増加に転じる可能性があるため、引き続き事業系食品ロスの削減に向けた取組を推進しています。
令和5(2023)年度においては、令和5(2023)年10月30日を「全国一斉商慣習見直しの日(*1)」と定め、食品小売事業者が賞味期間の3分の1を経過した商品の納品を受け付けない「3分の1ルール」の緩和や食品製造事業者における賞味期限表示の大括り化(年月表示、日まとめ表示)の取組を呼び掛けました。納品期限の緩和に取り組む事業者は、同年10月時点で297事業者に拡大しています。また、同年10月には、行政・食品業界・消費者で協調して食品ロス削減の取組を更に推進するため「食品廃棄物等の発生抑制に向けた取組の情報連絡会」を開催し、情報共有等を図りました。
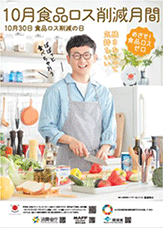
食品ロス削減月間を
呼び掛けるポスター
消費者への啓発については、食品ロス削減推進アンバサダーを起用した啓発ポスターの作成のほか、小売店舗が消費者に対して、商品棚の手前にある商品を選ぶ「てまえどり」を呼び掛ける取組を促進しています。「てまえどり」を行うことで、販売期限が過ぎて廃棄されることによる小売店での食品ロスを削減する効果が期待されます。
くわえて、食品の売れ残りや食べ残しのほか、食品の製造過程において発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品リサイクルの取組を促進しています。
1 令和元(2019)年10月に施行された「食品ロスの削減の推進に関する法律」において、10月が「食品ロス削減月間」、10月30日が「食品ロス削減の日」と定められている。
(賞味期限内食品のフードバンク等への寄附を推進)
食品ロス削減の取組を行った上で発生する賞味期限内食品については、フードバンクやこども食堂への寄附が進むよう企業とフードバンクとのマッチングやネットワークの構築を官民協働で推進し、経済的弱者支援にも貢献することを目指しています。
また、企業の様々な情報開示において、食品廃棄量の情報に加えてフードバンクへの寄附量の開示を促進することとしています。
さらに、国の災害用備蓄食品について、食品ロス削減や生活困窮者支援等の観点から有効に活用するため、農林水産省では「国の災害用備蓄食品の提供ポータルサイト」を設置し、更新により災害用備蓄食品としての役割を終えたものを、原則としてフードバンク団体等に提供しています。
(4)消費者の環境や持続可能性への理解醸成
(「商品購入時の環境、社会への配慮」に対する消費者意識は低調)
国際的にSDGs等の持続可能性について関心が高まっている中で、我が国においては、諸外国と比較して消費者の持続可能性に対する意識や行動が低調な状況にあります。日常生活の中で社会や環境に配慮してつくられた商品(フェアトレード、再生可能エネルギー使用、環境に優しい原材料等)を購入すると回答した消費者の割合は、我が国では7%であり、米国、英国、中国の2~3割と比較して低い水準となっています(図表2-4-3)。
一方で、サステナビリティ、フェアトレード、エシカル消費(*1)(倫理的消費)といった言葉の認知度については、令和5(2023)年度は令和元(2019)年度と比較して約2~4倍に高まってきています(図表2-4-4)。また、内閣府が令和5(2023)年9~10月に実施した世論調査によると、環境に配慮した生産手法で生産された農産物への価格許容度については、「価格が高くても購入する」としている人が6割以上になっています(図表2-4-5)。
将来にわたって持続可能なフードチェーンを維持していくためには、消費者が取り組むことができる行動や持続可能性に配慮した食料生産はコストを要することを事業者が正しく消費者に伝達することを通じ、消費者の理解を醸成しながら、行動変容を促していくことが必要となっています。
1 地域の活性化や雇用等も含む、人や社会、地域、環境に配慮した消費行動
(食と農林水産業のサステナビリティを考える取組を推進)
みどり戦略の実現に向け、農林水産省、消費者庁、環境省の連携により、企業・団体が一体となって持続可能な生産消費を促進する「あふの環(わ)2030プロジェクト~食と農林水産業のサステナビリティを考える~」を推進しており、令和6(2024)年3月末時点で農業者や食品製造事業者等191社・団体等が参画しています。
同プロジェクトでは、食と農林水産業のサステナビリティについて知ってもらうために「サステナウィーク2023」を開催し、「地球の未来のために何を選びますか?」をテーマに、環境に配慮した農産物の販売やその消費に資する情報の発信を集中的に行いました。また、サステナブルな取組についての動画作品を表彰する「サステナアワード2023」を実施したほか、消費者庁・農林水産省の共催で日経(にっけい)SDGsフォーラム特別(とくべつ)シンポジウムを開催するなど、持続可能な消費を推進しています。

あふの環2030プロジェクト
URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sustainable2030.html
(持続可能性の確保に向けた生産者の努力・工夫を「見える化」する取組を推進)
持続可能な食料システムを構築するためには、サプライチェーン全体で環境負荷低減を推進するとともに、その取組を可視化して持続可能な消費活動を促すことが必要です。
農林水産省では、生産者による環境負荷低減の努力を可視化するため、農産物の生産段階における温室効果ガス排出量を簡易に算定できる「農産物の温室効果ガス簡易算定シート」を作成しました。また、算定結果に基づき、地域の慣行栽培と比べて温室効果ガスの削減割合の度合いを星の数で表示する「見える化」の取組を推進しています。さらに、令和6(2024)年3月に、新たなラベルデザインを決定し、環境負荷低減の取組の「見える化」の本格運用を開始しました。同年3月末時点で、算定の対象は米や野菜等23品目に拡大しており、畜産物についても検討を進めています。くわえて、米については、生物多様性保全の取組についても温室効果ガス削減への貢献と合わせた表示を開始しました。
このほか、加工食品の温室効果ガス排出削減に関する取組が国内消費者の選択・行動変容につながるよう、カーボンフットプリント(CFP(*1))の算定に関する業界の自主算定ルールの方向性が提案されたことを受け、令和6(2024)年1月に、加工食品のカーボンフットプリントの算定実証を行いました。

「新しいラベルデザイン」を
公表する農林水産大臣
1 Carbon Footprint of Productの略で、製品・サービスのライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量のこと
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883