第2節 大規模自然災害からの復旧・復興
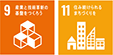
我が国は自然災害が発生しやすい環境下にあることから、発災そのものを抑制する「防災」、発生時の被害を小さくする「減災」、被災後速やかに同じ機能に戻す「復旧」、生活環境や経済を含め質的な向上等を目指す「復興」を効果的に連携させ、災害に対する国土の強靱(きょうじん)性を高めることで、食料の安定供給を確保していくことが重要です。
本節では、近年の大規模自然災害による被害の発生状況や災害からの復旧・復興に向けた取組について紹介します。
(1)近年の大規模自然災害からの復旧・復興の状況
(近年は地震や大雨等による被害が継続的に発生)
平成28(2016)年の熊本(くまもと)地震、平成30(2018)年の北海道胆振東部(ほっかいどういぶりとうぶ)地震、令和元(2019)年に立て続けに本州に上陸した台風を始めとして、近年は毎年のように日本各地で大規模な自然災害が発生しています。我が国の農林水産業では農作物や農地・農業用施設等に甚大な被害が発生しており、特に平成28(2016)年や平成30(2018)年、令和元(2019)年の自然災害による農林水産関係の被害額は、過去10年で最大級となりました(図表5-2-1)。
(「令和2年7月豪雨」、「令和3年8月の大雨」等からの復旧・復興を推進)
「令和2年7月豪雨」により被災した東北・東海・九州地方等の農地・農業用施設については、順次復旧工事が進み、令和6(2024)年3月末時点で、災害復旧事業の対象となる8,857件のうち約9割の8,316件で復旧が完了しました。また、被災した農業用機械や農業用ハウスについては復旧が全て完了しました。
「令和3年7月1日からの大雨」、「令和3年8月の大雨」により被災した農地・農業用施設については、令和6(2024)年3月末時点で、災害復旧事業の対象となる7,244件のうち約9割の6,698件で復旧が完了しました。
「令和4年8月3日からの大雨」、「令和4年台風第14号・第15号」等により被災した農地・農業用施設については、令和6(2024)年3月末時点で、災害復旧事業の対象となる4,582件のうち約8割の3,517件で復旧が完了しました(図表5-2-2)。
農林水産省は、引き続き、関係する都道府県や市町村と連携し、復旧工法に関する技術的支援等を行い、早期復旧を目指していくこととしています。

(事例)「平成29年7月九州北部豪雨」からの営農再開を後押し(福岡県)


果樹園の土砂撤去を行う
農業ボランティア
資料:筑前あさくら農業協同組合
福岡県朝倉市(あさくらし)の「筑前(ちくぜん)あさくら農業協同組合」(以下「JA筑前あさくら」という。)は、農業に特化したボランティアセンターを設置し、被災農地の営農再開を後押ししています。
同市では、平成29(2017)年7月に、停滞した梅雨前線に向かって暖かく非常に湿った空気が流れ込んだ影響等により、線状降水帯が形成・維持され、同じ場所に猛烈な雨を継続して降らせたことから、記録的な大雨となる「平成29年7月九州北部豪雨(きゅうしゅうほくぶごうう)」が発生し、人的被害や家屋等の被害のほか、農林業にも甚大な被害を受けました。
このような状況の中、JA筑前あさくらでは、同年11月から行政やNPO法人等と協力して「JA筑前あさくら農業ボランティアセンター」を開設し、一般ボランティアの協力による被災農家の営農再開に向けた支援活動を開始しました。
同センターでは、被災農家のニーズ把握やボランティアの派遣調整等を行い、令和2(2020)年8月末時点で延べ約5,400人の一般ボランティアが被災農地の土砂撤去等の復旧作業に協力しました。
また、JA筑前あさくらでは、令和5(2023)年7月の豪雨による被災時には、農協職員や行政機関職員等による農業ボランティアの派遣調整を行うなど、早期の営農再開に向けた復旧支援に取り組みました。
大災害からの復興は長期間を要し、継続的な活動が求められることから、JA筑前あさくらでは、引き続き関係機関と連携しながら、地域農業の振興を図っていくこととしています。
(コラム)「令和4年5月からの雹害」を乗り越え、地域農業の再生が進展
我が国は、その自然的、地形的条件から災害を極めて受けやすい状況にあり、降雨、洪水、暴風、地震等異常な自然現象により、全国各地で農地・農業用施設等の被害が見られています。そのような中、令和4(2022)年5~6月に発生した「令和4年5月からの雹(ひょう)害」については、東北・関東を中心に農作物等の被害が確認された一方で、降雹による被害を受けた農業者や食品事業者の中には、厳しい状況に直面しながらも、農業経営の立て直しや、地域農業の再生に向け、前向きな取組を展開している事例が見られています。
例えば埼玉県本庄市(ほんじょうし)の株式会社ファームサイドでは、ミニトマトの栽培ハウスの屋根に多数の大きな穴があき、張り替え工事が必要となったことから、クラウドファンディングを活用することで雹害からの復旧を図り、昔ながらの手法・技術と、最先端の技術・設備を融合させた新しい農業の実現に向けた取組を進めています。
また、群馬県高崎市(たかさきし)の梨生産農家で構成される里見梨(さとみなし)シードル研究会では、醸造企業と協力して降雹被害を受けて販売できなくなった梨を醸造酒の原料として活用することにより、地域特産の「和梨(わなし)のシードル」、「和梨のワイン」として深みと味わいのある商品を開発し、地域資源の有効活用や食品ロスの削減にも寄与する取組を進めています。
このような事例のように、被災した農林漁業者等が、困難を乗り越え、将来への希望と展望をもって農林水産業の早期の復興を図ることは、地域経済や生活基盤の復興に直結するだけでなく、国民に対する食料の安定供給を確保する上でも、極めて重要な意義を有しています。

雹害により多数の穴の開いたビニールハウス
資料:株式会社ファームサイド

降雹被害を受けた梨を利用した
和梨のシードルと和梨のワイン
資料:里見梨シードル研究会
(2)令和5(2023)年度における自然災害からの復旧
(令和5(2023)年は2,358億円の被害が発生)
令和5(2023)年においては、「令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号」や「令和5年6月29日からの大雨」、「令和5年7月15日からの大雨」、「令和5年台風第7号」等により、広範囲で河川の氾濫等による被害が発生し、これらの災害による農林水産関係の被害額は1,926億円となりました(図表5-2-3、図表5-2-4)。
このほか、大雪、大雨等による被害が発生したことから、令和5(2023)年に発生した主な自然災害による農林水産関係の被害額は2,358億円となりました。
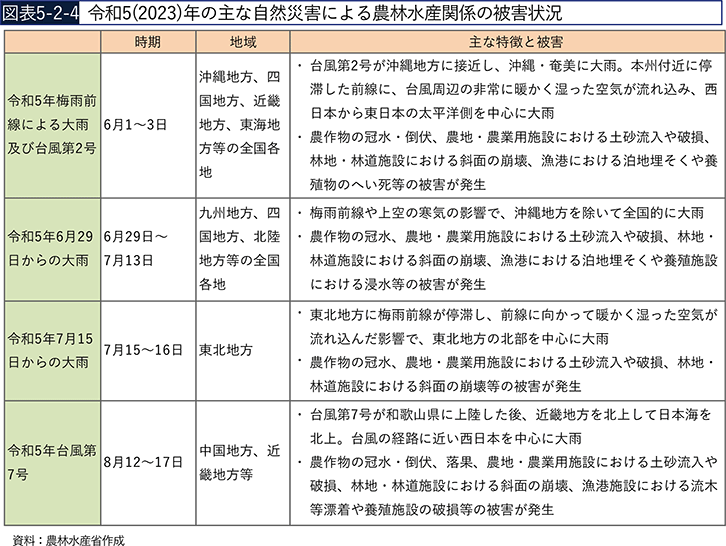

水田の土砂流入(鳥取県)
(令和5年台風第7号)

災害に関する情報(農林水産省)
URL:https://www.maff.go.jp/j/saigai/index.html
(激甚災害の指定により負担を軽減)
令和5(2023)年に発生した災害については、「令和5年5月5日の地震による災害」や「令和5年5月28日から7月20日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」、「令和5年8月12日から同月17日までの間の暴風雨による災害」、「令和5年9月4日から同月9日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」が激甚災害に指定されました(図表5-2-5)。これにより、被災した地方公共団体等は財政面での不安なく、迅速に復旧・復興に取り組むことが可能になりました。また、農地・農業用施設等の災害復旧事業について、地方公共団体、被災農業者等の負担が軽減されました。
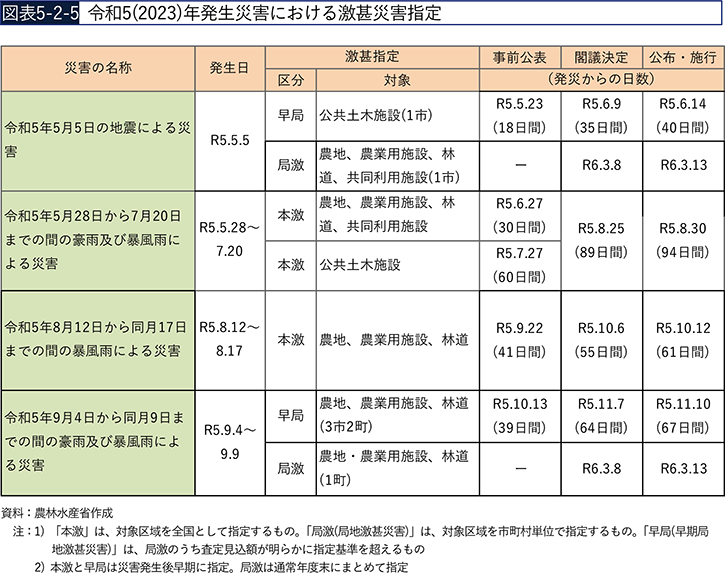
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883






