トピックス5 令和6年能登半島地震等への対応
令和6(2024)年1月に石川県能登(のと)地方で発生した地震は、石川県を中心に、人的被害のほか、農地・農業用施設や林地・林道施設、漁港等に大きな被害をもたらしました。その後、同年9月20日からの奥能登(おくのと)地域における豪雨(以下「奥能登豪雨」という。)が、同地域において更なる被害をもたらしました。
以下では、「令和6年能登半島(のとはんとう)地震(*1)」と奥能登豪雨による、被害の状況と復旧に向けた取組について紹介します。
*1 気象庁が定めた名称で、令和2(2020)年12月以降、能登地方周辺で発生している一連の地震活動のことを指す。
(令和6年能登半島地震により、石川県を中心に北陸各県等に大きな被害が発生)
令和6(2024)年1月に石川県能登地方で発生した最大震度7の地震による被害は、市街地ばかりでなく、農山漁村等にも広がり、石川県を始めとする北陸各県等の農林水産業にも甚大な被害をもたらしました(図表 トピ5-1)。
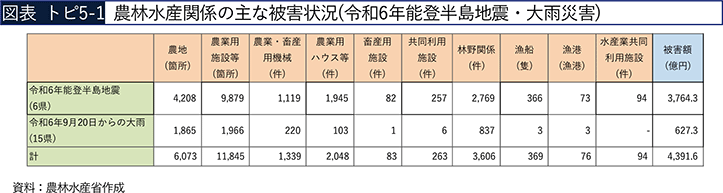
データ(エクセル:29KB)
被災した農地・農業用施設等は、多数、大規模かつ広範囲にわたり、くわえて、道路の寸断や積雪もあり、被害把握等に困難をきたしました。農林水産省は、発災直後から全国の地方農政局等から国の職員をMAFF(マフ)-SAT(サット)(農林水産省・サポート・アドバイスチーム)として現地に派遣し、被災した地方公共団体や関係団体等と連携し、農地・農業用施設等の被害状況の把握を迅速に行うとともに、できるだけ多くの農地で営農の再開がされるよう、応急復旧を全力で進めました。また、農村地域のライフラインである農業集落排水施設、営農飲雑用水施設についても、土地改良事業団体連合会等の関係団体の協力を得て、全国から派遣された技術者により点検・応急復旧が迅速に行われました。
さらに、政府は、発災直後から「食料・物資支援チーム」を設置し、被災地の要望を踏まえ、業界団体の協力の下、約514万点の飲食料、約1万8千kgの無洗米等を供給しました。食料支援に対するニーズの多様化を見越し、調達可能な品目のリストを被災各県に提示し、温かい状態で食べることができるレトルト食品、アレルギー対応食品、炊き出し用の無洗米、野菜ジュース等を発送しました。さらに、外食事業者の協力を得て、キッチンカーを活用した食事提供の取組を実施しました。
(「被災者の生活と生業支援のためのパッケージ」に基づく取組を推進)
政府は、緊急に取り組むべき施策について、令和6(2024)年1月に「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」(以下「支援パッケージ」という。)として取りまとめました。農林水産省でも、支援パッケージにおける農林水産関係の支援策に基づき、<1>農地、農業用施設、漁港等の生産インフラの復旧、<2>農業用機械、畜舎、漁船等の復旧、<3>金融支援や農業共済加入者への共済金の早期支払、収入保険に係る無利子のつなぎ融資等による各種支援を重層的に講ずることとしました。また、これらの支援策が被災地の農業者に活用されることを促進するため、国、県、農協が連携して設置した現地相談窓口(石川県下の農協等に6か所設置)において、農業者の個別の相談を受けつつ、事業申請手続の伴走支援を行ってきました。
(農林水産分野の生業再開が進展)
能登半島地震からの復旧・復興の状況として、農業については農地・農業用施設等の応急復旧等を進め、奥能登地域での令和6(2024)年の営農再開面積は令和5(2023)年の水稲作付面積の約8割となりました。林業については、被災した木材加工流通施設等について、再整備等の支援をしてきた結果、再開を望む60施設(石川県内)のうち49施設で営業を再開しました。また、漁業については、能登の北部地域の令和6(2024)年の漁獲金額は、前年同期比(1~12月)で約7割となっているほか、輪島(わじま)地区では、同年10月までに刺し網漁、底びき網漁が再開し、同年11月には、ずわいがに漁の操業開始となりました。
被災した農業用ダムや農業用水路等の国営造成施設(4地区)については、直轄災害復旧事業により復旧を進めており、うち、石川県内の3地区においては、農業用ダムや干拓堤防等の復旧に取り組み、富山県内の1地区においては、国、県、土地改良事業団体連合会等が協力し、被災した農業用水路等の被害調査や応急対策を迅速に行った結果、令和6(2024)年の田植えが例年通り行われました。
また、七尾市(ななおし)、輪島市(わじまし)等で甚大な被害を受けた農地海岸(1地区、7海岸)、農地地すべり(1地区)については、大規模災害復興法に基づく国の代行工事により、復旧に取り組んでおり、直轄代行工事等を推進するための現地拠点を同年4月に設置し、早期復旧に努めているところです。
(奥能登豪雨の発生と、地震・豪雨からの復旧・復興を一体的に推進)
奥能登地域においては、能登半島地震からの復旧・復興の途上で、奥能登地域において、令和6(2024)年9月の奥能登豪雨が発生し、河川の氾濫等により、約400haの農地で土砂・流木等が堆積するなど、甚大な被害がもたらされました。
農林水産省では、地震・豪雨からの一体的な復旧・復興を図る観点から、奥能登豪雨による被害についても、支援パッケージにおける農林水産関係の支援策と同様の支援を講ずることとしました。奥能登豪雨が収穫期であったことを踏まえ、浸水があった圃場(ほじょう)における農作物残さの処理等についても、支援を行っています。
また、奥能登地域の農業の復旧・復興に当たっては、地域の農業の将来の姿について、関係機関と地域の農業者が共通の認識をもって進めることが重要であるため、同年11月に「奥能登営農復旧・復興センター」を石川県穴水町(あなみずまち)の能登(のと)農業協同組合本店に、国、県、市町、農協が連携して設置しました。このセンターを拠点として、4者が一体となって、奥能登地域の各集落を巡回しながら、地域の担い手の参画も得つつ、農地等の復旧方針等について調整を進めています。地域での議論を受け、豪雨で被災した農地約400haのうち約170ha(約4割)が令和7(2025)年の作付けに間に合うよう、まずは、被害が小規模な農地を中心に復旧工事を行うこととし、調整を終えたところから、順次復旧工事を進めています。
さらに、土砂・流木・瓦礫(がれき)等が宅地・道路・農地等にまたがって堆積している場合には、市町が一括発注により、撤去を行い、その費用を事後的に事業間で精算することを可能とする農林水産省・国土交通省・環境省が連携した新たなスキームを構築し、迅速な復旧を支援しています。農林水産省では、地震の発災直後からこれまで、延べ約1万3千人以上の職員をMAFF-SATとして派遣しており、引き続き、県や市町、農協等と緊密に連携し、再び奥能登地域で営農したいという農業者の気持ちに寄り添い、地域の農業の将来を見据えた、地震と豪雨からの復旧・復興を一体的に推進するため、切れ目なく支援していきます。

農地の流木撤去の状況(輪島市)

流木撤去完了後の農地(輪島市)
(事例)地震・豪雨による災害からの棚田の復旧へ(石川県)
(1)棚田の保全活動を展開

石川県輪島市(わじまし)の公益財団法人白米千枚田景勝保存協議会(しろよねせんまいだけいしょうほぞんきょうぎかい)は、棚田オーナー制度を通じて、棚田を後世に残す活動に取り組んでおり、オーナー数は年々増加しています。また、白米千枚田を含む能登の伝統的な農村景観や農村文化等は、平成23(2011)年に我が国初の世界農業遺産に認定されました。
(2)令和6年能登半島地震による棚田の被害からの営農再開に向けた取組
令和6年能登半島地震では、棚田の田面の亀裂、畦畔法面(けいはんのりめん)の亀裂・崩落に加えて、用水路の一部が崩壊や目地の開き等により通水困難となるなど、大きな被害を受けました。

白米千枚田での田植えの様子
輪島市から復旧工事の委託を受けた石川県は、令和6(2024)年産の作付け再開を目指して、同協議会の会員である白米千枚田愛耕会(しろよねせんまいだあいこうかい)と連携し、昔ながらの工法で復旧作業を実施しました。同愛耕会は、同年5月に、損傷が軽微な棚田の一部で、棚田のオーナーや地元の高校生、ボランティア等とともに田植えを行い、同年9月には稲刈りにこぎ着けました。
(3)豪雨による被害からの営農再開に向けた取組
稲刈り後も引き続き棚田の復旧作業を進めようとしていた矢先、同年9月20日からの奥能登豪雨により、複数箇所で畦畔法面の崩落や用水路の損壊等が発生しました。
今後、同協議会は、同県及び同愛耕会と連携し、令和7(2025)年春の作付けに向けて、棚田や用水路等の復旧作業を行うこととしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




