トピックス4 農福連携の更なる推進
「農福連携」は、障害者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな担い手の確保にもつながる取組であり、農業分野での労働力の確保が喫緊の課題となる中で、地域の実情に応じた特徴のある取組も盛んになっています。改正基本法においても、基本的な施策として、障害者等の農業に関する活動の環境整備が新たに位置付けられました。
以下では、令和6(2024)年6月に決定された「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)」を中心に農福連携の推進に係る新たな動きを紹介します。
(農福連携に取り組む主体数は大きく増加)
「農福連携」は、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組です。農福連携に取り組む障害者就労施設の中には、認定農業者として地域農業の担い手となっているものや、農業生産に加えて農産物の加工・販売、レストランの運営等を行うものもあり、地域農業の維持や農村の活性化の観点から重要な取組となっています。また、障害者の賃金や工賃の引上げの観点からも農福連携への期待が高まっています。
令和5(2023)年度の調査によると、農福連携に取り組む主体数は、前年度に比べ836主体増加し7,179主体となりました(図表 トピ4-1)。令和元(2019)年度からの4年間で3,062主体増加し、令和元(2019)年6月に決定された「農福連携等推進ビジョン」の令和6(2024)年度までに新たに3千主体創出するという目標を1年前倒しで達成しました。
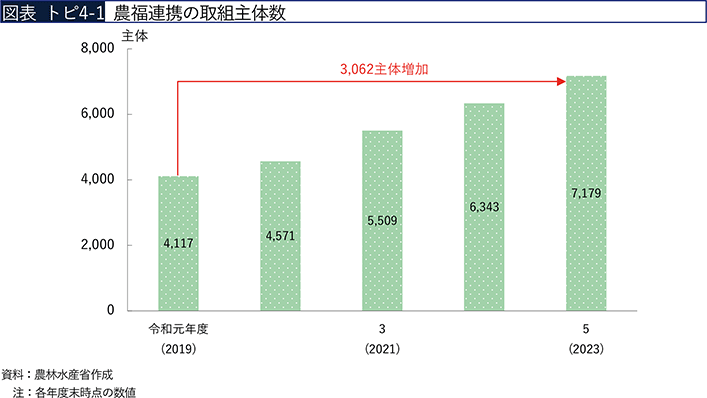
データ(エクセル:29KB)
(事例)農福連携の多角的な取組により、地域活性化に貢献(奈良県)
(1)障害者の成長や経済的自立に向け、農福連携を推進

奈良県奈良市(ならし)の社会福祉法人青葉仁会(あおはにかい)では、障害者が地域社会の中で自信と役割を持って生きていける仕組みを作るため、昭和60(1985)年に農福連携の取組を開始し、加工や販売も含めた多角的な事業に取り組んでいます。
(2)地域との関わりを持ちつつ、多角的に事業を展開

肥料散布作業
資料:社会福祉法人青葉仁会

干し芋のこん包作業
資料:社会福祉法人青葉仁会
同法人では、耕作放棄地となっていた約10.7haの農地で米やさつまいも、季節ごとの野菜、ブルーベリーやくり等の果樹を栽培しています。また、収穫時期にはブルーベリー園とさつまいも畑を観光農園として開放しており、障害者が運営にも携わることで、地域住民との交流が図られています。
さらに、生産された農産物は、同法人内の飲食店での提供に加え、障害者が主力として働く加工部門の事業所で給食の材料として活用するほか、ジャムや干し芋等に加工し、販売しています。さらに、廃校を活用した食品加工場では、生産した野菜を使用したレトルト食品や冷凍食品を製造しており、障害者が活躍する場の創出や工賃向上、地域の雇用拡大等に貢献しています。
このような取組を通じ、令和6(2024)年12月時点の同法人において農福連携の関連業務に携わる障害者は、平成30(2018)年から122人増加し428人となり、これまでに40人を超える障害者が一般就労に移行しています。
(3)障害者の活躍を通じて、地域の活性化を推進
同法人の活動は、地域において理解され、受け入れられており、農地を貸し出す農業者も増えていることから、今後は、耕作放棄地を活用した生産規模の拡大や収量の増加に取り組んでいく方針です。また、障害者が主体となったマルシェ、レストラン、農産物販売、農業体験等の場の提供を通じて、過疎化の進む地域の活性化とコミュニティの維持・発展にも貢献していくこととしています。
(新たな農福連携等推進ビジョンの決定)
令和6(2024)年6月には、「農福連携等推進会議」が5年ぶりに開催され、農福連携等を通じた地域共生社会の実現を目指して、「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)」(以下「新たなビジョン」という。)を決定しました。
新たなビジョンでは、「地域で広げる」「未来に広げる」「絆を広げる」を新たなスローガンに、市町村、農業や福祉の関係者等が参画する地域協議会の拡大を推進するとともに、ノウフクの日(11月29日)等による企業・消費者も巻き込んだ取組の意義や効果の理解促進、世代や障害の有無を超えた多様な者が農業体験を通じて社会参画を図るユニバーサル農園の普及・拡大等を推進することとしています。また、農業経営体等や障害者就労施設のみならず、高齢者施設、矯正施設、更生保護施設、特別支援学校、ユニバーサル農園等において、農福連携等に取り組む主体数を令和12(2030)年度末までに1万2千以上とし、地域協議会に参加する市町村数を200以上とする新たな目標を設定しました。今後、地域協議会が中心となり、地域内の農業と福祉の関係者のネットワークづくりや地域内の農福連携の取組のルールづくり、地域の営農の特性等を踏まえたマッチング等により、農福連携の取組を地域で広げていくことが期待されます(図表 トピ4-2)。

(農福連携等応援コンソーシアムによる普及・啓発を推進)
農林水産省では、厚生労働省等の関係省庁と連携して、国・地方公共団体、関係団体等のほか、経済界や消費者等の様々な関係者が参画する「農福連携等応援コンソーシアム」による取組の輪の拡大に取り組んでいます。
同コンソーシアムにおいては、令和2(2020)年度より毎年、「ノウフク・アワード」の選定による優良事例の表彰を行っており、令和7(2025)年1月には、農福連携等に取り組む団体、企業等の優良事例22団体を「ノウフク・アワード2024」において表彰しました(図表 トピ4-3)。これまでの5年間で延べ110団体(44都道府県)の優良事例を表彰し、各地に横展開すること等を通じて農福連携等の認知度の向上に努めています。同コンソーシアムに参画する団体・企業等の数は年々増加し、令和7(2025)年3月末時点で601となっており、今後は、同コンソーシアムの会員間の連携等により、農福連携等の商品の共同販売や現場の課題解決等に向けた取組が期待されます。
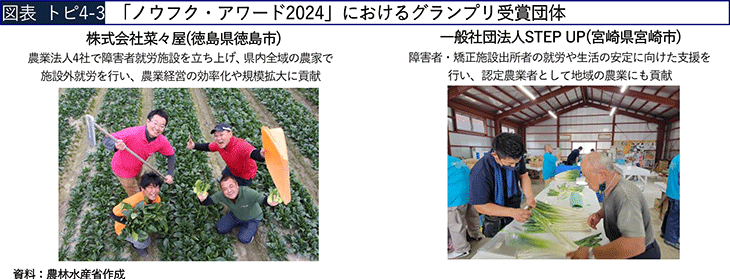
(ノウフクの日を制定)
農福連携等の取組が全国に広がり、各地で定着していくよう、新たなビジョンでは、11月29日を「ノウフクの日」とし、農福連携等の更なる展開や普及に取り組むこととされました。
初めてのノウフクの日となる令和6(2024)年11月29日には、内閣総理大臣官邸で「ノウフクの日」制定記念交流会が開催され、先進的な事業者や障害者との交流会が行われるなど、全国43か所でノウフクの日の関連イベントが開催されました。
これまでも、農福連携の認知度向上に向け、47都道府県が参画する「農福連携全国都道府県ネットワーク」による農福連携マルシェの開催、食品企業等を対象としたノウフクJAS(*1)商品等の商談会を始めとする各界が連携した取組を行ってきたところであり、ノウフクの日の制定を契機として、今後も消費者や企業を巻き込みながら、国民的運動として農福連携等を推進していくことが重要となっています。

「ノウフクの日」制定記念交流会

「ノウフクの日」の周知ポスター
*1 正式名称は「障害者が生産行程に携わった食品及び観賞用の植物の日本農林規格」
(農福連携の裾野を広げ、地域共生社会を実現)
農福連携が普及していく中で、農福連携の取組の裾野も広がっており、ノウフク・アワードの受賞団体では、農業者や障害者就労施設に加えて、企業、地方公共団体、農協、特別支援学校等の様々な主体が見られます。また、障害者の丁寧な手作業を活かして、有機農業や高品質な商品の製造を行うなど、農業の高付加価値化を実現している事例や、地域の商工業や観光業等との連携や地域の未利用資源の活用等により、農福連携を中心とした地域づくりに取り組む事例も見られます。

さらに、障害者のみならず、高齢者、生活困窮者、ひきこもりの状態にある者等の就労・社会参画支援、犯罪をした者等の立ち直り支援等にも対象が広がっています。世代や障害の有無を超えた多様な者が農業体験を通じて社会参画を図る「ユニバーサル農園」において、健康増進や生きがいづくり、働きづらさや生きづらさを感じている者への職業訓練、生涯にわたる学びの場としての活用等の取組も見られるようになっており、このような取組を通じた農地の利用の維持・拡大効果も期待されます(図表 トピ4-4)。
新たなビジョンに掲げられた取組を官民を挙げて実践することにより、我が国の食や地域を支える農業の発展や障害者等の一層の社会参画等が促進されるとともに、多様な分野に取組の幅が広がり、全ての人々がその生きる力や可能性を最大限に発揮できる地域共生社会の実現につながっていくことが期待されます。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




