第1節 世界の食料需給の動向
世界の食料需給は、途上国を中心とした世界人口の急増による食料需要の増加、気候変動による異常気象の頻発化、地政学的リスクの高まり等により不安定化しています。また、食料の国際価格は、新興国の経済発展による需要の増大やエネルギー向け需要の拡大、地球規模の気候変動の影響等により、上昇と下落を繰り返しています。
本節では、国際的な食料需給や食料価格の動向等について紹介します。
(1)国際的な食料需給の動向
(2024/25年度における穀物の生産量、消費量は前年度に比べ増加)
令和7(2025)年3月に米国農務省が発表した資料によると、2024/25年度における世界の穀物消費量は、途上国の人口増加、所得水準の向上等に伴い、前年度に比べ4.3千万t(1.5%)増加し28億6千万tとなる見込みです(図表1-1-1)。
また、生産量は、主に単収の伸びにより消費量の増加に対応しており、2024/25年度は前年度に比べ0.8千万t(0.3%)増加し28億3千万tとなる見込みです。
2024/25年度の期末在庫率は、前年度に比べ1.7ポイント低下し26.5%となる見込みです。FAO(*1)(国際連合食糧農業機関)が安全在庫水準としている17~18%を上回っていますが、中国を除いた場合の期末在庫率は12.0%にとどまっており、世界的な不作が発生した場合には、食料不足や価格高騰が起こりやすい状況にあります。

データ(エクセル:34KB)
2024/25年度における世界の穀物等の生産量を品目別に見ると、小麦は前年度からEU及びロシアの収穫面積及び単収の減少等があるものの、豪州等の収穫面積及び単収の増加等により、前年度に比べ0.8%増加し8億tとなる見込みです(図表1-1-2)。
とうもろこしは、ブラジルや中国の収穫面積及び単収の増加等があるものの、ウクライナの収穫面積及び単収の減少や米国の収穫面積の減少等により、前年度に比べ1.1%減少し12億1千万tとなる見込みです。
米は、インドの収穫面積及び単収の増加等により、前年度に比べ2.0%増加し5億3千万tとなる見込みです。
大豆は、ブラジルや米国の収穫面積及び単収の増加等により、前年度に比べ6.5%増加し4億2千万tとなる見込みです。
期末在庫率については、小麦、とうもろこし、米は前年度に比べ低下する一方、大豆は前年度に比べ上昇する見込みです。

データ(エクセル:29KB)

データ(エクセル:23KB)
また、2023/24年度における世界の穀物等の期末在庫に占める中国の割合を見ると、とうもろこし67.3%、米57.4%、小麦49.9%、大豆38.5%となっており、突出して高い水準となっています(図表1-1-3)。
*1 Food and Agriculture Organization of the United Nationsの略
(世界経済の鈍化等により、中期的には穀物等の需要の伸びは鈍化の見込み)
世界経済は、中期的には、中国の成長の鈍化や人口減少が見込まれる一方、インド等の新興国・途上国において相対的に高い経済成長率が維持されると見られています。将来的に先進国だけでなく途上国の多くの国で、経済成長はコロナ禍以前より鈍化すると見られ、世界経済はこれまでより緩やかな成長となる見込みです。
このような中、令和14(2032)年における世界の穀物等の需給について、需要面においては、途上国の総人口の増加、新興国・途上国を中心とした相対的に高い所得水準の向上等に伴って食用・飼料用需要の増加が中期的に続くものの、先進国だけでなく新興国・途上国においても今後の経済成長の弱含みを反映して、穀物等の需要の伸びは鈍化してコロナ禍以前より緩やかとなる見通しとなっています。供給面では、今後、全ての穀物の収穫面積が僅かに減少する一方、穀物等の生産量は、主に生産性の上昇によって増加する見通し(*1)となっています。
世界の食料需給は、農業生産が地域や年ごとに異なる自然条件の影響を強く受け、生産量が変動しやすいこと、世界全体の生産量に比べ貿易量が少なく輸出国の動向に影響受けやすいこと等から、不安定な要素を有しています。
また、気候変動や大規模自然災害、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病、感染症の流行、ロシアによるウクライナ侵略といった多様化するリスクを踏まえると、食料の安定供給の確保に万全を期す必要があります。
*1 農林水産政策研究所「2032年における世界の食料需給見通し」(令和5(2023)年3月公表)
(コラム)令和42(2060)年にかけての世界の超長期食料需給の見通し
農林水産省では、国立研究開発法人国際農林水産業研究(こくさいのうりんすいさんぎょうけんきゅう)センター(以下「国際農研」という。)と農研機構等と連携し、食料関係の予測モデルを用いた世界の超長期食料需給予測を公表しました。このモデルでは、平成23(2011)~令和2(2020)年の平均である基準年から令和33(2051)~令和42(2060)年の平均である予測年にかけ、世界の人口は74億人から95億人へと1.3倍に、世界の1人当たり実質GDPは0.6万ドルから1.7万ドルへと2.8倍に増加し、いずれの主要作物・畜産物についても、実質価格は長期的に上昇する可能性が示されました。
また、世界の農地面積は、基準年では9.8億haとなっていますが、世界の平均気温が1.7℃、2.0℃、2.4℃上昇するシナリオ(*)を採用した場合は、予測年にかけ、1.7℃上昇するシナリオでは0.6億ha減少、2.0℃、2.4℃上昇するシナリオでは1億~1.4億ha増加し、さらに、世界の農地面積を上限として求められる収穫面積は、基準年から予測年にかけて1.0~1.5倍、単収は気候変動や技術進歩等の影響を受け1.0~1.3倍となる可能性が示されました。
くわえて、人口増加と経済発展による需要の増加に対応して、世界の小麦、米、とうもろこし、大豆の生産量は、予測年には基準年に比べ1.4倍、牛肉、豚肉、鶏肉の生産量は1.5倍に増加となる可能性が示されました。
* シナリオとは、全球平均の嘉永3(1850)~明治33(1900)年平均気温に対する、令和23(2041)~令和42(2060)年平均気温の1.7℃、2.0℃、2.4℃の上昇をもたらす気候変数を用いてシミュレーションを行い、気候変動が食料需給に与える影響を捉えたもの。
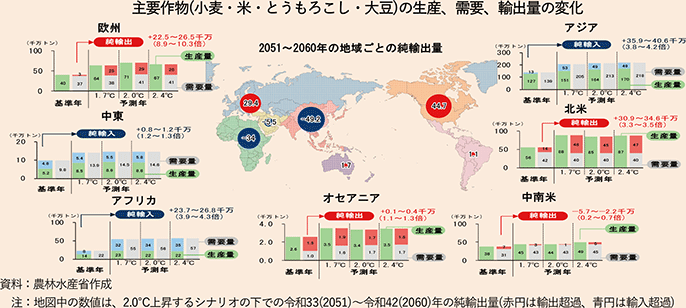
(世界の食料貿易フローは大きく変化)

食料需給見通し
(農林水産政策研究所)
URL:https://www.maff.go.jp/primaff/
seika/jyukyu.html
世界の食料貿易の状況は、この20年で大きく変化しました。約20年前は、我が国は小麦及びとうもろこしの世界有数の輸入国でしたが、特にアジア地域では人口増や経済成長に伴い食料の輸入量が増加しており、主要輸出国における輸出先が多角化していることがうかがわれます(図表1-1-4)。
輸入量に占める我が国のシェアは低下しており、平成14(2002)年度(前後3か年度平均)と令和3(2021)年度(同平均)を比較すると、小麦は6%から3%へ、とうもろこしは22%から9%へ、大豆は9%から2%へとそれぞれ低下しました。これとともに、中国の輸入量の増加は顕著であり、輸入量に占めるシェアは、小麦は4%、とうもろこしは11%、大豆は59%へと上昇しました。

(フォーカス)世界の穀物等調達は約20年で変化
食料貿易の状況を見ると、中国のほか、インドネシア、ベトナム、メキシコ等も今後輸入国としての地位が高まる可能性があります(図表1-1-4)。これらの3か国は人口増加率及び経済成長率の両方で我が国を上回っており、小麦、とうもろこし、大豆の生産量と輸入量を2001/02年度と2023/24年度で我が国と比較しました。
まず、小麦については、インドネシアの2023/24年度における輸入量は我が国の約2.4倍となっています。同国の小麦の輸入量は2001/02年度と比べ約3.5倍に増加しており、さらに、我が国の主要な調達先である豪州からも輸入しています。また、メキシコについては、小麦を国内で生産しているものの、2023/24年度の輸入量は我が国とほぼ同水準であり、かつ、隣国であって経済的な関係も深い米国から輸入しています。ベトナムについては国内生産を行っておらず、2023/24年度の輸入量では我が国とほぼ同水準であり、我が国の主要な調達先である豪州から輸入しています。
次に、とうもろこしについては、2023/24年度に生産量と輸入量の合計が我が国を上回っているのはメキシコで、その輸入量は2001/02年度に比べ約6.1倍に増加しています。ベトナムは、2023/24年度は我が国を下回っており、国内生産量は約2倍に増加しているものの、輸入量は約85倍に増加しています。
そして、大豆については、2023/24年度のメキシコにおける生産量と輸入量の合計は我が国を上回り、その輸入量は我が国の輸入量の約2.1倍に相当し、かつ、我が国の重要な調達先である米国から輸入しています。
このように穀物等に係る世界の調達状況は過去20年間で大きく変化してきました。今後、引き続き動向を注視するとともに、我が国は穀物等の調達先である貿易パートナーとの友好な関係の継続に努め、我が国内においても生産性の向上を図り、これら穀物等の生産を増加させることが必要と考えられます。
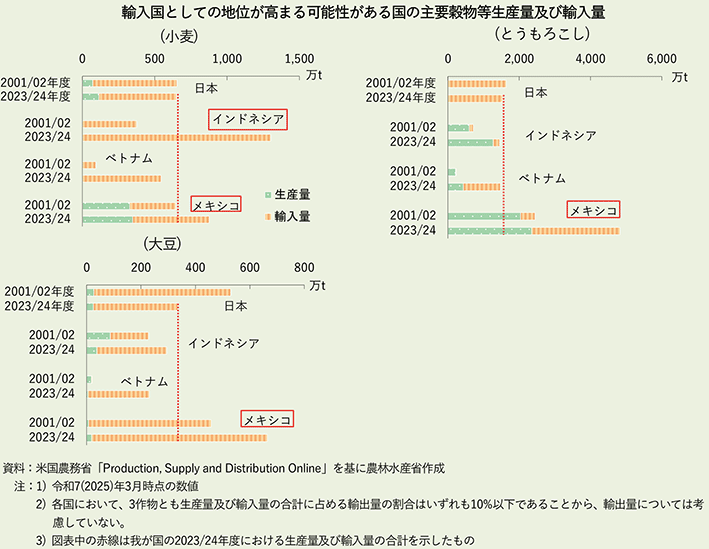
データ(エクセル:28KB)
(世界の穀物等の生産量・輸出量のシェア)
米国農務省では2024/25年度における世界の穀物等の生産量、輸出量の見込みを示しています。小麦の主要生産国は、中国、EU、インド、ロシア、米国で、世界全体の64%のシェアを占めています(図表1-1-5)。約20年前の伝統的な輸出国は米国、カナダでしたが、2024/25年度の上位輸出国は、ロシア、EU、豪州、カナダ、米国、ウクライナであり、ロシアやウクライナのシェアが高まっています。
とうもろこしの主要生産国は、米国、中国、ブラジル、EU、アルゼンチンで世界全体の75%のシェアを占めています。他方、上位輸出国は米国、ブラジル、アルゼンチン、ウクライナ、パラグアイ、ロシアです。輸出量に占めるブラジルやウクライナのシェアの伸びが顕著であり、また、パラグアイとロシアの輸出量はほぼ同水準となっています。
大豆の主要生産国は、ブラジル、米国、アルゼンチン、中国、インドであり、世界全体の88%を占めています。上位輸出国は、ブラジル、米国、パラグアイ、カナダ、アルゼンチンであり、ブラジルのシェアが高まっています。
我が国において、小麦は主に米国、カナダ、豪州から、とうもろこしは主に米国、ブラジルから、大豆は主に米国、ブラジル、カナダから輸入しています。

データ(エクセル:26KB)
(世界の輸送の状況)
食料輸送の際の安全確保は、食料安全保障上、非常に重要です。海運による物資の輸送に関して、世界各地にはチョークポイントと呼ばれる運河や海峡等の海運の要衝が存在します。このチョークポイントのうち、パナマ運河では、令和5(2023)年11月から降雨不足に伴う通航制限が実施されていましたが、雨季の到来による水位の回復を受け順次通航制限を緩和し、令和6(2024)年9月には通航制限前の状態まで回復しました。一方、スエズ運河では、令和5(2023)年12月中旬から中東での戦闘が継続する中、スエズ運河経由で地中海とインド洋を結ぶ紅海を巡行する商船が攻撃されるといった影響があることから、依然として通航が回避されています。
我が国の港湾の位置付けを見るために、世界の主要港におけるコンテナ取扱量の推移を見ると、昭和55(1980)年には我が国の3港が20位以内に入っていました。東京港の取扱量は、昭和55(1980)年に比べ、平成13(2001)年には約4.4倍、令和5(2023)年には約7.2倍に増加しましたが、令和5(2023)年時点で世界では46位にとどまっています(図表1-1-6)。世界の他港での取扱量が大幅に増加しており、相対的に我が国の位置付けが低下しています。世界でコンテナ取扱量が多い港湾は、上海・シンガポールといったアジア地域のハブ港湾で、特に中国港湾が上位10港のうち7港を占めています。
(海外農業の持続可能性)
世界の農業・土地利用等由来の温室効果ガス(GHG)排出量については、令和元(2019)年は排出量全体の22%を占めており、また、世界の水使用量の約70%は農業用水であること等から、気候変動や生物多様性へ大きな影響を与えており、温室効果ガスの排出削減や土壌・水資源の保全や適切な利用等が求められています(図表1-1-7)。
また、持続可能な食料生産のためには、地球環境の保全に加え、強制労働や児童労働といった人権への配慮等の持続的な社会・経済の形成への取組も重要です。国際的には、例えばEUでは令和2(2020)年5月に持続可能な食料システムへの包括的なアプローチを示した「Farm to Fork(農場から食卓まで)戦略」を公表し、令和12(2030)年を目標年とする具体的な数値目標が設定されているほか、二国間貿易協定にサステナブル条項を入れるなど、国際交渉を通じたEUのフードシステムをグローバル・スタンダードにしようという動きが見られます。
くわえて、ビジネスにおいても持続可能性を確保する取組が企業評価やサステナブルファイナンス(*1)における重要な判断基準となりつつあります。

*1 新たな産業・社会構造への転換を促し、持続可能な社会を実現するための金融
(コラム)児童労働に従事する子供の数が平成12(2000)年以降初の増加
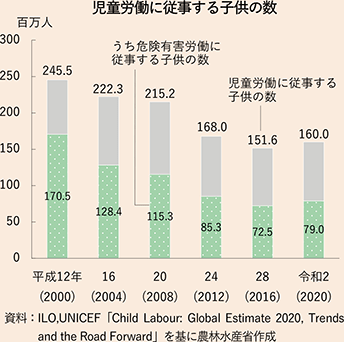
データ(エクセル:27KB)
児童労働は、子供を肉体的・精神的に搾取することであり、また、教育の機会を奪い、子供の身体的・知的・社会的・道徳的発達を阻害すると同時に、その子供の次の世代にも悪影響を及ぼし、貧富の差を拡大させ、その国の発展を阻害します。
令和3(2021)年にILO(*1)(国際労働機関)とUNICEF(*2) (国連児童基金)が公表した報告書によると、令和2(2020)年の児童労働に従事する子供の数は4年前より840万人増加し、世界全体で推定1億6千万人となりました。また、そのうちの5歳から17歳の子供の約7割が農業部門で働いています。米国労働省によると、さとうきび、コーヒー、畜産物、米、魚介類、カカオを中心とした農林水産物が児童労働を伴って生産されているとしています(*3)。
児童労働に従事する子供の数は、平成12(2000)年以降減少傾向にあり、平成28(2016)年までに9,390万人減少していましたが、令和2(2020)年に初めて増加に転じました。児童労働の原因には、貧困、差別、慣習、武力紛争、自然災害、教育機会の欠如等の様々なものがあり、新型コロナウイルス感染症によって収入が減ったことや学校が閉鎖されたことにより更に増加しました。
児童労働は食品の原材料となる農産物を生産する開発途上国等で多く発生しています。我が国においてもサプライチェーンや取引先で児童労働が発生していないかモニタリング等を行い、人権への負の影響を特定し防止・軽減する、人権デュー・ディリジェンスの実施が求められており、政府が公表した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」に沿って取組を促進させることが求められています。
*1 International Labour Organizationの略
*2 United Nations Children's Fundの略
*3 米国労働省「List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor」(参考文献一覧を参照)
(2)国際的な食料価格の動向
(穀物等の国際価格は、おおむねロシアによるウクライナ侵略前の水準まで低下)
穀物等の国際価格は、新興国の畜産物消費の増加等を背景とした需要やバイオ燃料等のエネルギー向け需要の増大、地球規模の気候変動の影響等のほか、令和4(2022)年のロシアによるウクライナ侵略が重なったこともあり、上昇傾向で推移していましたが、その後おおむねロシアによるウクライナ侵略前の水準まで低下しました。
小麦の国際価格は、ロシアによるウクライナ侵略等により、令和4(2022)年3月に過去最高値を更新し、523.7ドル/tとなったものの、ウクライナからの臨時回廊による輸出再開等により、おおむねロシアによるウクライナ侵略前の水準まで低下しています(図表1-1-8)。また、とうもろこし、大豆の国際価格についても、ロシアによるウクライナ侵略時に高騰したものの、令和7(2025)年3月時点では、ブラジル等における豊作等により、おおむねロシアによるウクライナ侵略前の水準まで低下しています。

(食料価格指数は安定しているものの、植物油と乳製品は上昇傾向)
FAOが公表している食料価格指数(*1)については、食料品全体で見ると令和4(2022)年3月に160.2をピークに下落しており、令和6(2024)年も120前後で安定して推移しています(図表1-1-9)。
品目別では、植物油は世界的な需給逼迫(ひっぱく)を受け、令和6(2024)年11月に164.1と前年同月比で32.2%上昇しました。また、乳製品は若干上昇傾向にありますが、穀物や肉類といったその他の品目はほぼ横ばいで推移しています。

データ(エクセル:35KB)
*1 国際市場における五つの主要食料(穀物、肉類、乳製品、植物油及び砂糖)の国際価格から計算される世界の食料価格の指標
(世界のバイオ燃料用農産物の需要は増加の見通し)
近年、米国、EU等の国・地域において、化石燃料への依存の改善や温室効果ガス排出量の削減、農業・農村開発等の目的から、バイオ燃料の導入・普及が進展しており、とうもろこしやさとうきび、大豆等のバイオ燃料用に供される農産物の需要が増大しています。
令和6(2024)年7月にOECD(*1)(経済協力開発機構)及びFAOが公表した予測によると、令和5(2023)年から令和15(2033)年までに、バイオエタノールの消費量は1億3,161万kLから1億5,427万kLへ、バイオディーゼルの消費量は6,586万kLから7,853万kLへとそれぞれ増加する見通しとなっています(図表1-1-10)。

データ(エクセル:31KB)
*1 Organisation for Economic Co-operation and Developmentの略
(とうもろこしは買越しに転換、大豆もやや買越しへ)
商品先物取引とは、農林水産物や鉱物、電力等の一定の商品を、将来の一定期日に売買することを約束し、その価格を現時点で決める取引です。商品先物市場では、明確に定められたルールに基づいて取引が成立し、成立した価格が直ちに公表されるため、透明性の高い価格形成が行われます。形成された価格は将来の価格の方向性を示すため、計画的な生産及び流通に利用できる価格発見機能を担っています。また、価格変動を伴う商品を扱う事業者等は、商品先物取引を活用することにより、価格変動のリスクを回避でき、産業インフラとしての重要な経済的機能も担っています。
一方、穀物や原油等の商品市場の規模は、株式市場や債券市場と比較して極めて小さく、まとまった金額の買いによって相場が上がりやすいという特徴を有しています。
有利な投資先を求める投機資金の穀物市場への流入は、令和2(2020)年後半以降、需給が引き締まり価格上昇が見込まれてからより一層顕著になり、投機筋の買越枚数(*1)については、とうもろこしでは令和3(2021)年1月に53万5千枚となり、小麦や大豆でも高水準となりました(図表1-1-11)。その後、小麦は令和4(2022)年8月以降は売越しの状況となっています。とうもろこしは令和5(2023)年8月以降は売越しの状況でしたが、令和6(2024)年10月以降買越しとなりました。大豆は令和6(2024)年1月以降は売越しですが、令和7(2025)年1月及び2月は買越しとなりました。
巨額の運用資金を有するヘッジファンド等からの投機資金の穀物市場への流入は商品価格が大きく変動するリスクとなり得ることから、引き続き注視していく必要があります。

*1 1枚は5,000ブッシェル。1ブッシェルは小麦、大豆においては約27.2kg、とうもろこしにおいては約25.4kg
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883





