第2節 我が国における食料の供給
我が国において農業者の急速な減少や高齢化が見込まれる中、食料安全保障を確保し、農業の持続的な発展を図るためには、人・農地等の資源をフル活用し、食料自給力を確保することが必要であり、この旨が新たな基本計画において盛り込まれました。こうしたことから農地の確保(*1)、サスティナブルな農業構造の構築(*2)や、生産性の向上(*3)を図っていくことが必要です。本節では、我が国における食料供給の状況、農業生産の動向等に加え、食料自給率について紹介します。
(1)我が国における食料供給の状況
(国産と輸入先上位4か国による食料供給の割合は約8割)

データ(エクセル:26KB)
我が国の食料供給は、国産と輸入先上位4か国(米国、豪州、カナダ、ブラジル)で、供給熱量の約8割を占めています(図表1-2-1)。今後の食料供給の安定性を維持していくためには、国内の農業生産の増大を図るとともに、主要輸入先国との安定的な関係を維持していくことも必要となっています。
*1 第2章第2節で記載
*2 第2章第3節で記載
*3 第2章第4節で記載
(食料安全保障の確保に向けた構造転換対策を推進)
農林水産物・食品の過度な輸入依存は、原産国の不作等による穀物価格の急騰のほか、化学肥料の原料産出国の輸出規制による調達量の減少が生じた場合等には、思うような条件での輸入が困難となること等から、平時でも食料の安定供給を脅かすリスクを高めることとなります。
このため、食料安全保障の確保に向けた国民に対する食料の安定的な供給については、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと併せて安定的な輸入や備蓄の確保を図ることが必要です。
また、農地、人や生産資材等の資源を確保し、それらと、農業生産基盤の整備・保全、先端的技術の開発・普及が効率的に組み合わされた農業構造へ転換し、土地生産性及び労働生産性を向上させることにより、食料自給力を確保することとしています。この農業の生産性向上と農産物の付加価値向上を通じ、農業経営の収益力を高め、農業者の所得の確保・向上を図ることにより、農業の持続的発展を図っていく必要があります。
(2)食料自給率の動向
(供給熱量ベースの総合食料自給率は38%、生産額ベースの総合食料自給率は61%)
食料自給率は、国内の食料消費が国内生産によってどれくらい賄えているかを示す指標です。新たな基本計画においては、総合食料自給率の目標は、令和12(2030)年度を目標年度として、供給熱量ベースで45%、生産額ベースで69%とし、また、摂取熱量ベースの食料自給率の目標は、53%としています。
供給熱量ベースの総合食料自給率は、生命と健康の維持に不可欠な基礎的栄養価であるエネルギー(カロリー)に着目したものであり、消費者が自らの食料消費に当てはめてイメージを持つことができるなどの特徴があります。
令和5(2023)年度の供給熱量ベースの総合食料自給率は、小麦の生産量増加や油脂類の消費量減少がプラス要因となる一方、てんさいの糖度低下による国産原料の製糖量の減少がマイナス要因となり、前年度並みの38%となりました(図表1-2-2)。

データ(エクセル:41KB)
一方、生産額ベースの総合食料自給率は、食料の経済的価値に着目したものであり、畜産物、野菜、果実等のエネルギーが比較的少ないものの高い付加価値を有する品目の生産活動をより適切に反映させることができます。令和5(2023)年度の生産額ベースの総合食料自給率は、輸入された食料の量は前年度と同程度でしたが、国際的な穀物価格や農業生産資材価格の水準が前年度と比較して落ち着いたこと等を背景として、前年度に比べ輸入総額が減少したことにより、前年度に比べ3ポイント上昇し61%となりました。
供給熱量ベースの総合食料自給率は長期的には低下傾向にあり、平成10(1998)年度に40%まで低下し、近年はおおむね40%程度で推移しています。長期的に食料自給率が低下してきた主な要因としては、米の消費が減少する一方、畜産物や油脂類の消費が増大するなどの食生活の変化が考えられます(図表1-2-3)。畜産物は、その消費拡大に伴い輸入の割合が増加するとともに、飼料の海外への依存度が高まっている状況です。

また、品目ごとの消費・生産について、供給熱量ベースの総合食料自給率の影響を見ると、輸入に依存している小麦や大豆の国内生産の拡大が総合食料自給率を押し上げる方向に作用する一方、食料自給率の高い米等の消費量が減少したこと等が総合食料自給率を引き下げる方向に作用しています(図表1-2-4)。今後、食料安全保障の確保のため、輸入依存度の高い麦・大豆等の国内の農業生産の増大を図ることが重要です。

データ(エクセル:29KB)
(コラム)英国政府が新たな「英国食料安全保障指数」を公表
英国政府は令和6(2024)年2月に、英国の食料安全保障の状況を評価するため、新たな食料安全保障指数を導入することを発表しました。
この指数は、英国政府が3年ごとに公表している「英国食料安全保障報告書」を補完するように設計されており、<1>主要な食料安全保障テーマの広範な傾向を反映すること、<2>毎年変化する興味深い短期的なトレンドを捉えること、<3>公的統計の基準を満たしており英国全土の毎年更新されるデータによるものであること、を満たすものとして、下図の九つの指標が示されました。
このように食料安全保障は単一の指標やテーマに置き換えられるのではなく、様々な相互作用する要因によって形成されています。同年7月に公表された総合評価によると、英国の食料安全保障は全体的におおむね安定した状況であると評価されています。
また、英国エコノミスト誌の調査部門であるエコノミスト・インパクトが令和4(2022)年に公表した「Global Food Security Index 2022(*)」によると、我が国は、調査対象の113か国の中で6位となり前年の8位から順位を上げました。同調査は食料安全保障を国内生産だけではなく、「システム」として位置付け、各国の状況を「手頃な価格」「入手のしやすさ」「品質と安全性」「持続可能性・適応」の4項目で数値化し、100点満点で評価するもので、平成24(2012)年から公表されており、我が国は「手頃な価格」と「入手のしやすさ」の項目で高く評価されています。
* 参考文献一覧を参照
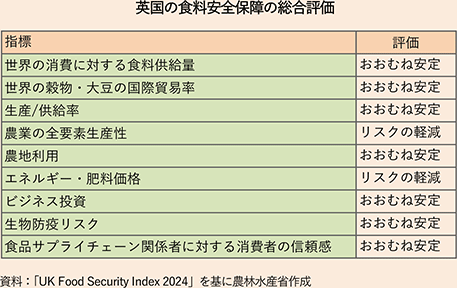
(3)米の生産動向
(主食用米の生産量は前年産に比べ増加)
令和6(2024)年産の主食用米の生産量(*1)は、北日本・東日本を中心に飼料用米からの転換により作付面積が増加したこと、全国的におおむね天候に恵まれたこと等から、前年産に比べ2.8%増加し679万2千tとなりました(図表1-2-5)。

データ(エクセル:28KB)
*1 農林水産省「作物統計」における主食用米の収穫量の数値
(米粉用米の生産量は前年度に比べ減少)

データ(エクセル:26KB)
令和5(2023)年度の米粉用米の生産量は、前年度に比べ12.2%減少し4万tとなりました(図表1-2-6)。一方、需要量は、グルテンフリーの食スタイルといった健康志向の高まり等を背景として、前年度に比べ17.8%増加し5万3千tとなりました。

広がる!米粉の世界
URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/
(飼料用米の作付面積は前年産に比べ減少)

データ(エクセル:26KB)
令和5(2023)年産の飼料用米の作付面積は、前年産に比べ5.7%減少し13万4千haとなりました(図表1-2-7)。また、生産量についても、前年産に比べ7.3%減少し74万5千tとなりました。
今後は、より定着性が高く、安定した供給につながる多収品種への切替えを進めていく観点から、令和6(2024)年産以降、水田活用の直接支払交付金における一般品種に対する飼料用米の支援単価を段階的に引き下げていくこととしています。
(4)麦・大豆の生産動向
(小麦の作付面積は前年産並み)
令和6(2024)年産の小麦の作付面積は、前年産並みの23万2千haとなりました(図表1-2-8)。また、収穫量は、主に九州において、2月から4月まで多雨傾向で推移したことから湿害や病害の発生が見られたことに加え、4月以降の日照不足や高温により、登熟が不良であったことから、前年産に比べ5.9%減少し102万9千tとなりました。このほか、単収は前年産に比べ5.9%減少し444kg/10aとなりました(図表1-2-9)。
(事例)独自の輪作体系により多収量・高品質の小麦生産を実践(北海道)
(1)道内でもトップクラスの多収量・高品質の小麦を生産

北海道中札内村(なかさつないむら)の中札内村(なかさつないむら)農業協同組合「麦豆事業部会」では、小麦と豆類の生産から調製・出荷に関する事業を行っています。
同部会の構成員は、令和6(2024)年度時点で84戸であり、約925haの小麦生産においては、大型コンバインによる一斉収穫や可能な限り低水分収穫に努め、乾燥・調製施設の効率稼働による経費の低減に取り組んでいます。えだまめ等を組み込んだバランスの取れた輪作体系を構築することにより、小麦の適期に安定した播種(はしゅ)が可能となり小麦の連作を抑え、安定生産を実現しています。また、縞萎縮病(しまいしゅくびょう)を始めとする土壌病害対策、安定多収に向けた取組を進めており、道内でもトップクラスの多収量・高品質の小麦を生産している地域へと発展しました。なお、品種は「きたほなみ」を作付けし、主な用途はうどん等の日本めんに利用されています。
(2)生産拡大に向けたICTの積極的な導入と施設の増強

小麦収穫の様子
資料:中札内村農業協同組合「麦豆事業部会」
同部会は、同村内のRTK基地局による高い精度の測位データを活用し、ほぼ全生産者がGPSガイダンスと自動操舵(そうだ)システムを導入しています。十勝(とかち)管内の中でも大規模経営であることから、作業精度の確保と営農補完、播種から収穫までの労働生産性の向上に寄与しています。
さらに、高品質な小麦生産に向けては、各種情報収集と高度な栽培技術体系に取り組むことにより、生産者の作付意欲を高め、受入・乾燥調製施設をフル稼働してきました。しかしながら、施設の老朽化が課題となってきたため、持続的な小麦生産に向けては、令和6(2024)年度に、貯蔵サイロの増設及び乾燥能力と収容能力を増強しているところです。今後は、「十勝地域組合員総合支援システム(TAF(*))」を活用した、圃場(ほじょう)単位での土壌マップによるきめ細やかな可変施肥技術の導入やドローン等による生育センシング及び適期収穫判定を普及推進して、生産量の向上及び高品質な国産小麦の安定供給を目指すこととしています。
* Tokachi total Assistance system for Farmersの略
(大豆の作付面積は前年産並み)
令和6(2024)年産の大豆の作付面積は前年産並みの15万4千haとなりました(図表1-2-10)。また、令和5(2023)年産の大豆の収穫量は生育期間中において北海道や九州でおおむね天候に恵まれ、着さや数が多かったことから、前年産に比べ7.4%増加し26万1千tとなりました。このほか、単収は前年産に比べ5.6%増加し169kg/10aとなりました(図表1-2-11)。
(事例)「播種半作」を念頭にした大豆栽培(岐阜県)
(1)地域の担い手としての役割を担う農業法人

岐阜県本巣市(もとすし)の農業法人であるアグリード株式会社は、平成25(2013)年に法人化し、農地中間管理機構を通じた農地集積を積極的に進め、地域の担い手としての役割を担っています。同社は水稲を中心に小麦や大豆等の生産も行っています。大豆については加工適性に優れ、実需者からのニーズが高い「フクユタカ」、農研機構が育成した収量が高い「そらみのり」、高オレイン酸大豆「SKT01」の3品種全てにおいて、株間を狭めることにより雑草の発生を抑制し、中耕除草を省略できる狭畦密植栽培(きょうけいみっしょくさいばい)を行っています。
(2)「播種半作」を念頭にした大豆栽培

アグリード株式会社の社員
資料:アグリード株式会社

大豆栽培圃場
資料:アグリード株式会社
水稲の生産においては、良い苗を作ることができるかどうかでその年の作柄・収量を左右するくらい苗づくりが重要であるということを表した「苗半作」という表現があります。同社は、大豆の生産においても、水稲と同じように準備の段階が最も重要であると考え、土壌診断に基づく土づくりや弾丸暗渠(だんがんあんきょ)の施工等の圃場内の排水対策等の作付け前の作業を重点的に行い、梅雨時期の播種に備えています。これにより、単収は162kg/10aと、同県の平均を約3割上回る単収を実現しています。
今後同社は、ドローン等のスマート農業機械の活用による低コスト化を行いながら、多収量品種「そらみのり」の作付けを中心に単収増加と作付面積を拡大することを目標としています。
(5)油糧作物・甘味資源作物の生産動向
(なたねの収穫量は前年産に比べ減少)
令和6(2024)年産のなたねの作付面積は前年産に比べ3.4%減少し1.7千haとなりました(図表1-2-12)。また、収穫量は前年産に比べ14.7%減少し3.1千tとなりました。このほか、単収は前年産に比べ11.4%減少し187kg/10aとなりました(図表1-2-13)。
(てんさいの収穫量は前年産に比べ増加)

データ(エクセル:27KB)
令和6(2024)年産のてんさいの作付面積は、前年産に比べ4.5%減少し4万9千haとなりました(図表1-2-14)。また、収穫量は前年産に比べ2.4%増加し348万5千tとなりました。このほか、糖度は褐斑病(かっぱんびょう)が多発した前年産に比べ2.0ポイント上昇し15.7度となりました。
農林水産省では、直播(ちょくはん)栽培の拡大を始め、省力化や生産コスト低減等の取組を推進しています。
(さとうきびの収穫量は前年産に比べ減少)

データ(エクセル:27KB)
令和5(2023)年産のさとうきびの収穫面積は、前年産に比べ2.2%減少し2万3千haとなりました(図表1-2-15)。また、収穫量は前年産に比べ7.1%減少し118万2千tとなりました。このほか、糖度は前年産に比べ0.8ポイント上昇し14.8度となりました。
農林水産省では、持続的なさとうきび生産に向けて、人手不足に対応した機械化一貫体系の導入や担い手、作業受託組織の育成・強化等を推進しています。
(6)園芸作物の生産動向
(野菜・果実の生産量は前年度に比べ減少)
令和5(2023)年度の野菜の生産量は、夏季の記録的な高温や干ばつによる生育不良等により一部の品目で減少したことから、前年度に比べ2.9%減少し1,087万tとなりました(図表1-2-16)。
令和5(2023)年度の果実の生産量は、生産者の減少・高齢化等により栽培面積が減少したことに加え、りんごの春先の凍霜害による着果数の減少や夏の極端な高温による日焼け等の影響により生産量が減少したことから、前年度に比べ7.3%減少し244万7千tとなりました(図表1-2-17)。
(花きの産出額は前年産に比べ増加)

データ(エクセル:28KB)
令和4(2022)年産の花きの産出額は、前年産に比べ4.9%増加し3,684億円となりました(図表1-2-18)。一方、作付面積は前年産に比べ2.5%減少し2万4千haとなりました。
農林水産省では、「物流の2024年問題」に対応した花き流通の効率化、病害虫被害の軽減や需要期に合わせた生産・出荷等の課題解決に必要な技術導入、需要のある品目への転換や導入を支援するとともに、花き需要の拡大に向けて、新たな需要開拓、花き利用の拡大に向けたPR活動等の前向きな取組を支援しています。
(茶の栽培面積は前年産に比べ減少)

データ(エクセル:42KB)
令和6(2024)年産の茶の栽培面積は、前年産に比べ2.5%減少し3万5千haとなりました(図表1-2-19)。また、荒茶の生産量は、前年産に比べ1.7%減少し7万4千tとなりました。
農林水産省では、消費者ニーズへの対応や輸出の拡大等に向け、茶の改植や新植、有機栽培や輸出向け栽培体系への転換、需要創出に向けた情報発信の取組を支援しています。
(薬用作物の栽培面積は前年産に比べ減少)

データ(エクセル:27KB)
漢方製剤等の原料となるミシマサイコやセンキュウ等の薬用作物の栽培面積については、令和4(2022)年産は、前年産に比べ2.8%減少し494haとなりました(図表1-2-20)。
農林水産省では、産地と実需者等が連携した栽培技術の確立のための実証圃(じっしょうほ)の設置等の取組や、販路の確保・拡大に向けた地域相談会の開催等の取組を支援しています。
(かんしょの収穫量は前年産並み)
令和6(2024)年産のかんしょの作付面積は、前年産に比べ0.6%減少し3万2千haとなりました(図表1-2-21)。一方、収穫量は前年産並みの71万7千tとなりました。

データ(エクセル:26KB)
農林水産省では、共同利用施設の整備や省力化のための機械化体系確立等の取組を支援しています。また、サツマイモ基腐病(もとぐされびょう)の発生・まん延の防止を図るため、土壌消毒、健全な苗の調達等を支援するとともに、苗や種イモの高感度スクリーニング技術、圃場の発病リスク診断技術、発病リスクに応じた対策技術等に対する研究開発を進め、得られた成果を踏まえつつ、防除技術の確立・普及に向けた取組を推進しています。
なお、令和5(2023)年産のかんしょ生産において、一部の圃場でサツマイモ基腐病と異なる腐敗症状を呈するかんしょが確認されたことから、オープンイノベーション研究・実用化推進事業の緊急対応課題において、令和6(2024)年度は腐敗症状の主たる原因菌を特定し、効果的な防除対策の提案を行うため、農研機構が鹿児島県、宮崎県、鹿児島県経済農業協同組合連合会と連携して研究を行っています。
(ばれいしょの収穫量は前年産に比べ増加)

データ(エクセル:27KB)
令和5(2023)年産のばれいしょの作付面積は、前年産並みの7万1千haとなりました(図表1-2-22)。一方、収穫量は前年産に比べ3.5%増加し236万4千tとなりました。
農林水産省では、省力化のための機械導入や収穫時の機上選別を倉庫前集中選別等に移行する取組を支援しています。また、ばれいしょ生産に必要な種ばれいしょの確保に向けた取組を支援するとともに、ジャガイモシストセンチュウやジャガイモシロシストセンチュウの発生・まん延の防止を図るため、共同施設の整備等の推進や抵抗性品種への転換を推進しています。
(7)主要畜産物の生産動向
(肥育牛の飼養頭数は前年に比べ減少、牛肉の生産量は前年度に比べ増加)
令和6(2024)年の繁殖雌牛の飼養頭数は、前年に比べ0.7%減少し64万頭となりました(図表1-2-23)。
また、令和6(2024)年の肥育牛(肉用種・乳用種)の飼養頭数は、前年に比べ1.1%減少し161万7千頭となりました(図表1-2-24)。

データ(エクセル:26KB)
令和5(2023)年度の牛肉の生産量は、和牛や交雑種が増加したことから、前年度に比べ1.1%増加し35万1千tとなりました(図表1-2-25)。
(乳用牛の飼養頭数は前年に比べ減少、生乳の生産量は前年度に比べ減少)
令和6(2024)年の乳用牛の飼養頭数は、前年に比べ3.2%減少し131万3千頭となりました(図表1-2-26)。
また、令和5(2023)年度の生乳の生産量は、飼養頭数の減少と記録的な猛暑の影響等により、都府県では前年度に比べ4.0%減少し314万9千t、北海道では前年度に比べ1.9%減少し417万5千tとなりました(図表1-2-27)。その結果、全国では前年度に比べ2.8%減少し732万4千tとなりました。
(豚の飼養頭数は前年に比べ減少、豚肉の生産量は前年度に比べ増加)
令和6(2024)年の豚の飼養頭数は、前年に比べ1.8%減少し879万8千頭となりました(図表1-2-28)。
一方、令和5(2023)年度の豚肉の生産量は、1頭当たりの枝肉重量が増加したことから、前年度に比べ0.9%増加し90万9千tとなりました(図表1-2-29)。
(事例)養豚一貫経営により美味しさを追求(茨城県)
(1)育種から肥育までこだわった養豚一貫経営


地域と連携したブランド豚
資料:倉持ピッグファウム株式会社
茨城県下妻市(しもつまし)の倉持(くらもち)ピッグファウム株式会社は、創業当初は種豚の生産・販売を行っていましたが、倉持勝(くらもちまさる)さんが社長として経営を受け継ぎ、平成17(2005)年から種豚の生産・販売から、肉豚の繁殖、肥育、そして、最終的な豚肉の加工まで自社で一貫して行えるよう経営の多角化を図りました。
繁殖から加工まで一貫して行うことで、自社ブランドを構築できる可能性を見いだし、肉質の研究と改良を重ね、3か月齢時から出荷するまで地元の飼料用米を中心とした独自の植物性の飼料を用いることで、赤身にはアミノ酸が、脂肪の部分にはオレイン酸が多く含まれるさっぱりとした味わいが特徴の自社ブランドの豚肉を作り上げました。
(2)直売所「ぶぅーぶー~豚職人工房~」をオープン

直売所で販売している加工品
資料:倉持ピッグファウム株式会社
お客様に直接おいしさを届けたいという思いから、同社は、加工部門として平成28(2016)年に直売所「ぶぅーぶー~豚職人工房(ぶたしょくにんこうぼう)~」をオープンしました。食肉学校で加工技術を学んだ二男の暁成(としあき)さんが製造を担当しており、モモ等の余りやすい部位の肉は、ハンバーグやウインナー等の加工品にして販売するなど工夫しています。また、近年は商品ラインナップを増やすことにより、ECサイトでの販売に力を入れており、ECサイトの売上げが直売所の売上げを上回る月もあるとのことです。
今後同社は、更なる母豚の増頭や直売所・ECサイトの売上向上を目指しており、地域と連携したブランド豚や6次産業化による経営多角化の取組は、全国の養豚場の規範になることが期待されています。
(鶏肉の生産量は前年度に比べ増加、鶏卵の生産量は前年度に比べ減少)
令和5(2023)年度の鶏肉の生産量は、安定した需要が継続していることを背景として、前年度に比べ0.5%増加し169万tとなりました(図表1-2-30)。
一方、令和5(2023)年度の鶏卵の生産量は、令和4(2022)年シーズンの高病原性鳥インフルエンザの大規模発生の影響により、前年度に比べ3.1%減少し247万8千tとなりました(図表1-2-31)。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883





















