第3節 我が国における農業生産資材供給の状況
農業生産に必要な肥料や飼料等の農業生産資材については、輸入価格の高騰や原料供給国からの輸出の停滞等の安定供給を脅かす事態が生じるなど、食料安全保障上のリスクが増大しています。このため、輸入依存度の高い農業生産資材について、未利用資源の活用を始め、国内で生産できる代替物へ転換していくことが重要となっています。
本節では、農業生産資材の安定確保に向けた取組や価格高騰への対応について紹介します。
(肥料の供給状況)
主要な肥料の原料となる資源は、世界に偏在しており、りん酸アンモニウムの主な原料であるりん鉱石はモロッコ、中国、エジプト等が、塩化加里の主な原料である加里鉱石はカナダ、ベラルーシ等が世界の経済可採埋蔵量の大半を占めています。
このような中、我が国は主要な肥料原料である尿素、りん酸アンモニウム及び塩化加里のほとんどを輸入に依存しています。
令和3(2021)年秋以降、中国による肥料原料の輸出検査の厳格化やロシアによるウクライナ侵略の影響により、これらの国から我が国への肥料原料の輸入が円滑に進まなくなりました。これを受け、我が国においても、輸入業者が調達国を転換する取組を進めており、その結果、例えばりん酸アンモニウムでは、中国からの輸入割合が90%から73%まで減り、代わって、モロッコ等からの輸入が増えています(図表1-3-1)。

データ(エクセル:28KB)
(肥料原料の輸入通関価格は令和5(2023)年1月以降、おおむね下落基調)

データ(エクセル:27KB)
肥料原料の輸入通関価格は、令和3(2021)年以降、上昇傾向にある中で、ロシアによるウクライナ侵略等の要因も重なり、尿素は令和4(2022)年4月に過去最高値となる11万7千円/t、りん酸アンモニウムは令和4(2022)年7月に過去最高値となる16万7千円/t、塩化加里は令和4(2022)年10月に過去最高値となる16万1千円/tとなるなど価格が急騰しました(図表1-3-2)。その後、国際的な需要の落ち着き等を背景として、令和5(2023)年1月以降はおおむね下落基調となりましたが、今後も需給動向を注視する必要があります。

データ(エクセル:26KB)
また、我が国の農業生産資材価格指数(肥料)は、令和3(2021)年以降、上昇傾向で推移し、令和5(2023)年4月には155.3まで急騰しましたが、その後はやや落ち着いてきています(図表1-3-3)。
肥料価格は、農業経営に影響を及ぼすことから、今後も国際情勢等を含め、価格動向を注視していく必要があります。
(肥料原料の備蓄の取組を支援)
肥料は原料の大部分を輸入に依存していることから、世界的な穀物需要の増加や紛争の発生等の国際情勢の変化により、供給途絶リスクが顕在化しています。
このため、令和4(2022)年5月に成立した経済安全保障推進法(*1)に基づく特定重要物資として肥料を指定し、特に供給途絶リスクの高い肥料原料であるりん酸アンモニウムと塩化加里を対象に、令和9(2027)年度までに年間需要量の3か月分の備蓄体制を構築することを目標に、肥料関係事業者における原料保管に係る取組を支援しています。令和6(2024)年11月末時点で、りん酸アンモニウムは2.4か月分、塩化加里は3か月分の備蓄体制を構築しました。
*1 正式名称は「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」
(農薬の供給状況)
我が国では、農薬製剤の大部分、農薬原体の相当量を国内生産し、双方とも輸出を行っており、比較的供給途絶リスクの小さい農業生産資材と言えます(図表1-3-4)。農薬原体の輸入先国については、インド、ドイツ、米国等が上位を占めていますが、全体で30近い国・地域から輸入されており、輸入先は分散しています。

データ(エクセル:29KB)
(種苗の安定供給)
穀物、果樹の種苗は、ほぼ全量国内で生産されている一方、野菜種子については、国内流通の約9割が国外で生産されています。これは、我が国の種苗会社が、良質な種子を安定的に供給するため、種子生産に適した北半球・南半球の複数国でリスクを分散して生産を行っていることによるものです。くわえて、種苗会社が約1年分を国内で備蓄することにより、安定供給体制は十分に確保されています。
農林水産省では、このような安定供給体制をより盤石なものとするため、近年の気候変動による採種適地の変化等に備えた採種地の開拓を推進するとともに、国内の採種農家の高齢化等を踏まえた効率的な採種技術の開発・実証を進めることとしています。
(コラム)国内種苗会社が野菜種子の安定供給に向けて取組を展開
我が国の種苗会社には、グローバル企業も多く、170か国以上に向けて野菜種子を販売している会社もあります。
野菜種子の品質として、特に発芽力が収穫の出来具合に大きく影響しますが、このような種子の能力の確保は、採種地選びが命運を握っていると言っても過言ではありません。種苗会社が野菜種子の新たな採種地の候補を検討する際は、まずはその野菜の原産地やその時点で野生種が存在する場所を考慮します。例えば、にんじんの原産地は、アフガニスタン周辺です。また、令和6(2024)年時点で野生にんじんが存在する場所は世界に幾つかあり、いずれも極端な冬の寒さがなく、春から夏にかけて穏やかな天候で乾燥している地域です。
種苗会社は、このような場所の中から、他品種と交雑しない立地条件か、生産に適した日照・気温・雨量・土壌条件か、周囲に病害の発生要因となる植物等がいないか、農業者の採種技術等の栽培インフラや輸送インフラが適切かどうかなどの環境条件を確認しながら候補地を選んでいます。候補地では、実際に栽培試験を行い、計画どおりに開花・交配が可能か、混入や交雑をしないか、必要な量や品質を確保できるかなどについて確認を行います。このような行程を経て、採種地が適切と確認できたら、種苗会社は我が国から原種を持って行き、本格的に栽培を開始します。
このように、我が国の種苗会社は、世界各地に野菜種子の採種地を分散し、発芽が良く、病原菌の付着や異物の混入がなく、目的とした形質や性質を発揮できる高品質な野菜種子を安定的に供給することを目指した活動を行っています。
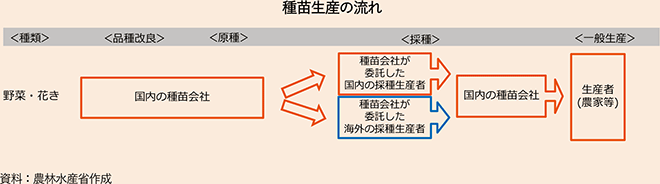
(飼料の供給状況)
令和5(2023)年度の畜産における飼料供給量は、概算で2,369万3千TDN(*1)tとなっており、自給率が高い粗飼料が20%、自給率が低い濃厚飼料が80%となっています。飼料穀物の輸入量は1,286万tで、そのうちとうもろこしが約9割となっています(図表1-3-5)。とうもろこしの輸入については、米国とブラジルで約9割を占めている状況です。飼料穀物の不測の事態に備え、配合飼料メーカー等が、飼料穀物の需要量の約1か月分に相当する100万tを備蓄しています。

データ(エクセル:27KB)
*1 Total Digestible Nutrientsの略で、家畜が消化できる養分の総量
(飼料作物の収穫量は前年産に比べ減少)
飼料作物のTDNベースの収穫量については、令和5(2023)年産は水田において牧草から稲発酵粗飼料用稲(稲WCS(*1))や食用の麦への転換が進められたこと等から、前年産に比べ2.2%減少し336万4千TDNtとなりました(図表1-3-6)。
また、令和6(2024)年産の飼料作物の作付面積は、前年産に比べ0.8%減少し87万7千haとなりました。

データ(エクセル:29KB)

青刈りとうもろこし生産の推進
URL:https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/
lin/l_siryo/aogari_corn.html
*1 Whole Crop Silageの略で、実と茎葉を一体的に収穫し、乳酸発酵させた飼料のこと
(飼料自給率は前年度と同水準で推移)
令和5(2023)年度の飼料自給率は、前年度に比べ1ポイント上昇し27%となりました(図表1-3-7)。その内訳を見ると、粗飼料自給率は前年度に比べ2ポイント上昇し80%へ、濃厚飼料自給率は前年度と同じ13%となりました。国際情勢に左右される輸入飼料への過度な依存から脱却するためには、限られた農地や労働力を有効に活用し、国内飼料生産基盤に立脚した生産へ転換する必要があります。
このため、農林水産省では、畜産農家と耕種農家の連携、コントラクター(*1)等の飼料生産組織の運営強化、品質表示による販売拡大、国産粗飼料の広域流通、草地整備による生産性向上等を支援するとともに、飼料生産も含めた地域計画の策定や実現に向けた取組の促進により、国産飼料の生産・利用拡大を推進しています。

データ(エクセル:41KB)
*1 畜産農家から、播種や収穫等の自給飼料の生産のための作業を受託する外部支援組織
(配合飼料価格は低下傾向で推移するも高止まり)

データ(エクセル:27KB)
家畜の餌となる配合飼料は、その原料使用量のうち約5割がとうもろこし、約1割が大豆油かすとなっています。我が国は原料の大部分を輸入に依存していることから、穀物等の国際相場の変動に価格が左右されます。令和3(2021)年以降、とうもろこしの国際相場がロシアによるウクライナ侵略等を背景に高騰し、配合飼料の工場渡価格は、令和4(2022)年10月に過去最高となる10万1千円/tとなりました(図表1-3-8)。令和5(2023)年以降は、主産国である米国及びブラジルの豊作等により、とうもろこしの国際相場が下落したこと等を受け、低下傾向で推移しつつあります。一方で、円安基調の継続により、依然として高止まりしていることから、今後も価格動向を注視していく必要があります。
(農林水産分野では、エネルギー利用の約9割以上を化石燃料に依存)
我が国は、石油や天然ガス等の資源に乏しいためエネルギー自給率が低く、令和4(2022)年度のエネルギー自給率(IEAベース)は、前年度に比べ0.7ポイント低下し12.6%となっています。
経済産業省の調査によると、令和4(2022)年度における農林水産業のエネルギー消費量は、前年度に比べ3.5%減少し、20万9千TJ(テラジュール)(*1)となっています(図表1-3-9)。
農林水産業分野では、エネルギー利用の約9割以上を化石燃料に依存しており、電力の利用は全体の6.3%となっています(図表1-3-10)。化石燃料の中では、重油の消費が最も多く、次いで軽油、ガソリン、灯油の順となっています。特に重油は、農業分野では施設園芸の暖房に用いられる燃焼式加温機で多く消費されています。軽油やガソリンは農業機械、灯油は穀物を乾燥させる乾燥機で利用されることが多くなっています。

データ(エクセル:58KB)
また、原油価格は、ロシアによるウクライナ侵略直後に大きく上昇し、令和4(2022)年度以降はおおむね下落基調にあるものの、高い水準で不安定に推移しています(図表1-3-11)。
化石燃料については、その価格は地政学上のリスクや国際的な市場の影響等の他律的な要因に左右されやすいことから、農業経営に係る価格の見通しを立てることが難しい農業生産資材と言えます。農林水産分野の持続的な発展に向けては、地域の再生可能エネルギー資源の一層の活用といった化石燃料に依存しない持続可能なエネルギー調達も重要となっています。
*1 テラ・ジュールの略。テラは10の12乗のこと。ジュールは熱量単位
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883






