第4節 輸入の安定化
国内生産で国内需要を満たすことができない一部の食料・農業生産資材については、一定の輸入が不可欠となっており、平時から安定的な輸入を確保するための環境整備が重要となっています。
本節では、食料輸入の状況と食料・農業生産資材の安定的な輸入を確保する取組について紹介します。
(1)我が国における食料輸入等の状況
(農産物の輸入額は前年に比べ5.4%増加)

データ(エクセル:27KB)
令和6(2024)年の農産物輸入額は、前年に比べ5.4%増加し9兆5,461億円となりました(図表1-4-1)。このうち農産品は4.4%増加し6兆9,310億円、畜産品は7.7%増加し2兆6,047億円となりました。
(我が国の主要農産物の輸入構造は少数の特定国に依存)
令和6(2024)年の農産物輸入額を国・地域別に見ると、米国が1兆9,409億円で最も高く、次いで中国、豪州、タイ、カナダ、ブラジルの順で続いており、上位6か国が占める輸入割合は約6割程度になっています(図表1-4-2)。
品目別に見ると、とうもろこし、大豆、小麦の輸入は、世界の上位生産国数か国のシェアが大きく(*1)、このようなこともあって特定国への依存傾向が顕著となっており、上位2か国で8~9割を占めています。小麦については、2000年代以降にロシアやウクライナ等が世界市場で輸出国となりましたが、我が国での用途に適した小麦を生産しているカナダ、米国、豪州の上位3か国に輸入の99.8%を依存している状況です。
一部の品目では輸入先の多様化が進みつつあるものの、我が国の農産物の輸入構造は、依然として米国を始めとした少数の特定国への依存度が高いという特徴があります。

データ(エクセル:33KB)
*1 第1章第1節を参照
(将来の食料輸入に不安を持つ消費者の割合は約8割)
将来の食料輸入に対する消費者の意識について、公庫が令和7(2025)年1月に実施した調査によると、81.2%の人が日本の将来の食料輸入に「不安がある」と回答しました(図表1-4-3)。また、日本の将来の食料輸入について「不安がある」と回答した人にその理由を聞いたところ、「気候変動や自然災害が輸出国における食料生産に影響を与え、必要な輸入量を確保できなくなる懸念があるから」と回答した人が32.7%と最も高くなりました(図表1-4-4)。世界的な食料需要の増加や国際情勢の不安定化等に伴う食料安全保障上のリスクが高まる中、将来にわたって食料を安定的に確保していくことが求められています。
(サプライチェーンの強靱化に向けた取組が重要)
食料安全保障の観点からは、国内生産の増大を図り、輸入と備蓄を適切に組み合わせるとともに、サプライチェーンの持続性を高め、強靱(きょうじん)化に向けて取り組むことが必要です。
公庫が令和6(2024)年7月に実施した調査によると、食品産業全体における外国産農林水産物の調達見込みに対する企業の意識について、61.2%の企業が「懸念がある」と回答し、その理由について、「価格の高止まりまたは上昇の見込みがある(円安要因含む)」と回答した企業が91.8%と最も高くなりました(図表1-4-5)。また、公庫が令和7(2025)年1月に実施した調査によると、食品事業者が仕入れ・調達段階で取り組んでいるリスク対策については、「事前契約により原材料などを確保」を挙げた企業が45.9%で最も高く、次いで「仕入れ・調達先の地域を分散」、「主要な仕入れ・調達先から代替可能な仕入れ・調達先を確保」の順となっています(図表1-4-6)。実際に、食品事業者がサプライチェーンの強靱化に向けて、原材料の安定調達等に必要な措置を講ずる動きも見られています。
農林水産省が令和4(2022)年6月に公表した「食料の安定供給に関するリスク検証(2022)」によると、国内におけるリスクの「サプライチェーンの混乱」について、国内生産においては、季節や品目により主産地が変化し、生鮮品で穀物等と比較して日持ちしない野菜や果実、生乳、水産物に加え、食肉処理施設や小売店における食肉カット技術者の人材不足等が懸念される国産の牛肉、豚肉、鶏肉は、その起こりやすさが中程度で、他の品目と比べ高いと分析しています。輸入においては、小麦や大豆、なたね、砂糖類、飼料穀物については、製粉・油脂製造・精製糖・飼料工場が太平洋(たいへいよう)側に偏在しており、南海(なんかい)トラフ地震等の大地震が発生した場合、代替地での製造が難しいことから、その影響度が大きく、注意すべきリスクと評価しています。
(2)食料・農業生産資材の安定的な輸入の確保
(食料・農業生産資材の安定的な輸入の確保を推進)
国内生産では国内需要を満たすことができない食料・農業生産資材の輸入に当たっては、気候変動によるリスクや地政学的リスクの高まり等も踏まえ、平時から安定的な輸入を確保するための環境整備が重要となっています。このため、農林水産省では、輸入相手国における調達網の強靱化を図るため、我が国事業者が海外現地で行う穀物等の集出荷・港湾施設等への投資案件の形成を支援するとともに、輸入相手国の多様化の観点も含め、輸入相手国との政府間対話の活用、食料や農業生産資材の安定輸入のための海外からの情報収集、国内における官民による情報共有等を推進することとしています。
輸入相手国との政府間対話としては、令和6(2024)年9月に、ブラジルとの間で第5回日伯農業・食料対話を開催し、ブラジルから日本への穀物の安定供給等について議論を行いました。この対話の成果として、農業・食料分野における両国間の協力に関する政府間覚書を締結し、引き続きブラジルからの穀物の安定的な輸入の確保に取り組んでいくこととなりました。また、同年11月には、カナダとの間で第2回日加農業食料政府間協力対話を開催し、食料供給に関する不測の事態が生じた場合に、政府間で効率的な情報共有等を行えるようにする「食料安定供給に係る対話枠組み」の設立に合意しました。
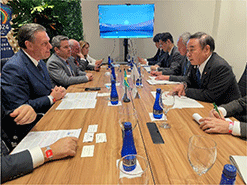
第5回日伯農業・食料対話での農林水産大臣と
ブラジル農業・畜産大臣のバイ会談

第5回日伯農業・食料対話に際しての
ブラジルの穀物積出港の視察
さらに、官民による情報共有の取組の一環として、農林水産省では、同年6月に食料の安定的な輸入の確保に関する協議会合を開催し、我が国への日々の輸入を担っている一般社団法人日本貿易会(にほんぼうえきかい)の会員企業との間で、主要穀物等の調達をめぐる国内外の情勢等について、意見交換を行いました。今後ともこのような会合を含む様々な機会を通じ、我が国の輸入事業者が行う輸入・調達事業をめぐる課題や要望を適切に把握の上、これを踏まえて官民の協力・連携の下に関連施策を講ずることとしています。
(食料の安定的な輸入に向け、港湾機能を強化)
我が国では、食料や農業生産資材の多くを海外に依存しており、その多くが海運を通じて輸入されています。輸入穀物の多くは、バルク船と呼ばれる貨物船で輸送されていますが、世界で利用されるバルク船は、輸送効率化のために大型化される傾向にあります。一方、我が国の港湾では、岸壁の水深が10~14mであることが多く、大型バルク船が接岸できる水深14m以上の港湾は限られていることから、食料の安定供給のためにも、大型船に対応できる港湾整備等が重要となっています。
国土交通省では、ばら積み貨物の安価で安定的な輸入を実現するため、大型船に対応した港湾機能の拠点的確保や企業間連携の促進等による効率的な海上輸送網の形成に向けた取組を推進しています。また、令和6(2024)年2月には、おおむね5年間程度で取り組むべき施策を取りまとめ、他のアジア主要港との競争が可能な北米・中南米地域向けの貨物を中心とした東南アジア等からの広域集貨に向けた輸送ルートの構築や、船舶の大型化・積替円滑化等に対応した大水深・大規模コンテナターミナルの形成等に取り組むこととしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883








