第5節 不測時における措置
世界的な食料需給の変化や生産の不安定化等により、我が国の食料安全保障上のリスクが高まっている中、食料供給が大幅に減少する不測の事態への対応が必要となっています。
本節では、令和6(2024)年6月に公布された食料供給困難事態対策法等について紹介します。
(1)不測時における食料安全保障の対応の強化
(世界の食料需給等をめぐるリスクが高まり)
昨今、気候変動等による世界的な食料生産の不安定化、世界的な食料需要の拡大に伴う調達競争の激化等に、ウクライナ情勢の緊迫化、中東情勢の不安定化等も加わり、輸入する食品原材料や農業生産資材の価格高騰を招くとともに、産出量が特定の国に偏っている化学肥料原料の輸出規制や、コロナ禍における国際物流の混乱等による供給の不安定化も経験するなど、世界の食料需給等をめぐるリスクが高まっています(図表1-5-1)。食をめぐる国内外の状況が刻々と変化する中、食料安全保障の強化が国家の喫緊かつ最重要課題となっています。

(食料供給困難事態対策法が公布)
近年、世界的な食料需給の変化と生産の不安定化により、食料供給が大幅に減少するリスクが高まる中、食料供給が減少し、国民生活・国民経済に影響が生じる事態を防止するため、平時からの対応に始まり、政府一体となって早期から必要な対策を行う食料供給困難事態対策法が令和6(2024)年6月に公布されました。同法は、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針の策定、食料供給困難事態対策本部(以下「政府対策本部」という。)の設置、特定食料の安定供給の確保のための措置等について定めており、食料安全保障の確保に寄与し、もって国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保に資することを目的としています(図表1-5-2)。

(コラム)スイスやドイツでは食料安全保障の確保に向けた取組を展開
我が国では、令和6(2024)年6月に食料供給困難事態対策法が公布されたところです。世界に目を転じると、諸外国の中には、スイスやドイツのように、既に不測の事態にかかる対策法を制定している国があります。各国は、深刻な事態に陥る前の「おそれ」の段階から対処を始めることが重要という考え方の下で、備蓄放出や輸入、流通規制等の措置を講ずることとするなどの事態の深刻度に応じた対応を整理しています。
また、これらの措置を実施する上で必要となる、情報収集に関する規定や、措置の実施に伴う経済的な損失に対する補償措置についても、法的に規定されています。
例えばスイスでは、不測時の対策として、生産・加工・流通等を含めたサプライチェーンの各段階において各種措置を規定しており、平成29(2017)年に国家経済供給法を改正した際には、「迅速な対応により、経済への深刻なダメージを防ぐか、最小限に抑えることが重要である」という考え方の下、「おそれ」の段階から措置を発動できるように規定されました。
これに加えて、事態の深刻度に応じて各種措置を発動することを戦略として掲げており、<1>特定商品の3か月内の短期間の不足の場合には、備蓄放出や輸入等により対応し、<2>そうした供給不足が1年程度続く場合には販売制限等により需要を抑制し、<3>供給不足が1年以上続く深刻な事態においては、配給や生産の転換により、国民が最低限必要とする熱量供給を確保することを定めています。
また、ドイツでは、供給危機に至る前段階の措置として、買占めや売惜しみの防止等を含む流通規制や、備蓄に関する措置等をとることができる旨が規定されています。その上で、供給危機時においては、サプライチェーンの各段階における制限の強い措置を規定しています。これに加え、「食料の秩序ある流通を確保するための対策をできるだけ早く講ずることが決定的に必要」という考え方の下、所管省庁権限で法規命令が発布される前に暫定的に対策を講ずることができる旨も規定されています。
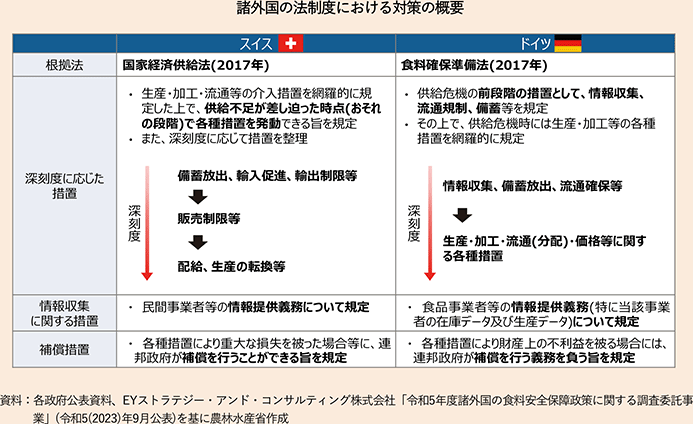
(供給不足の兆候を捉えた早期の段階から、政府一体となった対策を実施)
食料の供給不足による国民生活や国民経済に支障が生じる事態を未然に防止し、早期に解消するためには、供給不足が生じ得る兆候を捉えた早期の段階から、関係する省庁が一体となって必要な対策を講じていくことが重要です。このため、気象災害や家畜の伝染性疾病の発生等の食料供給が不足する兆候を把握した場合(以下「食料供給困難兆候」という。)に、内閣総理大臣を本部長、全ての国務大臣を構成員とする政府対策本部を設置することとしています。政府対策本部では、供給を確保すべき重要な食料やその生産資材の供給目標数量や供給確保対策を盛り込んだ実施方針を策定し、事態の深刻度に応じて、関係省庁が連携して必要な対策を総合的に実施することとしています。
(供給確保対策の対象とする重要な食料と生産資材をあらかじめ指定)
国民の食生活又は国民経済上の重要性を踏まえ、対策の対象とする重要な食料を「特定食料」、その食料の生産に不可欠な生産資材を「特定資材」として政令で定める仕組みとしており、令和7(2025)年2月に特定食料には米穀、小麦、小麦粉、大豆、なたね、油やしの実、植物油脂、てんさい、さとうきび、砂糖、牛肉、豚肉、鶏肉、生乳、飲用牛乳、乳製品、鶏卵、液卵、粉卵が、特定資材には肥料、農薬、種苗、飼料、動物用医薬品が指定されました。
(平時からの対策)
不測時の対策を円滑かつ効率的に実施する観点から、不測時に備えて平時から行うべき取組や、不測時に講ずる対策の基本的な考え方等を、法律に基づく基本方針として定めることとしています。この基本方針に基づき、平時から国内生産基盤の強化や、食料・生産資材のサプライチェーンの維持・強化に向けた施策を推進していくほか、国内外の食料需給に関する情報の収集・分析、適切かつ効率的な備蓄の運用、国内生産で国内需要を満たすことができない農産物等の安定的な輸入の確保等を進めていくこととしています。特に不測時の発生初期における効果的手段である備蓄については、国内に存在する民間在庫も含めた官民合わせた備蓄をトータルで捉える総合的な備蓄を推進していくことや、そのためにも国内にある特定食料や特定資材の民間在庫等を把握するための情報収集を行っていくこととしています。
(不測時の供給確保対策)
不測時に国民に食料供給を安定的に確保するためには、国はもとより、食料の生産、輸入、出荷・販売に携わる事業者の協力が必要となる一方、不測時であっても民間の事業活動に対する国の介入は必要最小限にとどめるべきものです。このため、食料供給困難兆候の段階では、出荷販売業者や輸入事業者、生産業者等の事業者には、あくまで自主的な取組を求める「要請」を行うことができる仕組みとしています。事態が改善せず、食料供給が大幅に減少し、国民生活等に支障が生じる事態、「食料供給困難事態」に至り、要請では必要な供給確保が見込めない場合に限り、事業者に対して、出荷販売等の計画の作成・届出を「指示」することができることとしています。また、届出された計画に沿って供給が行われたとしても事態の解消が困難な場合であって、当初の計画の内容等から見て計画変更が可能と認められる事業者に限って、計画変更を指示することができることとしています。
(供給確保の取組が円滑に行われるための措置)
不測時において事業者が要請等に応じた事業活動を行う場合には、金銭的な負担や経営への悪影響が生じる可能性が考えられます。このため、国は法律の規定に基づき、要請に応じて供給確保の取組を行う事業者に対し、その取組が円滑に行われるようにするための財政上の措置その他の措置を講ずることとしています。
また、政府として、確保可能な供給量を正確に把握し、実効性のある対策を講ずるため、計画の作成・届出を行わない事業者には罰則を規定しています。なお、計画の内容は各事業者が実施可能な範囲内でよいとともに、内容を実行できなかったこと自体は罰則の対象となりません。
(不測時における食料自給力シミュレーションモデルの構築)
農林水産省では、不測の事態を想定し、必要な対策を検討するため、諸外国の事例を参考とし、国内の農地や労働力を始めとする生産基盤の確保状況、品目ごとの輸出入量、食料等の備蓄状況、世界の需給動向を考慮し、供給熱量や栄養バランスを最適化する我が国の食料自給力シミュレーションモデルの構築を行うこととしています(図表1-5-3)。

(2)不測時に備えた備蓄の実施
(不測時に備えた穀物の備蓄を実施)
政府は国内の米の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、米を100万t程度(*1)備蓄しています。あわせて、海外における不測の事態の発生による供給途絶等に備えるため、食糧用小⻨については国全体として外国産食糧用小⻨の需要量の2.3か月分を備蓄し、そのうち1.8か月分の保管料を、飼料穀物についてはとうもろこし等約100万tを⺠間で備蓄し、そのうち75万t分の保管費等を政府が支援しています。
食料の備蓄強化に向けては、国内外の食料安全保障の状況を適切に把握・分析の上、これらを踏まえて、民間在庫量の把握等を進め、官民合わせた総合的な備蓄の推進を行うことが重要です。
*1 10年に1度の不作や、通常程度の不作が2年連続した事態にも国産米をもって対処し得る水準
(フォーカス)諸外国では食料安全保障の確保に向けた備蓄を実施
我が国の備蓄は、平時において食料安全保障の確保に向け実施する措置の一つです。諸外国においても、各国の状況・考えに応じて、食料の備蓄を行っています。ここではスイス、ドイツ、フィンランドにおける対応について紹介します。
スイスにおいては、備蓄は食料の供給不足の兆候が表れた際に、迅速に対応できる手段として、特に重要であると考えられています。法律に基づき官民が協力して備蓄を行いますが、あくまで主体は民間事業者であるという考えであるため、費用については、備蓄する品目の輸入事業者に課せられる輸入賦課金から負担する仕組みとなっています。また、コーヒーを備蓄しているのも特徴の一つです。コーヒーは、炭水化物、たんぱく質、脂質が少ないためエネルギーはほとんどなく、栄養学的観点からは備蓄を継続する必要はありませんが、スイスの消費習慣において重要な位置付けをされており、心理的な理由に基づき備蓄されています。
ドイツにおいては、国民の食料供給における短期的な対応を目的としており、平時の備蓄量は数日から数週間の範囲で最低限の水準となっています。しかし、不測の事態のおそれのある場合等で、備蓄水準が不十分であると判断した場合には、民間への備蓄命令により備蓄量を増やすこととしています。
フィンランドにおいては、ロシア・ウクライナ情勢等の今後数年間は継続する可能性のある安全保障上の問題を踏まえ、深刻な混乱や緊急事態が発生した場合の国内供給を確保することを目的として、食用の緊急備蓄を維持することとしています。
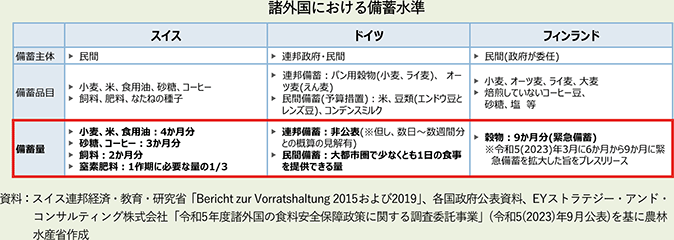
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




