第6節 国際戦略の展開
農林水産省では、我が国の農林水産業が「国の基(もとい)」として発展し、将来にわたってその重要な役割を果たしていけるよう交渉を行うとともに、我が国の農林水産物・食品の輸出拡大につながる交渉結果の獲得を目指しています。また、途上国等の自立的な経済発展を通じた我が国との関係強化を図るため、様々な形態による農林水産・食品分野での協力を行っています。
本節では、経済連携交渉等の交渉への対応状況や国際協力の推進等について紹介します。
(1)交渉への対応
(複数の国・地域とのEPA/FTA交渉を実施)
特定の国・地域で貿易ルールを取り決めるEPA(*1)/FTA(*2)等の締結が世界的に進み、令和6(2024)年12月時点では405件に達しています。
我が国においても、令和7(2025)年3月時点で、21のEPA/FTA等が発効済・署名済です(図表1-6-1)。これらの協定により、我が国は世界経済の約8割を占める巨大な市場を構築することになります。輸出先国・地域の関税撤廃等の成果を最大限活用し、我が国の強みを活かした品目の輸出を拡大していくため、我が国の農林水産業の生産基盤を強化していくとともに、新市場開拓の推進等の取組を進めることとしています。

令和6(2024)年度には、バングラデシュとの間でEPA交渉会合を4回実施したほか、同年9月にアラブ首長国連邦との間でEPA交渉を立ち上げ、同年11月及び令和7(2025)年2月に交渉会合を実施しました。さらに、GCC(*3)(湾岸協力理事会)との間でEPA交渉を再開し、令和6(2024)年12月に交渉会合を実施しました。また、同年8月に日・インドネシアEPA改正議定書への署名を行いました。
*1 Economic Partnership Agreementの略で、経済連携協定のこと
*2 Free Trade Agreementの略で、自由貿易協定のこと
*3 Gulf Cooperation Councilの略
(WTO農業交渉は議論を継続)
世界共通の貿易ルールづくり等が行われるWTO(*1)(世界貿易機関)では、これまで数次にわたる貿易自由化交渉が行われてきました。平成13(2001)年に開始されたドーハ・ラウンド交渉においては、依然として途上国と先進国の溝が埋まっていないこと等により、農業分野等の交渉に関する今後の見通しは不透明です。我が国としては、世界有数の食料輸入国としての立場から公平な貿易ルールの確立を目指し交渉に臨んでおり、我が国の主張が最大限反映されるよう取り組んでいます。
令和6(2024)年2~3月にアラブ首長国連邦で開催された第13回WTO閣僚会議では、第14回WTO閣僚会議に向けた農業交渉の道筋について議論されましたが、合意には至りませんでした。
*1 World Trade Organizationの略
(IPEFの3つの協定に署名)
米国、日本、豪州等14か国が参加するインド太平洋経済枠組み(IPEF(アイペフ)(*1))については、令和6(2024)年6月の閣僚級会合において「IPEFクリーン経済協定」、「IPEF公正な経済協定」及び「IPEF協定」の署名式が行われ、同年10月に締結済の署名国について発効しました。
*1 Indo-Pacific Economic Framework for Prosperityの略
(令和6(2024)年11月にコスタリカのCPTPP加入作業部会設置、12月に英国の加入議定書が発効)
「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(CPTPP(*1))について、令和6(2024)年11月のTPP委員会において、コスタリカの加入手続の開始及び加入作業部会の設置が決定されました。
また、同年12月にCPTPPへの英国との加入議定書が、締結済の我が国を含む10か国について発効しました。
*1 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnershipの略
(ブラジルでG20農業大臣会合、イタリアでG7農業大臣会合が開催)
令和6(2024)年9月に、ブラジルでG20農業大臣会合が開催され、農業・食料システムの持続可能性や食料安全保障への国際貿易の貢献、小規模家族農業支援等について議論が行われました。同会合において我が国は、令和5(2023)年4月のG7宮崎農業大臣会合での議論を踏まえつつ、農業の生産性向上と持続可能性の両立を実現すべきことを各国に呼び掛け、G20農業大臣宣言に我が国が主張した「国内生産の重要性」等が盛り込まれました。

G7農業大臣会合サイドイベントで
2027年国際園芸博覧会をPRする
ブース
また、令和6(2024)年9月にイタリアで開催されたG7農業大臣会合では、強靱(きょうじん)で持続可能な食料システム、漁業と養殖業、科学イノベーションと気候変動等について議論が行われました。我が国は、G20農業大臣会合と同様に、農業の生産性向上と持続可能性の両立を実現すべきことを各国に呼び掛け、G7農業大臣声明に我が国が主張した「貿易と国内生産を両立する必要性」等が盛り込まれました。
(二国間関係の戦略的な構築)
農林水産省では、輸出拡大、輸入安定化や協力関係強化等に向けて、各国と戦略的な関係構築に取り組んでいます。
東アジアでは、令和6(2024)年8月に農林水産大臣が香港を訪問し、日本産食品に対する輸入規制の即時撤廃を求め、対話の継続を確認しました。令和7(2025)年1月には農林水産大臣が中国を訪問し、中国への輸出拡大に向けた働き掛けを行うとともに、農林水産分野での協力の推進を確認しました。
東南アジアでは、令和6(2024)年5月にフィリピンとの間で日比農業合同委員会を初開催し、農業分野での協力の推進や輸出拡大に向けた課題等について意見交換を行いました。同年同月には農林水産大臣がタイを訪問して輸出拡大に向けて働き掛け等を行ったほか、同年6月には同国と協力強化のための政府間対話を行いました。
オセアニアでは、令和7(2025)年2月に、豪州との間で農業・食品のバリューチェーンに関する協力文書に署名し、農産物貿易や農業投資関係の強化等に取り組むこととしました。
欧州では、令和6(2024)年9月のG7農業大臣会合の機会を捉え、イタリア及びドイツとの間でそれぞれ農業・食料分野における二国間協力に関する覚書に署名し、強靱で持続可能な食料システムの構築への協力強化を確認しました。
北米では、同年4月の日米首脳会談において、「強靱で責任ある水産物サプライチェーンの促進」や「食料安全保障及び持続可能な農業の強化」について一致し、持続可能な農業に関する日米間の協力の一環として、同年8月のAPEC(*1)食料安全保障担当大臣会合開催に合わせて、気候変動問題に対応するため、データに基づく政策立案の促進により食料安全保障に取り組むためのワークショップを日米ほかで共同開催しました。同年11月には、カナダとの間で第2回日加農業食料政府間協力対話を実施し、「食料安定供給に係る対話枠組み」の設立について一致しました。
南米では、同年9月にブラジルにて、農林水産大臣がブラジル農業・畜産大臣及び農業開発・家族農業大臣と会談し、同国からの穀物の安定供給、我が国からの輸出環境整備及び生産性向上のための技術協力について意見交換を行い、農業・食料分野における協力に関する覚書に署名しました。
*1 Asia Pacific Economic Cooperationの略
(2)国際協力の推進
(グローバルみどり協力プランを策定)
令和6(2024)年11月に開催されたG20サミットにおいては、飢餓と貧困の撲滅に向けた取組への支援とその加速化のために「飢餓と貧困に対するグローバル・アライアンス」が創設されたところです。また、内閣総理大臣から、温室効果ガス排出の低減を含めた持続可能で生産性の高い農林水産業を中南米や新たなパートナーに広げていく旨を表明しました。これを受け、中南米やアフリカ諸国を含むグローバルサウス地域に対する我が国の農林水産業に係る技術・知見を活用した協力内容を「グローバルみどり協力プラン」として同年12月に策定し、農業生産に係る地域の特性に配慮し、グローバルサウス諸国との緊密な協力を通じて、強靱で持続可能な農業及び食料システムの構築を支援することとしています。
(農林水産・食品分野での各国との協力を推進)
農林水産省とウクライナ農業政策・食料省は、令和6(2024)年4月に「日ウクライナ農業復興戦略合同タスクフォース」第2回会合をオンラインで開催し、我が国からは農林水産省のほか、ウクライナの農業復興に取り組む関係機関、民間企業から約120人が参加しました。同タスクフォースでは、同年2月に開催された日・ウクライナ経済復興推進会議における農業分野の成果を報告するとともに、ウクライナの農業復興協力に向けた我が国民間企業の取組計画を両国の関係省庁・関係企業間で共有し情報交換が行われました。本取組結果の状況については、令和7(2025)年1月に開催した第3回会合で共有し、今後の更なる連携強化に向けた意見交換を行っています。

ウクライナ農業政策・食料省との会談
また、農林水産省は、令和6(2024)年4月にウクライナを訪問し、ウクライナにおける農業生産力回復に向けた官民連携による協力について、ウクライナ農業政策・食料省、閣僚会議、国有財産基金、国営農業機械リース会社等との協議・意見交換を行いました。
このほか、農林水産省とバングラデシュ人民共和国農業省は、令和5(2023)年4月に署名した、農業ベースのビジネス強化等を通じた食料・農業分野における両国間のビジネス交流等での協力を促進する協力覚書に基づき、令和6(2024)年5月にバングラデシュで第1回合同農業作業部会を開催し、両国の民間企業の取組の共有や、我が国からの食料・農業関係の官民ミッション派遣の計画等について意見交換を行いました。
同年6月には、ウズベキスタンに農林水産・食品分野のビジネスミッションを6年ぶりに派遣し、「農業・食品産業発展フォーラム」や「日本食材を用いたレセプション」を初めて開催するとともに、同国の食品小売等の視察、関係省庁や団体等との意見交換を実施しました。
また、インドでは、ウッタル・プラデシュ州内に設けた「モデルファーム」のキックオフ会合を同年8月に開催し、令和7(2025)年2月には、現地農業者や事業者の参画を得て、我が国民間企業の技術のデモンストレーションや取組報告を行いました。
(コラム)ウクライナの農業生産力の回復を通じ、復興支援に貢献
ウクライナ農業の復興・発展の加速に向け、令和6(2024)年6月にドイツで「日・ウクライナ官民ラウンドテーブル」が開催され、農林水産副大臣が出席しました。
同ラウンドテーブルでは、農林水産省とウクライナ農業政策・食料省の間で、協力活動に関係するウクライナ人の出国支援や、協力活動に使用する物品の通関等の支援に関して協力する文書を公表したほか、農業機械メーカー等日本企業4社とウクライナ農業政策・食料省等との間で協力する計4本の文書が公表され、官民を挙げて更に協力を前進させることを表明しました。食料・農業分野では、同年2月の日・ウクライナ経済復興推進会議において署名された8本の覚書を含め、これまでに13本の協力文書をウクライナ政府関係機関との間で署名しています。
農林水産省では、日ウクライナ農業復興戦略合同タスクフォースの下、日本企業の技術・製品等を活用した農業生産力の回復を図るために必要な調査を行うとともに、実現可能性調査等の日本企業のウクライナ事業展開に向けた必要な取組を支援し、官民が連携して総合的な活動を行っています。取組の実施により、日本企業のウクライナ農業復興への参画を促し、農業生産力の回復を通じたウクライナ復興支援や世界の食料安全保障の確保に寄与することを目指しています。
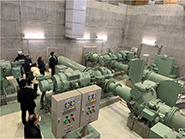
ウクライナ代表団による日本企業の
技術・製品(揚水機場)の視察
(アフリカへの農業協力を推進)
アフリカ各国が食料安全保障を強化し、経済発展を達成するためには、各国の農業生産の増加や所得の向上が不可欠です。我が国は、アフリカへの農業の生産性向上や持続可能な食料システム構築等に向けた様々な支援を通じ、アフリカ農業の発展に貢献しています。

耐塩性・耐干性イネ品種の開発
令和6(2024)年度は、令和7(2025)年8月に神奈川県横浜市(よこはまし)で開催予定の第9回アフリカ開発会議(TICAD(ティカッド)(*1))等を見据え、アフリカの食料安全保障と栄養を改善するため、国際農業研究機関と連携し、気候変動への対応や栄養供給の向上に資する作物品種の開発を促進しました。
今後ともアフリカ各国や関連する国際機関等との連携を図りつつ、農業分野の課題解決を図ることとしています。また、各国の投資環境や消費者ニーズを捉え、我が国の食産業の海外展開や農林水産物・食品の輸出に取り組む企業を支援していくこととしています。
*1 Tokyo International Conference on African Developmentの略
(「ASEAN+3緊急米備蓄」を推進)
我が国は東アジア地域(ASEAN(アセアン)(*1)10か国、日本、中国及び韓国)における食料安全保障の強化と貧困の撲滅を目的とした米の備蓄制度である「ASEAN+3緊急米備蓄」(APTERR(アプター)(*2))について、平成24(2012)年の協定発効以来、現物備蓄事業への拠出や事務局への日本人専門家の派遣等を通じ、積極的に支援しています。
令和6(2024)年度には、我が国が拠出した米がフィリピン及びラオスにおいて災害の被災者等の支援に活用されました。また、我が国とフィリピンの間で、令和6(2024)年10月に、APTERR唯一となるTier1プログラム(*3)(申告備蓄の活用事業)実施に関する取組について、さらに3年間延長するための協力覚書改訂書に署名を行いました。

APTERR理事会会合の様子
同年同月に開催されたASEAN+3首脳会議では、内閣総理大臣よりこれまで我が国がAPTERRの取組を主導してきており、ASEAN食料安全保障情報システムの組織強化を含め、食料安全保障分野での協力についても議論を主導していく決意を表明しました。
また、令和7(2025)年2月には、我が国で初めてAPTERR理事会会合を開催し、APTERRの更なる活動強化に向け引き続き加盟国間で協力することを確認しました。

ASEAN+3緊急米備蓄(APTERR)について
URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/higasi_asia/index.html
*1 Association of South-East Asian Nationsの略で、東南アジア諸国連合のこと
*2 ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserveの略
*3 APTERR加盟国が保有する備蓄のうち、緊急時に放出可能な数量をあらかじめ申告し、緊急事態発生時に申告の範囲内で備蓄を放出するプログラム
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883





