第6節 経営意欲のある農業者による創意工夫を生かした農業経営の展開
農業の持続的な発展のためには、経営意欲のある農業者が創意工夫を生かした経営を展開していくことが重要です。また、農業法人の経営基盤の強化を図るため、その経営に従事する者の経営管理能力の向上、雇用の確保に資する労働環境の整備、自己資本の充実を促進していくことも必要です。
本節では、認定農業者制度、農業経営の法人化の進展、経営基盤の強化、労働力の確保等の取組について紹介します。
(1)認定農業者制度を通じた経営発展の後押し
(農業経営体に占める認定農業者の割合は24.5%に上昇)

データ(エクセル:29KB)
認定農業者制度は、農業者が経営の改善を進めるために作成した農業経営改善計画を市町村等が認定する制度です。同計画の認定数(認定農業者数)については、令和5(2023)年度は前年度に比べ1.4%減少し21万7千経営体となった一方、農業経営体の減少に伴い、農業経営体に占める認定農業者の割合については、令和5(2023)年度は前年度から0.9ポイント上昇し24.5%となっています(図表2-6-1)。このうち法人経営体の認定数については一貫して増加しており、令和5(2023)年度は前年度に比べ1.4%増加し2万9千経営体となり、法人経営体に占める認定農業者の割合は87.2%となっています。
農林水産省では、認定農業者が同計画を達成できるよう農地の集積・集約化や経営所得安定対策等の支援措置を講じています。
(2)農業経営の法人化の進展と経営基盤の強化
(農業法人の大規模化が進展)
農業経営の法人化には、経営管理の高度化や安定的な雇用、円滑な経営継承、雇用による就農機会の拡大等の利点があります。令和6(2024)年の法人経営体数は前年から1.2%増加し3万3,400経営体となりました(図表2-6-2)。農業生産に占める法人経営体等の団体経営体のシェアは年々拡大しており、令和2(2020)年は農産物販売金額の37.9%、経営耕地面積の23.4%を占めています。

データ(エクセル:27KB)
都府県における経営耕地面積規模別の経営体数については、平成12(2000)年以降、5ha未満の経営体数は減少する一方、10ha以上の経営体数は一貫して増加しています(図表2-6-3)。特に大規模層ほど法人経営体が占める割合が増加しており、30ha以上の経営体では平成27(2015)年に50.0%であった法人経営体の割合は令和2(2020)年には60.0%に拡大しています。離農した経営体の農地の受け皿となることにより、農業法人の大規模化が進展している様子がうかがわれます。
農林水産省では、農業経営の法人化や改善を進めるため、都道府県が整備している農業経営・就農支援センターによる経営相談や専門家を活用した助言等を通じた支援を行っています。

データ(エクセル:32KB)
(農業法人の財務基盤は他産業と比べて脆弱な状況)
農業法人の経営状況については、売上高の減少に対する耐性を示す指標である損益分岐点比率が過半の部門で90%を超えており、概して売上高の減少に対する耐性が低くなっています(図表2-6-4)。また、本業の収益性を示す売上高営業利益率は、ほとんどの営農類型でマイナスの状況です。くわえて、中長期的な財務の安全性を示す指標の一つである自己資本比率はおおむね30%を下回っている一方、借入金依存度は50%を上回る水準となっています。
経営規模や産業特性の異なる、他産業の中規模企業と一概に比較することはできませんが、農業法人については、総じて、債務超過となるリスクが高く、財務基盤が脆弱(ぜいじゃく)であるといった実態にあることがうかがわれます。このため、農業経営の改善を進めるなどの取組を通じて、経営基盤の改善・強化を図っていくことが求められています。

データ(エクセル:29KB)
(農業者の経営管理能力の向上に向けた取組が重要)
効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するためには、営農の類型及び地域の特性に応じ、農業生産基盤整備の推進、農業経営の規模拡大その他農業経営基盤の強化を図ることが重要です。そのためには、農業法人等が離農農地の受け皿となり規模拡大や事業の多角化等を進めていくために必要な経営管理能力の向上に向けた取組等が重要となっています。
農林水産省では、農業者の経営管理能力及び農業者を支援する者の支援能力の向上に向けて、関係機関等が有機的に連携できるよう、農業者の支援を行っている各民間セクターを会員とした「農業経営人材の育成に向けた官民協議会」を令和6(2024)年6月に設置しました。同協議会では、経営戦略や財務・労務管理等を学ぶ研修プログラムの策定、農業経営の財務分析システムの開発等に取り組んでいます。
また、雇用確保や事業拡大、環境負荷低減や生産性向上のための新技術の導入等の様々な経営課題に対応できる人材の育成・確保を図るため、農業者のリ・スキリング(*1)等を推進しており、各都道府県においても、営農しながら体系的に経営を学ぶ場として農業経営塾を開講する取組等により、農業者に対する研修機会の提供に取り組んでいます。
さらに、農地を適正かつ効率的に利用する者による農地の利用促進等を目的として、令和6(2024)年6月に改正農業経営基盤強化促進法(*2)が公布されました。農地所有適格法人の中には取引企業との連携による経営発展のニーズがあることに対応し、農地所有適格法人が、出資により食品事業者等との連携を通じて農業経営を発展させるための農業経営発展計画について、農林水産大臣の認定を受けた場合は、議決権要件の特例を措置することとしています。これにより農業経営基盤の強化の促進が見込まれます。
*1 職業能力の再開発・再教育のこと
*2 正式名称は「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律」
(3)労働環境の整備と労働力の確保
(雇用労働力の確保等の課題に対応する必要)
農業における就業者数のうち雇用者数については、平成12(2000)年の30万人から令和6(2024)年は55万人にまで増加しています(図表2-6-5)。
一方、国内の生産年齢人口が今後大幅に減少していくことが避けられない状況において、各産業で人材獲得競争が激化することが見込まれます。
農林漁業の有効求人倍率については、平成26(2014)年以降は1.0倍を超過するなど、人手不足の状況が継続しています(図表2-6-6)。
農業就業人口の減少が進む中で、人材を雇用する経営体が人と農地の受け皿となる事例が増加しており、今後、このような経営体が必要な雇用労働力を確保できなければ、地域農業を支えていくことが難しい状況にあります。今後、農業分野で雇用労働力の継続的な確保が課題となる中、食料安全保障の観点からも、雇用労働力の確保に関する施策を講じていくことが重要となっています。
農林水産省では、農業における労働力不足を解消するため、国内外からの人材の受入体制整備、呼び込み・確保、育成までの総合的な支援等に取り組んでいます。
(農業経営における労働環境を改善する必要があると回答した経営体の割合は約6割)

データ(エクセル:24KB)
農業では、天候や季節等の自然的条件に強く影響されること等を理由に、労働基準法の労働時間等に関する一部規定の適用除外や保険加入に関する特例が認められています。
令和6(2024)年1~2月に実施した調査によると、農業経営における労働環境を改善する必要性について、「改善する必要がある」と回答した経営体は約6割となっています(図表2-6-7)。また、「改善する必要がある」と回答した経営体のうち、農業経営における労働環境で改善が必要だと思う点については、「賃金の上昇」、「農業機械等の導入による作業負荷軽減」、「労働時間の短縮」等が挙げられており、他産業との人材獲得競争の中で、雇用労働力を確保していくためには、農業の労働環境改善を図ることが重要になっています。
農林水産省では、雇用人材の確保・育成を推進するとともに、農業の労働環境改善を図るため、産地の農業経営体と地方公共団体等で構成される地域協議会等による、昇給制度の導入や作業工程の見直し等による従業員の働きやすさを高める取組を支援しています。
(事例)多様な人材を呼び込み誰もが安心して働ける環境づくりを推進(熊本県)
(1)経営内容の変化に合わせて、働き方改革に挑戦
熊本県益城町(ましきまち)の株式会社みっちゃん工房(こうぼう)は、もともと家族経営により、すいかやにらを栽培していました。平成13(2001)年に女性でも作業しやすいベビーリーフの栽培を開始し、経営規模を拡大する中で、多くの子育て世代の従業員を雇用するようになりました。このような中、出産時に退職する従業員が出始めたことを契機として、生活やライフステージが変化しても、復帰できる体制が必要と考え、働き方改革に取り組んできました。
(2)安心して働ける環境づくりと従業員との信頼関係構築に取組
同社では、従業員が安心して働くことができるようにするために、全従業員の希望に沿った勤務シフトやパート従業員も活用できる育児休業制度、退職金共済への加入、子の看護、介護休業等を導入しました。
また、従業員との信頼関係を築くため、毎年の決算報告会や定期的な面談を行うことで、従業員への情報開示と対話を行う場を設け、売上げに対して経費が削減できていた場合には賃上げを実施することとしました。
このような取組の結果、離職者が減少し、職員の定着が図られたほか、県内外から正社員の求人への応募も増加しています。また、従業員のコスト意識の醸成とモチベーションの向上等により、従業員の労働時間縮減と売上げの増加の両方の実現に成功しました。
(3)従業員との対話により誰もが安心して働ける環境づくりを推進
同社では、新入社員や外国人従業員に対する研修等を通じスキルアップにも取り組んでおり、今後も、性別や国籍に関係なく、それぞれのライフステージに合わせて従業員とのきめ細やかな対話を続けながら、誰もが働きやすい環境づくりを進めていくこととしています。


工場を訪れる育児休業中の従業員
資料:株式会社みっちゃん工房

従業員への決算報告会の様子
資料:株式会社みっちゃん工房
(他産地・他産業との連携等による労働力確保を推進)
農業の現場では、品目や産地に応じて、年間を通じた繁閑期が異なっており、繁忙期における労働力の確保が課題となっています。
農林水産省では、農業者と求職者をマッチングする労働力募集アプリの活用等による労働力確保の取組を支援しています。
また、繁閑期の異なる複数産地で労働者をリレー雇用する取組を支援し、他産地・他産業との連携等による労働力確保を推進しています。
(事例)企業との連携によって農繁期の人手不足を解消(山形県)
(1)農繁期の人手不足解消が課題

山形県天童市(てんどうし)では、おうとうの栽培が盛んですが、収穫やパック詰め等の作業が短期に集中することから、農繁期の労働力不足が課題となっています。このため、同市では、おうとうの収穫や出荷作業等への市職員の副業の許可、他の地方公共団体等との協力による援農ボランティアバスツアーの実施等により、農繁期の労働力確保に取り組んできました。
(2)企業で働く人が農作業に参加する企業連携プログラムを開催して、農繁期の人手不足解消を推進
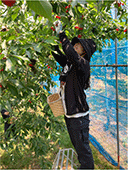
企業連携プログラムによる
おうとう収穫作業の様子
資料:東日本旅客鉄道株式会社
同市では、更なる人手不足の解消に向けて、民間企業従業員の副業等による人材確保にも取り組んでおり、令和6(2024)年度には、東日本旅客鉄道(ひがしにほんりょかくてつどう)株式会社、東日本電信電話(ひがしにほんでんしんでんわ)株式会社、日本郵便(にっぽんゆうびん)株式会社と連携して、企業で働く人の副業・ボランティアによる農作業支援を促進する企業連携プログラムを開催しました。
同プログラムは、1日単位で農業に従事したい人と農業者をマッチングするスマートフォンアプリを活用した民間企業従業員によるおうとう収穫等の農作業と異業種間での合同ディスカッションで構成されており、農繁期の労働力確保を図るとともに、プログラムの参加者が農業に関心を持ち、同アプリを活用するきっかけとなることも期待されています。
(4)外国人材の労働力確保
(農業分野の外国人材の総数は前年に比べ増加)
農村における高齢化・人口減少が進行する中、外国人材を含め生産現場における労働力の確保が重要となっています。
令和6(2024)年における農業分野の外国人材の総数は、特定技能制度の活用が進んだことにより、前年に比べ7千人増加し5万8千人となっています(図表2-6-8)。

データ(エクセル:27KB)
このうち特定技能制度は、人手不足が続いている中で、外国人材の受入れのために平成31(2019)年に運用が開始された制度で、農業を含む16分野(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業)において、「特定技能」の在留資格で一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れています。「特定技能」には在留期間に通算5年の上限がある「特定技能1号」と在留期間の更新に制限のない「特定技能2号」があり、いずれにおいても農業分野は対象となっています。
令和7(2025)年3月に法務省が公表した資料によると、令和6(2024)年12月末時点での農業分野における特定技能在留外国人数は、前年同月末に比べ5,470人増加し、29,331人となりました。
農林水産省では、農業分野における外国人材の確保と適正かつ円滑な受入れに向けて、外国人材の知識・技能を確認する試験の実施や働きやすい環境の整備等を支援しています。
(人材の育成と確保を目的とする育成就労制度が創設)
令和6(2024)年6月に、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成と確保を目的とする育成就労制度が創設されました。
育成就労制度では、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的としており、育成就労外国人の本人意向による転籍を一定要件の下で認めること等により、労働者としての権利保護を適切に図ることとしています。
令和6(2024)年12月には、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の下、「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」を設置し、令和7(2025)年3月に、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針について」が閣議決定しました。農林水産省は、引き続き、主務省庁である法務省及び厚生労働省等の関係省庁と連携し、令和9(2027)年度第1四半期の運用開始に向けて、必要な準備を進めています。
(5)農業金融
(農業向けの新規貸付額は、5年前と比較して減少)
農業向けの融資においては、農協系統金融機関(信用事業を行う農協及び信用農業協同組合連合会並びに農林中央金庫(以下「農林中金」という。))、地方銀行等の一般金融機関が短期の運転資金や中期の設備資金を中心に、公庫がこれらを補完する形で長期・大型の設備資金を中心に、農業者への資金供給の役割を担っています。農業向けの新規貸付額については、平成30(2018)年度と令和5(2023)年度を二時点で比較すると、農協系統金融機関、一般金融機関、公庫ともに減少しています(図表2-6-9)。
農林水産省では、物価高騰等の影響を受けた農業者等が円滑な資金の融通を受けられるよう、金融支援対策を講じています。
また、令和6(2024)年9月には「農林中金の投融資・資産運用に関する有識者検証会」を立ち上げ、検証・分析を行いました。同検証会では、令和7(2025)年1月に報告書を取りまとめ、農林水産省及び農林中金に対し、農林中央金庫法等の改正を含め、農林中金の組織や運用の体制の見直し及び農業出融資の拡大が提言されました。

データ(エクセル:29KB)
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883






