第7節 鳥獣被害対策とジビエ利活用の促進
野生鳥獣による農作物被害は、営農意欲の減退をもたらし耕作放棄や離農の要因になるなど、農山漁村に深刻な影響を及ぼしています。このため、被害防止のために捕獲を進めるだけでなく、有害鳥獣をプラスの存在に変えていくことが重要であり、ジビエ利活用の拡大に向け、より安全なジビエの提供や消費者のジビエに対する安心の確保を図る取組等が必要となっています。
本節では、鳥獣被害対策やジビエ利活用等に向けた取組について紹介します。
(1)鳥獣被害対策の推進
(野生鳥獣による農作物被害額は前年度に比べ増加)
シカやイノシシ、サル等の野生鳥獣による農作物被害額は、平成22(2010)年度の239億円をピークに減少傾向で推移しましたが、令和5(2023)年度は、捕獲強化の取組等によりイノシシ等による被害額が減少したものの、北海道等で被害額が増加したことによりシカの被害額が増加したことや、堅果類の不作等によりクマの出没が増え被害額が増加したこと等から、前年度に比べ8億円増加し164億円となりました(図表6-7-1)。鳥獣種類別に見ると、シカによる被害額が70億円で最も多く、次いでイノシシが36億円、鳥類が27億円となっています。また、令和5(2023)年度のクマ類による農作物被害額は前年度に比べ3億円増加し7億円となりました。

データ(エクセル:29KB)
野生鳥獣の捕獲頭数については、令和5(2023)年度はイノシシが前年度に比べ6万8千頭減少し52万頭となっています(図表6-7-2)。一方、シカの捕獲頭数は前年度に比べ6千頭増加し72万頭となっています。
全国各地で鳥獣被害対策が進められている一方、野生鳥獣の生息域の拡大や荒廃農地の増加等を背景として、鳥獣被害は継続的に発生しています。鳥獣被害は、営農意欲の減退、耕作放棄・離農の増加等をもたらし、被害額として数字に現れる以上に深刻な影響を農山漁村に及ぼしていることも踏まえた、更なる対策の強化を図っていくことが必要です。

データ(エクセル:35KB)
(鳥獣の捕獲強化等に向けた取組を推進)
鳥獣被害の防止に向けては、鳥獣の捕獲による個体数管理、柵の設置等の侵入防止対策、藪(やぶ)の刈払い等による生息環境管理を地域ぐるみで実施することが重要です。このため、鳥獣被害防止特措法(*1)に基づき、市町村による被害防止計画の作成や鳥獣被害対策実施隊の設置・体制強化を推進するとともに、市町村が作成する被害防止計画に基づく鳥獣の捕獲体制の整備、捕獲機材の導入、侵入防止柵の設置、鳥獣の捕獲・追払いや、緩衝帯の整備を推進しています。
令和6(2024)年4月末時点における、被害防止計画の策定市町村数は前年度に比べ1市町村増加の1,518市町村となりました。また、鳥獣被害対策実施隊を設置する市町村数は1,256市町村、同隊員数は4万2千人となっています。農林水産省では、鳥獣被害防止総合対策交付金により、実施隊の活動や地域ぐるみの被害対策を支援しています。
また、捕獲による個体数の管理について、農林水産省では、環境省と連携し、農林業や生態系等に深刻な被害を及ぼしているシカ、イノシシについて、生息頭数を平成23(2011)年度比で令和10(2028)年度末までに半減させることを目標としています。半減目標の達成に向けて、捕獲活動への支援等を通じてシカ、イノシシの捕獲強化を図っているところです。
さらに、シカやイノシシ等は、都府県や市町村をまたいで移動するため、広域的な捕獲の強化に加え、集落点検活動を通じて侵入防止柵の正しい維持管理や放任果樹の除去等といった生息環境管理等の実施を進めるなど、集落や地域が鳥獣被害対策の当事者として主体的に取り組むことが必要です。
クマ類については、令和5(2023)年に人の生活圏への出没や人身被害が増加し、甚大な被害が発生したことを受けて環境省が関係省庁とクマ被害対策施策パッケージを取りまとめました。農林水産省では、クマ類を農地に近付けないための、餌となる柿や栗の実の処分に加え、農地周辺におけるクマ類の捕獲の支援、捕獲技術者の育成・確保の支援等を関係省庁と連携しながら行うこととしています。
くわえて、高齢化が進む捕獲人材の育成・確保に向けて、現場での見学・体験を内容とするセミナーの開催を支援しているほか、狩猟免許取得時の研修・講習や狩猟免許取得後の経験の浅い者を対象としたOJT研修等の実施を支援しています。
今後、野生鳥獣による様々な問題がますます深刻になると懸念される中で、改正基本法では、新たに「鳥獣害の対策」が盛り込まれました。そのため、農林水産省では、ICTの更なる活用や侵入防止柵の広域化等の一層効率的な対策を講じていくこととしています。
*1 正式名称は「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」
(事例)地域住民が主体となったサル被害への対策を展開(京都府)
(1)地域住民が主体となった獣害対策を継続

京都府福知山市(ふくちやまし)の、6集落で地域ぐるみの農地管理を行う川合地域農場(かわいちいきのうじょう)づくり協議会(きょうぎかい)では、サルによる農作物被害を防止するため、地域住民が主体となった対策を長期にわたり継続するとともに、ICT機器等を効果的に活用し、被害の軽減と個体数管理に成功しています。
(2)当事者意識の共有による体制構築とICT等の活用

受信機でサルの群れを追跡
資料:川合地域農場づくり協議会
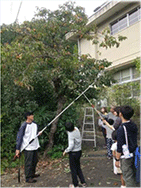
放置かきのもぎ取りイベント
資料:川合地域農場づくり協議会
川合地区(かわいちく)では、平成15(2003)年頃からサルによる農作物被害が発生し、電気柵による圃場(ほじょう)の防除を行っていましたが、平成28(2016)年には人家への侵入等の生活環境被害も発生しました。
同協議会では、地区内で発生するサル被害に対し、地域内での話合いを通じた目標の設定と共有を行うことで、被害の有無に関係なく当事者意識の共有を図り、地域ぐるみの対策を実施しています。主な対策は、住民参加型の組織的な「追払い」、電気柵による「防除」、群れの数を一定数に維持するための「捕獲」を3本柱としており、近年では、サル位置情報共有システムや遠隔で監視・捕獲が可能なICT捕獲わなの活用、電柵電圧遠隔管理システムの導入により、取組の効率化を図っています。
このような取組の結果、令和4(2022)年度のサルによる被害金額は、令和元(2019)年度の約40万円から約2万7千円まで減少しました。
(3)地域づくりの手段として、獣害対策を展開
同協議会では、「獣害対策を継続して行うには、楽しみながら取り組むことが重要」としており、取組の一環として、地域内の廃校をキャンプ場として活用し、キャンプ場利用者を対象にサルやクマの誘引物となる放置かきのもぎ取りイベントを実施しています。
今後とも、「川合がいつまでも川合であるために」を合言葉に、持続可能な地域づくりの一環として、引き続き獣害対策に取り組んでいくこととしています。
(2)ジビエ利活用の拡大
(ジビエ利用量は前年度に比べ増加)
食材となる野生鳥獣肉のことをフランス語でジビエ(gibier)と言います。我が国では、シカやイノシシによる農作物被害が大きな問題となる中、これらの捕獲が進められるとともに、ジビエとしての利用も全国的に広まっています。害獣とされてきた野生動物も、ジビエとして有効利用されることで食文化をより豊かにしてくれる味わい深い食材となり、あるいは、農山村地域を活性化させ、農村の所得を生み出す地域資源となります。捕獲個体を無駄なく活用することにより、外食や小売、学校給食、ペットフード等の様々な分野においてジビエ利用の取組が広がっています。
令和5(2023)年度のジビエ利用頭・羽数は、シカが最も多く12万1千頭で66%を占めており、次にイノシシが4万頭となっています(図表6-7-3)。
また、令和5(2023)年度のジビエ利用量は、新型コロナウイルス感染症の影響による需要の落込みから回復したこと等から、前年度に比べ30.9%増加し2,729tとなりました(図表6-7-4)。ペットフード向けは、ジビエ利用量の約3割を占める866tまで増加しており、このほか、動物園では肉食獣の餌に利用されるなど、新たな試みも見られています。
(コラム)ジビエ給食の取組が拡大
全国各地で野生鳥獣による農業被害が生じている中、教育現場と地域社会が連携し、鳥獣被害防止対策の理解促進、地産地消・食育の推進、食文化の継承、農山村に対する関心の向上等を図る取組として、学校給食でジビエを提供する動きが広がりを見せています。
令和5(2023)年度にジビエを給食で提供する小中学校は946校となり、平成28(2016)年度の約2.5倍に増加しており、ジビエ活用校のある市町村は95市町村となっています。

ジビエ(イノシシ肉)を
利用したふるさと給食
資料:大分ジビエ振興協議会
大分県では、学校給食でのジビエ利用の定着や食育の推進を図るため、県内の小中学校においてジビエ食材の提供や栄養士・PTA等への説明会、子供が食べやすいメニュー開発等を進めています。また、県や市町村、猟友会、23の処理加工施設等が連携し、捕獲から搬送・集荷、処理加工、販売を地域一体で取り組む体制を構築し、学校給食を始めとした需要拡大を進めるとともに捕獲圧の強化に取り組んでいます。
農林水産省では、ジビエの利活用推進に向け、捕獲・処理加工・供給・消費の各段階において、利活用推進に必要な取組や課題を共有し、関係者が一体となって取り組むこととしています。
(外食産業・宿泊施設や小売業者向けのジビエ販売数量が増加)
食肉処理施設からのジビエ販売数量については、令和5(2023)年度は消費者への直接販売が前年度に比べ減少した一方、卸売業者や外食産業・宿泊施設、小売業者向けの販売数量は増加しました(図表6-7-5)。

データ(エクセル:27KB)
ジビエの利用拡大に当たっては、より安全なジビエの提供と消費者のジビエに対する安心の確保を図ることが必要です。このため、農林水産省では、国産ジビエ認証制度に基づき、厚生労働省のガイドラインに基づく衛生管理の遵守やトレーサビリティの確保に取り組むジビエの食肉処理施設を認証しています。令和7(2025)年3月末時点の認証施設数は30施設となっており、認証施設で処理されたジビエが大手外食事業者等によって加工・販売され、ジビエ利用量の拡大につながる事例も見られています。
また、捕獲個体をジビエ利用に適した状態でより広域的にジビエ処理施設に搬入できるよう、農林水産省では、解体機能を有する車両等の広域搬入機器の開発支援を行いました。こういった機器が各地域の地理的条件等に合わせて導入されることで、更なるジビエの利用拡大が期待されます。
くわえて、需要喚起のためのプロモーション等に取り組んでおり、ポータルサイト「ジビエト」では、ジビエを提供している飲食店等の情報を掲載しています。また、令和6(2024)年11月から令和7(2025)年2月において、全国ジビエフェアを開催し、特設ウェブサイトにてジビエメニューを提供する全国の飲食店等を紹介しました。

ジビエト
URL:https://gibierto.jp/
(ジビエハンター育成研修制度の取組を推進)
有害鳥獣を捕獲しても、捕獲の方法によってはジビエに適さないため、捨てられてしまうケースもあることから、そのような個体を減らすことが必要です。このため、農林水産省では、ハンターがジビエに適した捕獲方法等の知識を学べるジビエハンター育成研修制度を令和5(2023)年度から開始し、令和6(2024)年度まで21回の研修を開催し、704人が受講しました。
また、近年ペットフードへの利用も注目される中、ペットフード原材料としてのジビエについても安全の確保が必要となっています。農林水産省では、令和6(2024)年3月にジビエペットフード製造や原料の衛生的管理等を整理したマニュアルの改訂版を作成し、処理施設等に周知しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883






