第8節 都市と農村の交流による農村関係人口の創出と移住の促進
我が国では人口減少が続いていますが、このような状況下においても、農村の地域コミュニティを維持することが求められています。そのためには、農業体験や都市農業等を通じ、都市住民と農業・農村との交流を深めることにより、農村に関心と関わりを持つ「農村関係人口」を創出・拡大するとともに、都市から地方への移住・定住につなげていくことが不可欠です。
本節では、農村関係人口の創出・拡大、移住・定住の促進や都市農業等の取組について紹介します。
(1)農村関係人口の創出・拡大
(農村と関わりを持っている人は約6割)
内閣府が令和5(2023)年9~10月に実施した世論調査によると、農村との関わりについて、「農村地域との関わりを持っていない」と回答した人は約4割となっており、約6割が何らかの関わりを持っていることがうかがわれます(図表6-8-1)。また、今後の農村との関わり方として、「農村地域の特産品の購入をしたい」と回答した人が約5割となっています。

データ(エクセル:29KB)
(農村関係人口の裾野拡大に向けては複線型アプローチが必要)
農村関係人口については、「農村への関心」や「農村への関与」の強弱に応じて多様な形があると考えられ、徐々に段階を追って農村への関わりを深めていくことで、農村の新たな担い手へとスムーズに発展していくことが期待されます。しかし、このような農村への関わり方やその深め方は、人によって多様であることから、農村関係人口の拡大に向けては複線型アプローチが重要となっています(図表6-8-2)。

例えば農泊や農業体験で農村に触れた都市住民が、援農ボランティアとして農村の仕事に携わるようになり、二地域居住を経て、最終的には就農するために農村へ生活の拠点を移すケース等が想定されます。
また、主に都市に住む小・中学生が農山漁村へ留学する「山村留学(さんそんりゅうがく)」の人数が、令和5(2023)年度は前年度に比べ減少して632人となったものの、近年は再び増加傾向にあります(図表6-8-3)。理由としては、受入れを始める学校が増えたこと、実績がある地域に安定的に参加者が集まっていることや、子供単身ではなく家族とともに留学するケースが増えたこと等が考えられます。留学を終えた子供たちが留学先の農村と継続的に関わりを持つことで、農村関係人口の増加につながることも期待されます。
さらに、都市と農村の交流によって農村関係人口を増加させ、農村における農産物・食品等の特産品の消費拡大や地域の共同活動への参加を促し、集落機能を補完する取組を進めることも重要です。
農林水産省では、農村関係人口を増加させるため、従来の都市と農村の交流に加え、農業・農村が有する様々な資源を活用して、二地域居住や農泊等を推進することとしています。

データ(エクセル:34KB)
(事例)地域ぐるみの農泊普及により、関係人口の創出・拡大を推進(栃木県)
(1)約180軒の農家へ農泊を斡旋


古民家を改修した農泊施設
資料:株式会社大田原ツーリズム
栃木県大田原市(おおたわらし)の株式会社大田原(おおたわら)ツーリズムは、同市を中心とした周辺4市町で農泊を推進しています。
同社は、グリーン・ツーリズムを推進する同市と地元の民間団体が共同出資する形で、平成24(2012)年に設立され、農泊の受入れを希望する約180軒の農家の窓口を務めているほか、体験プログラムの企画・提供を行っています。
農業が盛んで観光収入が少ない地域において、同社がまず取り組んだ事業は、農業体験を中心とした団体向け教育旅行の受入れでした。この取組では、100を超えるプログラムを用意し、付加価値を付けるとともに、農家向けのマニュアル作成・配布や勉強会の定期開催等の農家のサポート体制を構築することで、旅行者の満足度向上に取り組み、リピーターの獲得を図っています。
(2)個人旅行客向けの農泊を開拓
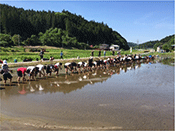
田植え体験
資料:株式会社大田原ツーリズム
これまで同社が斡旋(あっせん)してきたのは、学生等の団体旅行客向けがほとんどでしたが、令和5(2023)年度からは個人旅行客を誘致する取組に力を入れています。農家の敷地内の自宅の蔵や古民家等の改修により、個人旅行客が宿泊しやすい施設の整備を農家に促すことで、農泊の更なる普及、ひいては関係人口の増加と地域のブランド力向上を目指しています。
同社を通じた延べ宿泊数は、令和5(2023)年度には約9,400人泊に達し、農泊による関係人口の創出・拡大に加え、地域経済の活性化にも貢献しています。
(事例)関係人口の創出・拡大で持続可能な地域社会づくりを推進(岐阜県)
(1)関係人口の創出・拡大で地域課題を解決


「ヒダスケ!-飛騨市の
関係案内所」参加者
資料:岐阜県飛騨市
岐阜県飛騨市(ひだし)は、令和2(2020)年度から困りごとを抱えた同市民と、地域の手伝いをしたい人をウェブサイト上でマッチングする「ヒダスケ!-飛騨市の関係案内所」というサービスを始めています。同サービスには、農作業や景観保全、イベント運営といった、様々な分野で外部の人材を呼び込み、地域との関係づくりを推進する狙いがあります。
同サービスの参加人数は、令和5(2023)年度に延べ3千人を超え、そのうち7割が中京圏や首都圏等の市外から来訪しています。
高齢化率が4割に達し人口減少が続く同市では、農繁期における農作業の担い手を確保できず、農業生産に支障が出るなどの課題が顕在化していますが、同サービスによって農繁期の人員を確保できたことから、一部にはトマト等の農作物を増産する農家が現れるといった成果が出てきています。
(2)移住を希望しない都市住民を呼び込む

河川清掃の様子
資料:岐阜県飛騨市
令和2(2020)年12月に同市が東京大学等と発表した関係人口に関する研究によると、地域の関係人口の中には、将来的に移住を希望する層より、移住を希望しない層の方が多いことが分かっています。そのため、同市では、関係人口の創出・拡大には移住促進とは異なるアプローチが必要との認識に立ち、関心・愛着が高い順に、「行動人口」、「交流人口」、「関心人口」の三つに分類し、「行動人口」に対しては「ヒダスケ!-飛騨市の関係案内所」、「交流人口」に対してはイベント交流等を促す「飛騨市ファンクラブ」、「関心人口」に対してはふるさと納税といった取組を行っています。
(子供の農山漁村交流を推進)
内閣官房・内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省及び環境省は、都市部の子供たちが農山漁村に宿泊しながら農林漁業体験や自然体験活動等を行う「子ども農山漁村交流プロジェクト」に取り組んでいます。同プロジェクトは、子供たちの学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識等を育み、力強い成長を支える教育活動として、農山漁村での宿泊体験活動を推進し、都市部と地方の子供たちの交流を通じて、都市と農山漁村の相互理解を図るものです。
農林水産省では、農泊地域等の受入れ側(農山漁村)の推進体制整備や体験メニューの磨き上げ、交流施設等の整備に係る支援を行っています。
(ワーケーション需要に応じた環境整備を支援)
リモートワークが普及する中、時間や場所にとらわれない働き方として「ワーケーション(*1)」が注目されています。近年、企業がワーケーションの滞在先として地方の農山漁村を選ぶケースが増えており、地方公共団体としても農山漁村を受入れ地域として積極的にワーケーションを誘致することで、地域の活性化を図ろうとする動きが活発になっています。
国土交通省の調査によると、従業員100人以上の企業におけるワーケーション制度の導入率については、令和6(2024)年は前年に比べ4.3ポイント低下し、12.7%となっています(図表6-8-4)。ただし、同調査では、ワーケーション制度の導入を検討している企業の割合は18.3%となっており、引き続き関心の高さがうかがわれます。

データ(エクセル:24KB)
また、ワーケーションの導入・利用推進のため、受入れ地域や施設に対して希望する環境やサービスについては、「セキュリティやスピード面が確保されたWi-Fi等の通信環境」が54.9%で最も多く、次いで「入退室管理やシュレッダーなどのセキュリティ対策」となっています。
農林水産省では、農泊に取り組む地域におけるワーケーション需要に対応するため、施設の改修、無線LAN環境の整備、オフィス環境の整備等を支援しています。
*1 「ワーク(仕事)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせたもので、観光地やリゾート地や帰省先等でパソコン等を使って仕事をすること
(2)移住・定住、二地域居住の促進
(農村への関心の高まりを背景として、地方移住の相談件数は増加傾向)
認定NPO法人ふるさと回帰支援(かいきしえん)センター(*1)は地方暮らしやUIJターンを希望する人のための移住相談を行っており、同センターへの相談件数は近年、増加傾向で推移しています。令和6(2024)年は前年に比べ4.1%増加し、過去最高の6万1,720件となりました(図表6-8-5)。

データ(エクセル:28KB)
内閣官房・内閣府は、地方への移住・定住を促進するため、東京23区に在住又は通勤する人が、東京圏(*2)外又は東京圏のうち条件不利地域(*3)の市町村へ移住し、地域の中小企業への就業や社会的起業等をする場合に、地方公共団体が行う取組を支援しており、令和7(2025)年度から農林水産業等への就業も新たに支援対象となることから、農業・農村への人の流れの後押しとなることが期待されます。また、総務省は、就労・就農支援等の情報を提供する「移住・交流情報ガーデン」の利用を促進しています。
*1 正式名称は「特定非営利活動法人100万人のふるさと回帰・循環運動推進・支援センター」
*2 条件不利地域を除く東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
*3 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法等において規定される条件不利地域を有する政令指定都市を除く市町村等
(改正広域的地域活性化法が施行)
生活拠点の地方への移動に当たっては、UIJターンのみならず、都市・地方の二地域又は多地域居住(以下「二地域居住等」という。)という選択肢もあります。国土交通省が令和4(2022)年8~9月に実施したアンケート調査に基づく推計によると、我が国の18歳以上の人口の約6.7%に当たる約701万人が二地域居住等をしていると推察されます(図表6-8-6)。また、二地域居住等をしていない者を対象にした調査では、約3割が二地域居住等に関心があると回答しました(図表6-8-7)。
このような状況を踏まえ、都市部の企業等が地方に遠隔勤務のためのオフィスである「サテライトオフィス」を開設し、本社機能の一部移転や二地域居住のワークスタイルを実践するケースが増えており、地方においても雇用機会の創出や移住・定住の促進、新しい産業の創出に向けて、サテライトオフィスの誘致に取り組む地方公共団体が増えています。
二地域居住等を推進するため、国土交通省は令和6(2024)年11月に改正広域的地域活性化法(*1)を施行し、市町村が二地域居住等の促進のための計画を策定することで、住宅、コワーキングスペース、交流施設等の二地域居住等に必要な環境整備に係る支援を受けやすくなるようにしました。
また、同年10月、地方公共団体や多様な民間事業者で構成され、二地域居住等の促進に係る様々な施策・事例の情報交換、課題の整理や対応策の検討・提言等を行う「全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム」が発足しました。国土交通省は、これと連携しつつ、二地域居住等の機運を醸成することとしています。
農林水産省としても、農山漁村における二地域居住等の推進は、地域の活性化や課題の解決に有効な取組であるとして、受入れに向けた環境整備や定住・交流を促進するための施設整備等を支援しています。
*1 正式名称は「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」
(3)農村の魅力の発信
(棚田地域振興法に基づく指定棚田地域は733に拡大)
棚田を保全し、棚田地域の有する多面的機能の維持増進を図ることを目的として、棚田地域振興法が令和元(2019)年に制定され、同法に基づき、都道府県、市町村、農業者や地域住民等の多様な主体が参画する指定棚田地域振興協議会による棚田を核とした地域振興の取組を、関係府省横断で総合的に支援する枠組みを構築しました。
令和6(2024)年度までに、同法に基づき累計で733地域が指定棚田地域に指定されたほか、指定棚田地域において同協議会が策定した認定棚田地域振興活動計画は累計で200計画となっています。

つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanadasen.html
これらの地域では、耕作放棄地の再生や都市農村交流等に取り組み、棚田地域の活性化が図られた事例があるなど一定の効果が出ています。
同法は時限立法であり、令和7(2025)年3月末に期限を迎えることから、同法の期限を5年間延長するとともに、農業振興や鳥獣被害防止等の棚田地域振興に必要な事項を配慮規定として定めることとした「棚田地域振興法の一部を改正する法律」が第217回通常国会において議員立法により成立し、令和7(2025)年3月に公布されました。
また、令和4(2022)年から開始した「つなぐ棚田遺産」の認定を機に、棚田地域における企業連携を積極的に推進していくことを目的として創設した「つなぐ棚田遺産オフィシャルサポーター制度」において、棚田地域の振興に関する取組を行う企業・団体等を公式にサポーターとして認定しており、令和7(2025)年3月末時点で43の企業・団体等が認定されています。
(日本農業遺産に新たに4地域が選定)
日本農業遺産は、我が国において重要かつ、伝統的な農林水産業を営む地域を農林水産大臣が認定する制度であり、令和7(2025)年1月に新たに兵庫県北播磨(きたはりま)・六甲山北部(ろっこうさんほくぶ)地域、兵庫県朝来(あさご)地域、徳島県県南(けんなん)地域及び沖縄県多良間(たらま)地域が認定され、認定地域数は28となりました。
また、世界農業遺産は、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業システムをFAOが認定する制度であり、国内の世界農業遺産認定地域は15地域となっています。
令和5(2023)年度からは、農業遺産地域の魅力を広く発信し、地域活性化を図る取組の一環として、農業遺産地域の高校生による、複数の農業遺産地域の産品を使った食品のアイデアを競う「高校生とつながる!つなげる!ジーニアス農業遺産ふーどコンテスト」を開催しています。

兵庫県北播磨・六甲山北部地域

兵庫県朝来地域

徳島県県南地域

沖縄県多良間地域
(世界かんがい施設遺産に新たに3地域が登録)
世界かんがい施設遺産は、歴史的・社会的・技術的価値を有し、かんがい農業の画期的な発展や食料増産に貢献してきたかんがい施設をICID(*1)(国際かんがい排水委員会)が認定・登録する制度であり、令和6(2024)年9月に、我が国で新たに南原穴堰(みなみはらあなぜき)(宮城県大崎市(おおさきし))、龍ケ池揚水機場(たつがいけようすいきじょう)(滋賀県豊郷町(とよさとちょう))及び西光寺野疏水路(さいこうじのそすいろ)(兵庫県姫路市(ひめじし)等)の3施設が登録され、国内登録施設数は54施設となりました。
農林水産省では、世界かんがい施設遺産の活用を通じた登録地域における地域活性化の取組を推進するとともに、ICID及びINWEPF(*2)(国際水田・水環境ネットワーク)において、諸外国に向けてかんがい技術の重要性や水田農業の有する多面的機能に関する情報発信を行っています。

南原穴堰(宮城県大崎市)

龍ケ池揚水機場(滋賀県豊郷町)

西光寺野疏水路(兵庫県姫路市等)
*1 International Commission on Irrigation and Drainageの略
*2 International Network for Water and Ecosystem in Paddy Fieldsの略
(「ディスカバー農山漁村の宝」に27団体と3人を選定)
「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」は「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に向け、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことによる地域活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例を選定し、全国へ発信することにより、他地域への幅広な展開を図る取組です。
第11回目となる令和6(2024)年度には、全国から27団体と3人を選定し、選定数は累計で345件となりました。
農林水産省では、選定された地区の活動を「ディスカバー農山漁村の宝」特設ウェブサイト等で紹介し、情報発信を行うことにより、農山漁村地域の活性化に対する国民の理解の促進を図るとともに、農山漁村の雇用・所得の創出・向上を推進します。

そば文化の継承を図る取組
(「ディスカバー農山漁村の宝」(第11回
選定)のグランプリ受賞)
資料:北海道幌加内高等学校

「ディスカバー農山漁村の宝」
URL:https://www.discovermuranotakara.com
(4)都市農業の推進
(約65%の都市住民が都市農地を残していくべきと回答)
都市農業は、都市という消費地に近接する立地特性を背景に、新鮮な農産物の供給に加えて、農業体験・学習の場や災害時の避難場所の提供、都市生活の安らぎ提供といった多様な機能を有しています。

データ(エクセル:23KB)
また、東京都の「江戸東京野菜」を始めとして、地域で歴史的に栽培されてきた野菜等の品種を復活させて名産品として売り出していくなど、各地域の特色を活かした農業生産も行われています。
都市農業が主に行われている市街化区域内の農地の面積は、我が国の農地面積全体の1.3%である一方、農業経営体数と農業産出額ではそれぞれ全体の12.4%、6.5%を占めており、消費地に近いという条件を活かした、野菜を中心とした農業が展開されています。
さらに、令和6(2024)年11月に都市住民を対象に実施したアンケート調査によると、64.9%が都市農地を残していくべきと回答しており、都市農業の多様な役割を評価している住民が多いことがうかがわれます(図表6-8-8)。
農林水産省では、都市住民と共生する農業経営の実現のため、農業体験や農地の周辺環境対策、防災機能の強化等の取組を支援することにより、多様な機能を有する都市農業の振興に向けた取組を推進しています。
(都市農地貸借法に基づき貸借された農地面積は拡大傾向)
生産緑地制度(*1)は、良好な都市環境を形成するため、市街化区域内の農地の計画的な保全を図るものです。市街化区域内の農地面積が一貫して減少する中、生産緑地地区(*2)の面積はほぼ横ばいで推移しており、令和5(2023)年の同面積は前年並みの1万2千haとなっています(図表6-8-9)。
また、都市農業の振興を図るため、意欲ある農業者による耕作や市民農園・体験農園の整備等による都市農地の有効活用も促進しています。農地所有者が、意欲ある農業者等に安心して農地を貸付けすることができるよう、都市農地貸借法(*3)に基づき貸借が認定・承認された農地面積については、令和5(2023)年度は前年度に比べ15.3%増加し、117haとなりました(図表6-8-10)。
農林水産省では、都市農地貸借法の仕組みに基づく制度の円滑かつ適切な活用を通じ、貸借による都市農地の有効活用を図ることとしています。
*1 三大都市圏特定市における市街化区域農地は宅地並に課税されるのに対し、生産緑地に指定された農地は軽減措置が講じられる。
*2 市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している原則500㎡以上の農地
*3 正式名称は「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」
(事例)地域密着型の特色ある都市農業を展開(東京都)
(1)都市農地を借り入れて新規就農


ネイバーズファームの圃場
資料:株式会社ネイバーズファーム
東京都日野市(ひのし)の株式会社ネイバーズファームは、消費地に近い都市農地ならではの特徴を活かし、地域密着型の農業を行っています。
同社代表の梅村桂(うめむらけい)さんは、平成30(2018)年の都市農地貸借法の施行を受け、平成31(2019)年3月に同市内の農地を借りて新規就農しました。これまでに同市内で合計三か所の農地を借り入れており、3棟の園芸用ハウスでのトマト栽培のほか露地野菜も栽培し、圃場に併設した自動販売機や地域の直売所における直販や近隣の飲食店等への販売を行っています。
(2)トマトの「フェス」で町おこし

「ひのトマトフェス」の会場
資料:株式会社ネイバーズファーム
もともと同市ではトマトの栽培が盛んでしたが、農家の高齢化や畑の宅地化が進んだことで、トマト農家の数も減っていました。そこで、同社では「トマトで日野をブランド化する」ことを目指し、トマトやその加工品等を販売するイベント「ひのトマトフェス」を主催しています。
令和6(2024)年4月に第3回目を迎えた同イベントには、同市等の都内のトマト農家のほか、地場の飲食店やビール醸造所等にも出店を依頼し、生のトマト以外にも、ビールやシェイクといったトマトを使った加工品を来場者に提供しました。同社のアンケート調査によると、来場者の7割が同市民で、地域住民との交流を推進する重要な機会となっています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883









