
2 豆の力で地域を元気に!
日本で流通している豆は約50種類にも及び、各地でさまざまな豆が栽培されています。今回は北海道の「白花豆」、山梨県の「あけぼの大豆」というふたつの特色ある豆の魅力と、それらを活用した地域おこしについて取材しました。

豆の女王と呼ばれる「白花豆」
「白花豆」は、インゲンマメ属ベニバナインゲンの一種。成長すると白く可憐な花を咲かせ、また、豆自体もきれいな純白であることから、明治時代までは観賞用として栽培されていたそうです。その美しさを讃えて「豆の女王」と呼ばれています。ベニバナインゲンの一種である白花豆の茎は、つる性で支柱の設置や支柱に巻きつくように誘引作業を行うため、機械化が困難で栽培はほとんどが手作業。そのため大量生産が難しく、虎豆、大福豆などとともに高級菜豆(こうきゅうさいとう)と総称されています。また、低温を好み、温暖地では花が咲いても結実しないため、北海道を中心とした冷涼な地域で栽培されており、なかでも北見市留辺蘂町は日本一の生産量を誇ります。

上品な香りと豆本来の甘さがあり、和菓子の白餡や甘納豆に使用されるのが一般的ですが、アヒージョやマリネにしてもおいしく食べられます。豆自体に鉄分やたんぱく質、食物繊維などが含まれていて、栄養価が高いのも魅力です。
生産量日本一までの道のり
かつて二ホンハッカの産地として名を馳せた北海道北見市ですが、安価な輸入ハッカや合成ハッカに押されて産業は衰退。新たな農作物を模索していましたが、北見市は表土が浅く石が多い地質のため、他の作物が育ちにくいという問題がありました。そこで研究されたのが、冷涼な土地で育つ「白花豆」の栽培。地域の人々が一体となって生産技術を磨き、やがて北見市は白花豆の生産量日本一となりました。現在では農業者だけでなく、さまざまな産業の人々が力を合わせて白花豆の魅力をPRし、その評判は道外にも広がりつつあります。
今回教えてくれたのは
監修者プロフィール
るべしべ白花豆くらぶ 会長
森谷 裕美さん
農業生産法人 (株)森谷ファーム代表取締役。2015年1月、白花豆の消費拡大と地域の活性化を目的として発足した「るべしべ白花豆くらぶ」の初代会長に選出。料理、植栽、観光の3つの分野で白花豆の普及に尽力している。

白花豆の普及活動
白花豆を使ったアイデア料理を募集した「白花豆料理コンテスト」の開催や、解説書付きの白花豆の種を配布する植栽活動、毎年開催している「おんねゆマルシェ」で白花豆のオリジナルスイーツを提供するなど、当クラブではさまざまな普及活動を行っています。

当クラブの最大の強みは、農業従事者だけでなく、酪農、観光業、商工会議所、レストラン、菓子店など多業種の人材が集まっていることにあります。会員の誰かが「こういうことをやってみたい」と考えれば、実現するためのアイデアが各方面から集まるため、白花豆を使った商品の制作や、イベントの開催がスムーズに行えます。
白花豆は生産に手間がかかる分、「おいしく育った豆を少しでも多くの方に食べてもらいたい」という思いを、会員の誰もが抱いています。これからも絶え間なく地道に活動を続けることで、いずれは「丹波の黒豆」のように、「北見の白花豆」がひとつのブランドになることを願っています。
豆を育てる苦労、食べる魅力
白花豆の栽培で大変なのは、機械による効率化が困難なところです。3メートル以上もつるが伸びるため、それを支える「女竹」の設置が必須であり、竹を設置する作業、つるを巻く作業、刈る作業などすべて手作業で行わなくてはなりません。

白花豆のつる刈り作業を行う。つる刈りは支柱に巻きついたつるの付け根を刈る作業。中腰状態で作業するためとても大変です。

畑撮影協力:児玉友和さん
収穫の大変さを体験

当クラブでは、地元産業についての教育の一環として、地元の中学校や高校の要請に応じ、白花豆の収穫体験を行っています。中腰になる作業が多いため慣れない作業に子ども達は苦労をしますが、「楽しかった」との感想も。2021年度には収穫体験だけでなく、種まきから収穫までのひと通りの作業を地元高校生に体験してもらう予定です。
白花豆のおいしさが詰まった人気の商品

○白花豆のドライパック「ゆで白花豆」
白花豆を食べるには、前日から豆を水に浸して、水を入れ替えながら丁寧に茹でるといった手間のかかる作業が必要になりますが、もっと気軽に、若い世代の方にも食べてもらいたいという思いから、「ゆで白花豆」は誕生しました。この商品ならそのままでも食べられ、すぐに料理に活用できます。
○白花かすてら
生地には白花はちみつを使ったふじや菓子舗のカステラで、中には白花豆の餡が入っています。上品で爽やかな甘味を感じられます。
このほかにも、大雪庵の「白花豆ダックワーズ」、種田養蜂場の「白花豆蜂蜜」や、レストランエフで販売している「白花豆プリン」などの商品を開発し、白花豆の消費拡大に向けてPR活動を行っています。
るべしべ白花豆くらぶがおすすめする
白花豆レシピ
シニア野菜ソムリエ 吉川雅子さん監修
白花豆のアヒージョ

材料(2人分)
作り方
にんにくは薄切りにする。エビは背わたを取る。
鍋にパセリ以外のすべての材料を入れて20分ほど弱火にかける。
仕上げにみじん切りにしたパセリをふる。
山梨の幻の大豆「あけぼの大豆」

山梨県といえば日本有数の果樹産地として有名ですが、南巨摩郡は豆類の作付けが多く、古くから大豆の栽培が行われてきました。とりわけ身延町曙地区で生産されていた大豆は、明治初期には流通されていたことが記録として残っています。1970年頃からは、枝豆としても市場に出荷されるようになり、その頃から「あけぼの大豆」という名称で呼ばれるようになりました。
同地区は標高300メートルから700メートルと高低差が大きい急峻な地形で、昼夜の寒暖差が大きく霧が多く発生します。また、礫岩質の土壌で水はけが良いことも特徴です。こうした気象条件の同地区でのみ生育するあけぼの大豆は、希少性の高さから“幻の大豆”と呼ばれています。白大豆の中では最大級の大きさであり、甘味が強いのが特徴。枝豆は茹でた後に味付けしなくてもうま味を味わうことができます。
あけぼの大豆の特徴

ほかの大豆との明確な違いは大きさと甘さです。一般的に大粒大豆とされる基準は7.9ミリメートル以上ですが、あけぼの大豆の大きさは一般的な大粒大豆より大きい9.5ミリメートル以上と規定されています。重さも百粒重で約67.6グラムと非常に重みがあります。そして、あけぼの大豆の全糖含有量は100グラムあたり約11.4グラムと、一般的な大豆と比べて約1.2倍であり、甘味が強いのも特徴です。このため、味噌に加工すると、深いコクを味わうことができます。
あけぼの大豆は極晩成であり、6月中旬から7月上旬に種まきを行い、収穫は枝豆が10月、大豆は11月下旬から12月中旬と、ほかの大豆と比べておよそ1カ月の違いがあります。
良質なあけぼの大豆を
生み出す苦労

品質の良いあけぼの大豆を生み出し続けるためには、種の品質を保つことが重要。種用の大豆を選別する際には、紫斑病などの病気にかかっていないか、種にシワがないかなどを一粒一粒目視で確認しています。楕円形をしているため、普通に転がすだけでは異常を見逃す場合があり、確認には大変な労力を要します。栽培においては、さる、しか、うさぎなどの獣害や天候不順の影響を受けることも多いですが、長年の経験をもとに対策を重ねて、生産量を確保しています。
今回教えてくれたのは
監修者プロフィール
あけぼの大豆生産農家
在来種曙大豆保存会 代表理事
河西 勝さん
「食べていただいた人が笑顔になることが最大の喜び」という思いのもと、有機農法にこだわり、あけぼの大豆の品質保持に貢献。良質なあけぼの大豆の種の生産の中心的な役割を担っている。
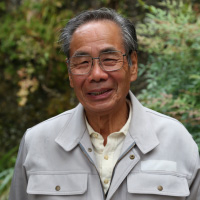
あけぼの大豆で行う町おこし
現在身延町では地域の活性化のため、特産品であるあけぼの大豆の6次産業化を目指し、あけぼの大豆の生産量向上や、販売促進、加工品の開発、PR活動などに取り組んでいます。

生産性を向上させるために、遊休農地を試験圃場として活用した栽培特性の調査・研究や、農機具の整備や貸し出しによる栽培工程の省力化・機械化、県外からの移住者の募集などを行っています。また、あけぼの大豆の素材の良さを活かした加工品の開発などを行うことで、あけぼの大豆の販売促進につなげています。毎年10月下旬に産地フェアを開催し、収穫体験や直売会を実施しています。フェアには毎年約2週間で3,000人から4,000人が来場するほどのにぎわいであり、あけぼの大豆と身延町のPRにつながっています。
今回教えてくれたのは
監修者プロフィール
身延町あけぼの大豆振興協議会 会長
望月 悟良さん
曙地区の名産あけぼの大豆を町全域に拡げるために、遊休農地増加を食い止める活動に尽力。高齢化が進むなか、生産者の意欲を保ちつつ、新たな生産者を募って農地を荒廃させないよう活動を行っている。
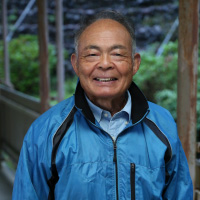
あけぼの大豆を使った
町の取り組み

廃校になった小学校の空き校舎を整備した「身延町あけぼの大豆拠点施設」を活用し、味噌や総菜など、あけぼの大豆を使用した加工品の製造を行っています。また、農家の方の負担を少しでも軽減するため、校舎の倉庫に農機具を置き、貸し出しも行っています。あけぼの大豆の6次産業化に向けたこのような取り組みは、平成28年度より、「身延町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の柱の1つとして、地域の雇用創出にもつながっています。

身延町公式オンラインショップ
「あけぼの大豆Online」

もともと県内では人気が高いあけぼの大豆ですが、全国的に知名度を上げるべく、2019年度からは「あけぼの大豆Online」というオンラインショップを立ち上げました。同サイトでは、以前から人気がある枝豆や味噌だけでなく、専属のシェフに依頼して開発した「極上枝豆シュウマイ」や「極上七宝煮」などの冷凍食品も展開しています。
あけぼの大豆で作った「極上味噌」

あけぼの大豆は甘味が強く、味噌にすることで濃厚なうま味が楽しめます。発酵や熟成に欠かせない麹には高品質な県内甲府市の老舗の麹を使用。糖度の高さにあわせて、米麹と麦麹を独自の割合でブレンドして作り上げた味噌は、販売から短期間で完売するほどの高評価を得ています。
今回教えてくれたのは
監修者プロフィール
地域おこし協力隊
浅野 秀人さん
身延町の魅力に惹かれ、2019年に横浜市から移住。あけぼの大豆の魅力を全国に広げるべく、広報活動やあけぼの大豆OnlineのSEO対策などに取り組む。あけぼの大豆に関する知識を新たに移住してきた方に伝えていくことを目標に活動中。
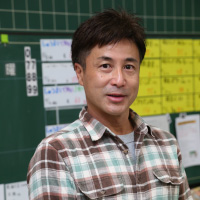
(PDF : 644KB)

この特集の記事はこちらから
編集後記
あけぼの大豆の生産地、山梨県身延町曙地区には、10月中旬に取材で伺いました。ちょうど枝豆の収穫時期で、畑にはあけぼの大豆の枝豆が立派に実っていました。枝豆を活用したポタージュやシュウマイなどの加工品も人気で、リピーターも多いのだそう。しかし、生産の過程では、記事でも紹介した種子の選定作業や、急峻な土地での手作業による苗の移植作業など、苦労も絶えないそうです。質の高いあけぼの大豆をつくるための生産者の方々の多大な努力を改めて感じました。取材にご協力頂き、本当にありがとうございました。(広報室AY)
記事の感想をぜひお聞かせください!
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449
FAX番号:03-3502-8766








 感想を送る
感想を送る