食を究めたスペシャリストが教えます 達人レシピ。
日本各地、旬の食材を提供する農家や漁師など、食のスペシャリストたちが、専門家だからこそ知っている秘伝のレシピを紹介。食材の味や、栄養を引き出し尽くす! 達人ならではのレシピをお見逃しなく!
第23回にら

高知県は年間を通しての日照時間が長く、温暖な気候を活かした高知なすなどの栽培が盛んです。一方で、みょうがやしょうがといった香味野菜のハウス栽培にも力を入れており、日本一の出荷量を誇る作物がいくつかあります。にらもそのひとつで、2019年の出荷量は1万4,000トン、全国の出荷量の約26パーセントを占めています(農林水産省 令和元年産野菜生産出荷統計)。
にらはネギ属に属する中国原産の多年草で、気候などの条件にもよりますが、真夏と真冬を除いて年に数回、長い場合は4年から5年にもわたって収穫することができます。肉厚で柔らかく育ったにら。収穫後には、丁寧に余分な葉が取り除かれ、束に仕上げて包装されます。
にら栽培の達人
JA高知県香美地区園芸部ニラ部会
副部会長 田村 文男さん(高知県香美市)
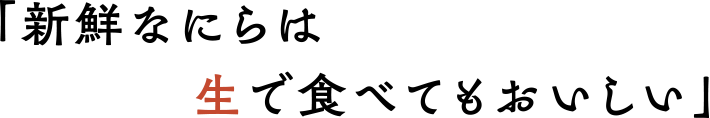

高知県内でもにら産地として知られるのが、県東部の内陸に広がる香美市。同市で120アールのハウスと40アールの露地でにらを栽培、出荷しているのが、JA高知県香美地区園芸部ニラ部会の田村さんです。
にらは、収穫した後も同じ株で何年も育てることができる多年草ですが、田村さんは品質の良いものを育てるため、植え替え(種から育てた新しいにらの苗を定植する作業)を1年ごとに行っています。ハウスでの収穫までのサイクルは、春から秋にかけての時期は約30日で、気温の低い冬場になると40日から50日かかります。冬場は春から秋の時期よりも収穫に時間がかかりますが、その分にらの葉は肉厚になります。にらは生命力が強い野菜ですが、近年は夏の異常高温で害虫が発生したり、病気にかかったりするため、その時期の栽培管理が難しくなっているそうです。
「にらは香味野菜ということもあって、炒め物のアクセントに使ったり、鍋に入れたり、餃子のタネに使ったりする人がほとんどだと思います。でも、根っこに近い部分には甘味やうま味が凝縮されているので、生のまま食べてもおいしいですよ。また、さっと湯通しすると香りが際立つので、和え物にするのもおすすめです」と田村さんは教えてくれました。

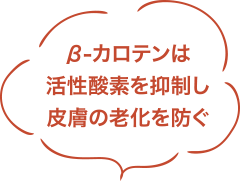
にらにはビタミンAに変換されて作用するβ-カロテンが特に豊富で、ビタミンB2やビタミンC、カルシウムも含まれます。β-カロテンは紫外線を浴びることによって体内に発生する活性酸素を抑制し、皮膚の老化を防ぎ健康な皮膚を保ちます。(監修:管理栄養士・国際中医薬膳師 清水 加奈子さん)
食のスペシャリストが教える! 達人レシピ"
-
 1
1にらは4センチメートルの幅に切り、葉と根元部分を分けておきます。豚バラ肉は大きければ食べやすい大きさに切り、もやしは洗って水気を切ります。
-
 2
2フライパンに油を入れて熱し、豚バラ肉を炒め、塩、こしょうを振ります。
-
 3
32にもやし、にらの根元部分を加えて炒め合わせます。
-
 4
4さらににらの葉を加えてさっと炒め、塩とこしょうで味を調えます。仕上げにごま油を少々回しかければ出来上がりです。好みでうま味調味料を振ってもいいでしょう。

ここがポイント!
高知の定番料理はレバニラ炒めではなくにら豚。炒めすぎないよう、さっと火を通すだけにして、香りやうま味、鮮やかな色合いを楽しんでください。

高知県産にらのほとんどはパーシャルシール包装を使用しています。これは高知県農業技術センターが開発した包装で、にらの呼吸を抑えることにより鮮度を保ちます。少量ずつ使うときなどは、この包装に戻し、あけ口を閉じて冷蔵庫に入れておくとよいでしょう。
こちらの記事もおすすめ
記事の感想をぜひお聞かせください!
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449
FAX番号:03-3502-8766









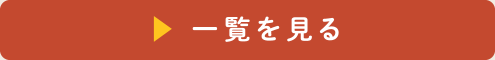
 感想を送る
感想を送る