食と地域を支える研究者 社会のニーズに応える!「米粉」研究の最前線


 生涯にわたって米を楽しむ!
生涯にわたって米を楽しむ!
「高アミロース米」を
活用した嚥下食の可能性
加齢などの影響で食べ物を飲み込む力が衰えると、「誤嚥」(食べ物が気道に入り込んでしまうこと)を起こしやすくなり、肺炎を引き起こす原因となります。そこで、誤嚥しやすい方々が飲み込みやすいよう、とろみをつけたり、形や柔らかさを調整した食品を「嚥下調整食(嚥下食)」といいます。高齢化の影響もあり、そのニーズはさらに高まると考えられています。農研機構の芦田かなえ上級研究員が取り組む、米粉を原料とした嚥下食の開発に向けた研究についてお話を伺いました。


食品健康機能研究領域ヘルスケア食グループに所属。大学時代はマメ科植物が微生物と共生する際に発現する遺伝子について研究。農研機構に入った後は、米のタンパク質やデンプン、米粉加工特性、炊飯米物性評価などの研究に取り組む。
嚥下食の可能性を拓く
高アミロース米の性質
米の主成分であるデンプンは、グルコースが直鎖状につながった「アミロース」と、ところどころが枝分かれしながらつながった「アミロペクチン」の2種類の成分からなります。このうち、アミロースの含有率が25パーセント以上の米を「高アミロース米」と呼びます。
「私が高アミロース米に出会ったのは、北海道農業研究センターに赴任中のことです。同センターで米の育種を担当している方から、当時新しく育成された『北瑞穂』などの品種を紹介していただき、高アミロース米の研究を始めました」と、芦田研究員は振り返ります。
アミロースには、米に含まれるデンプンの粘りを抑える性質があります。このため、アミロースの含有率が高い高アミロース米は、炊いてもパラパラとした質感で、普通に食べるよりも、チャーハンやパエリアなどの料理に向いています。
「その後、米粉の粘度測定をしていた際、ほかの米と異なり、高アミロース米の米粉に水を加えて加熱してできる糊を冷却すると、固まってゼリー状になることに気づきました。この性質を何かに利用できないかと考えたのが、この研究の始まりです」
以降、芦田研究員は、このゼリーの性質を活かした食品が作れないかと、離乳食や和菓子など、試行錯誤を繰り返しながら検討を重ねてきたそうです。
「その頃に出会った京都の方が、『京滋摂食嚥下を考える会』に参加しており、その方の勧めもあって、高アミロース米の米粉を活用した嚥下食の開発に力を入れることにしたのです」
高アミロース米と一般的なうるち米の
米粉ゼリーの比較

高アミロース米粉ゼリーは、ゲル状でまとまった形を維持しベタつきが少ない一方、うるち米の米粉で作った場合は形状を維持できず、ベタつく仕上がりとなります。
嚥下食としての実用化を目指す
「私たちが普段ご飯として食べている品種の米(うるち米)に水を加えて加熱しても、ドロドロで喉にへばりつくような食感となってしまいます。そのため、うるち米を嚥下障害を持つ方向けに調理する場合、まずはお粥として炊いて、お粥の粒をミキサーで溶かし、そしてゲル化剤を加えてゼリー化する、という行程を経て作る必要があります。しかも、粘りを抑えるため、ミキサーにはデンプンを分解する酵素も一緒に加えるなど、うるち米から嚥下食を作るのにはとても手間がかかります。一方、高アミロース米粉ゼリーは、米粉の量に対して10倍量の水を加えて混ぜ、鍋で沸騰するまで加熱し糊状にしたあとに冷やすだけでできるので、家庭でも比較的簡単に作ることができます」
現在、国立国際医療研究センターが代表をつとめる研究コンソーシアムでは、高アミロース米粉ゼリーの嚥下食としての実用化を目指して、臨床試験やレシピの開発が進められています。また、病院や介護施設などで大量調理をして提供する場合、衛生管理のための温度基準が定められており、そうした温度帯でも物性を保てるように、調理方法や提供手順のマニュアル化も進めているそうです。

専用の測定器でさまざまな米粉用品種から作る米粉ゼリーの物性を繰り返し試験。同じアミロースでも品種により性質が異なるため、それぞれの性質を把握し精査してブレンド率を決めていきます。
認知拡大を目指し
普及活動を展開!
「私たちは高アミロース米粉ゼリーの嚥下食への活用に期待しています。しかし、実際の現場で必要とされなければ実用化には至りません。そのため、病院や介護施設の厨房でメニュー開発や調理を担当する栄養士の方々への認知拡大に向け、栄養士会での発表のほか、Webサイト、YouTubeなどを活用した普及活動にも積極的に取り組んでいます。研究者というと、研究室に籠もっているイメージが強いかもしれませんが、農研機構では研究成果を広報する対外的な仕事も多いですね」と語る芦田研究員。農研機構で研究を始めてからは、研究への向き合い方にも変化があったそうです。
「学生時代はこの研究がどう役に立つのかまで考えることができていませんでしたが、農研機構ではいかに研究を実用に落とし込めるかということを常に考えるようになりました。私も、自分が携わった仕事がひとつでも実用化されたらハッピーだなと思いながら、日々、研究しています。高アミロース米粉ゼリーは、味付けも可能ですし家庭でも調理が可能です。食事制限がある人にも、食べる楽しみを味わってもらえる食品として受け入れられて欲しいですね」と笑顔で語ってくれました。

2022年5月に東京ビックサイトで行われた国際食品素材/添加物展・会議における研究成果の展示の様子。
 多様なニーズに応える!
多様なニーズに応える!
米粉品種の開発
近年、急速に高まる米粉の需要。パン、麺、お菓子などさまざまな用途への活用が広がっています。その原料には、米粉への加工に適した品種の米が利用されます。米粉用米の品種開発について、これまで農研機構で長年にわたり多くの米の品種開発に携わってきた、作物研究部門の竹内グループ長にお話を伺いました。
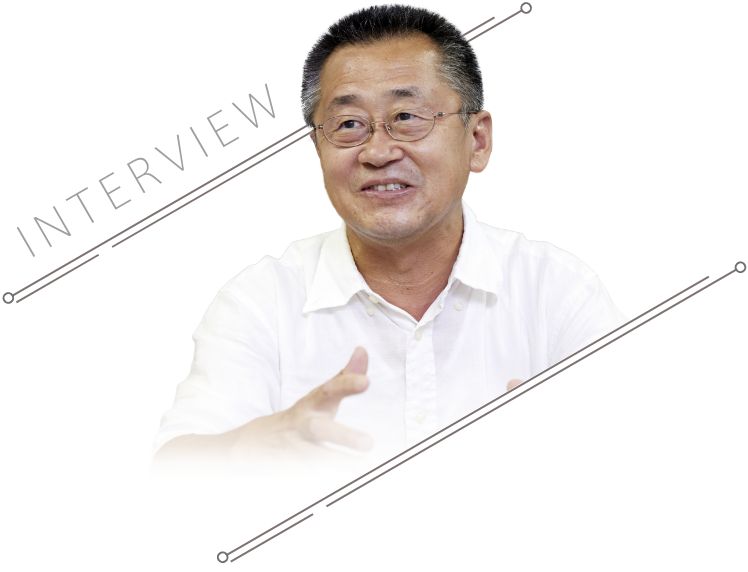

大学院で水稲の育種を研究。任期付き研究員を経て、採用後は米粉品種を含めた、イネの品種開発を行う。作物研究部門 スマート育種基盤研究領域 オーダーメイド育種基盤グループ、グループ長。最先端の技術を使いながら、生産者やメーカーへの足を使った緻密なリサーチを行い、さまざまなニーズに応える品種の開発を行う。
都道府県の枠を超えて展開する
農研機構の品種開発

パン用の米粉品種「笑みたわわ」。親品種である「ミズホチカラ」は、膨らみなど米粉パン用の品種として優れた特性を持っていましたが、晩生品種で九州での栽培には不向きであったため、九州でも栽培しやすいように改良した品種です。
「私たち農研機構が行う品種開発は、特定の都道府県にはとどまらず、国内で広く生産できる品種を開発することを目指しています。また用途も、例えば米であれば、主食用米だけでなく、中食用や外食用など、さまざまな用途に応じた品種の開発を目指しています。こうして開発された品種はスーパーなどで出回ることは少なく、あまり消費者に知られていない品種も多いのですが、実は私たちの食生活を陰で支えてくれる、そんな品種が多いですね」
農研機構では、北海道から九州まで、全国各地域に開発拠点を持っていて、それぞれの地域に適した品種を開発できることが強みです。
「イネの品種を開発する際には、食味や収量などについて詳細なデータを記録します。そうした数字の裏付けをもって、各地の農協や生産者などの方々に栽培の提案を行うこともあります」
農研機構で水稲品種開発を
行っている研究機関

北海道から九州まで、6つの水稲品種開発を行う研究拠点を持つ農研機構。寒地、寒冷地、温暖地、暖地など、それぞれの地域の気候や環境に適した品種を開発することができます。
「性質」の改良も
品種開発の重要な目的
農研機構では、膨らみやすく、パンへの加工に適した「ミズホチカラ」や「笑みたわわ」、麺への加工に適した「ふくのこ」や「亜細亜のかおり」など、用途に応じさまざまな米粉向け品種を開発しています。
「九州沖縄農業研究センターに赴任していた際、共同開発を行っていた地元の製粉メーカーから、『パンケーキに向いていて、かつこの地域でも作りやすい米粉用品種が欲しい』というリクエストがありました。パン用の米粉品種としてすでにミズホチカラが開発されていましたが、特に九州での栽培では、晩生で成熟期が遅いことが課題となっていました」
ミズホチカラは成熟までに時間がかかるため、その分、灌水の期間が短く限定されている地域や標高の高い地域では栽培に適していないという難点があったそうです。
こうした声を受けて開発されたのが、ミズホチカラよりも10日ほど早く収穫できる早生品種の笑みたわわ。ミズホチカラからの派生品種らしく、膨らみも良いパン適性に優れた品種で、かつ栽培適地も広いため、将来的にさらなる普及も期待されています。
「ほかにも、冷めても硬くなりづらい『ミルキークイーン』は栽培南限が鹿児島だったため、沖縄でも栽培できるよう、ミルキークイーンを元とする『ミルキーサマー』を開発しました。このように、品種開発の目的は食味の改善だけではなく、栽培に関わる性質の改良も重要な目的の一つです」
水稲品種間のアミロース含有率の
違いによるパンの膨らみ方の違い

笑みたわわは、パン用米粉に求められる膨らみの大きさが、親品種のミズホチカラと同等。膨らみが持続するため、パンを焼いてから時間が経っても美味しく食べることができます。
「ニーズに応えてこそ」の
品種開発
時代や嗜好の変化とともに移りゆく米へのニーズ。竹内グループ長は「品種開発は、そうしたニーズに応えてこそ意味がある」と語ります。
「イネの場合、通常は1年に1サイクルの栽培しかできません。このため、ひとつの品種を開発するまでには大抵10年はかかります。私の研究分野に関していえば、スタートから望むような性質を持つイネが開発されるまで、諦めずに続けられる強い信念が求められる仕事だと感じています。しかし、生産者や消費者の方々に喜んでいただける品種を提供できた時は、この仕事に非常にやりがいを感じますし、モチベーションになっていますね」と、笑顔で語ってくれました。

ミズホチカラの米粉を使用したパン(左/写真提供:熊本製粉(株))と、笑みたわわの米粉を使用したパンケーキ(右/画像提供:(株)兵四郎ファーム)。小麦アレルギーの消費者も食べることができる、グルテンを含まない米粉100パーセントのパンに使用されるなど、海外でのニーズも高い米粉。今後、日本産米粉のさらなる輸出拡大にも期待がかかります。
 農業で地方に活力を!
農業で地方に活力を!
九州沖縄経済圏
スマートフードチェーン
プロジェクト
新たな品種や技術など、日々生み出される研究成果。農研機構では、こうした成果の社会実装に向け、生産者の方々や企業と連携しながらさまざまな取り組みを行っています。今回は、九州を舞台に研究成果を海外展開や地方創生につなげることを目指したプロジェクトについて、田中健一事業開発部長にお話を伺いました。


2018年4月から農研機構に在籍し、農業界・産業界への研究成果の普及浸透を担当。また農研機構在籍以前は、農林水産省において「『知』の集積と活用の場® 産学官連携協議会」の立ち上げにかかわるほか、鳥獣害対策及びジビエ振興など幅広い事業を担当する。
九州を舞台に
国内農業生産基盤の強化と
輸出拡大を通じて
地方創生を目指す
「農研機構ではさまざまな品種や技術を開発していますが、これらは作って終わりではなく社会実装、すなわち、実用化、商品化をしなくては意味がありません。これを実現するために欠かせないのが、現場の生産者の方々や企業の方々との“連携”です。農研機構では、こうしたつながりを作り、研究成果を社会に還元するためのさまざまな取り組みを行っています」と語る、田中事業開発部長。
そのひとつが、九州沖縄経済圏を舞台に展開する、「九州沖縄経済圏スマートフードチェーン(SFC)プロジェクト」です。令和元年に発足したこのプロジェクトでは、農研機構の研究成果を結集し、生産、加工、流通、そして輸出までを九州沖縄経済圏で一貫して行う「スマートフードチェーン」を構築することで、農林水産物・食品の輸出拡大や国内農業の生産基盤の強化、そして、この地域の経済の活性化につなげることを目指しています。しかし、なぜ、九州沖縄経済圏を対象としたのでしょうか。
「九州沖縄経済圏では牛肉、いちご、かんしょ、緑茶などが国内でトップクラスのシェアを誇り、農業産出額が約2兆円(令和2年)と、国内の20パーセントを占める大きな存在感を持つ地域です。また、アジア圏と距離が近く、輸出が行いやすいという地理的な利点もあったことから、九州沖縄経済圏を中心とした試みとなりました」
九州沖縄経済圏SFC概要図

「九州沖縄経済圏スマートフードチェーン(SFC)プロジェクト」は、農研機構が九州経済連合会(産業界)、九州農政局・九州経済産業局(行政)の協力を得ながら、農業法人、JA、公設試、加工企業、流通企業等と連携を組み、研究成果の社会実装を進める取り組みです。
米粉の魅力を
九州からヨーロッパへ!
世界でグルテンフリーのニーズが高まるなかで、米粉や米粉パンは、近年、輸出への期待が高まっている品目のひとつです。今後は、グルテンフリーのニーズが高まっている、ヨーロッパ圏などにおける輸出拡大を目指していきたいとのことです。
「農研機構では、九州の生産者、製粉会社、製パン会社をつなぐ役割を担っています。たとえば、農研機構開発の米粉用品種『笑みたわわ』の産地づくりを行っている大分県では、笑みたわわの地産地消の仕組みを作るため、学校給食で笑みたわわを使用したパンの提供を始めました。また、フランス政府認定の『VITAGORA(ヴィタゴラ)』という農業・食品産業のイノベーションクラスターのプログラムに参画し、海外展開に向けたパートナーとして連携しています。これまでに、フランスを中心に市場調査を行うほか、製造された米粉を現地のシェフやパティシエなどに実際に活用いただき、使い勝手や食味などを試してもらうといった取り組みを行ってきました(農林水産省の令和2年度「地域の加工食品の国際競争力強化支援事業」活用)。この取り組みには、九州の米粉製粉会社や米粉専用のベーカリーなど米粉商品の会社にお声がけし、ご参加いただきました」
現地で高評価を得た米粉や米粉製品のなかには、プロユースとしてすでに商談が始まっているケースもあるとのこと。ヨーロッパの人々に日本産米粉の魅力が伝わる日も、そう遠い未来ではなさそうです。
「なかには、用途に応じて米粉の配合を変えて欲しいといったリクエストが来ることもあります。農研機構ではそうした際、製品特性の試験やブレンド比率の選定を行うなど、技術的な面からも協力をさせていただいています」
ヨーロッパの食卓に
日本産米の米粉料理が並ぶ日も近い!?

上:大分市の米粉製造専門会社「ライスアルバ」の「パン用米粉ミックス」と、パン粉のように使える「米フレーク」。大分県産米を湿式気流粉砕方式による製粉でデンプン粒子を壊さないことで、ふわりと軽く弾力性を持った生地になる米粉を製造しています。右:ライスアルバと共同で米粉パンの開発に取り組む、グルテンフリーの米粉パン専門店「虹の穂」には、食パンにバケット、惣菜パンなど米粉のおいしさが際立つ各種米粉パンがラインアップ。店舗はもちろんホームページでも販売しています。

画像提供:おおいた食品産業企業会
目指すは農業による地方創生
このプロジェクトをとおして、農研機構が開発した品種や技術を生産ー加工ー流通の現場で実証し実用化することで、生産性や品質向上を図り、地域の農業・食品産業の競争力を高めます。九州では、すでに海外への輸出を始めた企業もあるようです。
米粉に関しては、すでにパン用の米粉ミックスなどの輸出が始まっています。このほかにも、例えば近年海外への輸出が増加している日本茶であれば、鹿児島県の輸出業者が2019年に海外バイヤーを招聘し、同県南九州市知覧町で開催した現地説明会において、農研機構が育成した抹茶に適した新品種「せいめい」が注目を集めており、輸出が期待されているといいます。
また、アジアでは今焼き芋がブームとなっていますが、冬期になるとかんしょが輸送中に腐敗してしまい、冬期におけるかんしょの輸出を回避する事業者も多いことから、農研機構では腐敗原因の解明や腐敗防止技術の確立に向けた研究が行われているそうです。

左:農研機構が育成した新品種「せいめい」(上)とせいめいを使用した抹茶(下)。特に被覆栽培での収量や品質が優れ、抹茶の製造に適しており、海外への輸出を目指しています。右:令和2年では軟腐病や青かび病の発症で、海上輸送中の腐敗率が平均25パーセント、推定8,700万円の損害が発生していました。そのため農研機構は腐敗防止技術を開発し、令和5年度までに腐敗率5パーセント以下の実現を目指しています。

鹿児島県南九州市知覧町で2019年に開催された海外バイヤー向けの現地説明会の様子。
このプロジェクトの目指すこと、それはどんなところにあるのでしょうか。
「地域における生産性の向上や、輸出拡大に向けた取り組みをとおして、地方に活力を生み出していきたいと考えています。若い世代の方々に、地方でやりがいをもって働いていただけるようにしていきたい。農研機構がこれまで蓄積してきた数多くの研究成果を活かして、農業による地方創生を実現していきたいですね」と、力強く語ってくれました。
農研機構では「九州沖縄経済圏スマートフードチェーン」プロジェクト発足以降、各研究課題について共同研究機関などとともにその進展を図りながら、九州沖縄経済圏の農業・食品産業界等のニーズを確認し、新たな研究課題のテーマについて協議を重ねています。これらの活動結果についてご報告する場として、来る10月7日(金曜日)に、福岡市にて「事業化戦略会議」を開催いたします。ご興味のある方はぜひ、ご参加ください。
- 開催日時
- 2022年10月7日(金曜日)13時00分~16時30分
- 開催場所
- 電気ビルみらいホール
(福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館4階) - 開催方式
- 会場120名(先着順)及びweb配信
以下のURL又は二次元バーコードより各事項に必要事項をご記入の上、
9月26日(月曜日)17時までにお申し込み下さい。
定員になり次第、締切とさせていただきます。 (終了しました。)
(終了しました。) - 主催
- 農研機構
- 後援
- 一般社団法人九州経済連合会、農林水産省九州農政局、
経済産業省九州経済産業局 - お問合せ
- 農研機構九州沖縄農業研究センター
研究推進部事業化推進室
服部・金川
Tel. 096-242-7540, 7559
Fax. 096-242-7543
e-mail:
q_smart_entry@ml.affrc.go.jp
今週のまとめ
近年、需要が急速に拡大する米粉。
社会のさまざまな課題の解決に向けた研究が行われている。
地域の実情やニーズに応じた品種開発や、
研究成果の社会実装に向けた
プロジェクトもさかんに行われている。
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449







