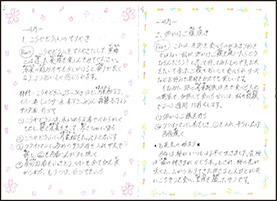2 関係省庁における取組~家庭での食育や子供食堂等への支援、デジタル化に対応した食育の推進等~
感染症による影響が長期化する中で、関係省庁においては、学校等の臨時休業等の際に生じる未利用食品の利用を促進する取組、家庭での食生活改善の重要性を普及・啓発するためのツールの作成、子供食堂・子供宅食やフードバンク等への支援、デジタル化に対応した食育の推進等を実施しました。
(文部科学省、厚生労働省、農林水産省 学校等の臨時休業等の際に生じる未利用食品の利用促進)
文部科学省、厚生労働省及び農林水産省は、オミクロン株の感染拡大に伴う小学校、中学校等の臨時休業等により、学校給食で使用される予定であった食品が未利用となり、やむを得ず廃棄されることが懸念されたため、地域の実情に応じながら、学校における未利用食品の利用促進等に取り組めるよう、教育委員会が他部署等と連携し、未利用食品をフードバンクや社会福祉施設等へ提供した取組事例等を示した事務連絡を令和4(2022)年2月に連名で発出しました。
(文部科学省 給食実施に当たっての留意点等を記した衛生管理マニュアルの作成)
文部科学省では、学校の衛生管理に関するより具体的な事項について、学校の参考となるよう、令和2(2020)年に「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~」を作成し、情勢等を鑑みながら改訂を行っています。本マニュアルにおいて、学校給食は児童生徒の健やかな育ちを支える重要な機能である一方、感染のリスクが高い活動でもあるため、給食を実施するに当たっての留意点等を記しています。また、地域の感染レベルに応じた学校給食の提供方法についても例示しています。
(厚生労働省 家庭での食生活改善の重要性を普及・啓発するためのツール作成)
感染症の感染拡大に伴う外出自粛等により、自宅で食事をとる機会が増加したことから、厚生労働省では、毎年9月に実施している食生活改善普及運動において、家庭での食生活改善の重要性を普及啓発するためのツールを作成し、ウェブサイトに掲載するとともに、地方公共団体や関係団体等に周知しました(第2部第3章第2節1「健康寿命の延伸につながる食育の推進」参照)。また、「おうち時間」が「健康づくり」のきっかけになるよう、感染症の感染拡大下での「新・健康生活」におけるポイントを紹介したリーフレットを作成し、厚生労働省ウェブサイトに掲載しました。
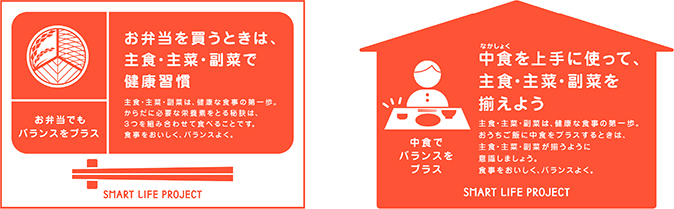
食生活改善普及運動 普及啓発ツール
(農林水産省 感染症の影響を受けた国産農林水産物等の学校給食や子供食堂等への提供を支援)
農林水産省は、「国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業」により、感染症の感染拡大による外食需要の減少等の影響を受け、在庫の滞留等が生じた国産農林水産物等を学校給食や子供食堂、子供宅食等へ提供する際の食材調達費や輸送費、インターネット販売を行う際の送料等への支援を行いました。例えば愛知県では、感染症の感染拡大による需要減少の影響を受け在庫が増加していた「名古屋(なごや)コーチン」が、親子丼やひきずり鍋(*1)などとして、県内の小・中学校で学校給食として提供されました。提供時には、「名古屋コーチン」の特徴や歴史等を紹介したパンフレットを配布し、子供たちからは「初めて食べたが美味しかった。」、「地元の特産品や地産地消について考える機会になった。」などの感想がありました。
*1 鶏肉を使ったすき焼きのこと(農林水産省:うちの郷土料理「かしわのひきずり」https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/kashiwanohikizuri_aichi.html)
(農林水産省 フードバンクへの支援強化)
令和3(2021)年は、感染症対策に伴う緊急事態宣言や営業自粛等に伴い食品関連事業者において活用できなくなった未利用食品が、やむを得ず廃棄されることが懸念されました。このような状況を踏まえ、令和2(2020)年3月から行っていた、食品関連事業者がフードバンクに寄附することを希望する未利用食品の情報を集約し、全国のフードバンクに対してこれらの情報を一斉に発信する取組を、令和3(2021)年も継続して行いました。この取組により、感染症対策に伴って食品関連事業者から発生する未利用食品のフードバンクへの寄附を促進しました。また、令和3(2021)年3月から12月までの間、緊急事態宣言の再発令の影響を踏まえた緊急対策として、フードバンクに対して、子供食堂等向けの食品の受入れ、提供を拡大するために必要となる経費を支援しました。
(農林水産省 子供食堂や子供宅食等に対する政府備蓄米の無償交付)
令和2(2020)年度に引き続き、子供食堂や子供宅食等における食育の一環として使用できるよう、政府備蓄米の無償交付を行いました。この、子供食堂等での食育の取組を支援するため、農林水産省のウェブサイトでごはん食や食育に関する啓発資料(チラシ、パンフレット等)を掲載しています。
(農林水産省 「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進)
農林水産省では、「新たな日常」における食育体験やオンライン体験の可能性について考えるセミナーとして、令和3(2021)年2月に「食育推進フォーラム2021 新しい時代の食育を考える ~コロナ時代の食育とは~」、令和3(2021)年6月に「令和3年度食育月間セミナー ~「新たな日常」でも実践!持続可能な食を支える食育の推進~」を開催し、先進事例紹介やパネルディスカッションを実施しました。また、令和2(2020)年度は、感染症の発生状況を踏まえ、食育推進全国大会の開催を中止しましたが、令和3(2021)年度は、岩手県において令和3(2021)年6月26日、27日に「第16回食育推進全国大会 in いわて」をオンラインで開催しました。
さらに、令和3(2021)年度は、「こども霞が関見学デー(*2)」の一環として公開されたウェブサイト「マフ塾」にて、食育に関するコンテンツ「おうち時間で 学ぼう♪ 調べてみよう♪ 作ってみよう♪」として、かまどでごはんを炊く様子や、うがい薬を使ってビタミンCが多い野菜や果物を調べる様子の動画等を掲載しました。
くわえて、「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進に向けて、感染症の感染拡大により対面での食育活動が困難となった人や、デジタル化に対応した食育を今後実践してみたいと考えている個人、グループをターゲットとした「デジタル食育ガイドブック」を作成しました。
*2 文部科学省をはじめとした府省庁等が連携して、業務説明や省内見学などを行うことにより、親子の触れ合いを深め、子供たちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会とするとともに、府省庁等の施策に対する理解を深めてもらうことを目的として実施するもの

デジタル食育ガイドブック(農林水産省)
URL:https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/network/movie/index.html
事例:子供宅食における食育活動
一般社団法人こども宅食応援団(東京都)、こども宅食えんまる便(長野県)、
クレエール子ども食堂宅食便(徳島県)
近年、支援を必要とする子育て家庭に定期的に食材を届ける子供宅食の取組が広がりつつあり、平成30(2018)年には一般社団法人こども宅食応援団が立ち上がりました。こども宅食応援団では、ウェブサイトを活用した情報発信等による子供宅食の普及や活動支援に取り組んでいます。
農林水産省では以前から、学校給食におけるごはん食の拡大を支援するため、政府備蓄米を無償交付する取組を行ってきましたが、令和2(2020)年度から、子供食堂や子供宅食において食育の一環としてごはん食を提供する取組に対しても交付を開始しました。各地の子供宅食実施団体では、政府備蓄米を各家庭に届ける中で、ごはん食の魅力を伝えるなどの食育の取組を行っています。
長野県長野市(ながのし)で活動する「こども宅食えんまる便」は、長野県立大学健康発達学部食健康学科の学生に協力を依頼し、学生が作成したレシピと手紙を米と一緒に子育て家庭に届けました。家庭によっては、食材が届いても調理の仕方が分からず、使用できないことがあるため、簡単に作れるレシピも同封することで、料理が苦手な人でもすぐに調理ができるように工夫しました。
徳島県徳島市(とくしまし)で活動する「クレエール子ども食堂宅食便」では、200軒の子育て家庭に米や手作り弁当などを届けており、米を届ける際には米の研ぎ方、炊き方、米を使ったレシピを同封しました。定期的に子供料理教室も開催しています。また、子供宅食の活動とは別に、令和元(2019)年6月と令和3(2021)年6月には、「おにぎりキッズ大会」を行いました。大学生のボランティアに協力してもらい、いろいろなおにぎりの材料を揃え、子供たちに好きな具材を選ばせたり、おにぎりの握り方を教えたりして、オリジナルのおにぎりを作り、みんなで一緒に楽しく食べました。子供たちの笑顔や喜んでお礼を言いながら帰る姿を見て、支援者も心地よい達成感を感じることができました。
事例:牧場と学校が連携したオンライン酪農体験授業の取組
吉田牧場(埼玉県)
埼玉県秩父郡小鹿野町(ちちぶぐんおがのまち)の吉田牧場では、乳牛約80頭を飼育しており、生産する生乳のほとんどが地域の小・中学校の学校給食に提供されています。また、生乳を生産するだけでなく、酪農教育ファーム(*1)の活動にも力を入れており、酪農教育ファーム認証牧場(*2)として、子供たちに、酪農体験の場を提供するとともに、学校に出向く出前授業等を実施してきました。酪農体験には、年間約500名の子供たちが参加し、牛への餌やりや牛舎の掃除、牛の乳搾り、アイスクリーム作り等を体験していました。しかし、感染症の感染拡大の影響により、こうした活動を行うことが困難となりました。この状況を打破するため、学校に協力をお願いして令和2(2020)年9月頃から、オンライン酪農体験授業の取組を開始しました。
オンライン酪農体験授業では、事前に、吉田牧場がオリジナルで作成した紙芝居「牛の一生」、「牛のからだ」、「人間と牛とのかかわり」を使った授業を学校の先生が行ったり、子供たちからの質問を受け付けてメールでやり取りすることで、子供たちの酪農への興味を高めます。その後、牧場と教室をオンラインでつなぎ、牧場内の様子や、子牛に牛乳を飲ませたり、牛の乳搾りをする様子を見せると、教室は大いに盛り上がります。映像で見てもらうだけでなく、実物大の牛が描かれた布や、牛が実際に食べている餌を教室に用意することで、五感を使って子供たちに牧場の様子を少しでも体感してもらいます。すると、子供たちからは、「牧場に行ってみたい!」、「やってみたい!」といった声が自然に上がってきます。子供たちとのコミュニケーションも大事にしており、一人一人からの質問に答える時間も設けます。例えば、「乳牛としての役目を終えた牛の肉を食べることは悲しくないか。」という質問に対し、「悲しいけれど、食べられずに捨てられてしまうことが一番残念なので、「ありがとう」という気持ちを持って食べる。」と回答するなど、命を感謝の気持ちを持って残さずに頂くことの大切さを伝えます。そして、感染拡大の状況が落ち着いたら牧場に遊びに来てほしいと呼び掛け、授業を締めくくります。授業の後は、授業中に答え切れなかった子供たちからの質問をメールで受け付けることで、子供たちの酪農への関心を絶やさないようにします。
始めたばかりの取組であるため、試行錯誤しながらの授業ではありますが、「子供たちの気持ちを牧場につなぎとめたい。」、「感染拡大が収束したら牧場に遊びに来てもらいたい。」という思いを持って、これからもオンライン酪農体験授業の取組を続けていきます。
*1 「食やしごと、いのちの学び」をテーマに、主に学校や教育現場等と連携して行う、酪農に係る作業等を通じた教育活動を行う牧場等のこと。一般社団法人中央酪農会議ウェブサイト参照:https://www.dairy.co.jp/edf/gaiyo.html(外部リンク)
*2 酪農教育ファーム推進委員会(日本における酪農教育ファームの推進を目指し、一般社団法人中央酪農会議の提唱により、教育関係者と酪農関係者の協力を得て設立された団体)が定めた認証規程に基づき、安全・衛生対策等をクリアして認証を受けた牧場等のこと。一般社団法人中央酪農会議ウェブサイト参照:https://www.dairy.co.jp/edf/sikumi.html(外部リンク)
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125
FAX番号:03-6744-1974