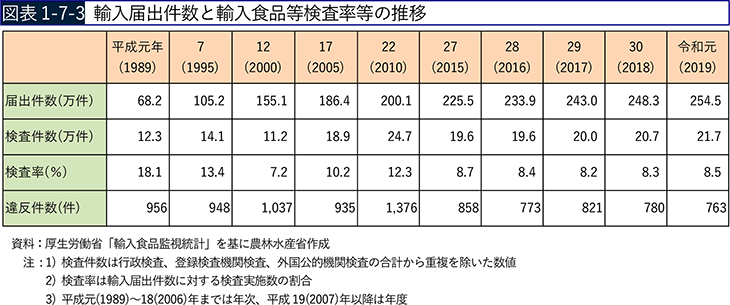第7節 国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保
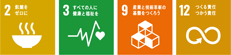
食品の安全性を向上させるためには、食品を通じて人の健康に悪影響を及ぼす可能性のある有害化学物質・微生物について、科学的根拠に基づいたリスク管理等に取り組むとともに、農畜水産物・食品に関する適正な情報提供を通じて消費者の食品に対する信頼確保を図ることが重要です。本節では、国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保のための取組を紹介します。
(1)科学の進展等を踏まえた食品の安全確保の取組の強化
(食品の安全性の向上のため、科学的根拠に基づいたリスク管理が重要)
食品の安全を確保するため、「後始末より未然防止」の考え方を基本に、科学的根拠に基づき、生産から消費に至るまでの必要な段階で有害化学物質・微生物の汚染の防止や低減を図る措置の策定・普及に取り組むことが重要です。
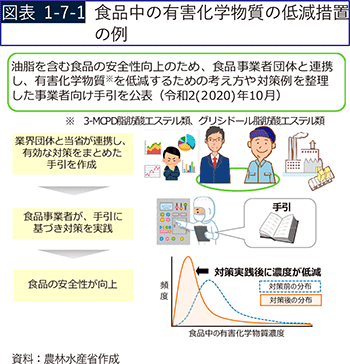
農林水産省は、食品安全に関するデータや消費者・食品関連事業者等関係者の意見、国際的な動向を考慮し、有害化学物質・微生物の中から優先的にリスク管理を行うものを優先リストとして選定し、5年ごとに改訂しています。この優先リストに基づき、5年間に実施すべき農畜水産物・食品中の含有実態等の調査の計画(サーベイランス・モニタリング中期計画)及び毎年度の計画(サーベイランス・モニタリング年次計画)を策定し、計画的に調査を実施しています。これらの調査の結果、対応が必要な農畜水産物・食品については、生産者や食品事業者と連携し、食品の安全性を向上させるための措置の策定や現場への普及に重点的に取り組んでいます。
令和2(2020)年度は、「農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト」について、最新の知見に基づいて改訂を行いました。また、作成したリストに基づき、令和3(2021)年度から令和7(2025)年度におけるサーベイランス・モニタリング中期計画を新たに作成しました。
また、令和2(2020)年度のサーベイランス・モニタリング年次計画に基づき、鉛、メチル水銀、アフラトキシン類(*1)、トリコテセン類(*2)、麦角(ばっかく)アルカロイド類(*3)、サルモネラ(*4)、ノロウイルス(*5)等について、農畜水産物や食品中の含有実態調査を行いました。
さらに、食品の安全性を向上させるための措置として、野菜類の生産段階における衛生上の注意点をまとめた「栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針」の改訂試行版(試行第2版)を公表し、生産現場からの意見を収集するとともに、現場での取組を推進しました。
このほか、食品中の3-MCPD脂肪酸エステル類やグリシドール脂肪酸エステル類について、国内関係団体と連携し、食品製造事業者が自主的に行う低減の取組を支援するため、低減のための考え方や対策例を整理した手引を作成しました(図表1-7-1)。
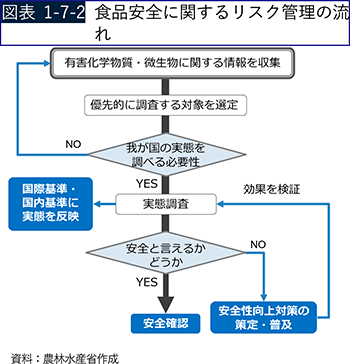
なお、食品安全に関する国際基準や規範の策定に貢献するため、これらの取組により得た科学的知見やデータをコーデックス委員会(*6) や関連の国際機関へ提供しています(図表1-7-2)。
農林水産省は、食品安全に関する情報の発信にも積極的に取り組んでいます。令和2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により新しい生活様式が求められる中、家庭で調理や食品の保存を行う際、飲食店から料理をテイクアウトする際の注意点、毒キノコ・山菜・ノロウイルス等、季節性の高い食中毒の防止について、Webサイトに掲載するとともに、SNS、動画等を活用して注意喚起を行いました。
1 アスペルギルス属の一部が産生するかび毒の総称で、ヒトの肝臓に強い発がん性を持つ。主に子実とうもろこし、落花生、ナッツ類、乾燥果実、香辛料類の汚染が知られている。
2 主に赤かび病菌の一部が産生するトリコテセン骨格という構造を持つかび毒の総称で、下痢、嘔吐、腹痛等の急性毒性のほか、体重抑制、免疫低下等の慢性毒性を持つ。主に麦類や子実とうもろこしの汚染が知られている。
3 主に麦角菌が産生するかび毒の総称。麦角菌は主にイネ科植物に感染し、穀粒に「麦角」と呼ばれる黒い角状の固まりを形成する。麦角中には麦角アルカロイド類が含まれており、麦角が穀粒に混入することで食品が汚染される。
4 食中毒の原因細菌の一つ。加熱不足の卵・肉・魚料理等が主な原因となっている。
5 食中毒の原因ウイルスの一つ。ノロウイルスによる食中毒は、食中毒事件の中で患者数が最も多く、主な原因食品は食品製造者・調理従事者を介してウイルスに汚染された食品である。そのほか、二枚貝も原因食品の一つとなっている。
6 用語の解説3(1)を参照
(輸入食品等の安全性確保のために検査体制を強化)
食品等の輸入については、厚生労働省がその重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進しています。輸入食品等の一層の安全性を確保することを目的として、毎年度、食品衛生法に基づき、輸入食品監視指導計画が定められています。同計画では、輸出国における生産等の段階から輸入後の国内流通の段階に至るまで、監視や検査を行うこと等が定められています。
厚生労働省の検疫所への輸入食品等の届出件数は、平成元(1989)年の68.2万件から大きく増加し、令和元(2019)年には254.5万件となっています(図表1-7-3)。
輸入食品等の検査件数も近年は増加傾向にあり、令和元(2019)年には21.7万件となりました。このような中、近年の違反件数は760~860件程度となっています。
引き続き、輸入食品監視指導計画に基づき、輸入食品等の安全性の確保に取り組んでいきます。
(動物分野における薬剤耐性対策を推進)
抗菌剤の不適切な使用により、抗菌剤が効かない細菌(薬剤耐性菌)が増加し、家畜の治療を難しくしたり、畜産物等を介して人に伝播して健康に影響を及ぼしたりすることがないよう、農林水産省では、家畜における薬剤耐性菌の全国的な動向調査や抗菌剤の使用を真に必要な場合に限定する「慎重使用」等の薬剤耐性対策を進めてきました(図表1-7-4)。さらに、平成28(2016)年4月に、関係閣僚会議において、省庁横断的に取り組むべき対策として取りまとめられた「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン」に基づき、農林水産省では、薬剤耐性菌の動向調査の強化、抗菌剤の飼料添加物としての指定の取消し(*1)等を進めました。
令和2(2020)年度には、医療分野と連携したシンポジウムの開催や大学における講義において、獣医師、家畜の飼養者、獣医系大学生等への抗菌剤の慎重使用に関する普及啓発の実施に加え、家畜、養殖魚及び愛玩動物における薬剤耐性の全国的な動向調査等を行いました。
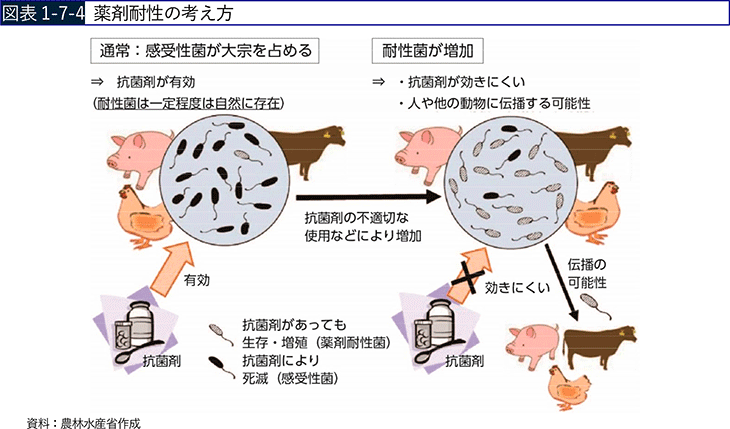
1 コリスチン、リン酸タイロシン、テトラサイクリン系等9種類の抗菌剤の飼料添加物としての指定を取消し、使用を禁止
(2)食品表示情報の充実や適切な表示等を通じた食品に対する消費者の信頼の確保
(米の表示に係る食品表示基準の改正)
令和2(2020)年7月に閣議決定した規制改革実施計画において、「農産物検査規格の見直し」が対象とされ、農産物検査を要件とする玄米及び精米に係る食品表示制度の見直しを行うこととされました。
これまでは、農産物検査による証明を受けている場合のみ、産地、品種及び産年の表示が可能でしたが、令和3(2021)年3月、産地、品種及び産年の根拠を示す資料の保管を要件とすることにより、農産物検査による証明を受けていない場合であっても、産地、品種及び産年の表示を可能とするよう、消費者庁において食品表示基準の改正が行われました (図表1-7-5)。
また、農産物検査証明によるなど表示事項の根拠を確認した方法の表示を可能とするとともに、生産者名等、消費者が食品を選択する上で適切な情報を、名称、原料玄米や内容量等を表示する一括表示枠内へ表示できるよう改正されました。
今回の食品表示基準の改正は、令和3(2021)年7月に施行することとしており、それ以降に販売される玄米や精米から新たな表示が可能となります。
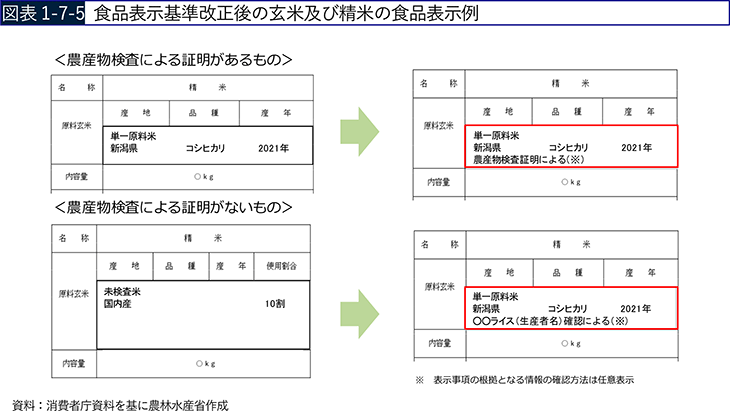
(原料原産地表示の義務化に対応するための取組を推進)
平成29(2017)年に改正された食品表示基準により、それまで一部の加工食品のみに義務付けられていた原料原産地表示について、国内で製造された全ての加工食品を対象に、重量割合1位の原材料の原産地を原則として国別重量順で表示する新たな制度が始まっています。
令和4(2022)年3月までは経過措置期間となっているため、農林水産省では、食品関連事業者が原料原産地表示制度に確実に対応できるよう、制度の概要や対応のポイントをまとめた「新しい原料原産地表示制度~事業者向け活用マニュアル~」をWebサイト上に掲載するとともに、消費者庁では消費者向けのセミナーを開催するなど、制度の周知を図っています。さらに、農林水産省では、令和2(2020)年度には、当該マニュアルに沿って制度を解説する事業者向け動画を作成・公開し、食品関連事業者の理解促進に努めました。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883