第8節 動植物防疫措置の強化
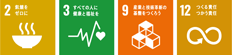
食料の安定供給や農畜産業の振興を図るため、高病原性鳥インフルエンザ(*1)や豚熱(ぶたねつ)(*2)を始めとする家畜伝染病や植物病害虫に対し、侵入・まん延を防ぐための対応を行っています。また、近年、アフリカ豚熱(*3)を始め、畜産業に甚大な影響を与える口蹄疫(こうていえき)等の越境性動物疾病が近隣のアジア諸国において継続的に発生しています。これら疾病の海外からの侵入を防ぐため、政府一丸となって取り組むことが重要です。
本節では、こうした観点から、動植物防疫措置の強化等に関わる様々な取組を紹介します。
1~3 用語の解説3(1)を参照
(鳥インフルエンザの感染拡大防止対策の強化)
令和2(2020)年11月、香川県で約3年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザが発生し、令和3(2021)年3月末時点で18県(*1)の農場において52例の発生が確認されています(図表1-8-1)。農林水産省は関係省庁や都道府県と連携し、迅速な防疫措置が実施されるよう、必要な人的・物的な支援を行いました。
また、令和2(2020)~3(2021)年シーズンは、世界的にも発生が相次ぎ、国内各地の野鳥の死体等からもウイルスが検出されるなど、環境中のウイルス濃度が高く、全国的に発生リスクが高いと考えられることに加えて、各発生事例について実施した疫学調査によれば、飼養衛生管理の不備によりウイルスが侵入した可能性が指摘されました。
このため、農林水産省から全国の都道府県に対して、発生状況等に応じて、飼養衛生管理基準の遵守指導の徹底等を通知するとともに、各都道府県を通じて、飼養衛生管理の全国一斉点検、全国一斉の緊急消毒、緊急的な防疫演習等の取組を実施しました。また、今シーズンの渡り鳥の飛来状況やウイルスの特徴を記載したリーフレットの作成等、分かりやすい情報の発信を行いました。
なお、我が国の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えています。
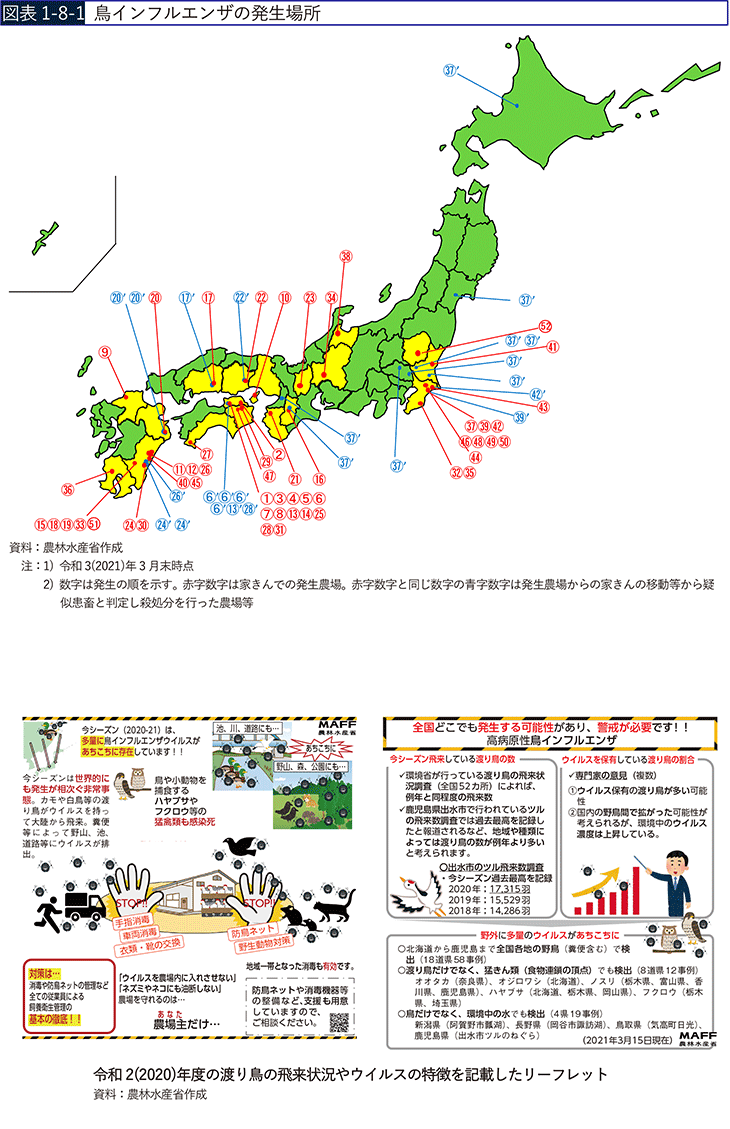
1 香川県、福岡県、兵庫県、宮崎県、奈良県、広島県、大分県、和歌山県、岡山県、滋賀県、高知県、徳島県、千葉県、岐阜県、鹿児島県、富山県、茨城県及び栃木県
(豚熱の感染拡大防止対策の強化)
平成30(2018)年9月、岐阜県で我が国において26年ぶりとなる豚熱が発生し、令和3(2021)年3月末時点で、12県(*1)の豚又はイノシシ(以下「豚等」という。)の飼養農場において63例の発生が確認されています(図表1-8-2、図表1-8-3)。
また、野生イノシシにも豚熱ウイルスが浸潤し、令和3(2021)年3月末時点で、24都府県(*2)にまで感染区域が拡大しており、豚等及び野生イノシシにおける感染拡大防止とその後の清浄化が急務となっています。
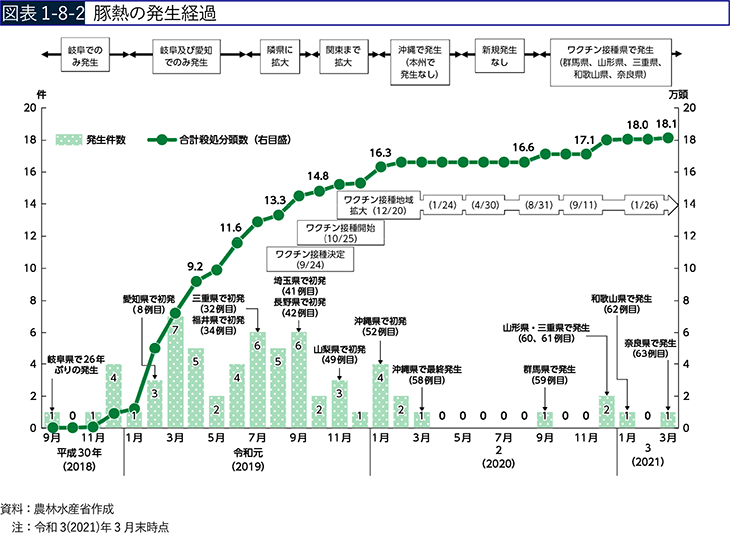
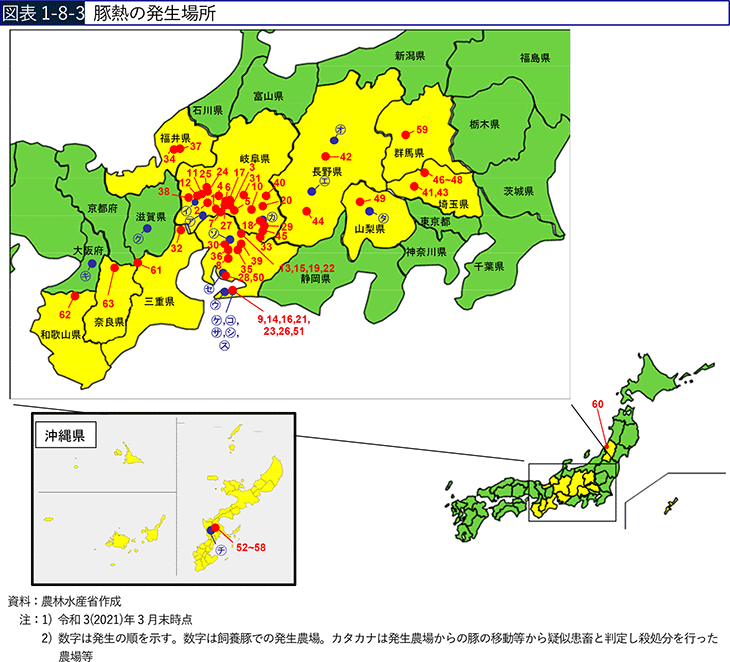
今般の豚熱の感染経路については、豚熱に感染した野生イノシシ由来のウイルスを人、車両又は野生動物が農場内に持ち込んだ事例が多いとされており、関係省庁、地方公共団体等が連携して、野生イノシシの捕獲を強化するとともに、空中散布も含めた経口ワクチンの散布等による野生イノシシ対策を推進しています。
また、農林水産省は、令和元(2019)年10月に、豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針を改訂し、同指針に基づき、12県(*3)をワクチン接種推奨地域に指定しました。その後も、野生イノシシにおける感染確認状況を踏まえ、随時、ワクチン接種推奨地域の見直しを行い、18都府県(*4)を追加し、合計30都府県をワクチン接種推奨地域に指定しました。ワクチン接種推奨地域については、野生イノシシにおける感染状況を踏まえつつ、定期的に見直しを行います。
さらに、豚熱の豚等への感染リスクの低減を図るためには、飼養衛生管理基準の遵守が極めて重要です。農場ごとの飼養衛生管理に係るマニュアル策定や野生動物侵入防止対策の義務付け、エコフィード(*5)の加熱基準の厳格化等を内容とする飼養衛生管理基準の改正を行いました。このほか、農林水産省や地方公共団体は、豚熱が豚等の病気であってヒトに感染することはなく、仮に豚熱に感染した豚等の肉を食べても人体に影響がないことを周知しています。今後は、これまでの国内防疫を継続するとともに、国内マーカーワクチンの開発に取り組むなど、将来的なOIE(*6)(国際獣疫事務局)の「清浄国」ステータス(*7)の再認定を目指すこととしています。
1 岐阜県、愛知県、長野県、三重県、福井県、埼玉県、山梨県、沖縄県、群馬県、山形県、和歌山県及び奈良県
2 岐阜県、愛知県、三重県、福井県、長野県、富山県、石川県、滋賀県、埼玉県、群馬県、静岡県、山梨県、新潟県、京都府、神奈川県、茨城県、東京都、福島県、奈良県、大阪府、和歌山県、栃木県、山形県及び兵庫県
3 岐阜県、愛知県、三重県、福井県、長野県、富山県、石川県、滋賀県、群馬県、埼玉県、山梨県及び静岡県
4 新潟県、栃木県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、奈良県、沖縄県、兵庫県、大阪府、和歌山県、福島県、宮城県、山形県、秋田県、鳥取県及び岡山県
5 用語の解説3(1)を参照
6 用語の解説3(2)を参照
7 OIEが、特定疾病の清浄性に係る状況を加盟国・地域の申請に応じ、専門家が評価した上でOIE総会において採択し、清浄ステータスを公式に認定したものをいう。
(アフリカ豚熱等の越境性動物疾病の侵入防止を強化)
近隣のアジア諸国においては、アフリカ豚熱を始め、畜産業に甚大な影響を与える口蹄疫(こうていえき)や高病原性鳥インフルエンザといった越境性動物疾病(*1)が継続的に発生しています。
これら疾病の海外からの侵入を防ぐため、農林水産省では、関係省庁と連携しながら水際検疫を徹底しています。令和2(2020)年7月には、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律が施行され、畜産物の輸出入検疫に係る家畜防疫官の質問・検査権限や廃棄権限、罰則の強化等を図るとともに、家畜防疫官の増員、検疫探知犬の増頭により検疫体制を強化しました。
1 国境を越えてまん延し、発生国の経済、貿易及び食料の安全保障に関わる重要性を持ち、その防疫には多国間の協力が必要となる疾病
(輸入エビの急性肝膵臓壊死症が国内で初めて発生)
令和2(2020)年10月に沖縄県において、我が国で初めて急性肝膵臓壊死症(*1)(AHPND)の発生が、また、令和3(2021)年3月には広島県で2例目となる発生がいずれも輸入されたバナメイエビの種苗で確認されました。本疾病は、持続的養殖生産確保法に基づく特定疾病であり、沖縄県及び広島県は同法に基づき、速やかに養殖場のバナメイエビの処分、水槽の消毒等のまん延防止措置を行いました。農林水産省は、沖縄県、広島県等関係機関と連携して本疾病の防疫措置を徹底するとともに、他の都道府県や関係者に対し輸入防疫対象疾病の発生防止について注意喚起を行いました。
1 特殊な毒素タンパク質を産生するビブリオ細菌が原因で発生する疾病で、死亡率が非常に高いことが特徴である。持続的養殖生産確保法で定める特定疾病であり、感受性種は、バナメイエビ(シロアシエビ)、ウシエビ、コウライエビ及びクルマエビ
(植物病害虫の侵入・まん延防止の取組)
農産物の生産に被害を及ぼす病害虫の侵入を効果的かつ効率的に防止するため、農林水産省では、海外での発生情報等を踏まえ、病害虫の侵入・まん延の可能性や、まん延した場合に農業生産に与える経済的被害について評価し、適切な検疫措置を検討する病害虫リスクアナリシスを行うとともに、その結果に基づいて侵入を警戒すべき病害虫の見直しや検疫措置の見直し等を実施しています。
また、病害虫の国内への侵入を防止するため、植物防疫所では、空港・港等において、量や商用・個人用を問わず、貨物、携帯品、郵便物等により輸入される全ての植物やその容器包装を対象に検疫を行っています。さらに、国内での病害虫のまん延を防ぐため、侵入警戒調査や、侵入病害虫に対する緊急防除等の取組を進めています。
国内で既に発生している病害虫についても、急激なまん延による我が国農業への被害を防止するため、病害虫の発生予測や発生予測に基づく的確な防除対策を推進しているところです。
令和2(2020)年6月以降、鹿児島県等において、かんきつ類の重要害虫であるミカンコミバエ種群の誘殺が相次ぎました。これを受けて農林水産省は県と連携し、初動防除として雄成虫を誘引して殺虫する誘殺板を設置するとともに、本虫に寄生された果実が確認された地域では、寄主植物の除去やヘリコプターによる誘殺板の散布(航空防除)を実施し、本虫の定着防止に努めています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883








