第9節 食料供給のリスクを見据えた総合的な食料安全保障の確立

世界の食料需給は、人口の増加や経済発展に伴う畜産物等の需要増加が進む一方、気候変動による農作物の生産可能地域の変化、家畜の伝染性疾病・植物病害虫の発生等が食料生産に影響を及ぼす可能性があり、中長期的に逼迫(ひっぱく)も懸念されます。このような世界の食料需給を踏まえ、我が国の食料の安定供給は、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これに輸入及び備蓄を適切に組み合わせることにより確保することが必要です。
本節では、こうした観点から、不測の事態に備えたリスク分析、国際的な食料需給の把握・分析、輸入穀物等の安定的な確保、国際協力の推進等、食料安全保障(*1)に関わる様々な取組を紹介します。
*1 用語の解説3(1)を参照
(1)不測時に備えた平素からの取組
(不測の事態に備えてリスク分析等を実施)
世界の人口増加等による食料需要の増大や異常気象による生産減少等、我が国の食料の安定供給に影響を及ぼす可能性のあるリスクは顕在化しており、さらに、自然災害や輸送障害、新型コロナウイルス感染症等のリスクも存在しています。
このため、農林水産省は、不測の事態に備え、平素から食料供給に係るリスクの分析等を行うとともに、我が国の食料の安定供給への影響を軽減するための対応策を検討、実施することにより、総合的な食料安全保障の確立を図ることとしています。
令和2(2020)年度は、(1)大規模自然災害や異常気象、(2)家畜の伝染性疾病、(3)新型コロナウイルスのような新たな感染症の三つの事象について、食料の安定供給に係るリスク分析・評価を実施しました。地球温暖化等の気候変動のリスクについては、現状評価で影響があり、将来については悪化すると見込まれると評価しました(図表1-9-1)。
また、国内における不作や輸入の大幅な減少等、食料の安定的な供給に影響を及ぼす不測の事態が生じた場合には、平成24(2012)年に策定した「緊急事態食料安全保障指針」に基づき国内での食料増産等の対策を講ずることとしています。令和3(2021)年1月には、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を踏まえ、我が国の食料供給に影響を及ぼす緊急の要因(リスク)として、「感染症の流行」を追加するなど同指針を改正しました。
政府は、国内の生産量の減少や海外における不測の事態の発生による供給途絶等に備えるため、米にあっては政府備蓄米の適正備蓄水準(*1)に基づき100万t程度を備蓄しています。食糧用小麦にあっては国全体として外国産食糧用小麦の需要量の2.3か月分を、飼料穀物にあってはとうもろこし等100万t程度をそれぞれ民間で備蓄しています。

*1 10年に1度の不作や、通常程度の不作が2年連続した事態にも国産米をもって対処し得る水準
(2)国際的な食料需給の把握、分析
(2020/21年度における穀物の生産量、消費量は前年度に比べて増加)
2020/21年度における世界の穀物全体の生産量は、小麦、とうもろこし、米が共に増加することから、前年度に比べて0.5億t(2.0%)増加の27.3億tとなり、3年連続で増加する見込みです(図表1-9-2)。
また、消費量は、開発途上国の人口増加、所得水準の向上等に伴い、近年一貫して増加傾向で推移しており、前年度に比べて0.7億t(2.5%)増加の27.4億tとなる見込みです。
この結果、期末在庫量は前年度から0.1億tの減少となり、期末在庫率は29.1%と前年度(30.3%)を下回る見込みです。
2020/21年度における世界の穀物等の生産量を品目別に見ると、小麦は、EU、ウクライナ等で減少するものの、豪州、ロシア等で増加することから、前年度に比べて1.7%増加し、7.8億tとなる見込みです(図表1-9-3)。
とうもろこしは、米国、ブラジル等で増加することから、前年度に比べて1.8%増加し、11.4億tとなる見込みです。
米は、インド等で増加することから、前年度に比べて1.3%増加し、5.0億tとなる見込みです。
大豆は、米国、ブラジル等で増加することから、前年度に比べて6.7%増加し、3.6億tとなる見込みです。
また、小麦、とうもろこし、米、大豆の期末在庫率は、前年度に比べて低下し、それぞれ38.8%、25.0%、35.2%、22.6%となる見込みです。
穀物等の国際価格については、とうもろこし、大豆が史上最高値を記録した平成24(2012)年以降、世界的な豊作等から穀物等価格は低下しました。平成29(2017)年以降は、ほぼ横ばいで推移しましたが、令和2(2020)年後半から、南米の天候が乾燥したことによる作柄懸念や、中国の輸入需要の増加等により、大豆を中心に上昇しています。米は、平成25(2013)年以降低下しましたが、令和2(2020)年のベトナムの輸出枠の設定等により同年3月末から上昇しました。同年4月末の輸出枠の解除等で下落しましたが、依然として高止まりしています(図表1-9-4)。

(世界の食料需給をめぐる今後の見通し)
世界の人口は、令和2(2020)年では78億人と推計されていますが、今後も開発途上国を中心に増加し、令和32(2050)年には97.4億人(*1)になると見通されています。
このような中、世界の穀物等の需要の伸びは、アジア・アフリカ等の総人口の継続的な増加や、緩やかな所得水準の向上等に伴う開発途上国を中心とした食用・飼料用需要の増加が続くことから、これまでの伸びに比べて緩やかではあるものの継続して増加する見込みとなっています。一方、供給面においては、主に単収の上昇によって需要の増加分を補っている状況にあります(*2)。
世界の食料の需給及び貿易は、農業生産が地域や年ごとに異なる自然条件の影響を強く受け、生産量が変動しやすいことや、世界全体の生産量に比べて貿易量が少なく、輸出国の動向に影響を受けやすいこと等から、不安定な要素を有しています。
また、気候変動や大規模自然災害、豚熱(ぶたねつ)(*3)等の動物疾病、新型コロナウイルス等の感染症の流行など、多様化するリスクを踏まえ、平素から食料の安定供給の確保に万全を期する必要があります。
*1 国連「World Population Prospects 2019」
*2 農林水産政策研究所「2029年における世界の食料需給見通し」(令和2(2020)年4月公表)
*3 用語の解説3(1)を参照
(コラム)人工衛星のデータを活用したモニタリングシステム
農林水産省では、食料の安定的輸入を確保する観点から、人工衛星による気象情報を活用し、世界の主要作物生産地域の作柄の判断に資する情報を収集・分析する取組を進めています。具体的には、作物生産に大きな影響を及ぼす気象データをWebサイト上でモニタリングするシステム(農業気象情報衛星モニタリングシステム:JASMAI)を国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)と連携して構築し、世界の主要作物生産地域の気象情報の把握・活用を行っています。なお、本システムについては、令和3(2021)年1月から一般公開を行っています。

(3)輸入穀物等の安定的な確保
(我が国の主要農産物の輸入は、特定の国に依存)
令和2(2020)年の我が国の農産物輸入額は前年比5.8%減少の6兆2,125億円となりました。国別の輸入割合を見てみると、米国が21.9%、次いで中国が10.6%で、カナダ、タイ、豪州と続いています(図表1-9-5)。
品目別に見ると、大豆は前年比4.9%減少の1,592億円、とうもろこしは前年比8.5%減少の3,516億円、牛肉は前年比7.2%減少の3,574億円、豚肉は前年比5.9%減少の4,751億円、鶏肉は前年比13.6%減少の1,173億円、生鮮・乾燥果実はほぼ前年並の3,469億円となりました。一方、小麦は前年比1.4%増加の1,628億円となりました。
海外からの輸入に依存している主要農産物の安定供給を確保するため、輸入相手国との良好な関係の維持・強化や関連情報の収集等を通じて、輸入の安定化や多角化を図ることが重要です。

データ(エクセル:1,313KB / CSV:3KB)

データ(エクセル:1,318KB / CSV:2KB)
(4)国際協力の推進
(世界の食料安全保障に貢献する国際協力の推進)
世界には約7億人の飢餓人口が存在する中、気候変動や令和2(2020)年以来の新型コロナウイルス感染症の拡大等のリスクが顕在化していることから、我が国は、G20等の国際的な枠組みを活用し、世界の食料安全保障に貢献すべく、国際協調を推進してきました。
令和2(2020)年9月にテレビ会議形式で開催されたG20農業・水大臣会合では、新型コロナウイルス感染症において各国が取り組むべき諸課題への対応について議論が行われました。我が国からは、新型コロナウイルス感染症の拡大により世界の課題となった、(1)食料や農業のサプライチェーンの強靭(きょうじん)化のために、「新たな日常」の中でしっかりとした農業基盤を作り上げること、(2)イノベーションやデジタル化への投資を活用して農業・食料センターの持続可能性を高めること、(3)各国が輸出規制等の措置を行わず国際的な市場の透明性と信頼性を向上させることの三つを重点事項として提案し、各国に協力を呼び掛けました。これにより、同会合では、我が国が提案した内容が反映された大臣声明も採択されました。
また、農林水産省は、FAO(国際連合食糧農業機関)を始めとする国際機関への拠出や、専門的知見を有する職員の派遣を通じ、アフリカを始めとする開発途上国における農業生産性の向上や栄養改善に取り組んでいます。令和2(2020)年度には、Africa Rice Center (アフリカ稲センター)と連携してアフリカの市場ニーズに適合した稲の品種やその栽培方法の開発を支援するとともに、Bioversity International(国際生物多様性センター)と連携して、アフリカにおいて地域農作物の栄養成分の分析を行い、地域の生活習慣や食文化に即した新たな栄養評価法の開発等に取り組みました。また、WFP(国際連合世界食糧計画)との間でも、西アフリカ地域において、小規模稲作農家の栄養に関する基礎的知識の向上と農業支援を併せて実施する事業に取り組みました。
さらに、東アジア地域(ASEAN(*1)10か国、日本、中国及び韓国)における食料安全保障の強化と貧困の撲滅を目的とした米の備蓄制度である「ASEAN+3緊急米備蓄」(APTERR(*2))への我が国拠出事業については、令和2(2020)年6月に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人々を支援対象に追加する運用の改善を行いました。これにより、新型コロナウイルス感染症が急激に拡大するミャンマーからの緊急支援要請に即応し、同年11月に30万米ドル(現地米750tに相当)の緊急米支援を実施しました。
*1 用語の解説3(2)を参照
*2 ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve の略
(コラム)食料システムを変革しSDGs達成を~国連食料システムサミット~
国連食料システムサミット2021は、SDGs(*1)を達成するための「行動の10年」の一環として、国際連合事務総長の呼びかけにより開催されることとなったものです。
7億人の栄養不足人口、20億人の肥満又は過体重、毎年10億tを超える食料ロス、温室効果ガスの排出等、世界の食料をめぐる課題が山積する中、同サミットは、食料の生産、加工、輸送及び消費に関わる一連の活動を「システム」の視点で捉えて、その持続性の確保を世界的な共通の課題として議論し、今後のあるべき姿を示そうとする各国ハイレベルによる初めての国際会議となるものです。
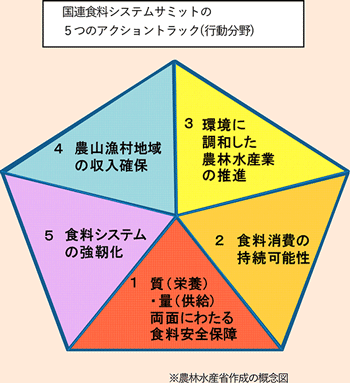
同サミットでは、各国が、食料をめぐる諸課題について、状況を変える突破口となるコミットメントを行うことが求められています。
我が国においても、令和2(2020)年度から、バランスの取れた食生活や農業現場の変革につながる技術への民間投資の重要性等について、幅広い国内関係者との対話を実施しているところです。
令和3(2021)年7月にはローマでプレサミットが、同年9月にはニューヨークで本サミットが開催される予定です。
これらの会合において、「みどりの食料システム戦略(*2)」を始めとする我が国の取組について積極的に情報発信し、世界の食料システムの変革に貢献していくこととしています。
*1 用語の解説3(2)を参照
*2 トピックス2を参照
(コラム)WFP(国際連合世界食糧計画)にノーベル平和賞
世界各地で飢餓の解消に向けて食料支援を実施してきた国際連合の機関「WFP(国際連合世界食糧計画)」に令和2(2020)年のノーベル平和賞が授与されました。
昭和36(1961)年に設立されたWFPは、紛争や武力衝突に加え、干ばつ、洪水、地震、ハリケーンや農作物被害等の自然災害の緊急事態が発生した際には、いち早く必要とされる場所に食料を届ける活動をしている、国際連合の人道支援機関です。毎年約80か国において、平均して8,000万人もの人々に食料を届けています。
今回の受賞は、WFPの長年にわたる取組と、令和2(2020)年以来の新型コロナウイルス感染症の拡大という厳しい情勢の中でも献身的に任務に当たってきた職員の努力が評価されたものであり、WFP関係者はもとより、世界全体の食料・農業関係者にとっても、自らの職業への誇りと今後の改善努力への勇気を与えるものになったと考えられます。
WFPは、令和12(2030)年までに世界から飢餓を一掃する目標を掲げていますが、近年、世界の飢餓人口は度重なる紛争や自然災害、新型コロナウイルス感染症に起因する社会経済的な影響で再び増加してきています。WFPは、現状のままでは飢餓を終わらせることは困難だとして、多国間連携の重要性を訴え、国際社会による人道的支援と危機解決に向けた協調を呼びかけています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883









