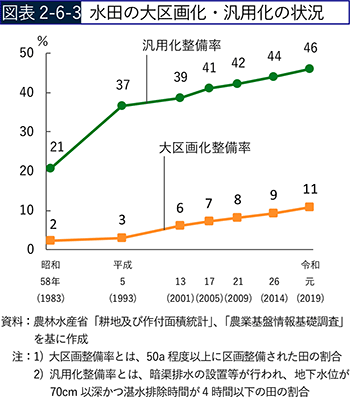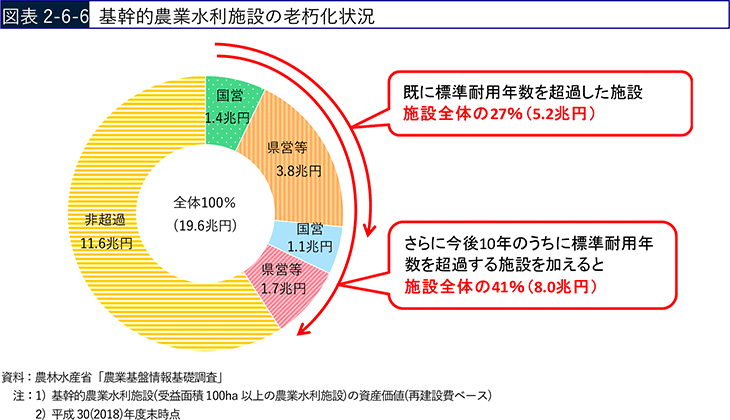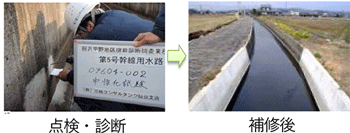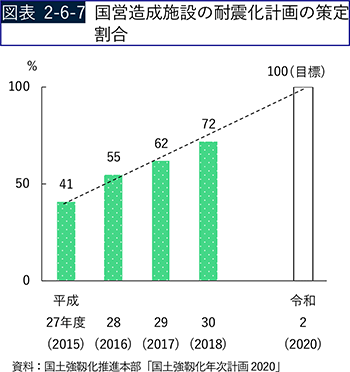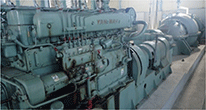第6節 農業の成長産業化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備
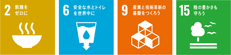
我が国の農業の競争力を強化し成長産業とするためには、農地を大区画化するなど、農業生産基盤を整備し、良好な営農条件を整えるとともに、大規模災害時にも機能不全に陥ることのないよう、国土強靱(きょうじん)化の観点から、農業水利施設(*1)の長寿命化やため池の適正な管理・保全・改廃を含む農村の防災・減災対策を効果的に行うことが重要です。
本節では、新たな土地改良長期計画のほか、水田の大区画化・汎用化等の整備状況や、農業水利施設の保全管理、流域治水の取組等による農業・農村の防災・減災対策の実施状況等について紹介します。
*1 用語の解説3(1)を参照
(1)新たな土地改良長期計画の策定
(新たな土地改良長期計画の策定)
土地改良事業は、農業者の発意・申請に基づき、実施地域内の農業者の3分の2以上の同意をもって実施することが原則となっています。事業の申請、同意、実施に至る過程においては、農業者を中心とした多様な関係者が、地域における農業・農村の将来像を見通し、世代を超えて事業の効果が発揮されるよう合意形成を図りながら実施されています。土地改良法では、土地改良事業の計画的な実施に資するため、事業の実施目標や事業量を定める土地改良長期計画を5年を一期として策定しています。令和3(2021)年3月に、政府は、令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までを対象年度とする、新たな土地改良長期計画を策定しました。
この新たな計画では、「生産基盤の強化による農業の成長産業化」、「多様な人が住み続けられる農村の振興」、「農業・農村の強靱化」といった3つの政策課題に対応した5つの政策目標を掲げ、「スマート農業の実装を可能とする基盤整備を行う地区の割合:約8割以上」、「防災重点農業用ため池における防災対策着手の割合:約8割以上」、「田んぼダムに取り組む水田の面積:約3倍以上」等を重要業績指標(KPI)として設定し、取組を進めることとしています(図表2-6-1、図表2-6-2)。
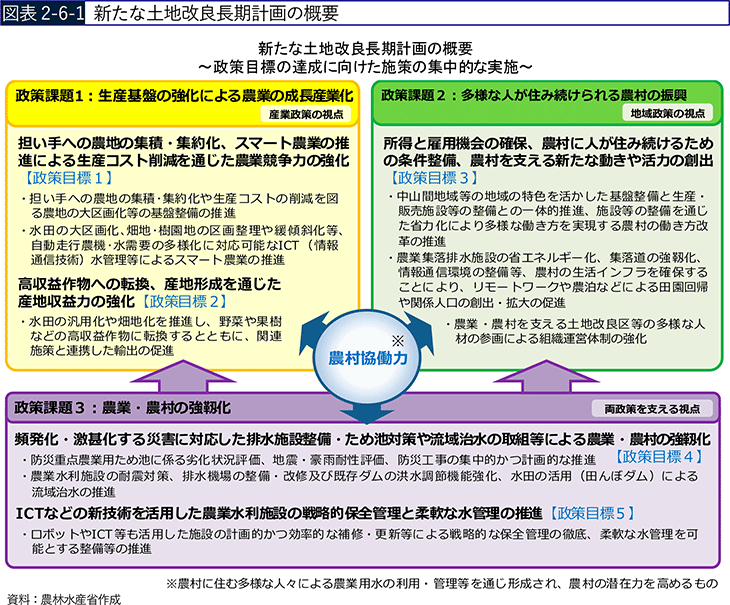
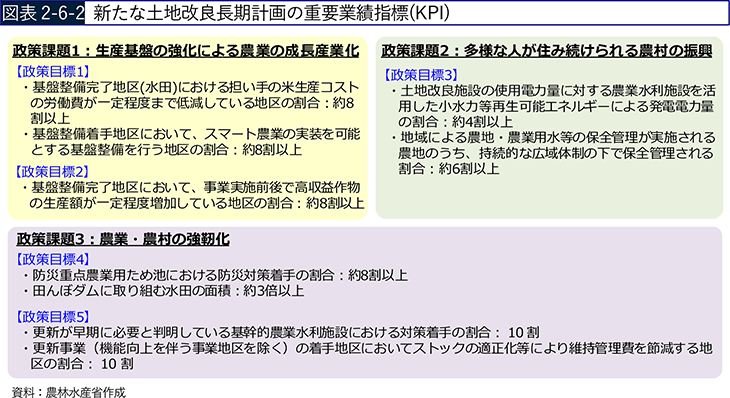
(2)農業の成長産業化に向けた農業生産基盤整備
(大区画整備済みの水田は11%、畑地かんがい施設整備済みの畑は24%)
我が国の農業の競争力を強化するため、農林水産省では、水田の大区画化や汎用化・畑地化、畑地かんがい施設の整備等の農業生産基盤整備を実施し、担い手への農地の集積・集約化(*1)や農業の高付加価値化等に取り組んでいます。
水田の整備状況について、令和元(2019)年における30a程度以上の区画整備済み面積は159万haであり、水田面積全体(239万ha)の66%となりました。その中でも、担い手への農地の集積・集約化や生産コストの削減に資する50a程度以上の大区画整備済み面積は26万haであり、その割合は11%となりました。
また、暗渠(あんきょ)排水の設置等による汎用化が行われた水田面積は110万haで、その割合は46%となりました。水田の汎用化(*2)により、野菜等の高収益作物への転換が進んでいます(図表2-6-3)。
一方、畑では、令和元(2019)年における畑地かんがい施設の整備済み面積は49万haであり、畑面積全体(200万ha)の24%となりました。また、区画整備済み面積は、128万haであり、その割合は64%となりました(図表2-6-4)。
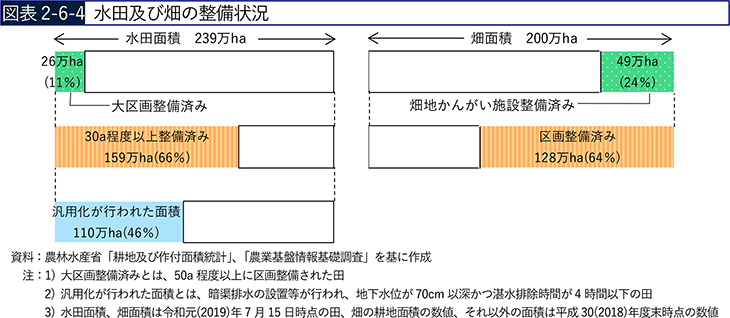
*1、2 用語の解説3(1)を参照
(事例)水田の大区画化、汎用化を通じた経営の多角化を実現(島根県)

島根県安来市能義第二(やすぎしのぎだいに)地区は、水田の基盤整備(大区画化、汎用化)により生産コストの低減や水管理の省力化を行うとともに、担い手への農地集積による経営規模の拡大に取り組んでいます。
基盤整備を実施する前の平成25(2013)年には、売上高の98.1%が水稲、1.4%が大豆、麦、なたねでしたが、区画整理や用排水路の整備を行うことにより大型農業機械の導入が可能となり、生産コストが低減されるとともに、水田の汎用化により、キャベツ等の作付けが可能となり、経営の多角化が実現しました。
この結果、能義第二地区での大豆、麦、なたねの売上高は平成25(2013)年から平成30(2018)年の5年で4倍に増加しました。また、新たに導入したキャベツ、トマトの売上高も平成28(2016)年から平成30(2018)年の2年で10倍になりました。
(自動走行農機やICT水管理等を活用するスマート農業が実装可能となる農業生産基盤整備を推進)
農業生産基盤については、令和2(2020)年2月に農林水産省が「自動走行農機等に対応した農地整備の手引き」を策定し、国、県、土地改良区等により自動走行農機やICT(*1)水管理等を活用するスマート農業が実装可能となる整備が進められています。
令和2(2020)年度では、水田について、用水需要の変化に応じて水田内の水位をセンサーにより把握し、遠隔で開閉操作を行う給水システムや大区画化された水田において地下水位を自動で制御するシステムの整備と併せて、自動走行農機がその性能を発揮しやすい大きさや形状の圃場(ほじょう)への整備が行われています。
また、自動走行農機による作業の効率化や圃場と農道の間の安全な行き来のために農道の両側に緩やかなスロープを設けたターン農道の設置を行うほか、障害物を減らすために水路を地下に埋設するなどの整備が実施されています。
*1 用語の解説3(2)を参照
(農村における情報通信環境の整備を推進)
農林水産省は、総務省と連携し、スマート農業の現場実装や農業水利施設の管理の省力化を推進するとともに、農村地域の活性化に資するよう、情報通信環境整備への支援について検討を進めています(総務省北海道総合通信局が開催する「北海道農業ICT/IoT懇談会」が行った試算では、平成29(2017)年度末時点で、光ファイバが利用可能な農地の面積は北海道における全農地面積に対し51.7%となっています(図表2-6-5)。)。
令和2(2020)年度においては、スマート農業実証プロジェクトと総務省が行う「地域課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証(*1)」の連携により、ロボットトラクタやロボット摘採機の無人自動走行等の実証を、北海道岩見沢市(いわみざわし)、山梨県山梨市(やまなしし)、鹿児島県志布志市(しぶしし)で行いました。また、ICTを活用したため池や農業用用排水路の監視・遠隔操作等の実証を、静岡県袋井市(ふくろいし)、兵庫県神戸市(こうべし)で行いました。
令和3(2021)年度においては、各実証を継続するとともに、地方公共団体等による情報通信環境の整備やそのために必要な調査・計画策定を支援するための新たな事業制度を創設することとしています。
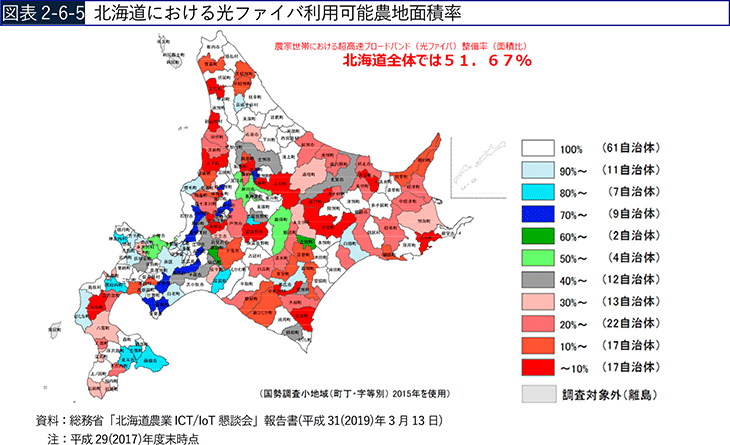
*1 令和3(2021)年度以降は「課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」に名称を変更
(3)農業水利施設の戦略的な保全管理
(老朽化が進む農業水利施設を計画的、効率的に補修・更新)
基幹的水路(*1)や基幹的施設(*2)(ダム、取水堰(しゅすいせき)等)等の基幹的農業水利施設の整備状況は、平成30(2018)年度末時点で、基幹的水路が5万1,454km、基幹的施設が7,632か所となっており、これら施設は土地改良区等が管理しています。
基幹的農業水利施設の相当数は、戦後から高度成長期に整備されてきたことから、老朽化が進行しています。令和元(2019)年度における、経年劣化やその他の原因による農業水利施設(*3) (基幹的農業水利施設以外も含む。)の漏水等の突発事故は、依然として高い水準となっています。標準耐用年数を経過している基幹的農業水利施設は、再建設費ベースで5.2兆円であり、全体の27%を占めています。さらに、今後10年のうちに標準耐用年数を超過する施設を加えると8兆円であり、全体の41%を占めています (図表2-6-6)。
このような状況の中、農林水産省は、点検や機能診断、監視等により、農業水利施設の老朽化によるリスクを評価し、その結果に基づき、予防保全も含めた補修・更新等の様々な対策工法を比較検討した上で、適切な対策を計画的かつ効率的に実施するストックマネジメント(*4)を推進することにより、施設の長寿命化とライフサイクルコスト(*5)の低減を図っています。
*1 農業用用排水のための利用に供される末端支配面積が100ha以上の水路
*2 農業用用排水のための利用に供される水路以外の施設であって、受益面積が100ha以上のもの
*3 用語の解説3(1)を参照
*4 施設の機能がどのように低下していくのか、どのタイミングで、どの対策を取れば効率的に長寿命化できるのかを検討し、施設の機能保全を効率的に実施することを通じて、施設の有効活用や長寿命化を図り、ライフサイクルコストを低減する取組
*5 施設の建設に要する経費、供用期間中の維持保全コストや、廃棄にかかる経費に至るまでの全ての経費の総額
(4)農業・農村の強靱化に向けた防災・減災対策
(国土強靱化基本計画等を踏まえたハード、ソフト面の対策を実施)
頻発する豪雨、地震等の災害に対応し、安定した農業経営や農村の安全・安心な暮らしを実現するため、農林水産省は、平成26(2014)年に閣議決定した「国土強靱化基本計画」(平成30(2018)年改定)を踏まえ、農業水利施設の長寿命化や統廃合を含むため池の総合的な対策の推進等のハード面での対策と、ハザードマップの作成や地域住民への啓発活動等のソフト面での対策を組み合わせた防災・減災対策を推進しています。
耐震対策が必要な農業用ダムや頭首工(とうしゅこう)の国営造成施設の耐震化計画の策定割合は令和2(2020)年度に100%を目標としていたところ、平成30(2018)年度末時点で、72%となっています(図表2-6-7)。また、令和元(2019)年度までにハザードマップを作成した防災重点ため池は約1万3千か所となっています。
令和2(2020)年12月に「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策(*1)」を閣議決定し、令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの5か年を対象に、必要な事業規模を定め、集中的に対策を講じることとなりました。農業・農村分野では、「流域治水対策(農業水利施設の整備、水田の貯留機能向上)」、「防災重点農業用ため池(*2)の防災・減災対策」及び「農業水利施設等の老朽化、豪雨・地震対策」等に取り組むこととしています。
*1 第4章第4節を参照
*2 防災重点ため池と同義。令和2(2020)年10月に施行された防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第2条に規定
(事例)排水機能の確保により、農地等への被害を未然に防止(愛知県)
愛知県の尾張西部(おわりせいぶ)地区は、名古屋市(なごやし)、一宮市(いちのみやし)、津島市(つしまし)、江南市(こうなんし)、稲沢市(いなざわし)、愛西市(あいさいし)、清須市(きよすし)、弥富市(やとみし)、あま市(し)、大治町(おおはるちょう)、蟹江町(かにえちょう)、飛島村(とびしまむら)にまたがる1万1,608haの農地を有する地帯です。豊かな木曽川(きそがわ)の水を活かして、水稲を中心に小麦、大豆、野菜等を組み合わせた農業経営が行われています。
尾張西部地区は、地区の大半が海面以下と標高が低いため、昭和34(1959)年の伊勢湾台風や昭和49(1974)年、昭和51(1976)年の豪雨により合わせて9,320haの農地が甚大な被害を受けました。そのため、昭和60(1985)年から平成8(1996)年にかけて国営かんがい排水事業により日光川(にっこうがわ)河口排水機場や尾西(びさい)排水機場を整備し、排水を改良しましたが、施設の経年的な劣化により、ポンプ設備の故障、ポンプ建屋のひび割れ等の機能低下が生じ、排水機能の維持、施設の維持管理に多大な費用を要することが懸念されていました。
このため、平成30(2018)年度から令和2(2020)年度にかけて排水施設の機能維持や長寿命化を図るため、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」に基づき、排水施設の機能保全、耐震化のための整備を行いました。
これにより、令和2(2020)年7月の豪雨では排水機場が稼働し、農地、宅地等の湛水(たんすい)被害を未然に防ぐことができました。
(ため池工事特措法を施行)
平成30年7月豪雨では32か所のため池が決壊し、甚大な被害が発生しましたが、その多くが防災重点ため池に選定されていないものでした。このため、平成30(2018)年に国が防災重点ため池の新たな選定基準として「決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池」を定め、都道府県が同基準に基づき再選定を行った結果、防災重点ため池の数は約1万1千か所から令和元(2019)年5月末時点で約6万4千か所へと大幅に増加しました。
防災重点ため池が増加する中で、都道府県知事や市町村長から「地方公共団体の財政やマンパワーには限界があり、計画的に防災工事を推進するためには、財政支援や技術支援が必要」との声が数多く寄せられたことから、令和2(2020)年6月、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」(以下「ため池工事特措法」という。)が議員立法により成立、同年10月に施行されました。
ため池工事特措法では、集中的かつ計画的に防災工事等を推進するため、都道府県が推進計画を策定し、国は必要な財政上の措置、地方債について特別の配慮を講ずることとされています。加えて、都道府県は、防災工事等の確実かつ効果的な実施に関して必要な技術的指導、助言その他の援助に努めることとされており、必要に応じて土地改良事業団体連合会の協力を求めることができる旨が規定されました。ため池整備に対する知見、能力を有する土地改良事業団体連合会が、ため池の点検調査、現地パトロール、劣化状況評価等の活動を「ため池サポートセンター」として行う先進的な事例もあり、農林水産省ではこれらの事例を全国的に広めていくこととし、ため池サポートセンターの設置や活動等を支援しています。
さらに、ため池工事特措法に基づき、ため池の貯水量、住宅等の数及び公共施設の重要度を踏まえて、優先度の高いものから防災工事等に取り組むとともに、防災工事等が実施されるまでの間についても、ハザードマップの作成や監視・管理体制の強化等を行うなど、これらの対策を適切に組み合わせて、ため池の防災・減災対策を推進することとしています。
(流域治水の取組を推進)
農林水産省では、関係省庁と連携して流域治水の取組を推進することとしています。
河川の流域には、水田、農業用ダム、排水機場、ため池が存在しており、流域全体で治水対策を進めていく中で、これらの農地・農業水利施設が持つ洪水調節機能の活用に取り組んでいます。このため、農林水産省では、関係省庁や地方公共団体、農業関係者等と連携しながら、大雨により水害が予測される際に、(1)事前に農業用ダムの水位を下げて雨水を貯留する「事前放流」、(2)水田に雨水を一時的に貯留させる「田んぼダム」、(3)ため池への雨水の一時的な貯留、(4)農作物への被害のみならず、市街地や集落の湛水(たんすい)被害も防止・軽減させる排水施設の整備等、流域治水の取組を通じた防災・減災対策を強化しています(図表2-6-8)。
令和元(2019)年12月に策定した「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」においては、1級水系の利水ダムについて、令和2(2020)年5月までに河川管理者、ダム管理者及び関係利水者との間で治水協定を締結し、事前放流や時期ごとの貯水位運用により、ダムの有効貯水容量を洪水調節に活用する新たな運用を図ることとされました。これを踏まえて、特に農業用ダムについては、1級水系に存在している265基全てのダムで治水協定を締結し、洪水調節機能を強化した新たな運用が開始され、2級水系においても、順次、治水協定の締結が進められています。
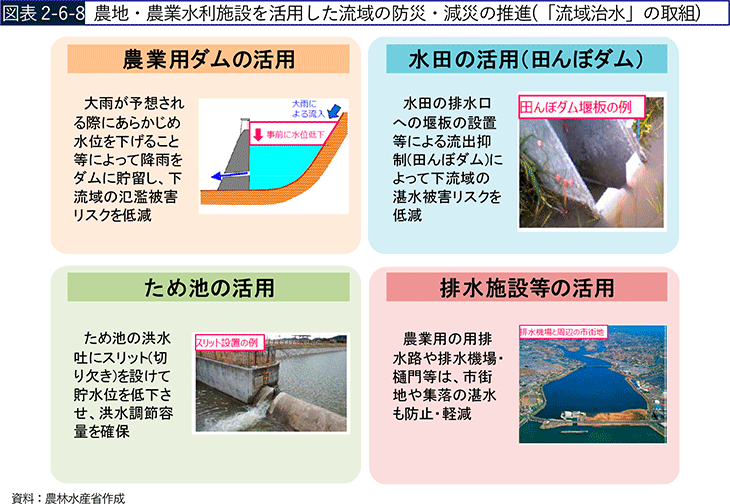
(低平地や干拓地の排水機場、海岸堤防の整備により周辺の農地、農作物を保全)
低平地や干拓地の排水機場の多くは、ダム、取水堰等の農業水利施設と同様に老朽化が進行しており、ポンプ設備が故障した場合、農地、農業用施設のみならず、地域に居住する住民の生命や財産に対して、甚大な被害が発生するおそれがあります。このため、農林水産省は、国営事業や補助事業等を活用し、予防保全も含めたポンプ設備の補修・更新等を推進しています。
また、農地周辺の海岸堤防は、津波、高潮、波浪等から周辺の農地、農作物等を守るものです。大規模地震が想定されている地域等で、耐震対策等を必要とする農地周辺の海岸堤防は約150kmに及び、大規模地震が発生した際、周辺の農地が被災するおそれがあります。
このため、令和2(2020)年度において、農林水産省は、大規模地震が想定され津波や高潮による浸水被害及び内水氾濫のおそれがある地域で、水門、排水機場等の大規模改修を計画的、集中的に行う補助事業を創設しました。これにより、農林水産省が3地区、また、19道県が創設した補助事業や農山漁村地域整備交付金等を活用して、農地周辺の海岸堤防、離岸堤(りがんてい)、消波ブロックの整備、地盤の改良等を行いました。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883