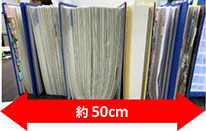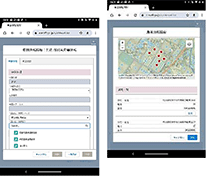トピックス4 スマート農業・農業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進
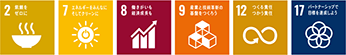
ITの急速な発展・普及により、農業や食関連産業等においても新たな発展が期待されています。特に農業分野では、農業者の高齢化や労働力不足が続いており、農業を成長産業としていくためには、デジタル技術を活用して、効率的な生産を行いつつ、消費者から評価される価値を生み出していくことが不可欠です。
以下では、スマート農業や農業のデジタルトランスフォーメーション(DX(*1))の実現に向けた農林水産省の取組について紹介します。
*1 用語の解説3(2)を参照
(農業DX構想に基づくデジタル変革の実現に向けて)
農林水産省では、農業や食品関連産業の分野におけるDXの方向性や取り組むべき課題を示し、食や農に携わる方々の参考となるよう、令和3(2021)年3月に「農業DX構想」を取りまとめ、公表しました。
この構想では、農業・食関連産業におけるDXの実現に向けて、農業・食関連産業の「現場」、農林水産省の「行政実務」、そして現場と農林水産省をつなぐ「基盤」の整備について、計39のプロジェクトを掲げています。現在、この構想の下で、データを活用したスマート農業の現場実装、「農林水産省共通申請サービス(eMAFF)」による行政手続のオンライン化等、多様なプロジェクトを進めています。
(スマート農業の現場実装を加速化)
農林水産省は、ロボット、AI(*1)、IoT(*2)等先端技術を活用したスマート農業技術を実際の生産現場に導入して、その経営改善の効果を明らかにするため、令和元(2019)年度から全国182地区でスマート農業実証プロジェクトを実施しています。
実証プロジェクトでは、農作業の自動化、情報共有の簡易化、データの活用等を行っており、令和3(2021)年度は、輸出、新たな農業支援サービス、スマート商流、新しい生活様式に対応したリモート化・超省力化、防災・減災の五つの農政上の課題に対応したテーマに基づき地区を採択しました。これまでの実証の成果として、生産者間でデータを共有することで、新規就農者(*3)を含めた産地全体で収量が向上し経営の改善につながった事例や、労働時間削減効果なども確認されています。その一方で、スマート農業機械の導入コストを回収するためには一定規模以上の農地面積が必要であることや、スマート農業機械の操作に慣れた人材が不足していることといった課題も明らかになりました。
このため、令和3(2021)年2月に改訂した「スマート農業推進総合パッケージ」で示す、今後5年間で展開する施策の方向性に則し、シェアリング等新たな農業支援サービスの育成と普及、農業データの活用、農地インフラの整備等による実践環境の整備、農業大学校・農業高校等での学習機会の提供等に取り組んでいるところです。また、実証に取り組む農業者の現場の声「REAL VOICE(リアルボイス)」を、Webサイトで公開しています。

スマート農業に取り組む
農業者の現場の声「REAL VOICE」
URL:https://www.affrc.maff.go.jp/docs
/smart_agri_pro/jissho_seika/
index.htm(外部リンク)
*1、2 用語の解説3(2)を参照
*3 用語の解説2(6)を参照
(eMAFFプロジェクトが本格始動)
農林水産省では、所管する法令や補助金・交付金において3千を超える行政手続がありますが、現場の農業者を始め、地方公共団体等の職員からは、申請項目や添付書類が非常に多いとして、改善を求める声が多数寄せられています。このような状況を改善し、農業者が自らの経営に集中でき、地方公共団体等の職員が担い手の経営のサポートに注力できる環境とするため、行政手続をオンラインで行えるようにするeMAFFの開発を進め、令和3(2021)年度から本格的な運用を開始しました。
eMAFFは、政府方針にある「デジタル化3原則」(デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンストップ)に則していることはもちろん、申請者等の負担を軽減するため、全ての手続について点検を行い、申請に係る書類や申請項目等の抜本的な見直し(BPR(*1))を行った上でオンライン化を進めています。令和4(2022)年3月末時点で、2,623の手続がオンライン化を完了しており、令和4(2022)年度末までに全てオンラインで申請できるようにすることを目指しています。
これにより、農業者を始めとした行政手続の申請者や、地方公共団体等の行政手続の審査者といったeMAFFの利用者にとって、実際に利便性を感じていただけるよう、運営していきます。また、今後は、様々な行政手続のデータが得られることによって、より効果的な施策を提案できるようになることが期待されます。
さらに、オンライン化に当たっては、幅広い農業者がデジタル化の恩恵を受けられるようにすることも重要です。このため、令和3(2021)年6月には、農業や食品関連産業分野におけるDXを実現していくための取組の一環として、eMAFFに関する包括連携協定を株式会社日本政策金融公庫(にっぽんせいさくきんゆうこうこ)との間に締結したところであり、他の民間事業者等との連携にも取り組んでいきます。
*1 Business Process Reengineeringの略で、業務改革のこと
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883