トピックス5 新たな国民運動「ニッポンフードシフト」を開始
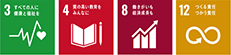
農林水産省は、食料の持続的な確保が世界的な共通課題となる中で、令和3(2021)年度から、食と農のつながりの深化に着目した、官民協働で行う新たな国民運動「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」(以下「ニッポンフードシフト」という。)を開始しました。以下では、これからの日本の食を確かなものにしていくために進めているニッポンフードシフトの取組状況について紹介します。
(多様なイベントやメディアを通じて食と農の魅力を発信)
ニッポンフードシフトは、次代を担う1990年代後半から2000年代生まれの「Z世代」をターゲットとして、全国各地の農林漁業者の取組や地域の食、農山漁村の魅力を全国各地で開催するイベントやテレビ、新聞、雑誌等のメディアを通じて発信し、それを国民の消費行動につなげていくことを目指しています。農林水産省は、この取組に賛同する1,711(*1)の企業・団体等を「推進パートナー」として登録し、官民一体となって国民運動を推進していくこととしています。
これまでのところ、まず、令和3(2021)年には、日本の食が抱える課題や目指す未来について考えるきっかけとするイベントを全国で開催したほか、高校生参加型のテレビ番組で食の課題を解決するためのアイディアコンテストを実施しました。また、吉本興業(よしもとこうぎょう)株式会社所属の「食」に関する芸名の芸人の参画を得た、食をテーマとした動画の発信、「食と農のマンガ」の雑誌での特集等を行いました。
さらに、令和4(2022)年には、47都道府県の地方新聞紙上で、各都道府県内で活躍する若手農業者等の栽培方法や品種への「こだわり」を紹介したほか、株式会社ビームスが手掛ける「BEAMS JAPAN(ビームスジャパン)」と連携してのオリジナル農業ウェアの販売等も行っています。

よしもと「食」芸人による動画
URL:https://www.youtube.com/watch?
v=mWhvqkHBWhw&t=4s(外部リンク)
1 令和4(2022)年3月時点
(ニッポンフードシフトを通じた食と農への関心の高まりと今後の展開)
令和3(2021)年10月に東京都で開催したフェスへの来場者に対して行ったアンケートでは、イベントへの参加により、「食や農業の重要性や持続性への理解」が「深まった」又は「やや深まった」と回答した割合は9割、「国産農林水産物を積極的に選択する意識」について「高まった」又は「やや高まった」と回答した割合は8割となっています。
我が国の食と農についての国民の理解が深まり、国産の農林水産物や有機農産物を積極的に選択する行動につながっていくよう、今後も様々な角度から食と農のつながりを深めていくための取組を展開していきます。
(事例)ニッポンフードシフト推進パートナーの取組事例(福島県)
福島県国見町(くにみまち)は、地産地消の推進や地場産品の販路拡大に力を入れており、ニッポンフードシフトの活動と同町が掲げるまちづくりの方向性が合致したため、ニッポンフードシフト推進パートナーの登録を行いました。
令和3(2021)年10月には、ニッポンフードシフトのロゴマークを使用し、生産者が直接消費者に同町産の農産物の安全性を説明しながら農産物の販売を行う「くにみマルシェ」を開催し、2日間で1万6千人が来場しました。
参加者からは、「ニッポンフードシフトのロゴマークを見て、マルシェの目的の一つである地産地消への意気込みを強く感じた。」と感想がありました。
同町は「ロゴマークを使用することは、地産地消を推進する上で効果がある。」として、今後も継続してこの取組にロゴマークを使用していくこととしています。

ニッポンフードシフト
公式Webサイト
URL:https://nippon-food-shift.maff.go.jp/(外部リンク)
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883









