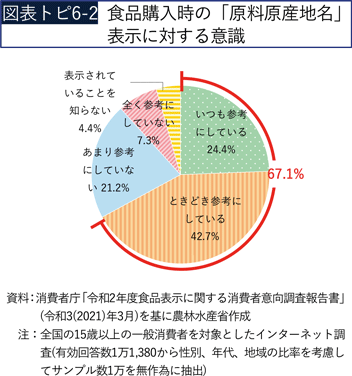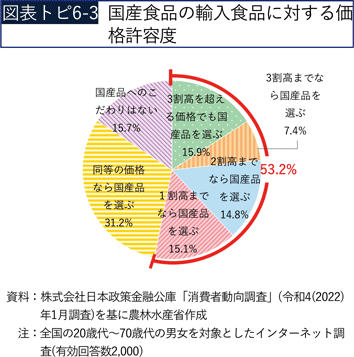トピックス6 加工食品の国産原料使用の動きが拡大

加工食品における国産原料の使用が広がっています。令和4(2022)年4月から加工食品の原料原産地表示が義務化される中で、今後、更なる広がりが想定されます。以下では、これらの動きについて紹介します。
(食品製造事業者の国産原料使用の広がり)
敷島製(しきしませい)パン株式会社では、平成24(2012)年から国産小麦を100%使用した製品の販売を行っています。令和2(2020)年時点で、全商品に使用する国産小麦の比率は11%となっており、令和12(2030)年に同比率を20%にする目標を掲げ、使用拡大に取り組んでいます。
豆腐メーカーの相模屋食料(さがみやしょくりょう)株式会社は、国産大豆の使用量を年々増やしており、令和2(2020)年度の国産大豆の比率は22%となっています。同年度の国産大豆使用量は平成27(2015)年度比で8割増となりました。令和7(2025)年度には国産使用量を現在の2倍にすることを目標とし、今後、国産大豆を使用した製品を増やす考えです。
米菓メーカーの岩塚製菓(いわつかせいか)株式会社は、平成26(2014)年から全ての商品に使用する原料米を国産にしています。海外販売も視野に入れ、令和3(2021)年3月から商品のパッケージに「日本のお米100%使用」と表示しています。
(加工食品の原料原産地表示の義務化が後押し)
平成29(2017)年9月の食品表示基準の改正により、全ての加工食品(*1)を対象に、重量割合1位の原材料の原産地を原則として国別重量順で表示する制度が施行されています。
令和4(2022)年3月末までは経過措置期間でしたが、同年4月から全ての加工食品の原材料の原産地表示が義務化されます。これを受け、消費者が加工食品を購入する際に表示を確認し、国産原材料を使用したものを選択することができるようになります。このことも、食品製造事業者による輸入原料から国産原料への切替えを後押ししていると考えられます(図表トピ6-1)。
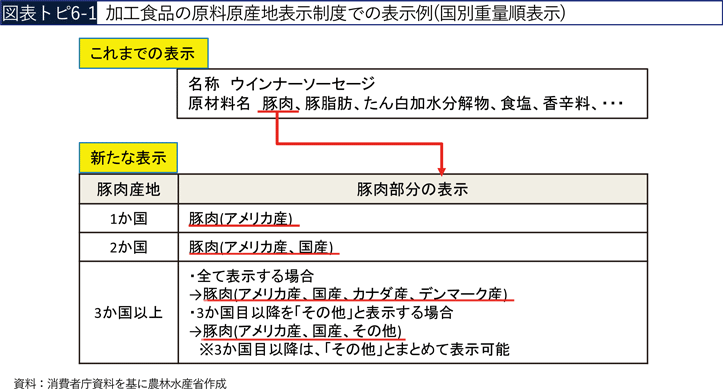
1 外食、容器包装に入れずに販売する場合、作ったその場で販売する場合、輸入品は対象外
(消費者の過半は原料原産地表示を確認し国産原料を選択、国内産地の活性化にも寄与)
消費者庁が令和3(2021)年3月に行った調査によると、食品を購入する際に原料原産地名の表示を参考にしていると回答した人は67.1%となっており、原料原産地表示が消費者にとって商品選択をする上で重要な要素となっています(図表トピ6-2)。また、株式会社日本政策金融公庫(にっぽんせいさくきんゆうこうこ)が令和4(2022)年1月に行った調査によると、割高でも国産品を選ぶと回答した人は53.2%となっています(図表トピ6-3)。
このような中、食品製造事業者による国産原料使用の取組が更に広がり、加工食品の原料を供給している国内産地の活性化にも寄与することが期待されます。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883