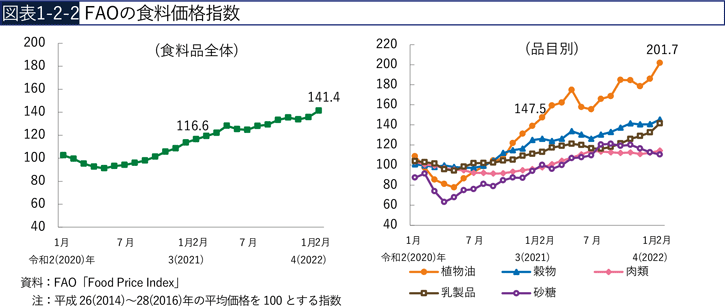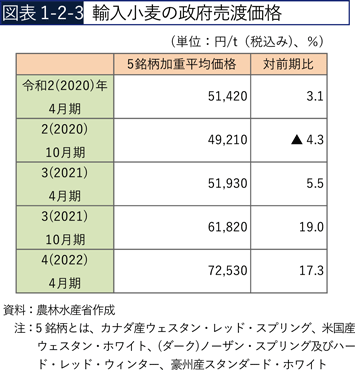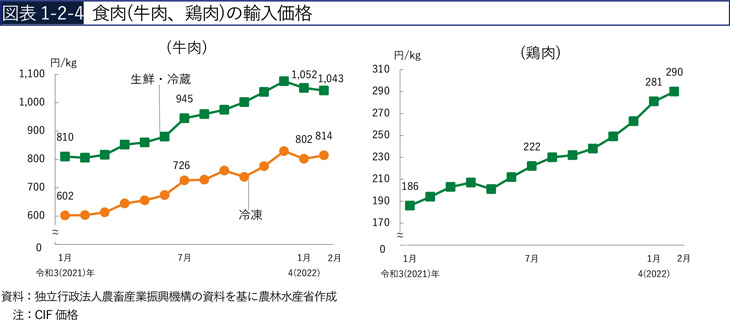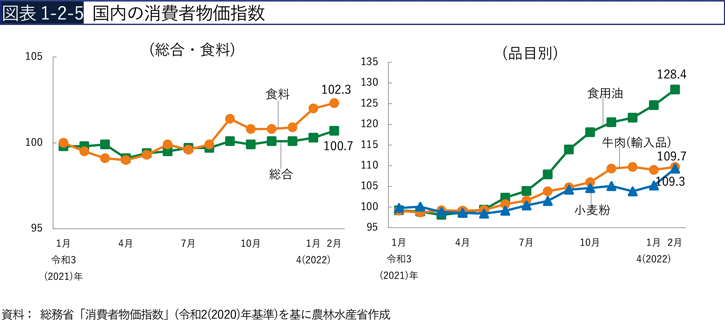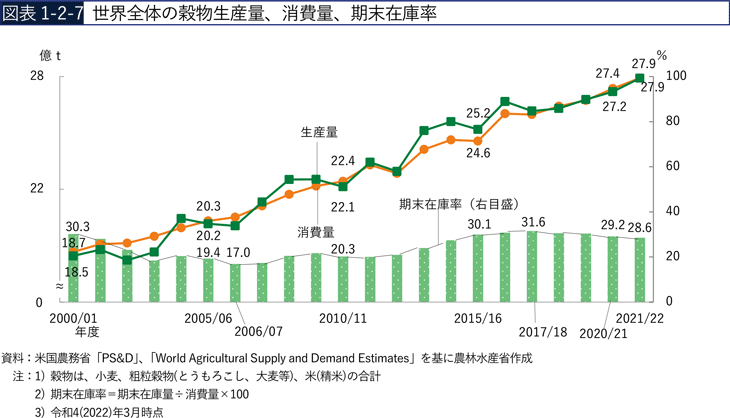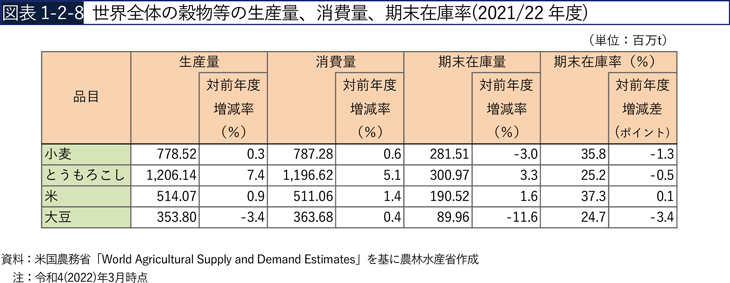第2節 食料供給のリスクを見据えた総合的な食料安全保障の確立
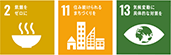
世界の食料需給は、人口の増加や経済発展に伴う畜産物の需要増加等が進む一方、気候変動や、家畜の伝染性疾病・植物病害虫の発生等が食料生産に影響を及ぼす可能性があり、中長期的には逼迫(ひっぱく)が懸念されます。このような世界の食料需給を踏まえ、我が国の食料の安定供給は、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これに輸入及び備蓄を適切に組み合わせることにより確保することが必要です。
食料の安定供給は、国の最も基本的な責務の一つであり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大やロシアのウクライナ侵略等により、世界的に、輸入国間の競合等の食料供給に対する懸念も生じている状況の中、食料自給率(*1)の向上や食料安全保障(*2)の強化への関心が一層高まっています。
本節では、直近の国内外の食料価格の上昇や、我が国の主要農産物の輸入状況、国際的な食料需給の動向等、食料安全保障に関わる様々な状況と取組を紹介します。
1、2 用語の解説3(1)を参照
(1)食料価格の上昇の状況
(穀物等の国際価格が上昇、小麦は過去最高値を記録)
穀物等の国際価格は、新興国の畜産物消費の増加を背景とした需要やエネルギー向け需要の増大、地球規模の気候変動の影響等により、近年上昇傾向で推移していましたが、令和3(2021)年以降において、小麦については主要輸出国である米国やカナダでの高温乾燥による不作や飼料需要の拡大に加え、ロシアによるウクライナ侵略が重なったことから、令和4(2022)年3月に523.7ドル/tと過去最高値を記録しました(図表1-2-1)。また、とうもろこし、大豆の国際価格についても平成24(2012)年の過去最高価格に迫る水準で推移しています。
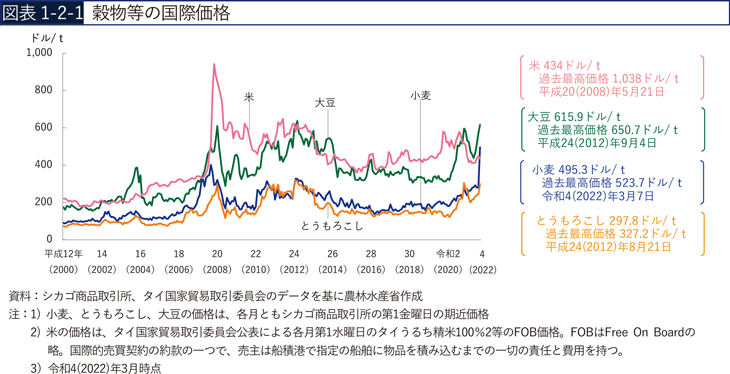
(世界的に食料価格が上昇)
穀物等の国際価格の上昇の影響を受け、FAO(国際連合食糧農業機関)が公表している食料価格指数(*1)は、令和4(2022)年2月に食料品全体で平成2(1990)年の統計公表以来最高値の141.4を記録し、前年同月比で21.3%上昇しました(*2)(図表1-2-2)。特に、植物油の価格指数は201.7と、前年同月比で36.8%上昇しました。これは、令和2(2020)年後半から、南米の乾燥による作柄懸念、中国の需要の増加等により大豆価格が上昇したことや、マレーシアにおいて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働力不足によって、パーム油の原料であるアブラヤシの収穫作業が滞ったことが影響しています。さらに、ロシアによるウクライナ侵略を背景に、穀物等の国際相場は高い水準で推移しつつ、不安定な動きを見せており、今後の動向を注視する必要があります。
1 国際市場における五つの主要食料(穀物、食肉、乳製品、植物油及び砂糖)の国際価格から計算される世界の食料価格の指標
2 令和4(2022)年3月4日公表時点
(国内でも食料価格が上昇)
世界の食料価格の上昇に加え、原油価格の上昇や為替相場の影響、さらには、世界的なコンテナ不足、海上運賃の上昇等、グローバル・サプライチェーン(供給網)の各段階における様々な要因が重なり、我が国の穀物等の輸入価格は上昇しています。
輸入小麦の政府売渡価格は、国際相場の変動の影響を緩和するため、4月期と10月期の年2回、価格改定を行っていますが、令和4(2022)年4月期の売渡価格は、国際価格の上昇等により7万2,530円/tと、令和3(2021)年10月期と比べて17.3%の引上げとなり、平成20(2008)年10月期の7万6,030円/tに次ぐ過去2番目の高値となりました(図表1-2-3)。
また、食肉についても輸入価格が上昇しています(図表1-2-4)。これは、我が国の牛肉の主要輸入相手国である豪州においてと畜頭数が減少したことや、鶏肉の主要輸入相手国であるタイの鶏肉加工場において新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生し、鶏肉加工場の一時閉鎖により食肉の生産量が減少したこと等が要因となっています。さらに、世界的に経済活動が再開されたことで外食の需要が回復し、食肉の引き合いが増えたことも輸入価格の上昇につながっています。
これら食料の輸入価格の上昇は、国内の食料価格にも影響を及ぼしており、国内における食料の消費者物価指数は、令和3(2021)年6月以降上昇傾向で推移しています(図表1-2-5)。ロシアによるウクライナ侵略等も踏まえ、今後も、食料の国際相場や国内の食料価格を注視していく必要があります。
(2)主要農産物の輸入状況
(我が国の主要農産物の輸入は特定の国に依存)
令和3(2021)年の我が国の農産物輸入額は7兆388億円となりました。国別の輸入額を見ると、米国が1兆6,411億円、次いで中国が7,112億円で、カナダ、豪州、タイ、イタリアと続いており、上位6か国が占める輸入割合は6割程度で推移しています(図表1-2-6)。
品目別に見ると、小麦、大豆、とうもろこし、牛肉は、特定国への依存傾向が顕著となっており、上位2か国で8~9割を占めています。小麦についてはロシアやウクライナからの輸入はないものの、米国、カナダ、豪州の上位3か国に99.8%を依存している状況です。
一方で、豚肉、生鮮・乾燥果実は、令和3(2021)年の上位2か国からの輸入割合が5割程度であり、平成28(2016)年と比べ、豚肉はカナダ、スペイン、メキシコからの輸入が、生鮮・乾燥果実はニュージーランド、メキシコ、豪州等からの輸入が増加しています。
このように、一部の品目では輸入先の多角化が進みつつあるものの、我が国の農産物の輸入構造は、依然として米国を始めとした少数の特定の国への依存度が高いという特徴があります。
海外からの輸入に依存している主要農産物の安定供給を確保するためには、輸入相手国との良好な関係の維持・強化や関連情報の収集等を通じて、輸入の安定化や多角化を更に図ることが重要です。一方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、ロシアによるウクライナ侵略等を踏まえると、国内の農業生産の増大に向けた取組がますます重要となっています。
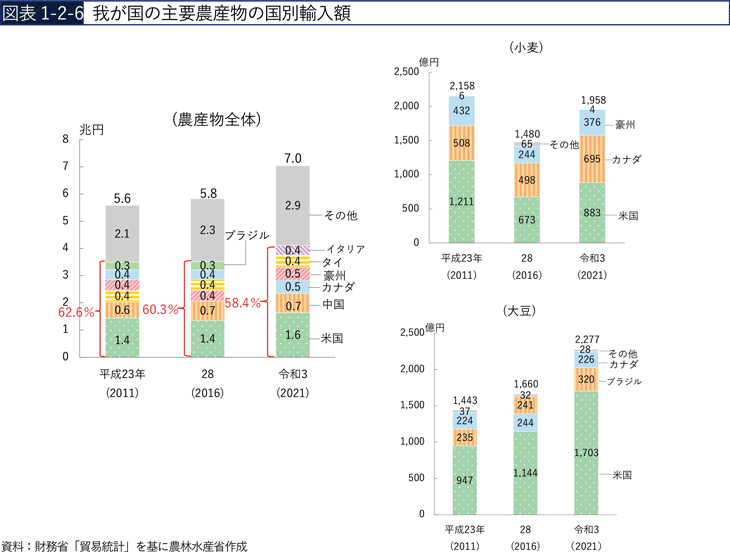
データ(エクセル:1,343KB / CSV:2KB)
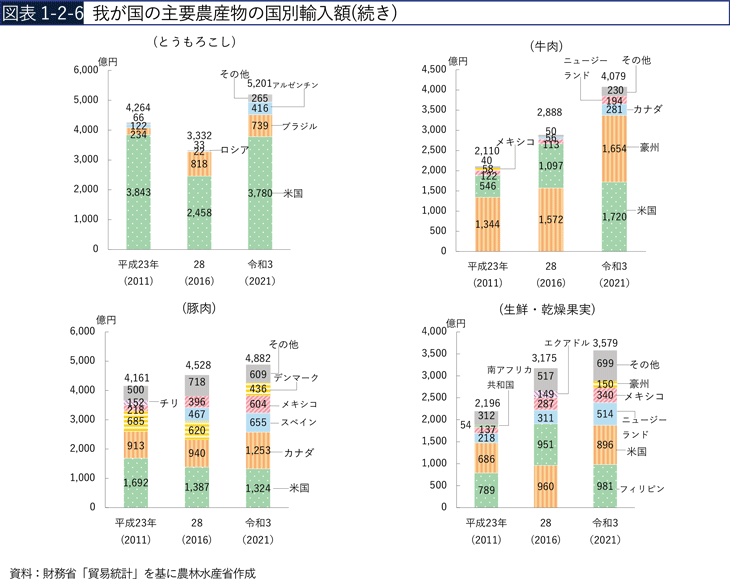
データ(エクセル:1,343KB / CSV:3KB)
(3)国際的な食料需給の動向
(2021/22年度における穀物の生産量、消費量は前年度に比べて増加)
令和4(2022)年3月に米国農務省が発表した穀物等需給報告(*1)によると、2021/22年度における世界の穀物全体の生産量は、前年度に比べて0.7億t(2.6%)増加の27.9億tとなり、過去最高となる見込みです(図表1-2-7)。
また、消費量は、開発途上国の人口増加、所得水準の向上等に伴い、一貫して増加しており、前年度に比べて0.6億t(2.0%)増加し27.9億tとなる見込みです。
この結果、期末在庫量は前年度に比べて0.1%の減少となり、期末在庫率は28.6%と前年度(29.2%)を下回る見込みです。
2021/22年度における世界の穀物等の生産量を品目別に見ると、小麦は、カナダ、ロシア等で減少するものの、EU、ウクライナ等で増加することから、前年度に比べて0.3%増加し、7.8億tとなる見込みです (図表1-2-8)。
とうもろこしは、米国、ブラジル等で増加することから、前年度に比べて7.4%増加し、12.1億tとなる見込みです。
米は、インド等で増加することから、前年度に比べて0.9%増加し、5.1億tとなる見込みです。
大豆は、南米の乾燥等によりブラジル等で減少することから、前年度に比べて3.4%減少し、3.5億tとなる見込みです。
消費量がいずれも前年度から増加した結果、期末在庫率については、小麦、とうもろこし、大豆は前年度に比べて低下、米は前年度に比べて僅かに増加する見込みです。
1 米国農務省「World Agricultural Supply and Demand Estimates」(March 9, 2022)
(世界の食料需給をめぐる中長期的な見通し)
世界の人口は、令和3(2021)年では79億人と推計されていますが、今後も開発途上国を中心に増加し、令和32(2050)年には97.4億人(*1)になると見通されています。
このような中、令和12(2030)年における世界の穀物等の需給について、需要面においては、アジア・アフリカ等の総人口が継続的に増加するものの、新型コロナウイルス感染症の世界的流行等の影響も受けて、中期的に多くの国で経済成長が鈍化し、所得水準の向上等に伴う途上国を中心とした食用・飼料用需要の増加がより緩やかになることから、需要の伸びはこれまでに比べて鈍化する見込みです。供給面においては、小麦等の一部の穀物における世界の収穫面積がやや減少する一方、単収の上昇によって需要の増加分を補う見込みです(*2)。
世界の食料の需給及び貿易は、農業生産が地域や年ごとに異なる自然条件の影響を強く受け、生産量が変動しやすいことや、世界全体の生産量に比べて貿易量が少なく、輸出国の動向に影響を受けやすいこと等から、不安定な要素を有しています。
また、気候変動や大規模自然災害、豚熱(ぶたねつ)(*3)等の動物疾病、新型コロナウイルス感染症等の感染症の流行、ロシアによるウクライナ侵略等、多様化するリスクを踏まえると、平素から食料の安定供給の確保に一層の万全を期する必要があります。
1 国際連合「World Population Prospects 2019」
2 農林水産政策研究所「2030年における世界の食料需給見通し」(令和3(2021)年3月公表)
3 用語の解説3(1)を参照
(4)不測時に備えた平素からの取組
(食料供給を脅かすリスクに対する早期の情報収集・分析等を強化)
農林水産省は、不測の事態に備え、平素から食料供給に係るリスクの分析等を行うとともに、我が国の食料の安定供給への影響を軽減するための対応策を検討、実施することにより、総合的な食料安全保障の確立を図ることとしています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による需要の急激な変化等により、フードサプライチェーンへの影響が発生したことを踏まえ、農林水産省は、食料供給を脅かす新たなリスクに適切に対応するため、令和3(2021)年2月に食料安全保障アドバイザリーボードを開催し、外部の有識者を交えて食料安全保障対策の強化について検討し、同年6月に検討結果を公表しました。
これを受け、同年7月に緊急事態食料安全保障指針(*1)を改正し、平素からの取組の中に早期注意段階を新設しました。主要農産物の国際価格の上昇といった当時の状況を踏まえ、早期注意段階を即時適用し、商社や業界団体との意見交換や、在外公館や調査会社等との連携により、情報収集・分析等を強化しました。
また、令和4(2022)年3月には、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえ、農林水産業や食品産業等の関連事業者に向けて、「ウクライナ情勢に関する相談窓口」を設置するとともに、政府の対策を一元的に確認できるWebサイトを農林水産省ホームページ内に開設し、燃油対策や資金繰り支援等の情報発信を強化しました。
このほか、政府は国内の生産量の減少や海外における不測の事態の発生による供給途絶等に備えるため、米にあっては政府米を100万t程度(*2)備蓄しています。あわせて、食糧用小麦にあっては国全体として外国産食糧用小麦の需要量の2.3か月分を、飼料穀物にあってはとうもろこし等100万t程度をそれぞれ民間で備蓄しており、今後も、これらの取組を着実に実施することとしています。

食料安全保障について
URL:https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/
1 平成24(2012)年に策定した、不測の要因により食料供給に影響が及ぶおそれのある事態に的確に対処するため、政府として講ずべき対策の内容等を示した指針
2 10年に1度の不作や、通常程度の不作が2年連続した事態にも国産米をもって対処し得る水準
(5)国際協力の推進
(世界の食料安全保障に貢献する国際協力の推進)
農林水産省は、国際機関への拠出や、二国間の技術協力を通じ、途上国におけるフードバリューチェーンの構築支援、飢餓・貧困の削減、気候変動や越境性感染症等の地球的規模の課題への対応に取り組んでいます。
WFP(国際連合世界食糧計画)との間でも、西アフリカ地域において、小規模稲作農家の食品栄養群や日常的に摂取する食物の栄養価等栄養に関する基礎的知識の向上と、生産技術や販売スキル向上のための農業支援を併せて実施する事業に取り組みました。
また、令和4(2022)年3月にオンラインで開催されたG7臨時農業大臣会合では、ロシアによるウクライナ侵略が世界の食料安全保障へ及ぼす影響について議論が行われ、我が国からは、ロシアによるウクライナ侵略を強く非難するとともに、食料輸出国による輸出規制等により、特に食料を輸入している途上国への食料供給が滞らないようにと訴えました。同会合では、食料危機を回避するために、G7が協力して対応していくことを決意した大臣声明が採択されました。
(持続可能な食料生産・消費に向けた取組)
令和3(2021)年12月、各国政府、国際機関、民間企業等の参画を得て、政府主催で「東京栄養サミット(*1)2021」を開催し、世界全体の栄養改善に向けて国際社会が今後取り組むべき方向性を取りまとめた成果文書として、「東京栄養宣言」が発出されました。
その際に農林水産省が主催した関連イベントでは、「東京栄養宣言」のテーマの一つである「食:健康的で持続可能な食料システムの構築」の実施に向け、食料システムの変革、食関連産業のイノベーションの推進、個人の栄養に関する行動変容の促進、途上国・新興国の栄養改善への支援等を内容とするアクションプランを発出しました。また、アクションプランに賛同した、60を超える民間企業・団体、非政府組織(NGO)等がそれぞれの具体的な取組を公表し、減塩や機能性に優れた商品の提供や途上国の栄養改善に向けた取組等を行っています。
1 栄養サミットは、英国が開始した栄養改善に向けた国際的な取組であり、オリンピック・パラリンピック競技大会に合わせて開催
(事例)G7で農業・食品関係企業の持続可能なサプライチェーンを議論
令和3(2021)年、英国が議長国となり開催されたG7の一連の会合では、大企業がどのように世界の持続可能性に貢献できるかが議題となりました。
この議論を踏まえ、持続可能なサプライチェーンの構築に向けて、企業の環境的、社会的取組の向上を目指す必要があるとの認識の下、G7各国の農業・食品関係企業が民間外部指標を活用して、自身の持続可能性の向上につなげることを目的とする「持続可能なサプライチェーンイニシアチブ」を立ち上げました。
同イニシアチブには、G7各国から22の企業が参加し、我が国からは、明治(めいじ)ホールディングス株式会社、日本(にっぽん)ハム株式会社及び株式会社セブン&アイ・ホールディングスが参加表明しています。
同年12月には、英国が同イニシアチブの立ち上げイベントをオンラインで開催し、我が国からは明治ホールディングス株式会社が、カカオ豆の調達に当たっての森林保全や、児童労働・強制労働排除に向けた活動等持続可能なサプライチェーン実現に向けた取組等についてプレゼンテーションを行いました。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883