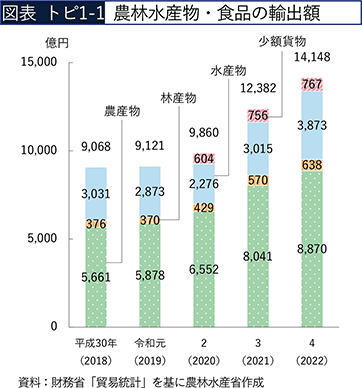トピックス1 農林水産物・食品の輸出額が過去最高を更新
農林水産物・食品の輸出額は年々増加傾向にあり、令和4(2022)年には1兆4,148億円と過去最高を更新しました。政府は、令和7(2025)年までに2兆円、令和12(2030)年までに5兆円とする目標の達成に向けて、更なる輸出拡大に取り組んでいます。
以下では、農林水産物・食品の輸出をめぐる動きについて紹介します。
(農林水産物・食品の輸出額が1兆4,148億円に拡大)
令和4(2022)年の農林水産物・食品の輸出額は、前年に比べ14.3%(1,766億円)増加の1兆4,148億円となり、過去最高を更新しました(図表トピ1-1)。農産物は8,870億円で、このうち非食品としては花き(91億円)等が含まれます。外食向け需要が新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による落ち込みから回復したこと、小売店向けやEC販売等が引き続き堅調だったこと等に加えて、円安による海外市場での競争環境の改善も寄与したものと考えられます。
品目別では、ホタテ貝やウイスキー、青果物のほか、牛乳・乳製品や日本酒の増加額が大きくなりました。
国・地域別では、中国向けが最も多く、次いで香港、米国、台湾、ベトナムの順となっています(図表トピ1-2)。
(生産者の所得向上にも寄与)
農林水産物・食品の輸出を拡大していくことは、国内の食市場の規模が縮小する中、今後大きく拡大すると見込まれる世界の食市場を出荷先として取り込み、国内の生産基盤を維持・拡大するためには不可欠です。くわえて、国内仕向けを上回る単価での販売による生産者の所得向上や海外需要拡大による国内価格の下支え等にもつながっていると考えられます(図表トピ1-3)。
また、加工食品の中には、例えば日本酒のように、国産原料を使用しているものがあります。こうした国産原料の使用は、地域の生産者に安定的な販路を提供し、その所得の向上につながるものと考えられます。
さらに、輸入原料を使用する場合でも、食品製造業が輸出により収益を上げることは、国産原料の買い手としての機能が地域で維持・強化されることにつながると考えられます。
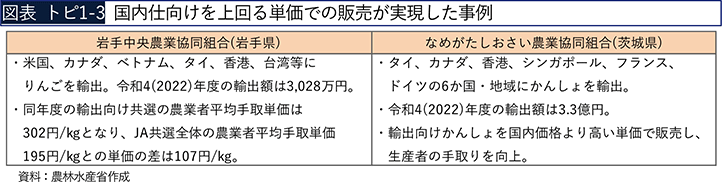
(事例)高度な衛生管理を基盤とし、米国等に向けて食肉輸出を推進(岐阜県)


飛騨牛のステーキ用肉と部分肉
資料:飛騨ミート農業協同組合連合会
岐阜県高山市(たかやまし)の飛騨(ひだ)ミート農業協同組合連合会(以下「JA飛騨ミート」という。)では、高度な衛生管理により飛騨牛(ひだぎゅう)の輸出拡大を進め、生産者の所得向上にも寄与しています。
JA飛騨ミートが運営する飛騨食肉センターは、国内トップクラスの衛生基準を有する食肉処理施設であり、コーデックスに基づくHACCP(*1)システムの構築に加え、岐阜県HACCPや食品安全の国際規格であるISO(*2)22000、GFSI(*3)が認める食品安全システム認証規格であるFSSC22000の認証を取得しています。令和5(2023)年3月末時点では、衛生基準の特に厳しい米国やEU(*4)を含めた18か国・地域の輸出食肉取扱施設の認定を受けています。
JA飛騨ミートでは、輸出拡大が農家所得の支えになっていることを踏まえ、現地バイヤーと直接対話する営業活動を増やすなど、更なる輸出拡大の取組を強化していくこととしています。
*1~2 用語の解説(2)を参照
*3 Global Food Safety Initiativeの略で、世界食品安全イニシアティブのこと
*4 European Unionの略で、欧州連合のこと
(令和7(2025)年に2兆円、令和12(2030)年に5兆円の目標達成に向け、取組を推進)
令和4(2022)年に入り、為替相場が円安傾向で推移している中、そのメリットを最大限引き出していくため、農業者の所得向上につなげつつ、農林水産物・食品の輸出拡大を強力に進めていくことが重要です。
農林水産省では、農林水産物・食品の輸出額を令和7(2025)年までに2兆円、令和12(2030)年までに5兆円とする目標の達成に向けて、品目団体を中核としたオールジャパンでの輸出促進、輸出支援プラットフォームによる海外現地での支援、大ロット輸出に向けたモデル産地の形成、知的財産の保護・活用等の取組を強力に推進しています。
→第1章第5節を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883