トピックス5 スマート農業技術の導入による生産性の高い農業を推進
農業従事者が減少する中にあっても、食料の供給基盤の維持を図っていくため、生産性の高い農業を確立することが求められています。デジタル変革が進展する中、スマート農業の基盤となるデジタル技術の更なる活用により、農業の生産性を向上させていくことが重要です。
以下では、スマート農業の社会実装を加速するための取組やスマート農業技術の導入による生産性の高い農業への転換に向けた取組について紹介します。
(多様なスマート農業技術を活用した取組が各地で展開)
令和元(2019)年度から実施してきたスマート農業実証プロジェクト(以下「実証プロジェクト」という。)では、スマート農業は、大規模法人だけでなく、中小・家族経営にとっても、現場の課題解決に役立つ一方、スマート農業機械の導入コストが課題となることから、農業支援サービス事業体の活用が有効であることが明らかになりました。
農業支援サービス事業体には、スマート農業技術を開発し、それらを用いて地域に合わせたサービスを提供するスタートアップも参入しています。中小・家族経営にも活用できるスマート農業技術では、例えばスタートアップが自ら開発した農薬散布ロボットを活用し、防除作業を行う農業支援サービスが登場しています(図表 トピ5-1)。
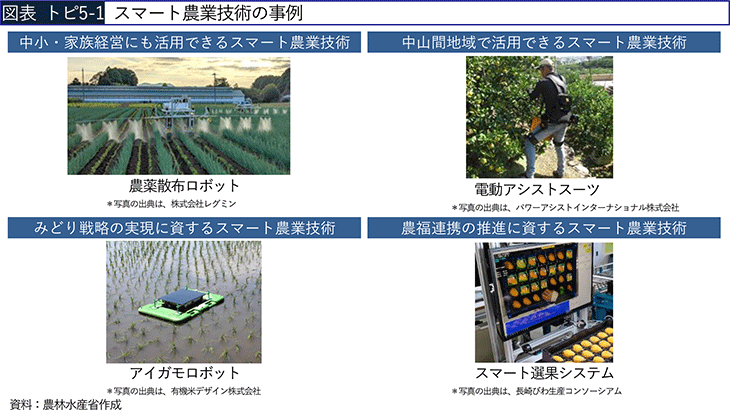
また、中山間地域においてもスマート農業技術が活用できるよう、狭小で傾斜の強い圃場(ほじょう)に導入可能なスマート農業技術の開発や地域ぐるみでの農業機械のシェアリング等を推進する必要があります。中山間地域で活用できるスマート農業技術では、例えば果樹園での電動アシストスーツの導入による収穫物の持上げや運搬作業等の軽労化、急傾斜地でのリモコン式草刈機の導入による作業の軽労化・省力化といった事例が見られています。
さらに、化学農薬や化学肥料の使用量の低減を始め、環境負荷の低減にもスマート農業技術は貢献しています。みどり戦略の実現に資するスマート農業技術では、例えば水田の泥をかき混ぜて雑草の生長を抑制し除草剤の使用を削減するアイガモロボットの活用、ドローンによる農薬のピンポイント散布、土壌センシングデータに基づく施肥量の自動制御の取組といった環境負荷の低減を図る動きが見られています。
くわえて、農福連携を推進する上でもスマート農業技術の活用は有効です。農福連携の推進に資するスマート農業技術では、例えばびわの選果作業において、等級等の選別結果を果実の表面に投影するスマート選果システムにより、容易に箱詰め作業が行えるようにするなど、障害を持った人の農作業をサポートする技術も登場しています。
(事例)スマート農業機械の導入による省力化と作業精度の向上を推進(広島県)


全自動収穫機による
キャベツの収穫
資料:株式会社vegeta
広島県庄原市(しょうばらし)の農地所有適格法人である株式会社vegeta(ベジタ)では、中山間地域における大規模野菜作経営での収益性向上に向け、スマート農業機械の導入による省力化と作業精度の向上等の取組を進めています。
同社は、令和4(2022)年12月時点で約130ha以上の農地を集積し、キャベツやトマト等の露地栽培を中心とした大規模生産を行っており、お好み焼き向けや加工・業務用等の出荷に積極的に取り組んでいます。
同社では、標高差を活かしたリレー出荷に取り組む一方、中山間地の圃場が過半であり、小規模な農地が多いことから作業の効率化が課題となっています。このため、令和元(2019)年度から実証プロジェクトに参画し、キャベツについてオートトラクターの技術体系の確立や全自動収穫機による作業の省力化等の実証を行いました。
このうち全自動収穫機の実証においては、10~12月収穫の品種では、作業者1人1時間当たりで、手収穫が150玉に対し、機械収穫は289玉となり、収穫に要する作業時間が48%削減できました。
従来の収穫方法は、作業者が包丁を持って畑に入り、キャベツの根元を切り、大きな外葉を捨てながら収穫していくものでしたが、全自動収穫機の導入により収穫作業の省力化が可能となっています。
また、中山間地では、圃場が畦畔(けいはん)に囲まれているため、機械に踏まれる圃場内の外縁部分をあらかじめ手収穫する労力を必要としていましたが、手収穫と機械収穫との常時セット作業を行うことにより、収穫作業は1.5倍の効率が図られています。
同社では、拡大する農地を少人数で省力的に管理できるよう、今後ともスマート農業機械を活用し、加工・業務用野菜の生産拡大を図りながら、地域社会の持続的発展に貢献していくこととしています。
(G7宮崎農業大臣会合においてスマート農業技術を紹介)
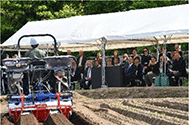
スマート農業技術の実演
を行う農業高校生
資料:G7宮崎農業大臣会合協力推進協議会
令和5(2023)年4月22~23日にかけて宮崎県宮崎市(みやざきし)で開催されたG7宮崎農業大臣会合において、農林水産省ではスマート農業技術の展示や現地での実演を実施しました。展示会場では、ピーマン自動収穫ロボットやスマートグラス等を紹介するとともに、実演会場となった宮崎県立宮崎農業(みやざきのうぎょう)高等学校では、同校の生徒も参加して自動走行トラクタやドローン等を実演し、各国の農業大臣等の高い関心を集めました。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




