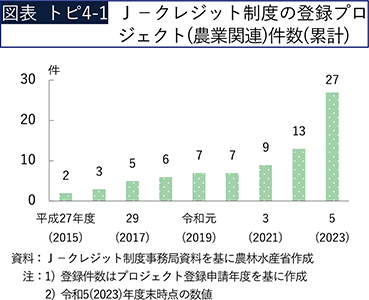トピックス4 農業分野におけるカーボン・クレジットの取組拡大を推進
気候変動問題への対応に加え、ロシアによるウクライナ侵略を受け、エネルギーの安定供給の確保が世界的に大きな課題となる中、我が国においては「グリーントランスフォーメーション」(以下「GX(*1)」という。)を通じて脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の三つを同時に実現する取組を推進しています。農業分野においては、みどり戦略を踏まえ、森林、農地、家畜等の自然由来の温室効果ガスの排出削減・吸収に資する取組の後押しとして、カーボン・クレジット(*2)の取組拡大等を推進しています。
以下では、J-クレジット制度の普及・推進に向けた取組等について紹介します。
*1 Green Transformationの略。GXのXは、Transformation(変革)のTrans(X)に当たり、「超えて」等を意味する。
*2 ボイラーの更新や太陽光発電設備の導入、森林管理等のプロジェクトを対象に、そのプロジェクトが実施されなかった場合の排出量及び炭素吸収・炭素除去量(以下「排出量等」という。)の見通し(ベースライン排出量等)と実際の排出量等(プロジェクト排出量等)の差分について、測定・報告・検証を経て、国や企業等の間で取引できるよう認証したもの
(脱炭素に向けた民間投資を促進)
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素に向けた民間投資を促進し、化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換するGXを加速していくことが重要です。
農林水産業の生産活動の場である森林・農地・藻場等は、温室効果ガスの吸収源として、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて不可欠な役割を担っており、それらの機能強化を図ることが重要となっています。このため、みどり戦略に基づき、有機農業や堆肥・緑肥の利用等の推進を図るとともに、民間資金を呼び込むJ-クレジット制度の活用や関係者の行動変容を促すといった食料・農林水産業分野における脱炭素・環境負荷低減に向けた変革の取組を推進しています。
(J-クレジット制度において農業分野では六つの方法論を承認)
世界的にカーボン・クレジットの取引市場が急拡大する中、我が国においても、森林、農地、家畜等の農林水産分野から創出されるカーボン・クレジットの取組拡大への期待が高まっています。令和5(2023)年10月には、株式会社東京証券取引所(とうきょうしょうけんとりひきじょ)がカーボン・クレジット市場を開設したところであり、価格公示による取引の透明化や流動化を通じた取引の更なる拡大が期待されています。
温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして国が認証し、民間資金を呼び込む取引を可能とする「J-クレジット制度」は、経済産業省、環境省、農林水産省の3省により運営されており、農林漁業者等が温室効果ガス排出削減・吸収の取組による温室効果ガスの削減量をクレジット化して売却することで収入を得ることができるものです。
同制度により創出されたクレジットは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく温室効果ガス排出量の報告に利用できるほか、海外イニシアティブへの報告、企業の自主的な取組といった様々な用途に活用することが可能です。J-クレジット制度では、令和6(2024)年3月末時点で70の方法論を承認しており、このうち農業分野では、令和5(2023)年4月に追加(*1)された「水稲栽培における中干し(*2)期間の延長」や、11月に追加された「肉用牛へのバイパスアミノ酸の給餌」を含め、六つの方法論(*3)が承認されています。
*1 令和5(2023)年3月に承認され、4月に施行
*2 水稲の栽培期間中、出穂前に一度水田の水を抜いて田面を乾かすことで、過剰な分げつを防止し、成長を制御する作業をいう。有害ガスの除去、刈取り時等の作業性の向上等の目的も含まれる。
*3 排出削減・吸収に資する技術ごとに、適用範囲、排出削減・吸収量の算定方法及びモニタリング方法を規定したもの
(農業分野におけるJ-クレジット制度の登録件数は27件)
J-クレジット制度におけるプロジェクトの登録件数については、令和6(2024)年3月末時点で608件であり、農業者が取り組むプロジェクトは、再エネ・省エネ分野の方法論を含めて27件、このうち農業分野の方法論を用いたプロジェクトは17件となっています(図表 トピ4-1)。
令和5(2023)年度においては、「水稲栽培における中干し期間の延長」に取り組むプロジェクト10件、「バイオ炭の農地施用」に取り組むプロジェクト4件、その他のプロジェクト1件が新たに承認されています。
(事例)J-クレジット制度を活用し中干しの延長によるメタン削減を推進(福井県)


水稲栽培における中干し
資料:株式会社クボタ
福井県大野市(おおのし)の広域営農組織である「3(さん)らいず」では、水稲の栽培期間中、出穂前に一度水田の水を抜いて田面を乾かす「中干し」の期間を延長することで削減できる温室効果ガスの数量をクレジット化する取組を推進しています。
同組織は、平成17(2005)年に設立され、3集落にまたがる約46haの水田で主食用米やWCS(*)用稲の生産を行っています。
同組織は、令和5(2023)年3月に、J-クレジット制度において「水稲栽培における中干し期間の延長」が新たな方法論として承認されたことを受け、プロジェクトの運営・管理者である株式会社クボタと連携し、水田からのメタン排出削減プロジェクトに取り組んでいます。
水田からのメタンの発生を減らすには、中干し期間を長くすることが重要ですが、作業上は特に負担なく取り組むことができるため、同組織では、制度が適用可能となった令和5(2023)年産の作付けから中干し期間を延長する取組を開始しています。
プロジェクトにおいては、同組織が水稲栽培における中干し期間を直近2か年以上の実施日数の平均より7日間以上延長し、モニタリング情報を提供することにより、プロジェクトの運営・管理者からクレジット収益が分配されることとなっています。
同組織では、今後とも中干し期間の延長の取組を推進し、環境負荷の低減につなげていくこととしています。
* 第3章第1節を参照
(方法論の新規策定等を支援)
農林水産省では、農業分野のJ-クレジット制度の取組推進に向け、普及用マニュアルや認証されるクレジットの見込量の簡易算定ツール等を作成するとともに、取組の間口を広げるため、方法論の新規策定等を実施しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883