トピックス7 令和6年能登半島地震への対応を推進
令和6(2024)年1月に石川県能登(のと)地方で発生した地震は、石川県を中心に、人的被害のほか、農作物等や農地・農業用施設等に大きな被害をもたらしました。
以下では、「令和6年能登半島(のとはんとう)地震(*1)」について、被害の状況と復旧に向けた取組について紹介します。
*1 気象庁が定めた名称で、令和6(2024)年1月1日に石川県能登地方で発生したM7.6の地震及び令和2(2020)年12月以降の一連の地震活動のことを指す。
(令和6(2024)年1月1日に石川県能登地方で地震が発生し、最大震度7を観測)
令和6(2024)年1月1日に、石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震が発生し、同県輪島市(わじまし)及び志賀町(しかまち)では震度7を観測したほか、沿岸部では津波に伴う海面変動も観測されました(図表 トピ7-1、図表 トピ7-2)。
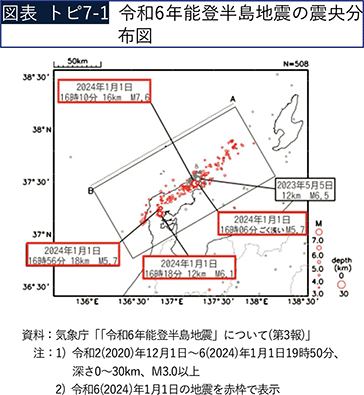
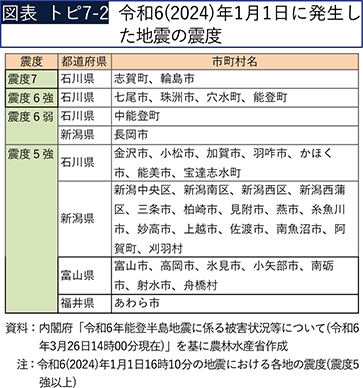
同地震により、石川県を中心に、人的被害のほか、建物の倒壊や火災の発生、交通インフラ・ライフラインの損壊等の甚大な被害がもたらされました。
能登地方は半島地域として三方を海に囲まれ、平地が少なく幹線交通体系から離れているなどの制約下にあることから、同地震の発生を受け、一部の地域では道路、水道、電気等の復旧に時間を要し、生活再建の動きを始められない状況や外部からのアクセスが途絶する孤立集落が発生する状況が見られました。
(災害対策本部を設置)

農林水産省緊急自然災害対策本部で
発言する農林水産大臣
政府は、発災直後から、警察、消防、自衛隊等を被災地に派遣し、被害状況の把握や救命救助、捜索活動等に当たるとともに、非常災害現地対策本部を設置し、各府省から多数の職員を被災地に派遣して、道路の啓開やプッシュ型による物資の支援、避難されている人々の命と健康を守るための二次避難の実施を行い、政府一体となって災害応急対策を進めてきています。
農林水産省においても、令和6(2024)年1月1日に、農林水産大臣を本部長とする農林水産省緊急自然災害対策本部を設置しました。
(被災地への食料支援を実施)

配送トラックへの食料等の積込み
政府は、令和6(2024)年1月1日、被災後直ちに「食料・物資支援チーム」を設置するとともに、被災地の要望を踏まえ、翌2日に、業界団体を通じた調達要請の結果、パン、パックご飯、即席麺及び乳児用ミルクについて、食品企業から輸送拠点への発送を開始しました。さらに、1月2日から3月23日までの間に、アレルギー対応食、介護食品、ベビーフード、栄養補助食品等を含む約514万点の飲食料及び約1万8千kgの無洗米等を広域物資輸送拠点に供給し、関係省庁と連携して被災地へ順次配送しました。
(コラム)キッチンカーを活用し、被災地での温かい食事の無償提供を実施
令和6(2024)年1月1日に石川県能登地方で発生した地震により甚大な被害を受け、被災後も厳しい冷え込みが続く被災地では、避難者から温かい食事を求める声が多数寄せられました。
このため、農林水産省では、外食業界団体である一般社団法人日本(にほん)フードサービス協会(きょうかい)と連携し、被災地方公共団体と調整の上、牛丼、カレー、うどんといった複数の外食事業者の協力を得て、キッチンカーを活用した食事提供の取組を実施しました。
外食事業者による取組は令和6(2024)年1月11日から開始され、石川県七尾市(ななおし)、輪島市、珠洲市(すずし)、穴水町(あなみずまち)、能登町(のとちょう)において温かい食事の無償提供が行われました。機動性の高いキッチンカーによる支援は、災害時に温かい食事を避難者に届けられる利点があります。キッチンカーの前には、避難者が列を作り、出来立ての料理を久しぶりに口にし、束の間のひとときに笑顔になる人も多数見られました。温かい食べ物は避難者の心の支えともなっており、避難者の食の質の改善に大いに寄与しています。

キッチンカーによる温かい食事の提供
資料:一般社団法人日本フードサービス協会
(農林水産省職員の現地派遣等を実施)
農林水産省では、食料供給・物流の円滑化や農地・農業用施設の早期復旧を図るため、職員の現地派遣等を行いました。

被害状況の調査
具体的には、令和6(2024)年3月末時点で農林水産省や地方農政局等の延べ8千人以上の職員をMAFF(マフ)-SAT(サット)(農林水産省・サポート・アドバイス・チーム)として石川県等に派遣し、被災状況の迅速な把握や応急対策、物流の確実な提供の実現等に向けた取組等を実施しました。早期の災害復旧に向けた復旧計画の策定、復旧工法の検討の指導を行うために災害査定官を石川県や被災市町村に派遣したほか、農村振興技術者を中心に全国から延べ7千人以上の職員を石川県、富山県、新潟県、福井県の37市町村に派遣し、関係団体との連携の下、農地やため池を含む農業用施設の被害状況の確認、応急措置、復旧方針の指導、査定設計書の作成に必要な業務支援を行いました。
また、農村のライフラインである農業集落排水施設や営農飲雑用水施設についても、関係団体との連携・協力の下、全国から派遣された技術者により迅速な点検が行われました。
さらに、農業用施設等の復旧・復興に早急に対応していくため、令和6(2024)年3月末までに北陸農政局管内の3か所に拠点を設け、直轄災害復旧事業等を実施しています。
(石川県を中心に甚大な農林水産被害が発生)
令和6(2024)年1月1日に石川県能登地方で発生した地震により、農地・農業用施設、畜舎や山林施設等の損壊、大規模な山腹崩壊、海底地盤の隆起等による漁港、漁場等の損壊等が発生し、石川県を始めとする各県の農林水産業に甚大な被害がもたらされました。
政府は、同年1月11日に、「令和6年能登半島地震による災害」を激甚災害として指定しました。激甚災害の指定により、農業関係では、農地、農業用施設、共同利用施設等の災害復旧事業について、被災農業者等の負担軽減を図りました。
(被災地方公共団体と連携し、被災農家に寄り添った対応を実施)

損壊した畜舎

破損した農業用パイプライン
石川県能登地方の畜産農家においては、断水、停電、施設損壊、生産物廃棄・家畜被害、道路損傷等の甚大な被害が生じています。農林水産省では、畜産経営が継続できるよう、被災地方公共団体等と連携しながら、畜産・酪農に係る被害について、水や電気の確保、配合飼料の緊急運搬等のほか、経営安定対策の特例措置の実施や負債整理資金の緊急融通等の支援を実施しています。
また、同地方においては、水稲の作付けに必要な農地・農業用施設、共同利用施設等への甚大な被害が生じています。農林水産省では、同地方の基幹産業である水稲作が継続できるよう、被災地方公共団体と連携しながら、令和6(2024)年産の作付けに向けて、水田や農業用用排水路等の応急復旧や水稲の作付継続に必要な農業機械の再取得や修繕、レンタル等の支援のほか、水稲の作付けを断念せざるを得ない場合には、他作物への転換に際しての種子・種苗供給等の支援を実施しています。
(石川県を中心に食品企業においても被害が発生)
令和6(2024)年1月1日に石川県能登地方で発生した地震により、醤油(しょうゆ)や味噌(みそ)、菓子、水産加工品等の食品企業においても製造・保管設備の損壊等が発生し、石川県を始め各県の食品産業にも甚大な被害がもたらされました。
(「被災者の生活と生業支援のためのパッケージ」を取りまとめ)
政府は、令和6(2024)年1月25日に、緊急に対応すべき施策を「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」として取りまとめました。
施策を実行するために必要となる財政措置については、令和5(2023)年度及び令和6(2024)年度の予備費を活用し、復旧・復興の段階に合わせて、数次にわたって機動的・弾力的に手当することとしています。
農林水産分野においては、地域の将来ビジョンを見据えて、世界農業遺産である「能登の里山里海(のとさとやまさとうみ)」等のブランドを活かした創造的復興に向け、被災農林漁業者が一日も早い生業の再建に取り組めるよう、災害復旧事業の促進や営農再開に向けた支援等を行うこととしています。具体的には、災害復旧事業の促進、共済金等の早期支払、災害関連資金の特例措置の実施、農業用機械や農業用ハウス・畜舎等の再建・修繕への支援、営農再開に向けた支援、被災農業法人等の雇用の維持のための支援、農地・農業用施設等の早期復旧等の支援等を実施しています。
政府は、被災地の声にしっかりと耳を傾けながら、「被災地・被災者の立場に立って、できることはすべてやる」という決意で、被災者の生活と生業の再建支援に全力で取り組むこととしています(図表 トピ7-3)。
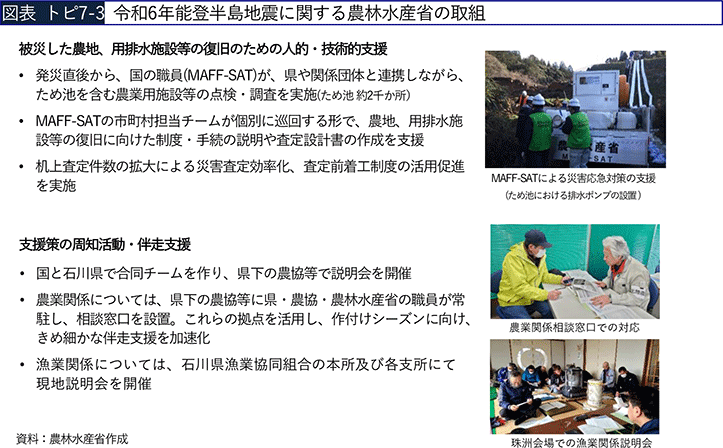
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




