トピックス1 農林水産物・食品の輸出促進
農林水産物・食品の輸出について、令和6(2024)年には初の1.5兆円超えとなる、1兆5,071億円となりました。農林水産省では、令和12(2030)年までに5兆円とする輸出額目標を設定し、農林水産物・食品の輸出促進に向け、より幅広い品目で、これまで以上に多くの生産者・事業者が海外市場を獲得できるよう、海外需要拡大と供給力向上の取組を車の両輪として推進していくこととしています。
以下では、特に「供給力向上」を図るための輸出産地形成に向けた取組や、輸出による生産者の所得向上への寄与について紹介します。
(生産・流通体系の転換による輸出産地の形成を推進)
農林水産物・食品の輸出拡大に向けて、残留農薬や動植物検疫といった規制の問題に対応することが求められるため、輸出先国・地域ごとや品目ごとに、産地が一体となって生産方式を転換していく必要があります。
そのため、農林水産省では、都道府県や農業協同組合(以下「農協」という。)、地域商社等の地域の関係者が一体となり、遊休農地等の活用、海外での需要や付加価値が高い有機農産物等の生産の拡大等による生産の転換、鮮度保持のためのコールドチェーンを確保した産地直送型集荷方法の確立や、混載を前提とした集荷から船積みまでの流通体系の構築等による流通の転換を図るなど、海外の規制・ニーズに対応した生産・流通体系への転換に取り組む大規模輸出産地の育成を目指しています。
さらに、農林水産省では、農林水産物・食品を輸出している産地のうち、(1)輸出先国・地域の規制やニーズに対応した輸出を行っていること、(2)一定の量又は金額の輸出実績があること、(3)サプライチェーンを構築し、継続的・安定的な輸出を行っていることを全て満たし、輸出取組の手本となる産地を「フラッグシップ輸出産地」として認定・公表しており、令和6(2024)年12月時点で、全国で80産地を認定しました(図表 トピ1-1)。
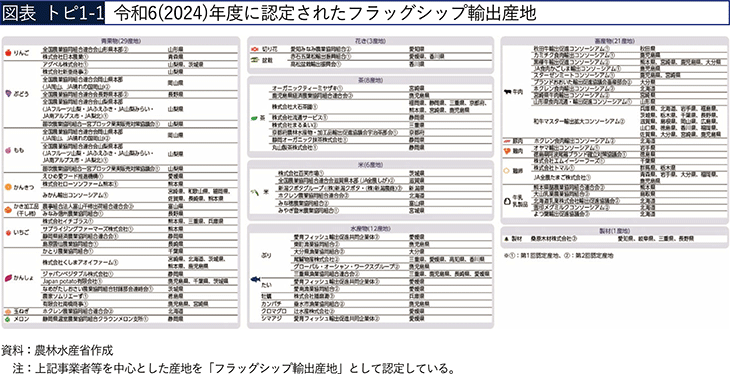
(事例)コンソーシアムで一体となり、うんしゅうみかんの輸出拡大を展開(宮崎県)
(1)輸出に取り組む企業がみかん輸出コンソーシアムを設立

宮崎県のみかん輸出(ゆしゅつ)コンソーシアムは、同県宮崎市(みやざきし)でうんしゅうみかんの生産等を行う株式会社ネイバーフッドを中心に生産、鮮度保持及び流通に関する企業等で構成され、令和5(2023)年に設立されました。同コンソーシアムでは輸出に向けた規制やニーズに対応した生産・流通に一体となって取り組んでいます。
(2)輸出先の規制やニーズに対応した生産・流通により、輸出を拡大

輸出先の店頭で販売される
うんしゅうみかん
資料:みかん輸出コンソーシアム
同コンソーシアムは、輸出先の残留農薬規制に対応するため、独自の防除暦の作成や残留農薬検査を実施し、令和5(2023)年にうんしゅうみかんを台湾やシンガポール等に輸出しました。また、他県の生産者と連携することで産地リレー体制を構築し、出荷可能期間を延ばしているほか、AIカメラ付き光センサーや光殺菌機等を導入した選別等を行い、廃棄ロスを削減することで価格を抑え、現地の家庭消費のニーズに対応した出荷を行っています。このような取組の結果、同年の輸出実績は3千万円となりました。
今後、同コンソーシアムでは、海外での新たな販路拡大を図るとともに、うんしゅうみかんの広域連携輸出モデルの確立や生産保管流通モデルの構築に取り組んでいくこととしています。

海外バイヤー招聘
資料:株式会社大石茶園

フラッグシップ輸出産地について
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/
export/gfp/flagship_yusyutsu.html
(生産者の所得向上に寄与)
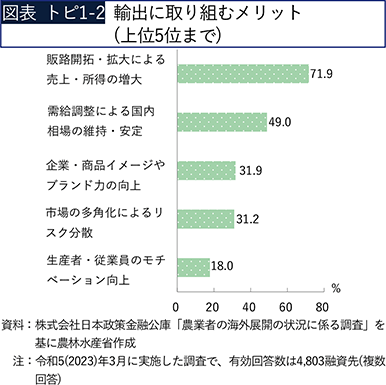
データ(エクセル:26KB)
公庫が実施した調査によると、海外展開している者の「輸出に取り組むメリット」について、「販路開拓・拡大による売上・所得の増大」と回答した生産者の割合は71.9%となっています(図表 トピ1-2)。このうち、肉用牛や果樹等において高い水準となっています。また、「需給調整による国内相場の維持・安定」と回答した生産者の割合は49.0%となっており、個々の生産者の稼ぎにつながるほか、輸出事業者だけでなくマーケット全体にもメリットが生じるなど、輸出の取組は国内の生産基盤の維持にも貢献しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




